招へい報告 バンコク都関係者が新宿区と横浜市の多文化共生の取組みを視察
移住労働者の児童の就学促進事業では、周辺諸国からの移住者を多く受け入れているタイで、移住労働者の子どもたちがタイの公教育を継続的に受けられるように、制度の周知やタイ語学習の支援を行っています。日本の多文化共生に向けた教育経験を参考にしていただくため、パイロット地域の1つであるバンコク都の関係者に、日本における外国につながる子どもたちへの教育の取組みを、新宿区と横浜市で見学していただきました。

笹川平和財団 常務理事 安達一
本シンポジウムでは、冒頭の当財団安達一常務理事からの開会の挨拶の後、フィリピン、ネパール、ウズベキスタンの大使館関係者、出入国在留管理庁、在外フィリピン人委員会、外国人コミュニティ、日本の市民社会の代表者らが参加し、以下のようなテーマについて発表と議論が行われました。
2023年度より、各関係機関が連携して渡航前・後のオリエンテーションを実施してきました。その中で明らかになったのは、外国人コミュニティと連携して、実際に必要な情報を確実に届ける仕組みづくりの重要性です。
外国人住民の状況や課題は、ライフステージごとに変化します。したがって、来日時の支援にとどまらず、日本側と外国人コミュニティが継続的に連携し、情報提供や相談体制を充実させていく必要性が強調されました。

ドゥルガ・バハドゥール・スベディ ネパール国特命全権大使

ミレーン・J・ガルシア・アルバノ フィリピン共和国特命全権大使 (ビデオメッセージ)

リクシボエフ・ユスフフジャ ウズベキスタン共和国大使館 二等書記官 兼 領事

出入国在留管理庁在留管理支援部 部長 福原氏
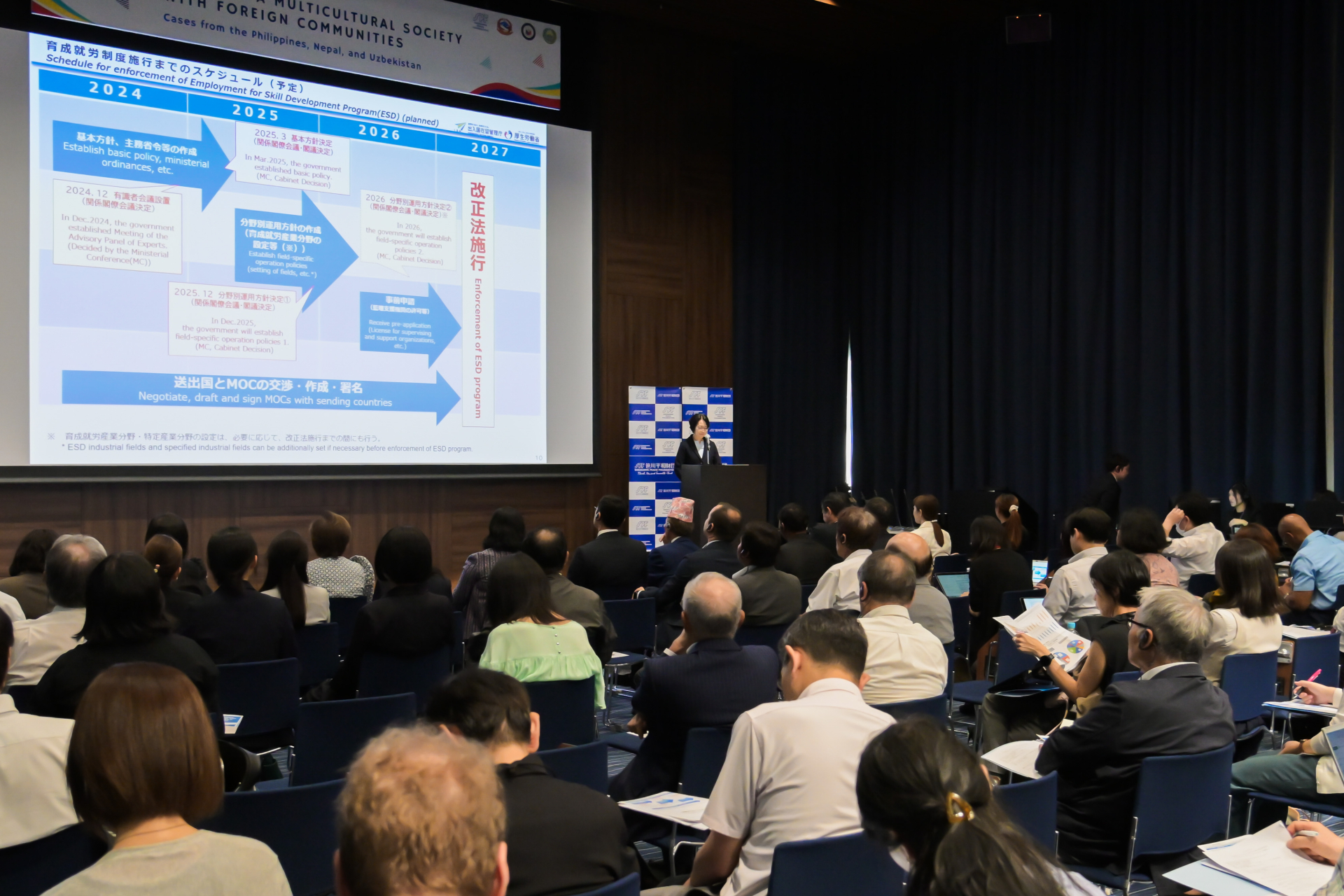
会場の様子

笹川平和財団第3グループ 研究員 岩品 雅子

ネパール・コミュニティのCINGAコーディネーター、サッキャ・ミナ氏

ウズベキスタン・コミュニティの アリエワ・マヒリヨ 氏

在外フィリピン人委員会委員長 ダンテ・クリンク・アング II 氏

フィリピン・コミュニティ Kakehashi代表 島田ビトゥイン 氏

笹川平和財団第3グループ長代理 長縄 真吾

出入国在留管理庁政策課 外国人施策推進室長 沼本氏
入管庁沼本氏からは、外国人がライフステージごとに直面する課題に対応するには、正確な情報提供とそれを支える地域との連携が欠かせない旨の説明がありました。また「家族滞在」資格で来日する外国人が31万人(10年間で2倍)に増加している一方で、就労制限があり、就労資格への変更は容易ではないこと、また、扶養者の収入が途絶えた場合、生活の不安定化や夫婦間の対立、離婚などにつながるリスクについて説明があり、それらは「事前に正しい情報を理解すること」で予防できる可能性があること、そのためには、日本で暮らすコミュニティの方々を始めとした様々な主体と連携したオリエンテーションによる情報共有が効果的である旨の発言がありました。 (詳細は資料参照)

CINGAコーディネーター 新居 みどり氏

フィリピン人コミュニティのKakehashiボランティア、粕谷マリア・カルメリタ 氏
粕谷氏は、フィリピン人が家族への送金を最優先する傾向があり、自身の将来設計が後回しになる現状に触れました。そのため、ライフステージごとの課題について段階的に伝えていく支援の重要性を訴えました。 (詳細は資料参照)
粕谷氏は、30年以上在日しているフィリピン人の間で、配偶者の死後の「遺産相続」「孤独」「年金や介護」などの新たな課題が急増していると指摘し、役所での案内や書類が難解で、「お悔やみの冊子」を渡されても理解できないケースがあると述べ、「死ぬまでの支援設計」が今から必要だと訴えました。
これに対し、沼本氏は、社会保障制度は日本人にとっても複雑な部分があるが、外国人にも社会保障制度のポイントや加入のメリットを理解してもらい、制度に参加してもらう仕組みが重要であると応じました。
また、ライフステージ別に情報を整理したポータルサイトを設置していること、四ツ谷の相談拠点FRESCや、地方での臨時相談会を展開していることも紹介しました。

パネルディスカッションの様子