招へい報告 バンコク都関係者が新宿区と横浜市の多文化共生の取組みを視察
移住労働者の児童の就学促進事業では、周辺諸国からの移住者を多く受け入れているタイで、移住労働者の子どもたちがタイの公教育を継続的に受けられるように、制度の周知やタイ語学習の支援を行っています。日本の多文化共生に向けた教育経験を参考にしていただくため、パイロット地域の1つであるバンコク都の関係者に、日本における外国につながる子どもたちへの教育の取組みを、新宿区と横浜市で見学していただきました。

全体のファシリテーターを務めた多文化ネットワークfuふ!代表の大仲 るみ子氏
標記のワークショップでは、多様な文化的背景を持つ外国出身者が全国各地に定住している現状で、地域の特性を活かしながら、外国人の受入れと共生に向けたさまざまな支援の取組みが進められていることを踏まえ、今後の沖縄における共生のあり方について参加者とともに考えました。行政、国際交流協会、JICA沖縄、多数のNGO/NPO、個人ボランティアなど52人が参加しました。ほとんどの参加者が、何らかの形で外国人支援に関わっている方々でした。
当財団では経験豊富な集住地域および先進的な取組みを行っている非集住地域に学びながら、非集住地域の自治体・支援者向けの『外国人住民との共生支援ハンドブック~受入れの基本姿勢とモデル事例集~』(仮称)を作成中です。
本ワークショップでは、上記ハンドブックを題材に、熊本県をはじめとする全国の先進的な事例を共有するとともに、令和6年度に沖縄県がとりまとめた「多文化共生社会の構築に関する提言書」の内容も踏まえながら、沖縄で現在行われている取組みを参加者間で共有し合い、課題と今後検討していきたい解決策について参加者とともに考えました。

『外国人住民との共生支援ハンドブック』の紹介を行うSPF 岩品研究員
冒頭に当財団第3グループ長縄グループ長代理より開会のあいさつを行った後、第3グループ岩品研究員より、作成中のハンドブックにおいて大切にしている価値と概要について紹介しました。
その後、社会福祉法人 日本国際社会事業団 常務理事 石川美絵子氏より、地域における外国人住民との共生において鍵となる支援の組立て・調整・連携について、外国人相談支援の特徴や連携するうえでの留意点について紹介されました。
その後、グループに分かれて議論を行いました。ハンドブックに掲載されている分野のうち、① 日本語教育、② 教育、③ 就労、④ 福祉と年金についてグループ討議を行い、まず参加者が現在行っている取組みに関する良い点と課題についてグループ内で共有した後、ハンドブックの該当の節を参照して、今後さらに知りたいことや取り組んでいきたいことを議論しました。
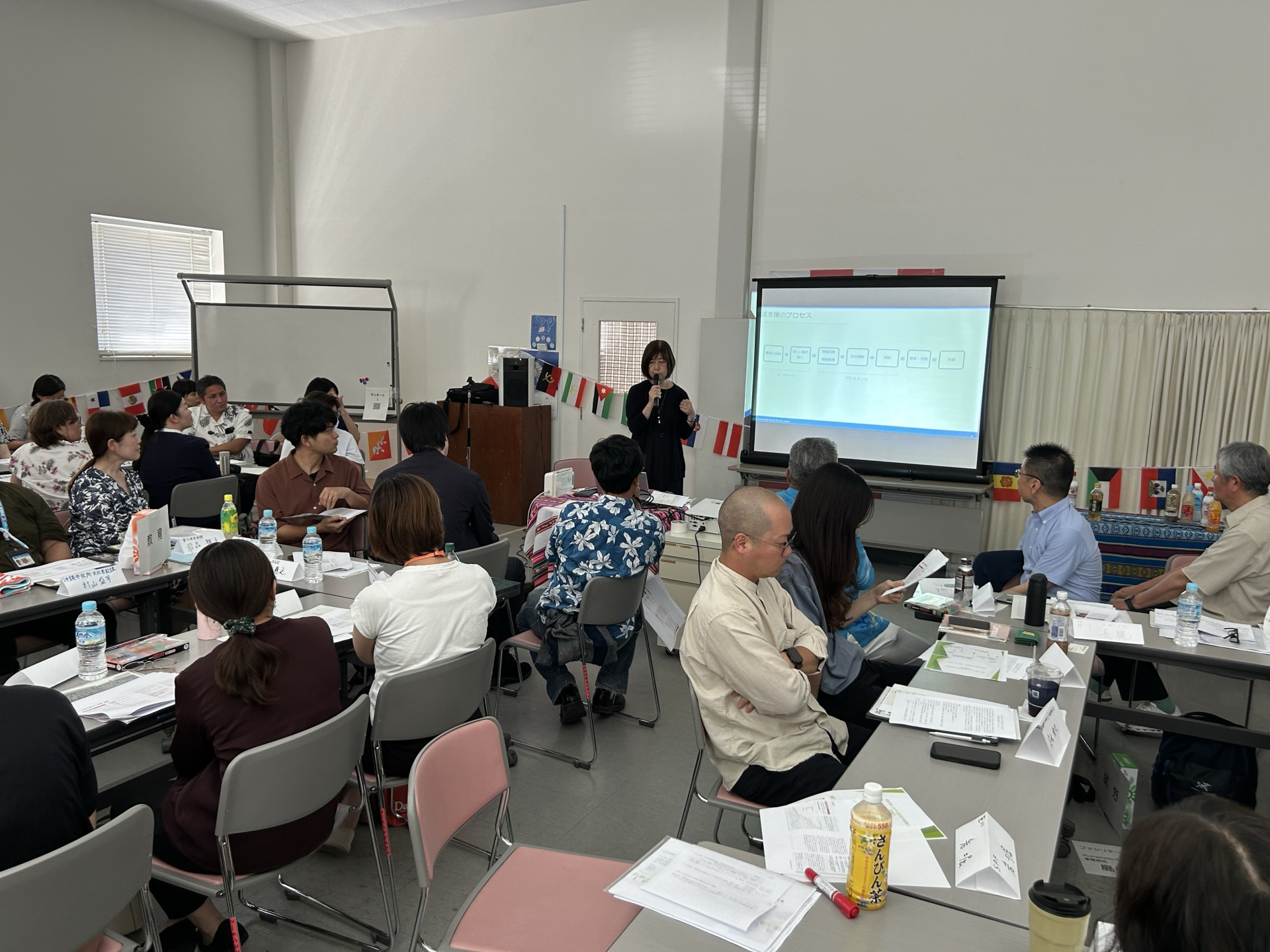
支援の組立て・調整・連携についてのプレゼンテーションを行う日本国際社会事業団 石川美絵子氏

グループワークの様子
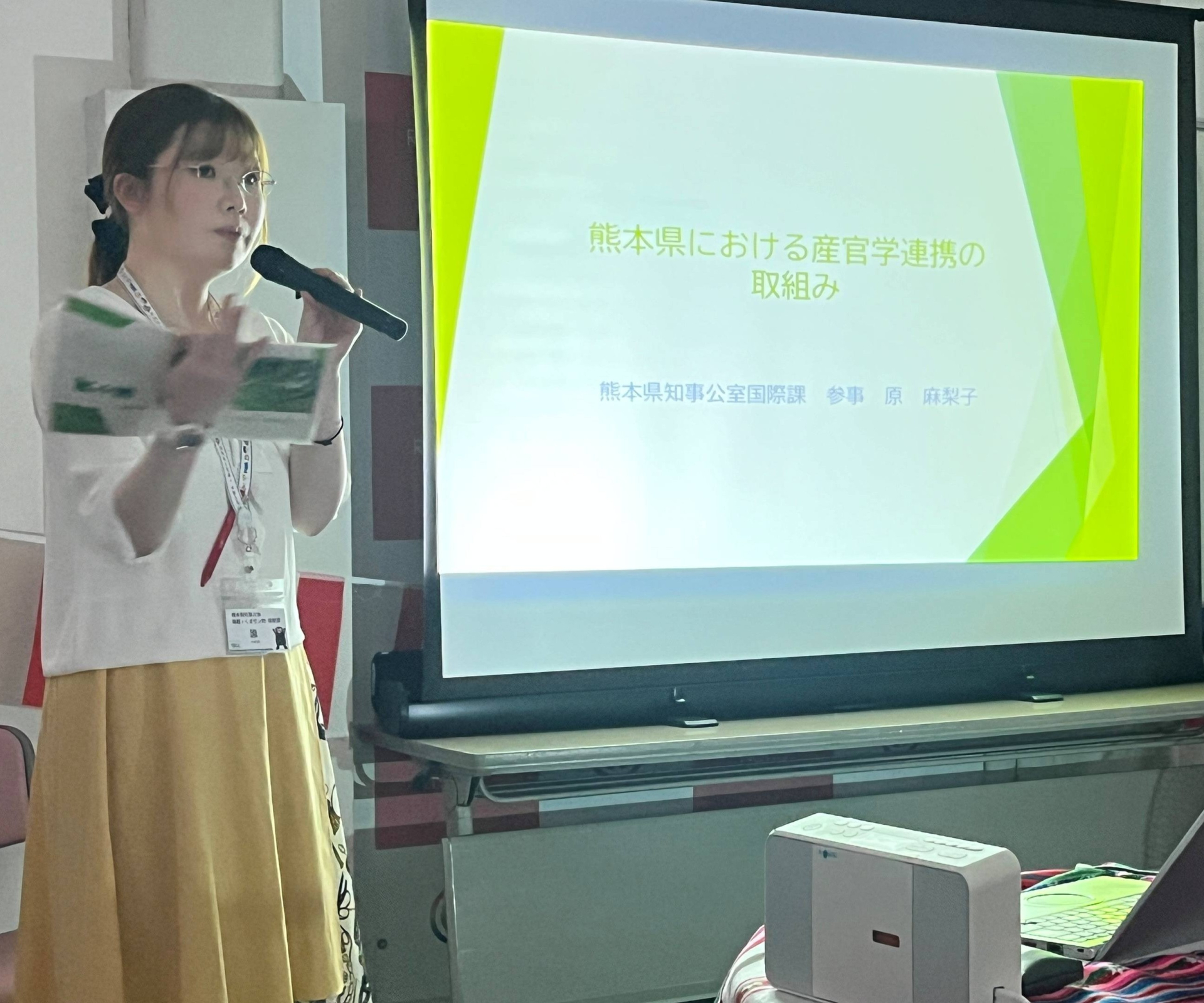
熊本の産官学のプラットフォームについてのプレゼンテーションを行う 熊本県 知事公室 原 麻梨子氏
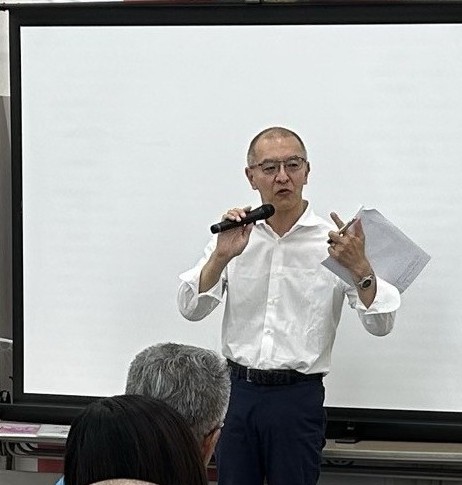
総括を行う筑波大学 明石純一教授
参加者の方々からは、事後アンケートで今後、共生社会への取り組みを進めるために希望することとして、以下のような声が届きました。
最後に、当財団で作成中のハンドブックで監修を務めていただいている筑波大学明石純一教授より、多文化共生は他の地域から学ぶことによって、効果的に取組みを進めることができる、とまとめられました。 笹川平和財団では、今回のワークショップでいただいたお声を反映して、より現場の役に立つハンドブックに仕上げていくとともに、地方自治体や支援者だけでは解決できない課題について、提言にまとめていく予定です。

参加者の集合写真