Ocean Newsletter
第41号(2002.04.20発行)
- 東洋英和女学院大学教授・慶應義塾大学名誉教授◆栗林忠男
- 日本財団常務理事◆寺島紘士
- 横浜国立大学国際社会科学研究科教授◆来生 新
- 日本財団海洋管理研究会作成
- 出典:The Global Maritime Boundaries、日本財団
- ニューズレター編集委員会編集代表者 ((社)海洋産業研究会常務理事)◆中原裕幸
資料
21世紀における わが国の海洋政策に関する提言
日本財団海洋管理研究会作成 国連海洋法条約および国連環境開発会議(リオの地球サミット)に掲げられた国際的な海洋管理の理念のもとに、わが国の管轄する沿岸域から排他的経済水域および大陸棚外縁までの開発、利用、保全、並びに公海を含む全海洋におけるわが国の権利義務の行使および国際協力に関して、国家としての基本理念と行動計画を掲げるわが国の海洋政策を策定し、内外に明示すべきである。 国連海洋法条約および国連環境開発会議(リオの地球サミット)に掲げられた国際的な海洋管理の理念のもとに、わが国の管轄する沿岸域から排他的経済水域および大陸棚外縁までの開発、利用、保全、並びに公海を含む全海洋におけるわが国の権利義務の行使および国際協力に関して、国家としての基本理念と行動計画を掲げるわが国の海洋政策を策定し、内外に明示すべきである。 |
1-1.わが国の海洋管理の基本理念として次の3点を明示すべきである。
- 海洋の国際法秩序の尊重と国際協調
地球上の7割を占める広大な海洋の問題は、一国だけでは適切に対応できない。わが国は海洋国家として、国連海洋法 条約その他の国際的取極めによって確立された海洋の国際秩序を尊重して、平和、安全、協力および友好関係の強化を旨として海洋管理に取り組む。 - 海洋の持続可能な開発、利用
海洋は、地球の生命維持システムに不可欠な構成部分であり、環境問題における海洋の重要性を認識し、海洋環境の保護および保全と両立する海洋および海洋資源の「持続可能な開発、利用」の実現に努める。 - 総合的管理
海洋の問題は、相互に密接な関連を有し、全体として検討される必要があるので、海洋および沿岸域の開発、利用および保全について総合的管理を行う。
1-2.海洋政策の策定は「海洋基本法」を制定して行うべきである。
わが国は、海洋政策を国家政策の中でも重要な課題として位置付け、その策定、実施のため、個別の海洋関係法令の上位規範として、基本理念、海洋管理基本計画、海洋の調査、開発、利用および保全に関する施策、国および地方公共団体の責務、海洋関係閣僚会議、海洋担当大臣の設置、海洋審議会の設置等を盛り込んだ「海洋基本法」を制定すべきである。
 海洋管理の基本理念に沿って政策が策定、実行されるように、関係する多数の省庁にまたがる海洋政策の総合的検討、策定およびその推進のための任務と権限を有する有効な行政機構を整備すべきである。 海洋管理の基本理念に沿って政策が策定、実行されるように、関係する多数の省庁にまたがる海洋政策の総合的検討、策定およびその推進のための任務と権限を有する有効な行政機構を整備すべきである。 |
2-1.海洋政策の総合的検討、策定とその推進のため、次のような行政組織を整備すべきである。
- 海洋政策を包括的に策定し、実施するため、内閣に総理大臣を長、海洋担当大臣を副とし、海洋関係行政を所管する各大臣からなる「海洋関係閣僚会議」を設置する。
- 「海洋担当大臣」を設ける。
- 内閣府に、総理大臣、海洋担当大臣を補佐し、海洋関係閣僚会議の事務を処理するため、「海洋政策統括室(仮称)」を設置する。
- 海洋政策の策定、実施並びに各省庁が行う海洋関係行政の円滑な調整を図るため、閣僚会議の下部組織として「海洋関係省庁連絡調整会議」を設置し、海洋政策統括室(仮称)がこれを主宰する。
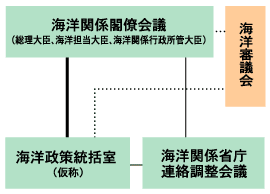
2-2.海洋政策・行政の効果的展開を図るため、海洋審議会のような組織を総理大臣(または海洋関係閣僚会議)の諮問機関として設置すべきである。
〈参考〉以上を図示すると右の通りである
 "沿岸域"を海陸一体となった独自の自然的・社会的環境を持つ区域として認識し、その生態系の総合的な環境保全のシステムを考慮した、開発と環境の両立を目指す持続的な総合的沿岸域管理について、必要な法制整備を検討すべきである。 "沿岸域"を海陸一体となった独自の自然的・社会的環境を持つ区域として認識し、その生態系の総合的な環境保全のシステムを考慮した、開発と環境の両立を目指す持続的な総合的沿岸域管理について、必要な法制整備を検討すべきである。また、沿岸域の開発と利用、保全の当事者、受益者として、地域住民の役割を積極的に評価し、沿岸域管理政策の立案、実施、評価、再実施のサイクル的プロセスに積極的な市民参加を実現すべきである。 |
3-1.沿岸域の環境の保護及び保全を図りつつ持続可能な開発、利用を行うために必要な総合的沿岸域管理のための法制整備をすべきである。
沿岸陸域と沿岸海域の一体性という沿岸域の特質を踏まえて、その持続的な利用と既存の海岸および沿岸域管理に関する個別の関連法制の総合調整を可能にする理念と手続を定める総合的沿岸域管理のための法制整備をすべきである。
前出の提案による「海洋基本法」の中で沿岸域の総合的管理に関する章を設けて行うのも一案である。
3-2.総合的沿岸域管理は自治体が行うものとし、その範囲と管理方法を確立すべきである。
総合的沿岸域管理については、理念と指針を国が示し、関係自治体(都道府県および政令指定都市を中心として、関係市町村が参加)が、その開発、利用および保全について総合管理計画を策定して行うべきである。
沿岸域の範囲は、自然の系、生態系および自治体の管理の実効性を考慮して、基本的に次のようにするのが適当である。
海岸線方向については自然の系と生態系を、陸域・海域方向については、陸側は流域圏に係る市町村の行政境界を、海側は3海里(閉鎖性および半閉鎖性海域の場合は全海域)を基準として、国と関係自治体が関係者や有識者の意見を参考にして協議して定める。
3-3.閉鎖性および半閉鎖海域については、その一体的性格が特に強いことを考慮して、総合管理体制を確立すべきである。
三大湾、瀬戸内海などの閉鎖性・半閉鎖性の海域とその沿岸陸域については、一般にその利用密度が高く、また、相互に影響を受け易い環境条件下にあることを考慮して、これを一体的に捉えて総合的な開発、利用、保全を行うために、総合的な管理体制を整備すべきである。
3-4.沿岸域の開発の抑制と自然環境の回復について積極的に取り組むべきである。
沿岸域における埋め立ては最大限抑制するとともに、臨海部埋め立て地帯の工場跡地、利用の目途が立たない造成地、並びに流域圏における機能を喪失した構築物などについては、極力自然環境への復帰を促すべきである。
3-5.沿岸域管理のサイクル的プロセスに、積極的な市民参加を実現すべきである。
当該沿岸域の地域住民、市民組織などは、沿岸域管理政策の立案、実施、評価、再実施に関して、その全プロセスについて「知る」権利を有しているとの考え方にもとづき、関連する諸情報への実質的なアクセスの権利を保障すべきであり、その全プロセスにおいて、可能な限り「参加」の機会を保障すべきである。
3-6.わが国にも「海洋保護区」制度を本格的に導入し、合理的な管理をすべきである。
わが国の沿岸域においては、自然公園法にもとづく海中公園地区が多数指定されており、また自然環境保全法による自然環境保全地域が西表島に1ヶ所指定されている。さらに、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」による生物種の保護制度も存在する。しかしながら、多様な生物が存在し、人類の生存基盤である海洋の生態系を保護するためには、これでは極めて不十分である。これらの諸制度をさらに一歩進めて、生息地として重要な海域、絶滅危惧種が生息する海域、貴重なサンゴ礁の存在する海域、湿地帯、干潟など適当な保護と管理を施す必要があると考えられる海域を「海洋保護区」として指定し、必要に応じて保護が必要な区域と利用する区域を区分するゾ-ニングなどの手法を用いて、合理的な管理を推進すべきである。
3-7.ミティゲ-ションの制度化について努力すべきである。
ミティゲ-ション(開発、利用の環境影響を回避、最小限化、または代償措置を講ずることを基本とする考え方)については、それが開発の免罪符として用いられることへの危惧や、効果測定の方法が確立していないこと等さまざまな問題点も指摘されている。しかし、ミティゲ-ションは、環境のこれ以上の悪化に対する歯止めの役割を果たす手法の一つとして、また、環境修復や望ましい環境の創造のためにも有用なものとして評価できるものであり、さらには、海洋開発の社会的コストを明らかにし、事業費の中に内部化する合理的な手法としても評価できると考えられるため、今後その問題点の解消に向けて一層の研究を積み重ねるとともに、その制度化に努力すべきである。
 "海洋資源の合理的かつ持続可能な開発の枠組みの中で、わが国周辺海域における水産資源の保存と管理、漁業の振興を一層図る必要がある。そのためには、漁業制度の近代化・合理化のための漁業協同組合や漁業権制度の見直しを含めた抜本的制度改革を今後とも継続的に進めるべきである。 "海洋資源の合理的かつ持続可能な開発の枠組みの中で、わが国周辺海域における水産資源の保存と管理、漁業の振興を一層図る必要がある。そのためには、漁業制度の近代化・合理化のための漁業協同組合や漁業権制度の見直しを含めた抜本的制度改革を今後とも継続的に進めるべきである。また、漁業と他の海洋利用との競合問題の調整や共存のための合理的な法制度の確立を図るとともに、漁業補償について、国民全般の支持を得ることのできる透明性と公正性を確保するための手続、手法の見直しを実施すべきである。 |
4-1.水産資源の合理的な利用のため、一層の資源管理および資源回復・培養に努めるべきである。
国連海洋法条約の批准と排他的経済水域(EEZ)の設定に伴い、合理的な資源管理のためにわが国においてもTAC(TotalAllowableCatch)制度が導入されたが、その対象魚種を漸次増やして一層の資源管理の推進を図るとともに、最近制定した「水産基本法」にもとづき、漁業の振興、水産資源の回復・培養、作り育てる漁業の振興などに一層努めるべきである。
4-2.漁業の産業的発展のために、漁業関係法制の改革に取り組むべきである。
わが国の漁業は遠洋漁業の縮小に伴い、200海里EEZを中心とした周辺海域における沖合漁業ならびに沿岸漁業に重点が移行してきているが、上記の資源管理、資源培養のための施策と並行して、これら漁業の国際競争力のある産業としての振興、発展のために必要な法制整備を行うべきである。
戦後民主化の強い要請の中で確立した漁業協同組合制度や漁業権制度は、その後50年を経た今日のわが国の経済状況の下では、逆に産業としての漁業の合理化、競争力の強化を妨げている面もあり、漁業への参入の容易化を含む関係法制の継続的な見直しをすべきである。
4-3.漁業補償に第三者機関による裁定方式の導入を検討すべきである。
漁業補償に関しては、補償基準と実態の乖離、消滅した漁業権の復活に伴う重複的な漁業補償等、その不透明性、公正性の欠如に対する非漁業者からの批判も強い。海の管理者として機能してきた漁業者の権利および漁業の振興という社会的価値と、国民共通の資源である海の合理的で持続的な利用の一層の促進という社会的価値を両立させ得るような、合理的で透明性の高い補償方式を導入すべきである。
その場合、補償基準と補償実態の著しい乖離を無くするような合理的な補償が可能になり、補償によって漁業の振興、水産資源の回復・培養、資源管理が一層充実するような新たな制度を構築すべきである。漁業補償の透明性を高めるために、第三者機関による勧告・裁定方式の導入も検討すべきである。
 わが国の排他的経済水域(EEZ)および大陸棚において、国連海洋法条約上の天然資源等に関する主権的権利や科学的調査、海洋環境保護等に関する管轄権を十分に行使するための総合的な海洋管理政策の策定を急ぎ、その具体的展開を図るべきである。 わが国の排他的経済水域(EEZ)および大陸棚において、国連海洋法条約上の天然資源等に関する主権的権利や科学的調査、海洋環境保護等に関する管轄権を十分に行使するための総合的な海洋管理政策の策定を急ぎ、その具体的展開を図るべきである。また、EEZおよび大陸棚について、境界画定に関する基本方針を定めて隣接国との協議等を進めるとともに、EEZおよび大陸棚に関する現行法の見直しを行い、わが国の海洋政策の具体的展開を推進するために必要な法制整備を行うべきである。 |
5-1.EEZおよび大陸棚の開発、利用、保全に関する総合的なわが国の海洋政策を策定すべきである。
国連海洋法条約を踏まえて、世界第6位と言われる広大なわが国のEEZ、および大陸棚の持続可能な開発、利用、保全を積極的に推進するため、総合的な海洋管理政策を策定すべきである。また、わが国のEEZおよび大陸棚について、境界画定に関する基本方針を定めて隣接国と協議を進めるとともに、条件を満たせば最大350海里まで拡大可能な大陸棚の範囲の画定に必要な調査活動を一層強化し、その確定に努力すべきである。
5-2.EEZおよび大陸棚に関する現行法の見直しを含めて、必要な法制整備を行うべきである。
国連海洋法条約が定めるわが国のEEZおよび大陸棚に関する主権的権利および管轄権の行使、ならびに同時に要請されている義務の履行を誠実かつ包括的に実施するため、単に国内法令の適用を述べるにとどまる現行の「排他的経済水域および大陸棚に関する法律」を見直すとともに、各種法制度の適用に関する具体的可能性の検討を踏まえて、総合的な海洋管理政策の推進のために必要な法制整備を行うべきである。
5-3.EEZおよび大陸棚における天然資源等の調査、開発、保存および管理のための法制整備を早急に行うべきである。
EEZおよび大陸棚における熱水鉱床、マンガン団塊、メタンハイドレート等の鉱物資源、エネルギー資源および生物資源の主権的権利および管轄権を明確にし、その調査、開発、保存および管理のための法制整備を早急に行うべきである。また、EEZおよび大陸棚以遠の近海域においても、関係国と開発をめぐる調査、協力の体制を整えるべきである。
 国民の海に対する知識や理解の向上を図り、海との共生についてその積極的関心を喚起するため、海洋に関する教育・啓発、特に青少年に対する海洋教育の拡充を図るべきである。 国民の海に対する知識や理解の向上を図り、海との共生についてその積極的関心を喚起するため、海洋に関する教育・啓発、特に青少年に対する海洋教育の拡充を図るべきである。また、海洋問題に総合的視点で取り組むため、自然科学系と社会科学、人文科学系の相互間を含む各分野の学際的研究と交流を促進するとともに、大学院レベルでの海洋管理に関する総合的な教育・研究システムを整備すべきである。 |
6-1.初等・中等教育において、私たちの生存基盤である海に関する教育の充実を図るべきである。
わが国は海に囲まれ、海から様々な恩恵を受けているが、残念ながら青少年に対して海に関する教育をあまり行っていない。小、中、高等学校の教育カリキュラムに海に関する事項を取り入れるとともに、教材の充実、教員の海に関する知識、理解の向上を図るべきである。
また、高等学校の「理科」で海洋科学の主要分野の基礎的事項を、「社会」で海洋利用の現状と問題点および持続可能な開発、利用について、学習できるようにすべきである。
6-2.学校教育および社会教育において、積極的に海について知識、理解の向上を図る機会を増加すべきである。
海は、大きな自然であり、実際に触れて初めて理解できることも多い。学校内の教育だけで海に対する関心を高め、知識や理解の向上を図るには限界がある。このため、学校教育においては、総合的学習の時間などを活用し、また、地域社会や家庭においても「海の日」や夏休みなどの機会を活用して、フィールド学習の機会を強化するとともに、近郊の港、博物館、海洋研究機関あるいは海洋体験施設などへの見学、体験の機会を増加させるべきである。
6-3.大学・大学院の海洋に関する教育・研究を学際的、社会的、国際的に開かれたものにすべきである。
海洋の諸問題は、相互に密接な関連を有し、全体として検討される必要があることを認識して、環境、生態系その他の総合的、学際的アプローチを必要とする問題への対応能力を培うため、自然科学部門内の各分野間はもちろんのこと、社会科学、人文科学との部門間を含む学際的教育・研究の充実を図るべきである。
また、海洋に関する教育・研究に、広く社会に出て行うインターンシップ制度を導入するとともに、産業界、行政、試験研究機関などに働きながら、海洋に関して講義を受け、研究することができるプログラムを整備すべきである。
さらに、海洋の国際的性格に鑑み、教授、学生の交流、単位の相互承認など内外の大学間の交流を促進し、国際的に開かれた海洋教育の実現を図るべきである。
6-4.海洋政策、海洋・沿岸域の総合管理などに関する高度な教育・研究の充実を図るべきである。
20世紀末に発効した国連海洋法条約の各国による実施が今世紀の大きな課題であることに鑑み、海洋法、海洋環境、資源管理、沿岸域総合管理など海洋の総合的管理に関する研究のための修士課程以上のコースを設置するとともに、日本および世界各国の海洋政策、海洋法制等を研究するプログラムを編成すべきである。
また、海洋政策についてアカデミックな立場から総合的に分析、評価し、提言する海洋政策研究センターを設立すべきである。
第41号(2002.04.20発行)のその他の記事
- 海洋秩序の先導国たれ! 東洋英和女学院大学教授・慶應義塾大学名誉教授◆栗林忠男
- 海に生きる日本の海洋政策の確立を急げ 日本財団常務理事◆寺島紘士
- 21世紀に向けての沿岸域管理のあり方 横浜国立大学国際社会科学研究科教授◆来生 新
- 資料21世紀における わが国の海洋政策に関する提言 日本財団海洋管理研究会作成
- 付録世界各国の海洋管理への取り組み比較表/世界の排他的経済水域図 出典:The Global Maritime Boundaries、日本財団
- 編集後記 ニューズレター編集代表 ((社)海洋産業研究会常務理事)◆中原裕幸
