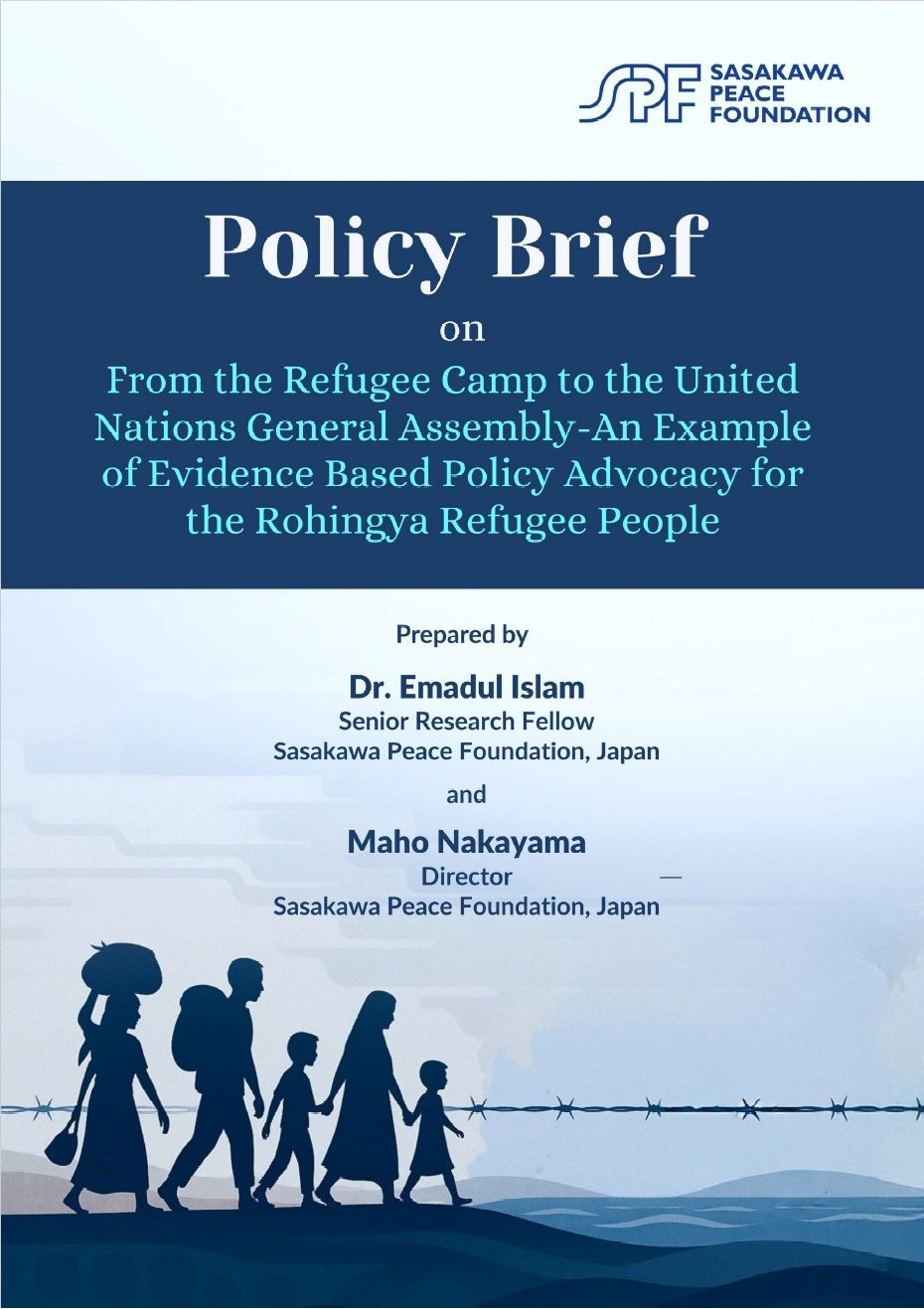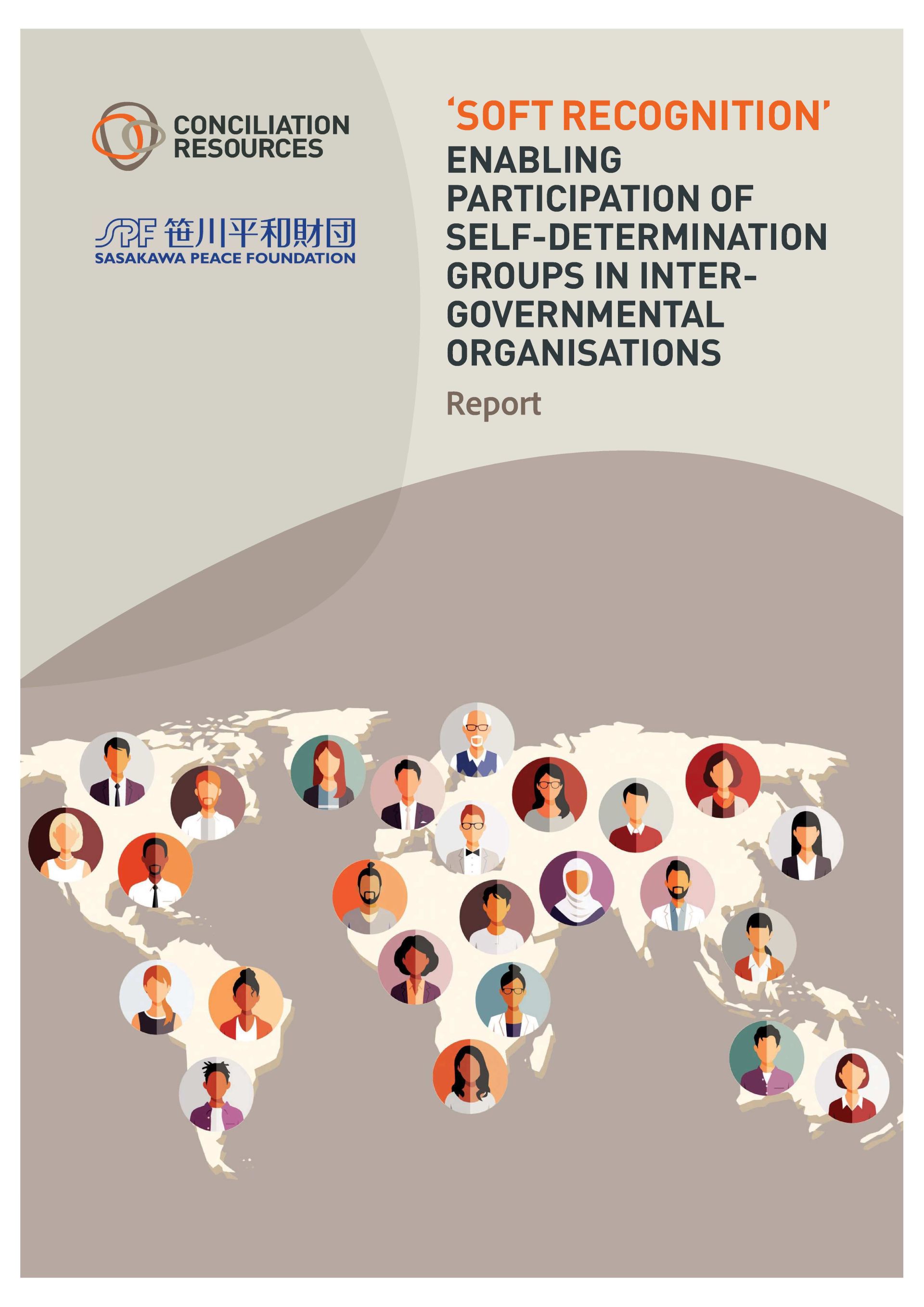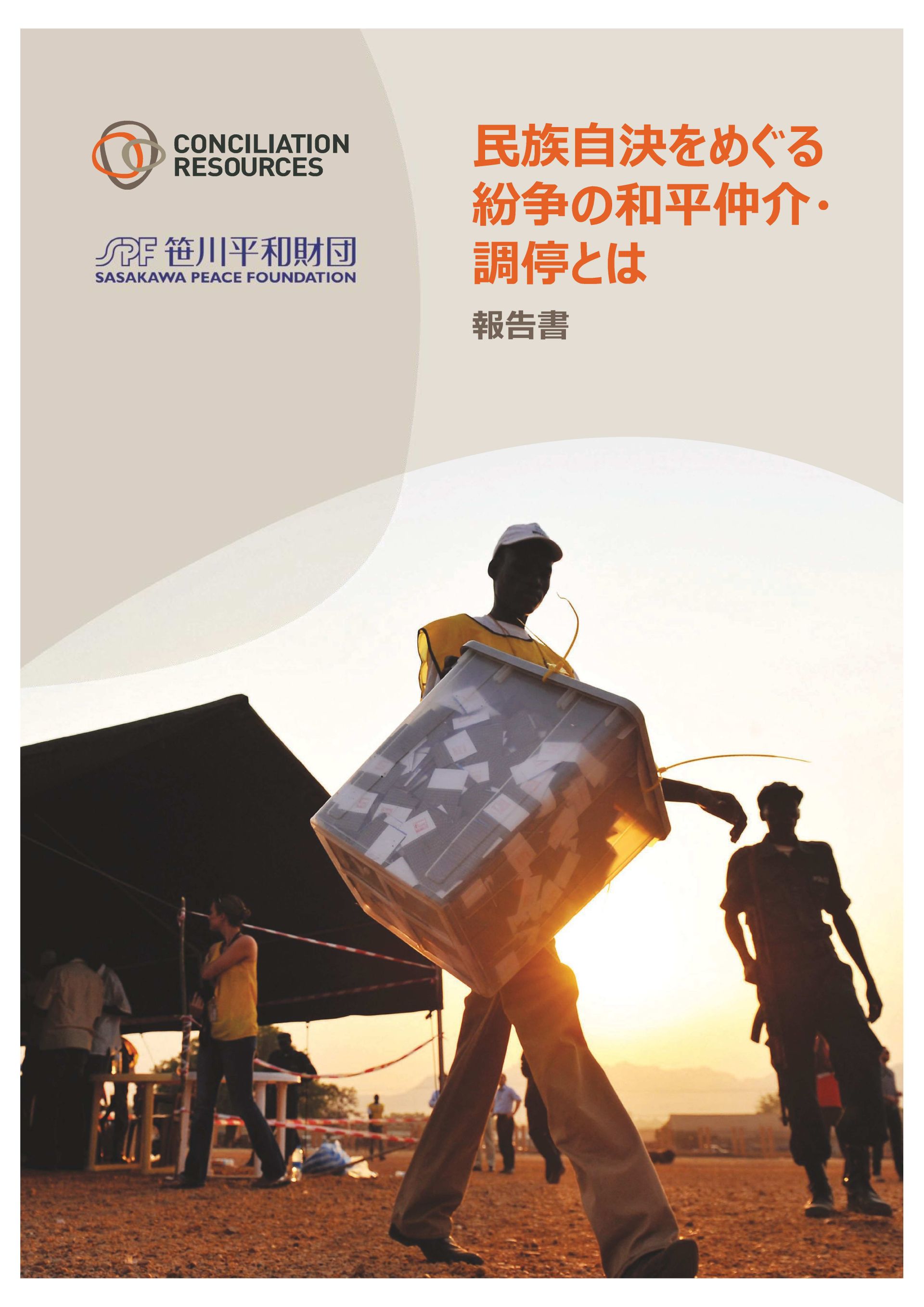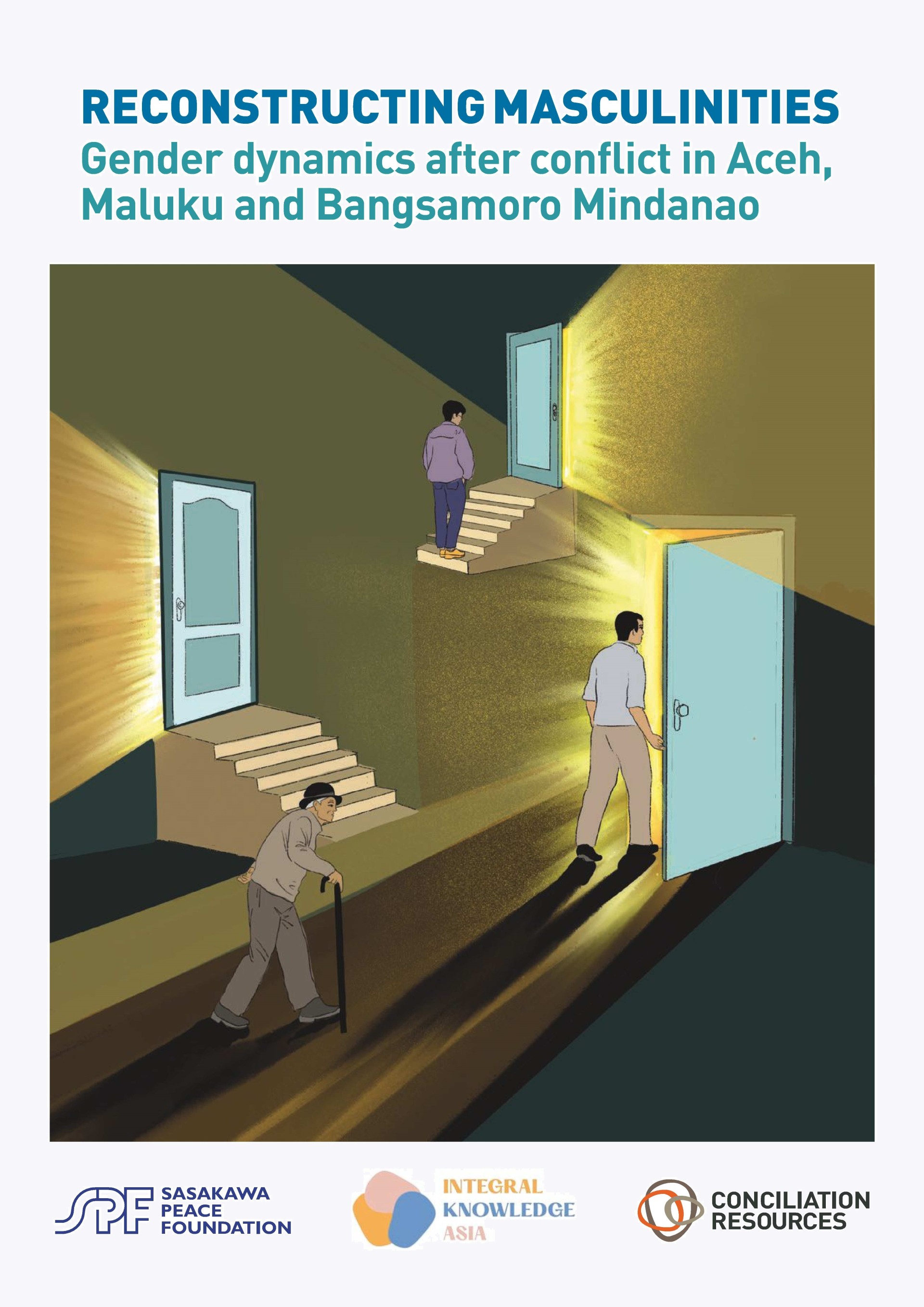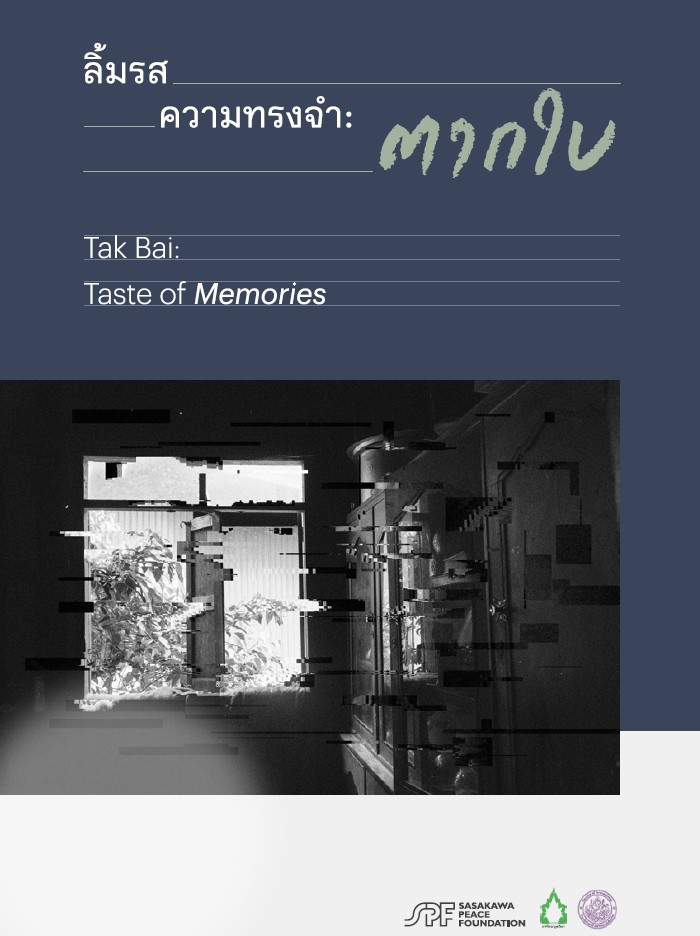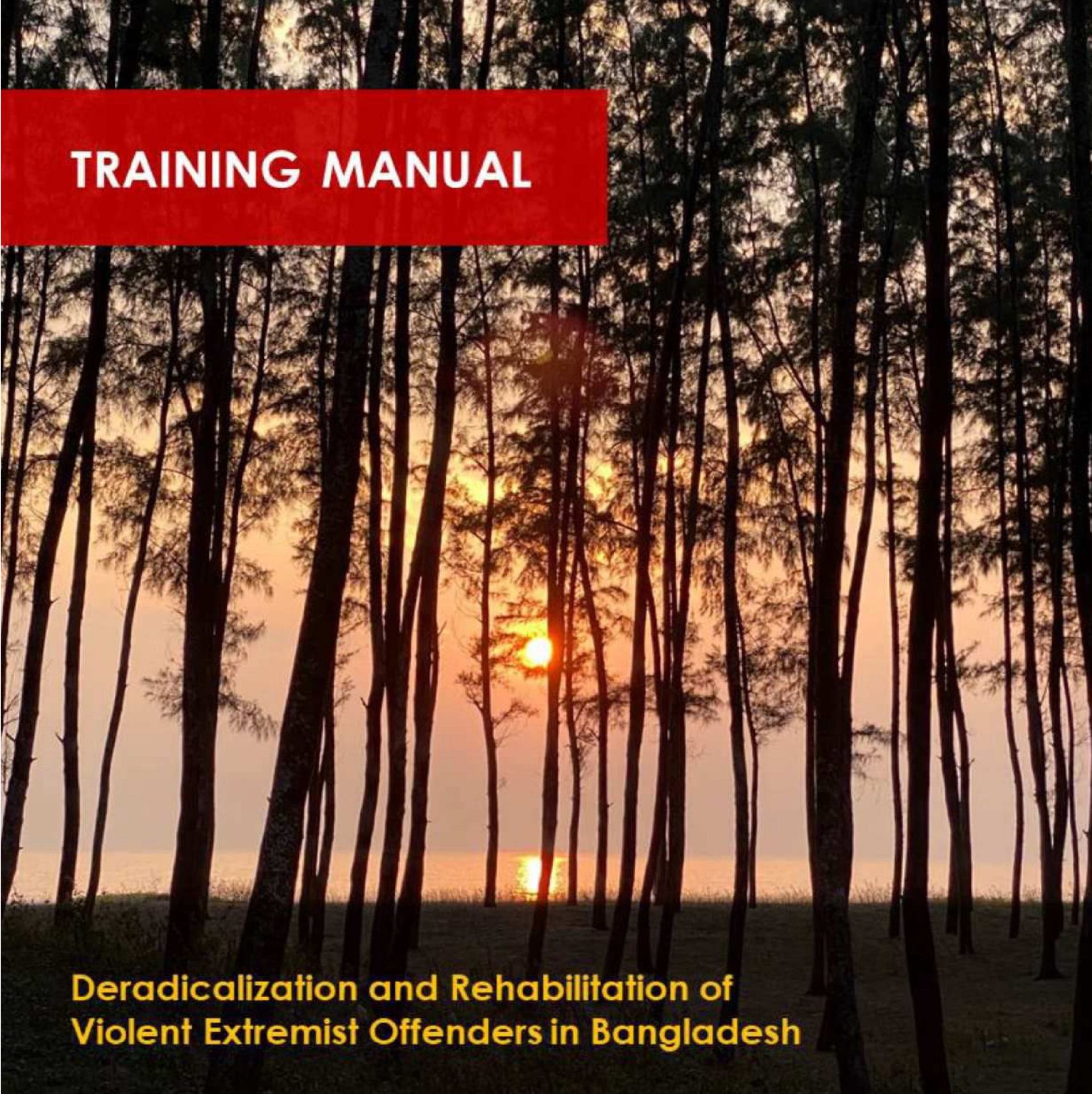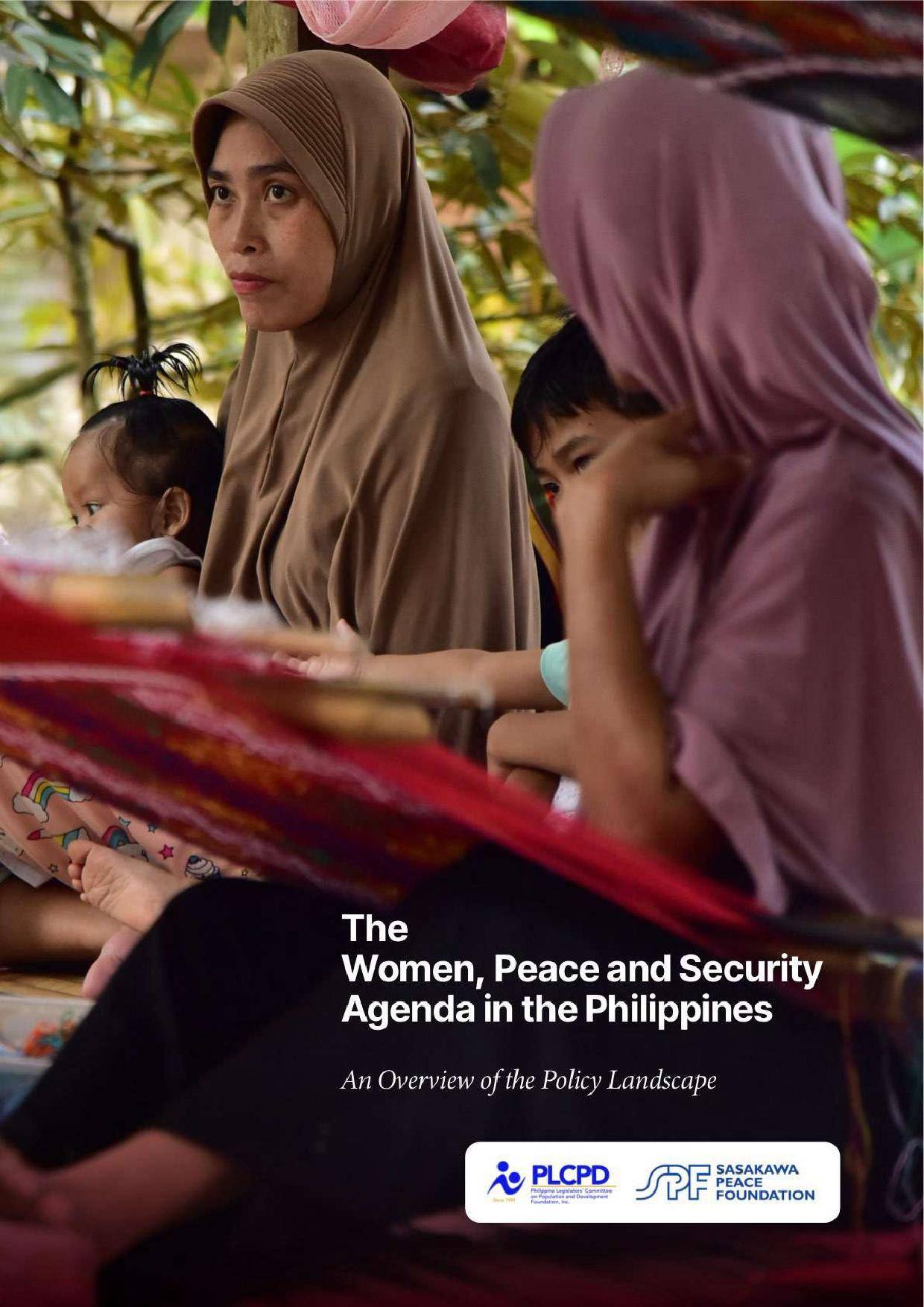
フィリピンにおけるWPS(女性・平和・安全保障)アジェンダに関する報告書のご紹介
第2グループ(平和構築支援担当)では、活動の柱の一つにいわゆるWPS(女性、平和、安全保障)アジェンダの推進を掲げております。この度、PLCPD (Philippine Legislators' Committee on Population and Development)と共に、フィリピンにおけるWPSアジェンダ推進に向けて、政策立案者、研究者、市民社会、教育機関など、幅広いステークホルダーの皆様にご参考として頂くべく、WPSの理念と実践を深く理解するための3本の報告書を作成いたしました。