Projects
事業紹介
Blue Impact Finance Initiative (BIFI)
ブルーインパクトファイナンス・イニシアチブ
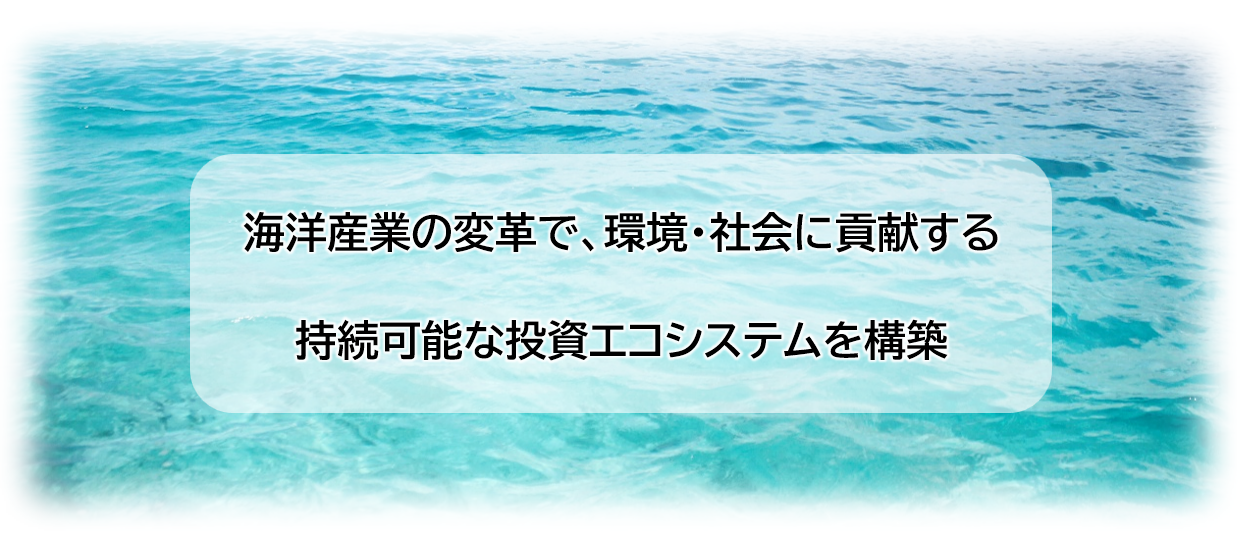
背景・目的
- 海洋問題の社会的課題を解決するための実践や方法がまだ不十分であり、海洋投資評価基準が不足しています。
- 実証例やエビデンスに基づく研究が不足しているため、海洋への影響を考慮した投資プロジェクトが少ないのが現状です。
- 海洋への影響を考慮した投資は、業界横断的な取り組みや金融業界の専門家との公私連携が不足しており、まだプラットフォームが存在していません。
- 2022年度から、社会変革推進財団 (SIIF) と海洋政策研究所 (OPRI) が共同で研究会を開催し、海洋産業における優れた事例や投資メカニズムに関する知見を提供し、より参入しやすい海洋投資環境を促進します。
ブルーインパクトファイナンスとは
インパクト投資とは、財務的リターンと並行して、ポジティブで測定可能な社会的及び環境的インパクトを同時に生み出すことを意図する投資行動を指します。従来、投資は「リスク」と「リターン」という2つの軸により価値判断が下されてきました。これに「インパクト」という第3の軸を取り入れた投資、かつ、事業や活動の成果として生じる社会的・環境的な変化や効果を把握し、社会的なリターンと財務的なリターンの双方を両立させることを意図した投資を、インパクト投資と呼びます。(引用:https://impactinvestment.jp/impact-investing/about.html)
持続可能なブルーエコノミーの実現に向けて、海洋に良いインパクトをもたらす海洋産業—特にスタートアップ、社会的企業、NPOなど—への投資エコシステムを促進するためのフレームワークを構築します。
持続可能なブルーエコノミーの実現に向けて、海洋に良いインパクトをもたらす海洋産業—特にスタートアップ、社会的企業、NPOなど—への投資エコシステムを促進するためのフレームワークを構築します。
インパクト評価手法
海洋投資分野では、インパクト測定の基準が統一されておらず、スタートアップごとに報告能力や意欲にばらつきがあるといった課題が指摘されています。こうした状況を踏まえ、世界経済フォーラム(WEF)は1000 Ocean Startups Coalition(1000 OS)およびSYSTEMIQと連携し、海洋スタートアップ投資における共通のKPIフレームワーク「オーシャン・インパクト・ナビゲーター(OIN)」を開発しました。同フレームワークは、2022年の国連海洋会議において正式に発表されました。
OINは、海洋インパクト・イノベーションの評価と報告を簡素化・統一・強化することを目的としています。2025年からは、日本版OINの監修をOPRIとSIIFが担っています。
OINは、海洋インパクト・イノベーションの評価と報告を簡素化・統一・強化することを目的としています。2025年からは、日本版OINの監修をOPRIとSIIFが担っています。
調査事例
北三陸ファクトリー(株)
農林水産加工物の製造加工・販売;6次化拠点開発の企画運営;水産業に関する技術開発
(同)シーベジタブル
海藻の種苗生産及び、陸上・海面栽培を通じた海藻の生産と販売
株式会社ARK
閉鎖循環式陸上養殖システムの設計・開発・製造及び付帯サービスの開発と提供
(株)ジーオー・ファーム
海洋深層水を活用してカキの完全陸上養殖に取り組む
農林水産加工物の製造加工・販売;6次化拠点開発の企画運営;水産業に関する技術開発
(同)シーベジタブル
海藻の種苗生産及び、陸上・海面栽培を通じた海藻の生産と販売
株式会社ARK
閉鎖循環式陸上養殖システムの設計・開発・製造及び付帯サービスの開発と提供
(株)ジーオー・ファーム
海洋深層水を活用してカキの完全陸上養殖に取り組む
関連情報
- BIFI特設ページ公表 (2025.7.21)
- 1000 Ocean Startups Coalition アドバイザリー委員会に就任 (2025.6.17)
- 「Ocean Impact Navigator」が世界にもたらす変化――KPIフレームワークが海洋×インパクト投資の最前線を築く (2025.4.22)
- オーシャン・インパクト・ナビゲーター(OIN) 日本版公表 (2025.3.7)
- 【開催報告】アジア太平洋地域における最初の「ブルーインパクトファイナンス」に関するワークショップおよび政策対話プラットフォーム (2024.3.1)
出版物
関連リンク
本サイトに掲載されているすべての内容の著作権は当財団および各会社、事例調査担当会社に帰属しております。
本サイトの掲載内容(画像、文章等)の一部及び全てについて、無断で複製、転載、転用、改変等の二次利用を固く禁じます。
本サイトの掲載内容(画像、文章等)の一部及び全てについて、無断で複製、転載、転用、改変等の二次利用を固く禁じます。