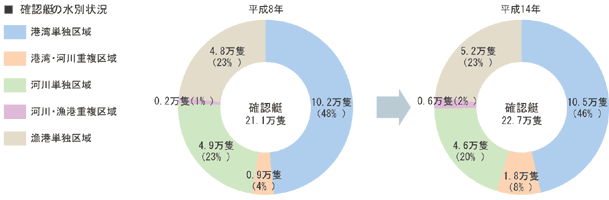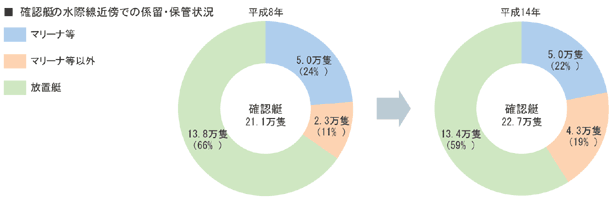Ocean Newsletter
第78号(2003.11.05発行)
- 中部国際空港株式会社 副社長◆山下邦勝
- 国土交通省港湾局環境整備計画室 専門◆酒井敦史
- 木更津市立金田小学校教諭、現在天神山小学校勤務◆今井常夫
木更津市立金田小学校教諭◆磯貝幸子 - ニューズレター編集委員会編集代表者(横浜国立大学国際社会学研究科教授)◆来生 新
「三水域連携による放置艇対策検討委員会」提言 放置艇対策の今後の方向性について
国土交通省港湾局環境整備計画室 専門◆酒井敦史平成14年度に国土交通省港湾局、河川局、水産庁が実施したプレジャーボート全国実態調査の結果、平成8年度の前回調査と比べ、放置艇の割合は減少したものの、依然、多くの放置艇が公共水域に存在しており、公共水域の適正な管理や周辺地域の生活環境を守る上で深刻な問題となっていることが判明した。この調査結果を受け、国土交通省港湾局、河川局、水産庁は共同で「三水域連携による放置艇対策検討委員会」を設置し、このほど放置艇対策の今後の方向性について提言をとりまとめた。
1.はじめに
プレジャーボート需要の増大を背景に港湾・河川・漁港など公共水域に放置されるプレジャーボート、すなわち放置艇(不法係留船等)は、(1)無秩序な艇の流出による公共施設の破損、(2)洪水、高潮時の流水の阻害、艇の流出による公共施設の破損、(3)沈廃船化による油流出等の水質汚染、(4)漁業操業者等他の水域利用者とのトラブル、(5)安全管理の不十分さに起因する事故や遭難、(6)違法駐車、騒音、ゴミ等の不法投棄、景観の悪化等を引き起こし、公共水域の適正な管理や周辺地域の生活環境を守る上で深刻な問題となっています。
プレジャーボートの全国的な実態については、平成8年度に初めて運輸省港湾局、水産庁及び建設省河川局の3省庁合同(当時)で調査を実施し、放置艇がかなりの割合にのぼることが確認されました。そのため、各水域管理者である地方自治体や国により、係留・保管能力の向上と規制を両輪とした様々な対策が進められてきました。
2.平成14年度プレジャーボート全国実態調査の実施

国土交通省港湾局、河川局、水産庁は、平成14年度に6年ぶりとなるプレジャーボート全国実態調査を合同で実施しました。この結果、港湾区域、河川区域、漁港区域及びその近傍の水域や陸域で確認されたプレジャーボートは約22.7万隻(平成8年度約21.1万隻)であり、実に、その約59%(同66%)にあたる約13.4万隻(同約13.8万隻)が本来係留すべきではない場所に不法もしくは無許可で係留された艇(放置艇)であります。また、平成8年度の前回調査と比べ、放置艇の割合は7ポイント減少したものの、依然、多くの放置艇が公共水域に存在していることが明らかになりました。水域別に見ると、河川区域、漁港区域では放置艇が減少しているものの、港湾区域では増加している結果となっています。(図参照 )
3.三水域連携による放置艇対策に関する提言
前記の調査結果を受け、国土交通省港湾局、河川局、水産庁は共同で「三水域連携による放置艇対策検討委員会(来生新委員長:横浜国立大学教授)」を設置し、放置艇問題に造詣の深い法律分野、工学分野の専門家、またジャーナリスト、舟艇利用者、水域管理者の方々に、様々な立場から見た放置艇対策の現状や問題点、及び今後の対策の方向性について議論して頂きました。
この8月に、検討結果が提言としてとりまとめられましたので、要点を紹介致します。
(1)放置艇対策の目指すべき方向
今後は、これまで放置艇対策として行われてきた各種施策を複合的に組み合わせることにより、総合的かつ効果的な対策を実施していくことが重要である。また係留・保管場所の義務化については、保管能力の向上を踏まえつつ、引き続きその実現に向けて検討を進める必要がある。
(2)地域の問題は地域の枠組みで解決する仕組みづくり
港湾・河川・漁港の各水域管理者が水域の枠を超え連携することはもとより、地方公共団体、民間マリーナ事業者、漁業関係者等地域の関係者との連携体制を確立し、地域の実情に即した対策を一体的に取り組む必要がある。
(3)連携による短期集中的な一斉対策の実施
社会問題的な性質をもつ放置艇対策を進めるためには、一般市民の放置艇に関する問題意識をより喚起する必要がある。それには水域管理者が連携し、短期集中的な一斉対策を実施することにより、行政側の積極的な姿勢を示すことが必要である。
(4)係留・保管能力の向上に向けた積極的な取り組み
依然として圧倒的に係留・保管能力が不足していることから、マリーナ等の恒久的な係留・保管施設の整備・支援を引き続き促進すると同時に、一定の条件を満たす水域を暫定的に活用した係留・保管施設やPFI※など民間活力を活用した施設整備、あるいは、自宅等の内陸保管の推進など、積極的に係留・保管能力の向上を図っていく必要がある。
(5)適正かつ効率的な管理運営の実施
受益者負担に基づく公共等係留・保管施設の料金設定や、利用者団体等による施設管理・運営推進、および利用料金未払い利用者に対する継続的な取り締まりの実施等、適正かつ効率的な管理運営を行っていくことが必要である。
5.今後の取り組みに向けて
現在、行政だけでなく地元関係団体等が協力し、各地域の状況を踏まえた対策を講じることにより、放置艇対策に多大な効果を挙げている地域があります。今後、前記提言を受けて、港湾・漁港・河川の各水域管理者が一層連携を図りつつ、係留・保管能力の向上と規制措置を両輪とした放置艇対策を早急に進めるとともに、プレジャーボート活動による地域振興を調和・両立させながら、豊かな国民生活の実現を目指していきます。(了)
※ PFI :民間資金等活用事業(Private FinanceInitiative)。公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間資金、経営能力及び技術能力を活用して行う手法。
【参照】プレスリリース 「平成14年度プレジャーボート全国実態調査結果」及び「三水域連携による放置艇対策検討委員会提言」について:http://www.jfa.maff.go.jp/release/15.09.10.1.pdf
第78号(2003.11.05発行)のその他の記事
- 中部国際空港"セントレア"の現況と運営体制 ~セントレアは「愛・地球博」の空の玄関です~ 中部国際空港(株) 副社長◆山下邦勝
- 「三水域連携による放置艇対策検討委員会」提言 放置艇対策の今後の方向性について 国土交通省港湾局環境整備計画室 専門◆酒井敦史
-
総合的な学習の時間に干潟を学ぶ ~「遊ぼう、知ろう、伝えよう」ぼくら干潟探検隊~
木更津市立金田小学校教諭、現在天神山小学校勤務◆今井常夫
木更津市立金田小学校教諭◆磯貝幸子 - インフォメーション 呉市海事博物館と瀬棚洋上風車の名称が決定
- 編集後記 ニューズレター編集代表(横浜国立大学国際社会学研究科教授)◆来生 新