Ocean Newsletter
第70号(2003.07.05発行)
- 瀬戸内海研究会議会長、香川大学元学長・名誉教授◆岡市友利
- 呉大学社会情報学部教授(海上保安大学校名誉教授)◆廣瀬 肇
- イルカ&クジラ・アクション・ネットワーク◆倉澤七生
- ニューズレター編集委員会編集代表者(横浜国立大学国際社会学研究科教授)◆来生 新
サハリンの石油開発によって脅かされるクジラ
イルカ&クジラ・アクション・ネットワーク◆倉澤七生およそ100頭ほどの群れしか生存していないとみられるコククジラのアジア系個体群が、いま危機に瀕している。彼らの移動ルートであるサハリン島周辺では、大陸棚に埋蔵されている海底油田の開発が始まっており、自然環境の変化がクジラにどのような影響を与えるか懸念される。開発にあたるサハリン社は環境への影響はないと報告しているが、その保証は全くない。
絶滅に瀕するコククジラのアジア系個体群
コククジラは体長13mあまり、北半球に生息するヒゲクジラである。口内に140~180枚のクジラヒゲをもち、浅い海の底の泥の中にすむ小さな底生動物を濾しとって食べている。頭部にびっしりとフジツボやクジラジラミをつけた彼らの姿は、10万年前の化石と変わらないという。
かつてコククジラは、アメリカで「Devil Fish」と呼ばれた。母クジラが子どもを守るために捕鯨船に襲いかかったからだそうだが、クジラにすれば不当ないいがかりではある。
沿岸性で泳ぎも遅いために古くから捕鯨の対象となり、北大西洋の群れはすでに絶滅、現存するのは、シベリアからメキシコを行き来している北太平洋のカリフォルニア系(東側)個体群とオホーツク海から南シナ海を行き来するアジア系(西側)個体群の2つである。
東側のカリフォルニア系個体群は、捕鯨のために20世紀半ばにはその数は2,000頭まで減少した。アメリカ合衆国は、コククジラの個体数回復に多大の力をそそぎ、90年代始めには2万頭近くに回復、1994年に絶滅危惧種の指定からはずされ、復活を果たした。
一方、西側のアジア系個体群は、16世紀から日本沿岸で網取り式捕鯨によって捕獲されてきた。その後、19世紀末に近代捕鯨導入とともに、日本、ロシアなどによる朝鮮半島沿岸での捕獲が増加してもともと多くなかった群れの急激な減少をもたらし、1970年代初頭には絶滅したものと考えられていた。奇跡的に1977年にオホーツク海域で100頭ほどの群れが見つかったが、現在はこの群れが西側のアジア系個体群のすべてだろうと考えられている。
1995年、旧ソ連崩壊後にロシアとアメリカによる本格的な合同調査が開始され、個体群の回遊経路や索餌海域などが次第に明らかになってきている。100頭前後の個体数のうち繁殖可能なメスは20頭ほどにすぎないという研究者もいる。大型クジラの中で、もっとも絶滅に近いのがアジア系個体群なのだ。
危惧されるサハリン開発の影響
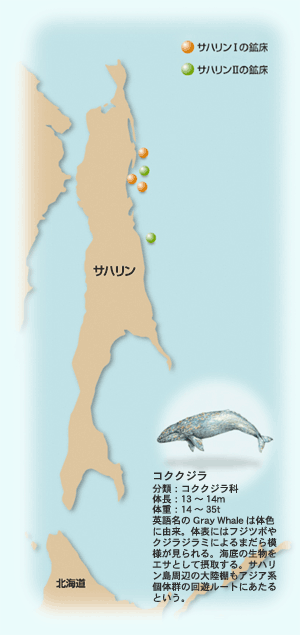
このクジラたちに危機が迫っている。それは、アジア系個体群の移動ルートであるサハリン島周辺の大陸棚に埋蔵されている海底油田の開発である。
1994年、イギリスのロイヤル・ダッチ・シェル社と日本の三菱商事、三井物産がサハリン・エネジー・インベスティメント(以下「サ社」)というロシア現地会社を組織し、サハリンIIと呼ばれる開発プロジェクトを開始した。現在、サハリン島周辺ではサハリン・プロジェクトと呼ばれる油田開発がIからVIIIまで計画され、そのうちのサハリンIIは島の北東部における石油・ガス開発で、1998年には第1期工事として掘削プラットフォーム1基がピルトゥン湾沖に建設された。現在は基地から貯蔵用タンカーに原油を送り、海が氷結しない夏場だけ積み出しを行っているが、通年供給をめざすサ社は、サハリン最南端まで島を縦断するおよそ800kmの原油と天然ガスパイプラインを埋め込む第二期工事を計画中だ。この掘削プラットフォームの作られているピルトゥン湾付近は、現在知られているアジア系個体群の唯一の索餌海域である。
このクジラの調査に1995年から携わってきたアメリカ海洋大気局(NOAA)のロバート・ブラウネル博士は、サハリンIプロジェクトの際の振動テストによって、コククジラが索餌海域を忌避したと報告した。クジラ類は音響の動物である。海底油田の掘削、そのための振動テスト、船の頻繁な行き来やヘリコプターなどの騒音は、クジラの行動様式を変えてしまう。この時は、振動テストをやめた後、すぐにクジラたちがこの海域に戻ったという。
最近、クジラの栄養状態が悪くなっており、子クジラの死亡率が増加、プロジェクトとの関連も懸念されている。
音だけではなく、廃棄物の海洋投棄も沿岸海域の底生動物を食べるコククジラにとっては問題だ。アラスカなど環境基準の厳しい所では、掘削の際の廃棄物はすべて埋め戻しが要求されるが、サハリンでは、環境保護団体などによると掘削の際の廃棄物が投棄されている可能性があるという。サ社の開発計画に関する環境影響評価では、過去3年間の調査の結果、環境への影響はないと記されているが、結論を出すのは早すぎるだろう。
最近とみに問題となっている油流出事故も懸念材料である。すでに1999年に起きた油もれによってニシンが大量死したと考える地元漁業者もいるが、サ社は因果関係を否定し、また油流出事故に関しては監視船を配置して緊急対策を取る用意があるので、大きな事故でも2~3日で油は除去できるという。それは本当に確かなのだろうか。
サ社は昨年末、コククジラについての107ページにおよぶ「保護プラン」を発表した。報告書は、「コククジラへの影響は現状では軽微」としながら、1:石油基地などの施設の存在が与える影響、2:振動テストなど音の与える影響、3:廃棄物による影響、を計測している。しかし、「はじめに開発ありき」の方針で作られた基準が守られれば保護が可能かといえば保証は全くない。ロシア政府はこの2月にサハリン北東部に開発制限海域を設ける予定であると発表した。しかし、ロシアにとっても石油開発は大きな収入源であるため、その実効性には疑問がある。当事者のはずのサ社は、「直接聞いていない」といっている。
20世紀というのは人類にとっては進歩の時代であったかもしれないが、一方で物凄いスピードで種の絶滅が起こった世紀でもあった。残念ながら、新しい世紀はまだその影を引きずっているし、よほど意識してかからなければその速度は増すばかりなのかもしれない。ここでは、人類の誇る科学技術も知恵も、今のところはあまり役には立っていないように見える。
コククジラ問題は、私たちがどのような未来を求め、そのためにどのような選択をするのかを問いかける。たとえば、サハリンII開発には国際協力銀行の融資が不可欠だが、その原資の一部は私たちの郵便貯金や厚生年金である。コククジラ絶滅の道のりに、私たちに責任がないわけではない。(了)
<参考>
・「日本の希少な野生水生生物に関する基礎資料」(社)日本水産資源保護協会
・「クジラ・イルカ大図鑑」アンソニー・マーティン編著/粕谷俊雄 監修
・「クジラとイルカの図鑑」マーク・カーワディーン著
・Western Gray WhaleProtection Plan : A Framework forMonitoring and Michigation MeasuresRelated to Sakhalin Energy Oil andGas Operations on the Northeast Coastof Sakhalin island, Russia SakhalinEergy Investiment Company Limited
・Report of the ScienceCommittee, London 2001 IWC ScienceCommittee・サハリンIIプロジェクトの問題点など;国際環境NGOFoE Japan(Friends of theEarth)のホームページ( http://www.FoEJapan.org)
第70号(2003.07.05発行)のその他の記事
- 瀬戸内海の環境保全について 瀬戸内海研究会議会長、香川大学元学長・名誉教授◆岡市友利
- 瀬戸内海の海砂利採取規制の実情と今後の方向 呉大学社会情報学部教授(海上保安大学校名誉教授)◆廣瀬 肇
- サハリンの石油開発によって脅かされるクジラ イルカ&クジラ・アクション・ネットワーク◆倉澤七生
- インフォメーション「わが国200海里水域の海洋管理ネットワーク構築に関する研究」(提言)
- 編集後記 ニューズレター編集代表(横浜国立大学国際社会学研究科教授)◆来生 新
