Ocean Newsletter
第68号(2003.06.05発行)
- 岡山大学経済学部助教授◆津守貴之
- 社団法人 海洋水産システム協会 専務理事◆長島徳雄
- 慶應義塾普通部教諭、慶應義塾大学教養研究センター所員、フェリス女学院大学国際交流学部講師◆太田 弘
- ニューズレター編集委員会編集代表者(横浜国立大学国際社会学研究科教授)◆来生 新
「スーパー中枢港湾」政策―可能性と今後の課題―
岡山大学経済学部助教授◆津守貴之日本の主要コンテナ港湾の「国際競争力の回復」を目的として、国土交通省が打ち出した「スーパー中枢港湾」政策は、可能性実現のハードルが多種多様に存在している。自治体、業界、省庁の枠を越えて日本のコンテナ物流全体の仕組みを変える突破口になりえるかどうかが、今問われている。
日本の主要コンテナ港湾の「国際競争力の低下」が論じられはじめて久しい。この問題は大きく分けて相互に関連する3つの要因によって生じている。即ち、(1)日本の製造業の空洞化=東アジア域内における日本の貨物需要シェアの低下、(2)日本の物流非効率性=東アジア主要港と比較した日本の主要港のコスト・サービス面での競争力の低下、(3)日本の政策ミス=コンテナ施設の過剰整備に見られる日本の港湾政策の方向のまずさである。このような状況の中で、日本の主要コンテナ港湾の「国際競争力の回復」を目的として国土交通省(主に港湾局)によって打ち出されたものが「スーパー中枢港湾」政策である。そこで本稿では「スーパー中枢港湾」の可能性と課題を整理することとしたい。
「スーパー中枢港湾」政策とは
「スーパー中枢港湾」は「国際海上コンテナ輸送における構造改革モデル港湾」として概略次の特徴を持つものとされている。
1) 特定のコンテナターミナルを「わが国コンテナ物流のコスト・サービスを向上させるための先導的・実験的な試みの場」として選定し、そこにおいて「官民一体、ソフト&ハード一体の特例的な施策の導入」を行う。
2) コスト・サービスの向上をはかるために「コンテナターミナルの整備・管理運営方式やコンテナ物流システムの改革を推進」する。
具体的には、
- 「港湾間の広域的な連携を促進して」コンテナターミナルの集約化を進め、それによって「スーパー中枢」に選定されたターミナルの稼働率の向上=コンテナ1本当たりコストの削減を達成する。
- 集約化された大量貨物を円滑に取り扱えるように、-15m以上の大水深岸壁を持ち、岸壁延長が約1km(連続3バース)の「高規格」ターミナルを整備する。
- 港湾の24時間365(364日)フルオープン化と港湾地区における貨物滞留時間の短縮を進める。
- 上記の効率化とサービス向上を実際に担うターミナル・オペレータを育成し、当該ターミナルにおいて荷主のサプライチェーン・マネジメントを受託するなどの様々な物流業務を行うとともに、トランシップ貨物も合わせて取り扱う。
- 「スーパー中枢港湾」選定作業は、国交省が概略上記4つの項目を選定基準として示した上で、港湾管理者である各地方自治体に「スーパー中枢港湾」への立候補および「スーパー中枢港湾」形成のための施策の立案・実行を促すというものである。
期待される、コンテナ物流の仕組み全体の再検討
「スーパー中枢港湾」政策の可能性とは日本のコンテナ物流の仕組み全体を再検討する突破口となりえる点であろう。具体的には、
- コンテナ港湾配置政策の「転換」――90年代以降の日本の港湾政策は港湾機能の地方分散を基本方針としてきた。「スーパー中枢港湾」政策はコンテナ港湾の拠点集約化によって国内ハブ機能を確保するというものであり、従来方針の大転換になる可能性がある。
- 港湾経営のあり方の再検討――日本の港湾経営は従来、各港それぞれが単体で行ってきた。また港湾にかかわる諸業務(荷役や保管、流通加工等だけでなく通関、動植物検疫等)がそれぞれの所管官庁ごとに縦割りで区切られ、全体で対応するということがほとんどなかった。「スーパー中枢港湾」政策は、(1)の点との関連では、港湾間連携の道を開くものであり、また関連官庁を横断する一元管理実現(およびそれをもとにした港湾諸手続きのシングル・ウィンドウ化実現)の可能性を持つものである。さらには本格的なコンテナターミナル・オペレータの出現を促すものでもある。
- 日本の物流全体の仕組みの再検討――コンテナ物流とはDoorto Door 輸送を基本としており、したがって海陸一貫物流の仕組みである。「スーパー中枢港湾」政策は、荷主のニーズに対応した形で、海上から港湾、内陸までを含めた日本の物流全体の再検討を促しえるものである。
「スーパー中枢港湾」政策における課題
もとより集約化が常にメリットをもたらすわけではない。たとえば港湾物流の効率化は必然的に関連事業者の転廃業およびそこで働く労働者の失業をもたらす。また密輸、密航、動植物検疫等の安全性の低下をもたらす可能性もある。これらの問題に対しては最低限のセーフティネット、たとえば円滑な転業・転職の仕組みや貨物情報管理・検査体制の強化等が必要とされるだろう。
しかしここではそれよりも大きな問題として「スーパー中枢港湾」政策の可能性とコインの裏表を成す可能性実現のハードルと課題を見ておこう。それは下記のものである。
(1)単一港湾内での港湾関連業者間調整の困難さ、(2)港湾管理者である地方自治体間の調整の困難さ、(3)港湾の一元管理に向けた各省庁間の調整の困難さ、(4)業界間の調整の困難さ、(5)中央と地方の連携の困難さ。
「スーパー中枢港湾」政策は自治体、業界、省庁の枠を越えて日本のコンテナ物流全体の仕組みを変える突破口になりえるものだけに、可能性実現のハードルが多種多様なものとなっている。したがってハードルも多くそのクリアの時間も当然かかる。これらのことを念頭に置いたうえで、現時点において「スーパー中枢港湾」政策に関する最大の課題を考えるならば、それは「何を目的とした政策なのか」をより明確にすることであろう。図のように段階を追って可能性を追求していくプロセスの出発点として今回の試みがあるのか、それとも図の第1段階の「港湾内でのターミナル集約化」が目的とされるものなのか。「スーパー中枢港湾」の別名は「国際海上コンテナ輸送における構造改革モデル港湾」であり、「先導的、実験的試み」とされている。この表現は上記の2つの政策目的のどちらにも対応している。「スーパー中枢港湾」政策の目的が「港湾内でのターミナル集約化」に矮小化されるのであればそれほど騒ぐ必要もない。それは旧運輸省港湾局時代からの仕事をアレンジしたターミナルの大規模メンテナンスにすぎない。「スーパー中枢港湾」の選定作業の間だけでなく、その後についても、国交省に対しては政策ヴィジョンと目的の明確化(および可能であればその実現の強い意志の表明)、地方自治体に関しては主体的な選択と集中による地方発の効果的な広域連携を期待したい。(了)
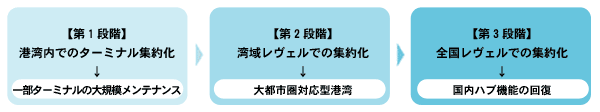
第68号(2003.06.05発行)のその他の記事
- 「スーパー中枢港湾」政策―可能性と今後の課題― 岡山大学経済学部助教授◆津守貴之
- 漁船漁業の構造改革 (社)海洋水産システム協会 専務理事◆長島徳雄
- 学校教育での「海図」の利用 ~海図で学ぶ海の地理・地誌学~ 慶應義塾普通部教諭、慶應義塾大学教養研究センター所員、フェリス女学院大学国際交流学部講師◆太田 弘
- インフォメーション 北朝鮮の工作船と搭載武器類を一般公開
- 編集後記 ニューズレター編集代表(横浜国立大学国際社会学研究科教授)◆来生 新
