Ocean Newsletter
第43号(2002.05.20発行)
- 防衛大学校国際関係学科教授◆真山 全
- JETROロンドン事務所Japan Ship Centre所長◆松村純一
- 独立行政法人 水産総合研究センター 瀬戸内海区水産研究所 研究室長◆永井達樹
- インフォメーション
- ニューズレター編集委員会編集代表者 ((社)海洋産業研究会常務理事)◆中原裕幸
クラゲの海からイワシの海へ
~瀬戸内海における漁業資源の回復をめざして~
独立行政法人 水産総合研究センター 瀬戸内海区水産研究所 研究室長◆永井達樹陸からの栄養塩の流入が過多になると、珪藻類に代わり非珪藻類の植物プランクトンやそれを餌とする小型動物プランクトンが増え、さらにそれらを餌として選り好みしないクラゲが増える。瀬戸内海をはじめ世界の海はこの問題に直面している。クラゲの海では魚類の生産が縮小する。富栄養化を改善し、瀬戸内海を「イワシの海」に回復させる努力が必要である。
陸上から水域に窒素や燐などの栄養塩が流入すると様々な生物の量が増える。これを富栄養化という。栄養塩の流入が過多になると、珪藻類に代わり非珪藻類の植物プランクトンやそれを餌とする小型動物プランクトンが増え、さらにそれらを餌として選り好みしないクラゲが増える。瀬戸内海をはじめ世界の海は今まさにこの問題に直面している。
漁獲量の経年推移から瀬戸内海を富栄養化以前(1960年以前)、富栄養化時代(1960~1990年まで)、富栄養化が過ぎた時代(1990年以降)に区分すると、それぞれ生物の種類が豊かであったり、表層の生物量が多かったり、生態系が歪んだ時代と言える。各時代に象徴的な生物種として、マダイ、カタクチイワシ、クラゲ類をとりあげ、魚類では資源量を、クラゲ類では出現頻度を調べ、種類別の最大値を1として経年推移を図にした。
これによると、マダイ豊度は1936年が最大で、1980年代には1/6に減少した。カタクチイワシは変動しながら徐々に増加し、1985年に最大となり、その後急速に減少し、1990年代前半に約1/3の水準になった。クラゲ類は1980年代に周防灘・豊後水道及び紀伊水道など入り口付近に出現し、1990年代後半に瀬戸内海全体に出現するようになった。
前述した各時代は「マダイの海」、「イワシの海」、「クラゲの海」と象徴的に呼べよう。クラゲの海では珪藻から主要で大型の動物プランクトンであるカイアシ類を経る魚類生産が縮小し、クラゲや利用されずに枯死するプランクトンを分解するバクテリアにいくエネルギーが太くなる。イワシの海ではイワシを捕食するサワラやトラフグが多かった。サワラやトラフグはカタクチイワシに比べ近年減少の程度が大きい。サワラでは1973年に揚網機が導入され、1980年頃から秋にサゴシ(0歳及び1歳)を漁獲するようになり、1985年には流し網の材質にテグスが使われ、羅網性能が高まり、かつ網目が小型化したので、漁獲が増加した。このように漁具・漁法の急速な改善によって、漁船の実質的な漁獲能力は格段に向上し、全体の漁獲能力が過剰となった。
瀬戸内海では水産庁の指導の下に関係府県が2002年からサワラを対象に資源回復計画に取り組む。サワラとカタクチイワシ資源は1990年頃までともに減少している。その後、サワラでは漁獲の影響が強く、さらに資源は減少した。著者はサワラの資源回復が1990年頃のカタクチイワシの資源水準に対応した最大時の約1/3まで可能とみて、回復のための管理方策を提言した。
瀬戸内海における既存の漁業は先取り・とり過ぎ体質をもつ。これは小さいうちにとり過ぎる成長乱獲や親をとり過ぎて生まれてくる仔を減らす加入乱獲の原因になっている。今後は、(1)資源管理型漁業を推進し個々の魚種の再生産を悪化させない、(2)富栄養化を改善し瀬戸内海を「イワシの海」に回復させる、(3)漁業被害をもたらす異常斃死や大量発生などの海の異変に注意を払い、これを少なくする努力が必要である。(了)
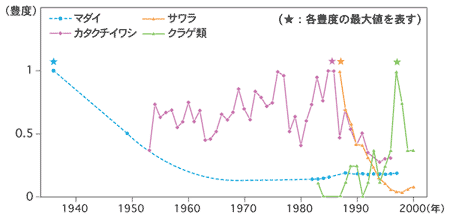
第43号(2002.05.20発行)のその他の記事
- 奄美大島沖不審船に対する威嚇射撃 防衛大学校国際関係学科教授◆真山 全
- 望まれる、わが国の海上テロ対策 JETROロンドン事務所Japan Ship Centre所長◆松村純一
- 読者からの投稿 クラゲの海からイワシの海へ ~瀬戸内海における漁業資源の回復をめざして~ (独)水産総合研究センター 瀬戸内海区水産研究所 研究室長◆永井達樹
- インフォメーション「TAJIMA」号事件、解決の行方は? ~公海航行中のパナマ船で日本人船員行方不明~
- 編集後記 ニューズレター編集代表 ((社)海洋産業研究会常務理事)◆中原裕幸
