Ocean Newsletter
第31号(2001.11.20発行)
- 兵庫県立水産試験場 増殖部長◆眞鍋武彦
- 国土交通省 国土技術政策総合研究所 研究総務官◆宇多高明
- 水産庁遠洋課 捕鯨班長◆森下丈二
- インフォメーション
- ニューズレター編集委員会編集代表者 (横浜国立大学国際社会学研究科教授)◆来生 新
東京MOU事務局が「旗国」ブラックリストを公表
インフォメーション
2001-2002年のターゲット
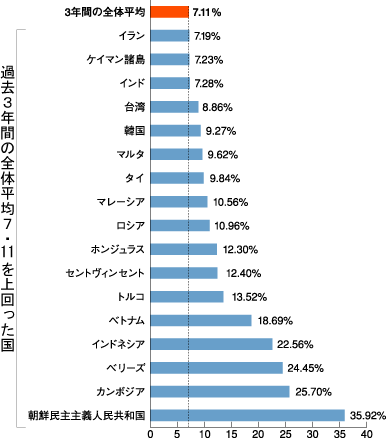
図表は、入港する外国籍船を対象に安全性をチェック(ポートステートコントロールという)しようという政府間の国際組織「東京MOU事務局」が、各国による検査の結果、重大な欠陥がみとめられたため「航行停止処分」とされた船を「船籍国」別に集計したもので、検査された船籍国の船の隻数との比で示される「航行停止処分率」が過去三年間の平均値でみて全体の平均値(7.11%)を上回った「旗国(船尾に掲げる旗の国)」の一覧のことで「旗国ブラックリスト」とも言われる。2001年/2002年には、朝鮮民主主義人民共和国、カンボジア、ベリーズ、インドネシア、ベトナム、トルコ、セントヴィンセント、ホンジュラス、ロシア、マレーシア、タイ、マルタ、韓国、台湾、インド、ケイマン諸島、イランの17カ国の船籍を持つ船舶は優先的にチェックの対象とされる。相変わらず新興海運国、便宜置籍国の多くは海事監督行政に失敗していることを窺わせる結果となった。
また、同時に発表された統計によれば2000年における東京MOUメンバー17カ国による検査は、総検査件数16,034件(域内航行船舶総数に対する検査率は65%)、この内、欠陥(条約不適合事項)のあった船舶数は10,628隻(欠陥総数58,435件)で欠陥は是正された。さらに、この内重大な欠陥があったため「航行停止処分」とされた船舶総数は1,101隻(検査件数に対する処分率は6.87%)であった。前年(1999年)と比べると、他のいずれの数値も前年を上回る結果となる中で、航行停止処分率(1999年は7.18%)は1999年以来低下している。
ポートステートコントロールとその仕組み
船舶の安全な運航と海洋汚染防止については多くの条約が発効しており、各国は条約に対応する国内法に基づき、「自国籍船舶」の安全管理を担保することが伝統とされてきた。しかしながら、船員や検査の制度等を必ずしも十分確立し得ていない新興海運国の台頭により、「アモコカディス号」座礁など大事故を含め全損事故件数が急増した。
これに対する策はただ二つ、一つはこうした新興海運国の海運管理能力の適正化を待つ、残る一つは、自国に寄港する劣悪な「外国籍船」をチェックする方法である。船籍国すなわち「旗国(Flag State)」において適正な検査・監督が行なわれないなら、「入港国(Port State)」において実施することにより、条約・規則の船舶への履行を補完しようというのが、ポートステートコントロールのねらいである。
ポートステートコントロールの地域協力体制
船舶の運航は国際的であることから、ポートステートコントロールは一カ国のみが実施/強化しても効果は限定されるので、検査情報の交換や手続き等について地域ぐるみで協力して実施することが重要である。ヨーロッパでは、1982年にいち早く「パリMOU」(Memorandum of Understanding : 覚書)と呼ばれる協力体制ができたが、10年遅れて世界の他の海域での協力体制が形成されている。
アジア太平洋地域の諸国のポートステートコントロール協力体制は、「東京MOU」のもとに1994年から活動を開始した。事務局は日本に置かれている。
(岡田光豊/(財)東京エムオウユウ事務局 専務理事)
● 東京MOU事務局ホームページ
http://www.tokyo-mou.org
第31号(2001.11.20発行)のその他の記事
- 新しい水利用の概念「漁業用水」 ~漁業の持続的発展をめざして~ 兵庫県立水産試験場 増殖部長◆眞鍋武彦
- 古老曰く「昔砂浜は広かった」これはまことか? 国土交通省 国土技術政策総合研究所 研究総務官◆宇多高明
- 読者からの投稿 新一次産業としての漁業の再生・確立 水産庁遠洋課 捕鯨班長◆森下丈二
- インフォメーション 東京MOU事務局が「旗国」ブラックリストを公表
- 編集後記 ニューズレター編集代表 (横浜国立大学国際社会学研究科教授)◆来生 新
