Ocean Newsletter
第294号(2012.11.05発行)
- 早稲田大学名誉教授、海洋政策研究財団特別研究員◆林 司宣
- 独立行政法人海洋研究開発機構 理事長◆平 朝彦
- 琉球大学工学部 電気電子工学科 教授◆藤井智史
- ニューズレター編集代表((独)海洋研究開発機構上席研究員/東京大学名誉教授)◆山形俊男
離島と沿岸域の総合的管理に海洋レーダネットワークの整備を
[KEYWORDS] 沿岸モニタリング/レーダネットワーク/観測インフラ琉球大学工学部 電気電子工学科 教授◆藤井智史
海表面の流速や波浪などを長期連続観測可能な海洋レーダの利用とネットワーク化が諸外国で進みつつある。海洋レーダの研究開発とITUでの国際標準化活動を進めてきた日本においても、防災、環境保全が注目される沿岸域や観測自体が自由にできない国境周辺海域のモニタリングには有用な観測技術であり、観測インフラとして展開していく時期に来ている。
海洋レーダによる沿岸モニタリングと周波数分配
海洋レーダは、電波の海面での散乱波をスペクトル解析することにより、表層流や波浪などの海表面の情報を得るものである。利用周波数によるが、これによって数10kmから200kmの範囲を面的かつ連続的に観測することができる。また、船舶観測やブイに比較して、陸上設置により保守が容易で荒天時でも運用できることから、長期連続観測に適している。
表層流観測により、海流や潮流、急潮などの海洋物理の研究に活用されているほか、卵稚子輸送などの生物環境把握、漂流物予測、海難救助、海上交通や漁業での利用が試みられている。さらに、東日本大震災の際に津波検知能力が実証され、津波そのものを面的に把握できる測器として注目されている。また、波浪、海上風の計測、船舶追跡などの研究も進められている。
2012年2月ジュネーブにて開催された国際電気通信連合(ITU)2012年世界無線通信会議(WRC-12)において、海洋レーダの周波数の国際分配が決議された。これにより、実験局としてしか開設できなかった海洋レーダが、実用局として免許を受けることができるようになった。海洋レーダ用の周波数として、すでに多くの通信や放送用無線局が利用している3~50MHz帯で10カ所以上分配された。これは、海洋レーダの有用性が全世界に認められたことを示す証左である。また、米国と共に前回WRC-07での議題提案を主導した後、足掛け5年間にわたり共用条件の検討と国際調整を行ってきた、日本政府代表団の成果とも言える。WRC-12での主要結果※1の一つに掲げられた、日本の海洋レーダ研究を基盤とした重要な国際貢献である。
海洋レーダ観測ネットワークの進展
米国ではIOOS(Integrated Ocean Observing System)の一部として、海洋レーダを海岸線にくまなく配備し、リアルタイムで流速マップを作成するレーダネットワークの構築が進んでいる。現在、全米で160基のレーダが展開され、特に太平洋岸ではメキシコ国境からワシントン州まで50基が稼動し、流速マップが1時間ごとに更新されている※2。欧州各国でも、定常観測システムとしての海洋レーダの導入が徐々に進んできている。オーストラリアでは科学研究インフラとして海洋レーダのネットワーク化が始まり、まだ6観測サイトだけであるが、全国規模への拡張を開始した段階である。より意欲的なのは台湾である。2011年までに海洋レーダ15基を台湾島全周に配備し終えており、TORI(台湾海洋科技研究中心)で一元的に運用している。韓国は、WRC-07提案時には周波数分配に消極的だったのとは打って変わり、この2、3年で20基を超えるレーダを導入し、WRC-12では韓国内用に独自の周波数帯を要求するほど活気付いており、全国組織を立ち上げ2012年5月に第1回アジア海洋レーダ会議を開催するに至った。中国の15基を始め、他のアジア諸国でも海洋レーダの導入する国が増えてきている。
今後、WRC-12の周波数分配により実用局として免許できるようになったことから、世界的に海洋レーダの活用の流れは加速すると考えられる。
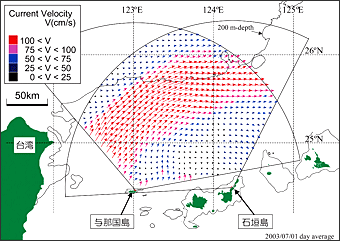
■図1:(独)情報通信研究機構(NICT)の海洋レーダによる東シナ海南部の観測例。与那国島と石垣島に設置したレーダで黒潮の流動を観測している。
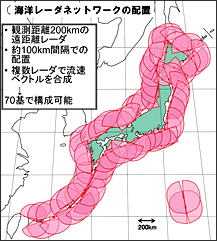
■図2:日本ネットワークの配置
ピンクの扇形が1台のレーダの観測範囲。2台のレーダのオーバラップする領域で流速ベクトルが計算できる。
日本の海洋レーダの現状と今後
日本は比較的早くから海洋レーダ研究を開始し、1990年代での移動観測用レーダの開発以降、海上保安庁の伊豆諸島海域・相模湾、北大の宗谷海峡・オホーツク沿岸、九大の対馬海峡、(独)情報通信研究機構(NICT)の東シナ海南部などの沿岸観測レーダシステムが構築された。その後、国土交通省港湾局が東京湾、伊勢・三河湾、大阪湾・紀伊水道、有明海の湾内モニタリングシステムとし導入した。現在、49基のレーダが免許されており、米国に次いで2番目の海洋レーダ数となっている。しかしながら、これらのレーダは各機関や地域で閉じたシステムになっており、米国、オーストラリア、韓国、台湾のように国全体の海洋観測インフラとして統括されたシステムではなく、インターネットから統一的にデータを閲覧する環境も整っていない。また、WRC-07への提案に伴い海洋レーダの扱いが確定するまで新設が凍結されたことからこの5年間増加していない。逆に、北大、九大、NICTは、その研究プロジェクトの収束時期になり、廃止の可能性も出てきている。この3機関のレーダは、宗谷海峡、対馬海峡、尖閣周辺海域をカバーしており、国境を接することで洋上観測が自由にできない海域の貴重なデータを取得している。
現在、台湾は北端にレーダ設置を画策しており、試験的にNICTの与那国レーダとの相互観測にて黒潮観測の研究を行っている。このような共同観測も日本側レーダがなくなればできなくなり、この海域は一方的にデータ提供を受けるだけになってしまうが、それが今後可能かどうか不明である。また、対馬海峡西水道では、韓国が釜山地域にレーダを6基設置し対馬西岸まで観測域としている。九大の対馬観測システムの西水道レーダはそのやや南側を観測しており、両者連携により西水道全体を観測でき相互に有用なデータとなりえる。しかし、九大のレーダが撤収となると対馬西水道は韓国のレーダでしか測っていないことになる。北大の宗谷海峡レーダは、国境以北での洋上観測がほぼ不可能であることから、宗谷海峡全域を観測できる唯一の方法となっている。
このような沿岸モニタリングシステムは安定的な観測インフラとして確保すべきと考える。例えば、北海道北端から南西諸島先島までの全沿岸海域をカバーするには、観測距離200kmの遠距離海洋レーダを約70基配置することで可能となる。米国のネットワーク整備にかかる費用試算を参考にすると、設置・整備に7~10億円、運用・保守は年間数千万円という規模である。これで、排他的経済水域のほぼ50%にあたる生活や経済活動に密接な沿岸部分のモニタリングができ、国境周辺海域を常時観測できるとすると、かなり経済的なシステムとなるであろう。加えて、現在立案中の次世代高度計衛星や海洋モデルシミュレーションを組み合わせることで、より高度なサービスが可能になり、わが国の海洋管理とともに、海の安全、安心にも大いに貢献することとなるため、是非とも積極的に推進すべきである。(了)
第294号(2012.11.05発行)のその他の記事
- 国連海洋法条約採択30周年を迎えて 早稲田大学名誉教授、海洋政策研究財団特別研究員◆林 司宣
- 海洋科学技術立国におけるJAMSTECの役割 独立行政法人海洋研究開発機構 理事長◆平 朝彦
- 離島と沿岸域の総合的管理に海洋レーダネットワークの整備を 琉球大学工学部 電気電子工学科 教授◆藤井智史
- 編集後記 ニューズレター編集代表((独)海洋研究開発機構上席研究員/東京大学名誉教授)◆山形俊男
