Ocean Newsletter
第293号(2012.10.20発行)
- 海洋政策研究財団常務理事◆寺島紘士
- 徳島大学教授、徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部 環境防災研究センター 副センター長◆中野 晋
- 北九州市長◆北橋健治
- ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所名誉教授)◆秋道智彌
関門潮流発電実施推進事業
[KEYWORDS] 関門潮流発電/再生可能エネルギー/環境未来都市北九州市北九州市長◆北橋健治
北九州市は、関門海峡の早く強い潮流をエネルギーとして活用するための実証実験を進めている。平成24年3月より実証実験を開始し、現在は発電設備を実際に動かすことにより、発電やブレードの状況などの課題を抽出するとともに、その解決のための検討が行われている。
発電した電力によるLED点灯などの見える化もすすめ、自然・再生可能エネルギーに関する市民啓発に繋げたいと考える。
はじめに
北九州市では、現在、関門海峡の強い潮流を利用した発電の実証実験を行っています。本稿では、この取り組みについて、ご紹介させていただきます。
本市は、平成20年に環境モデル都市、平成23年12月に環境未来都市に選ばれるなど、環境への取り組みを積極的に進めています。そのなかでも、以前から、自然エネルギー・再生可能エネルギー導入に力を入れてきました。平成23年度末までに、太陽光発電では、住宅用、公共・民生用を含め、約30,000kW、風力発電は、約17,000kWが導入されています。中小水力発電では、水道用の貯水池に、約1,700kWが設置されています。今年度も民間主導によるメガソーラーや、大規模な洋上風力発電、陸上風力発電も設置される予定になっています。また、本市は、様々なエネルギー関連施設が学ぶことができる次世代エネルギーパークの指定も受けており、若松区響灘地区を中心に、エネルギー関連施設の見学も行っています。
このような取り組みの中で、関門海峡の速く強い潮流を本市特有の自然エネルギーとして活用できないか、と以前から考えてきました。そのため、平成21年度、総務省による「緑の分権改革推進事業」を活用し、賦存量や利用可能量をはじめとした実施可能性調査から着手しました。
関門海峡の潮流発電実施可能性調査
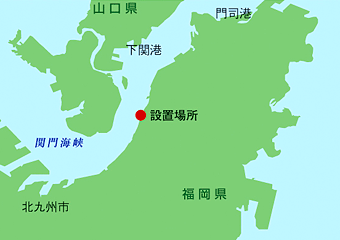
■図1 関門潮流発電の実証実験設置場所
この調査で、潮流の流速を調査し、海峡の断面積の数値も用いて関門海峡における潮流発電の"賦存量"や"利用可能量"を算出しました。それによりますと、賦存量は22.5億kWh(66万世帯分)という大きなものでした。しかし、これは、5m×5mの水平軸水車を関門海峡に隙間なく並べた場合、というもので、実際にはこれほどの発電はできません。関門海峡は、日本の航路の要所であり、漁業権区域も設定されています。これらの発電設備の設置が難しい区域を除いたものが、"利用可能量"です。この場合では、より小型の水車(1m×1mのダリウス型水車)を想定し算出しましたが、それでも5,500万kWh(1万6千世帯分)の発電量が得られる、という可能性が示唆されました。
この上で、さらに考えなければならないことがあります。それは、発電設備へのアクセスのしやすさや設置コストです。発電設備は、当然ながら、定期的な保守点検が必要です。また、発電した電気を利用する場所に近いことがコスト面からも求められるため、できるだけ陸に近い場所に設置することが望ましいのです。これらの点を考慮し、実証実験を行うのに最適な場所として、3カ所が候補に挙がりました。それは、関門橋の橋脚付近、ノーフォーク広場付近とニッカウヰスキー株式会社門司工場の桟橋です。この3カ所のなかでも、航路からの距離も十分にとれ、岸壁側に岩礁などの障害物がないことや、保守点検時のしやすさも考慮し、ニッカウヰスキー株式会社門司工場の桟橋がもっとも適していると判断されました。その後、ニッカウヰスキー株式会社と協議した結果、保守点検時や発電電力の活用などについて、全面的な協力を得ることができ、実証実験機の設置場所とさせていただきました(図1参照)。
実証実験機の設置
実証実験において、潮流を受けて回転するブレードなどの発電機構については、国立大学法人九州工業大学平木講儒准教授の研究技術を用いています。また、発電設備全体は、本市内で環境関連の業務を行っている株式会社九州テクノリサーチが総括的に開発しました。なお、発電設備については、公益財団法人北九州産業学術推進機構が実施する低炭素化技術拠点形成事業・ミニ実証の助成を受けて実施されています。
今回、実験する発電設備では、相反転という、発電機の軸とその周りの枠を逆方向へ回転させることにより、小型でもより大きな発電効率が得られるシステムを採用しています。
実験機の大きさや概観を図2に示しています。満潮時には、水車のブレード全体が水中に沈む形になっています。この装置で定格電力1.4kWとなっています。
この実証実験機を2012年3月17日に関門海峡に面するニッカウヰスキー株式会社門司工場桟橋先に設置しました。

■図2 ダリウス型水車を用いた潮流発電装置

実証実験の状況
当初は、発電機に接続せず、水車だけで回転を行い、相反転による回転が確認できました。その後、流れてきた海草がブレードに絡まったことによるブレードの停止や海草の除去、といったトラブルも発生しました。このようなトラブルの発生は、実証実験を行わなければわからないことであり、解決方法の立案と実施も含め、得られる知見が、今回の成果の一つと考えています。
その後、ブレードを実際に発電機に接続し、どのような挙動を示すかの実験に移りました。
発電機に接続すると、発電電圧など、電子回路の設計において、当初の想定とは異なる点もあり、発電・充電できない状況が発生しました。そのため、実際の発電電圧のデータを下に、制御システムを再検討しています。現在は、まだ改造の途上ですが、大潮、中潮の際には発電が確認できるなど、概ね良好な結果が得られています。今年度は、本市にあります独立行政法人国立高等専門学校機構北九州工業高等専門学校の協力も得て、さらに実験を進めていく予定です。
今後の予定
この実証実験により、発電やブレードの状況などのデータを収集し、今後の検討に活かしたいと考えています。また、発電した電気については、蓄電池に充電し、ニッカウヰスキー株式会社門司工場にあります赤レンガ倉庫のライトアップに活用する予定です。この赤レンガ倉庫は、国道199号線に面しており、多くの市民の皆様が目にすることができる場所です。このライトアップによって、関門潮流発電のような、普段はあまり目にすることができない自然エネルギーを見える化し、市民が皆様の自然エネルギーについて考えるきっかけとなれば、と思います。(了)
第293号(2012.10.20発行)のその他の記事
- リオ+20と海洋 海洋政策研究財団常務理事◆寺島紘士
- 東日本大震災の教訓を生かしたこれからの学校防災 徳島大学教授、徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部 環境防災研究センター 副センター長◆中野 晋
- 関門潮流発電実施推進事業 北九州市長◆北橋健治
- 編集後記 ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所名誉教授)◆秋道智彌
