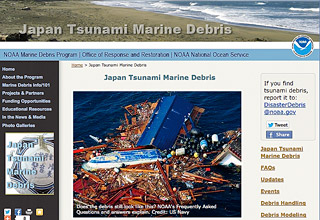Ocean Newsletter
第292号(2012.10.05発行)
- 神戸大学大学院法学研究科教授◆坂元茂樹
- 北海道大学名誉教授◆池田元美
- 富山県土木部港湾課環日本海拠点港推進班長◆太田浩男
- ニューズレター編集代表((独)海洋研究開発機構上席研究員/東京大学名誉教授)◆山形俊男
太平洋東岸への漂着がれきに関する政府への申し入れ
[KEYWORDS] 漂流物/国際条約/予測シミュレーション北海道大学名誉教授◆池田元美
アメリカやカナダなどへの東日本大震災による漂着がれきの対策について、わが国として一刻も早い対策を講じる必要がある。
国際法の観点からは、わが国には漂着物処理の義務は生じないと専門家は述べるが、国際的に誠意のある対処を念頭に置くと、太平洋東岸に漂着するがれきについてわが国としても多様な支援を提供すべきである。
東日本大震災による漂着がれき対策への提言
表題に示した政府への申し入れを8月21日に、総理大臣、国土交通大臣、総合海洋政策本部事務局長宛に送付したので、報告する※1。作成・送付した主体は、日本海洋学会などの有志で、筆者ならびに、上 真一(広大教授)、大西光代(編集業)、木暮一啓(東大教授)、清野聡子(九大准教授)、藤井賢彦(北大准教授)、中埜岩雄(GODI)、古恵 亮(ハワイ大)、古谷 研(東大教授)、吉成浩志(Alfred Wegener極域海洋研)の諸氏を含め約40名である。がれきの処理について、一刻も早くわが国のとるべき基本方針を公表するよう申し入れ、その中には以下の項目を含めることを求めた。
海洋科学に関する項目として
・震災に起因する漂流がれきの予測、および慎重な対処が必要な汚染物や侵入種となりうる生物などについては、限られた機関への委託研究だけに頼るのではなく、専門家の意見を広く聴取し、それらを取りまとめて速やかに公表すると共に、漂着物の適切な処理を行う。
・漂流・漂着がれきの記録を残し、処理の適切さを検証すると共に、震災起源以外の漂着ごみの処理にも資する。
海洋環境保全に資する国際関係を構築する項目として
・国際法ではわが国に処理の責任は生じないとしているが、震災に起因する国外への漂着がれきの処理に、誠意を持ち、国際関係を重視した対処をする。
・漂着国とわが国のボランティアへの支援を充実させる。
これまでの漂着がれきの報道
新聞やテレビでは、漂流がれきがアラスカ沿岸に現れ、その中にあったバレーボールを持ち主に送り届けてくれたことなど、今のところ美談が強調されているが、米国とカナダの太平洋沿岸に漂着したがれきの処理に苦慮している様子も報道されている。総合海洋政策本部のホームページには京都大学などが行ったシミュレーション結果が示され、今秋以降に大量のがれきが米国とカナダに漂着するならば、ますます大きな問題になると予想される。
総合海洋政策本部でも報告され、新聞にも書かれているように、わが国の政府が委託研究によって予測シミュレーションを実施しており、また米国で取り組んでいる研究者や行政担当者たちと共同作業もしている。日米政府間の協力ができていること自体、注目し、評価すべきである。しかし、がれきの除去に関して日本政府がこれまで行っていることは、NGOの自主的な訪問を取り次ぎ、彼らに任せているだけである。上記ホームページのQ&Aにおいても、日本政府が今後どのように取り組もうとしているのか全く明確になっていない。
米国西海岸での現状
米国のサイトには、市民の不安と、それに対するNOAAやNGOの対応が記されており、状況を把握するのに役立つ。浮き桟橋が漂着したオレゴン州ニューポートでは、研究者と市民が付着生物を除去し、外来種の侵入を警戒している。日本でよく見られるマヒトデも見つけられ、慎重な監視が必須である。わが国の環境省が調査のため現地に派遣したNGOと海洋研究者によれば、外来種に関する情報を日本の専門家に期待する声も聞かれる。
見えてきた課題
国際法の観点からは、わが国には漂着物処理の義務は生じないと専門家は述べている。国内における海岸漂着物処理推進法などに基づく日本政府の措置は、まず地方自治体が漂着ごみを除去・処理する責任を有しているのに対し、国はその経費を支援する場合もあり、発生を抑える措置や国際協力にも手を尽くさねばならないとも述べている。国際的に誠意のある対処を念頭に置くと、地震被災国への思いやりと支援を受けたわが国としては、米国とカナダなど太平洋沿岸に漂着するがれきにもわが国の漂着がれきに準ずる支援を提供すべきである。もし、明確な支援を行わないなら、これまで発してきた他国からの漂着物への抗議も根拠を失うであろう。もちろん国際関係の重視によって、東北の復興を妨げている膨大ながれきの処理をおろそかにすることは許されず、バランスのある計画を立案し、遂行していくことが基本である。
震災以前から漂着物の処理に努力を重ねてきたNGOの取り組みに鑑みると、震災に伴う漂流がれきにもNGOの貢献は必須であり、政府の支援を拡充するのが現実的な措置である。また、処理を促進する国際基金の設立、および国際条約の立案を主導することを望むものである。しかし、それだけに頼るのではなく、漂着がれきの処理を迅速に進めるための手立てが急務である。
政府への申し入れを行った時期までのメディア情報では、政府ががれき除去に向けて米国と相談を進めており、何らかの経費を投入するよう補正予算を組む可能性があるとのことだ。それを知った上で、いますぐに政府に求めたい項目を申し入れた次第である。国民が方針に同意し、ボランティアとして参加する人が出るなら、漂着国の人々との相互理解も格段に進むと確信する。なお、申し入れを行ってから少し時を経た9月初頭に、政府は処理費用の負担を表明しており※2、ようやく前に進み始めた感がある。
海洋科学専門家のこれからの取り組み
最後に、われわれ海洋科学専門家が取り組むべきことを述べておく。
・漂流を決める風と海流の状況、漂流物の海洋における分布。
・漂着がれきに付着している可能性のある汚染物質および生物。
・海洋環境保全に適切と考えられる処理。
これらについて、情報を収集し、試料を分析すると共に、将来予測を実施し、結果を評価する。例えば、省庁から委託を受けている専門家に働きかけ、セカンド・オピニオンを提示することによって、予測結果の評価をし、より信頼性の高い情報を迅速に開示することが可能となる。今後の海洋科学専門家の国内外への取り組みが必要とされている。(了)
第292号(2012.10.05発行)のその他の記事
- 尖閣諸島ー国有化後の課題 神戸大学大学院法学研究科教授◆坂元茂樹
- 太平洋東岸への漂着がれきに関する政府への申し入れ 北海道大学名誉教授◆池田元美
- 環日本海クルーズの実現に向けて 富山県土木部港湾課環日本海拠点港推進班長◆太田浩男
- 編集後記 ニューズレター編集代表((独)海洋研究開発機構上席研究員/東京大学名誉教授)◆山形俊男