Ocean Newsletter
第268号(2011.10.05発行)
- 東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻教授◆佐藤愼司
- 公益財団法人原子力安全研究協会会長◆松浦祥次郎
- 海の中道海洋生態科学館 館長◆高田浩二
- 「21世紀の海洋教育に関するグランドデザイン」が完成
- ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・研究科長)◆山形俊男
原子力と海
[KEYWORDS]原子力エネルギー/原子力船/海水ウラン捕集公益財団法人原子力安全研究協会会長◆松浦祥次郎
原子力と海の関係は、わが国の原子力研究開発の歴史上に重要な一里塚を建てた原子力船「むつ」に遡る。
海水中には超低濃度だがウランが溶解しており、すでにこの捕集に関する開発実験も行われている。
原子力船開発は「むつ」のみで放棄されたが、原子力と海には無限の夢がつまっている。
はじめに
本誌の編集代表山形俊男先生からのお誘いを奇貨として、長年心に留めていた海と原子力についての夢を気軽に書かせていただくことにしました。原子力と海から直ちに浮かぶ私のイメージは原子力第一船「むつ」と、海水ウランの捕集なのです。二つとも私が旧特殊法人日本原子力研究所(以下原研)に勤務していた時にかなり執着をもって関わっていた事項です。
原子力船「むつ」は実験航海を1991年に終了し、その後間もなく退役・解体されました。ですから日本が原子力船を自力で開発し、外洋で約80,000kmに及ぶ原子動力全速力実験航海に成功していたと言うことを知っている人はいまやほとんどいないでしょう。しかし、「むつ」がわが国の原子力研究開発の歴史上に重要な一里塚を建てたことは事実です。幸いに、日本原子力学会から「むつ」開発の事績に対して原子力歴史構築賞が先般授与されたのは何よりのことと喜んでおります。
原子力船「むつ」開発

■「原子力船「むつ」開発のあゆみ」(原子力研究所発行)より
■年間1,200tのウラン捕集規模でのコスト試算結果
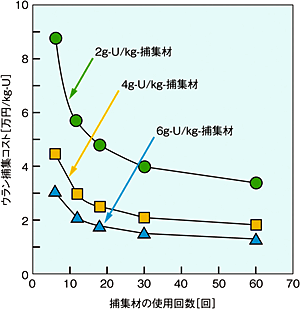
玉田正男、瀬古典明、笠井昇、清水隆夫、モール状捕集システムによる海水ウラン捕集コスト試算、日本原子力学会和文論文誌5(2006)358-363
私は1961年に原子炉物理研究員として原研に採用されました。最初の仕事は、軽水型動力炉(BWRおよびPWR)の炉物理特性研究用小型原子炉(臨界実験装置;TCA)の建設と、それによる動力炉の特性研究でした。同じ1961年に原子力委員会原子力船分科会で原子力第一船建造が答申され、旧原子力船開発事業団(以下原船団、後に原研に統合)が設立され、原子力第一船建造プロジェクトが開始されたのでした。
これは大変野心的な事業でした。日本は原子力開発に着手して間もない時期であり、原子力第一船に搭載する原子炉は設計から製造まで全部国産とする第一号動力炉だったのです。そのため、かなりの試験研究が必要でした。
その一部として、原研TCAを用いて第一船用炉心核設計の実験的検証をすることになりました。この「原子力第一船炉心臨界実験」は原研と原船団の共同研究契約のもと、われわれTCAグループと旧三菱原子力工業(MAPI)から派遣された数人の若い外来研究員とがまさに夜を日に継いで実施しました。実験グループリーダーの私が30歳そこそこでしたから、20代後半の人間で計画、機器準備、実験、解析をすべてやっていたわけです。そのような時代でした。
この一連の実験は、実質的にわが国では初めての本格的な動力炉核設計確認実験でした。臨界実験ですから200W以下の低出力実験ですが、種々の炉物理特性値を核設計検証に必要十分な精度で得ることができ、核設計の精度確認と、改良への示唆を与えることができました。
この実験結果により、原設計2領域炉心のウラン濃縮度組み合わせ2.7~3.2%を3.2~4.4%に上昇すべきこと、制御棒吸収材料を高価だったハフニウムから銀・インジウム・カドミウム合金に変更可能なこと等が確認できました。しかし、この一連実験の最も重要な成果は、軽水動力炉の核設計確認・改良のために必要な体系的実験手法を確立できたことでした。参画した研究員一同は自分達の仕事に十分満足できました。
「むつ」と命名された原子力第一船建造はいくつかの困難を乗り越え、1974年にようやく出力上昇試験を太平洋上で実施しました。しかし、出力上昇を開始した途端に放射線漏洩を起こしました。初めはどんな放射線が何処から漏れているのか分からなかったのですが、炉物理試験員として乗船していたTCAグループの小林岩夫氏の発案で見事な確認実験を行い、原子炉圧力容器と周辺コンクリート遮蔽体の間隙から速中性子束が漏れていることが確認できました。それは実験者らしい発案で、中性子吸収剤のボロンを入れて炊飯した飯を軍足に詰めて、形状可変な中性子吸収体を作り、これを炉心周辺に適切に配置して漏洩が速中性子であることを確認したというものでした。この速中性子漏洩の遮蔽は技術的には比較的容易でしたが、政治的・社会的問題は深刻なものとなり、結局原子力船開発は「むつ」のみで放棄されてしまいました。しかし最近、原子力船の可能性が再評価されています。
海水ウラン捕集
さて、次に海水ウランの捕集です。海水中には超低濃度(海水1トン中3.3mg)ですがウランが溶解しています。しかし、総量は膨大で45億トンと推定されています。ちなみに、陸上の確認埋蔵量は約400万トン、未確認推定埋蔵量は約1,600万トンと評価されています。この超低濃度の海水ウランを捕集する技術が原研・高崎研究所(現日本原子力研究開発機構;JAEA)で開発され、すでに青森県と沖縄県の沖合実海域で実証試験がなされました。基本原理は有機官能基のアミドキシム基がウランを特異的に捕集する特性を利用するのです。このアミドキシム基をポリエチレン繊維に放射線照射でグラフト重合し、できたアミドキシム基付き繊維で製作した捕集具で海水ウランを捕集し、それを塩酸処理することでウランを得るというものです。上記の実証試験の結果、海水ウランは陸上ウランの約3倍程度のコストで捕集可能なことが実証されたと、JAEAの玉田正男研究員から原子力委員会に報告(平成21年6月)されています。ウランのほかにもアミドキシム基はバナジウムなど貴重な資源を海水中から捕集できる可能性が確認されています(図参照)。
海に開かれる原子力利用の可能性
大型原子力船内にウラン捕集・精製工場、レーザー濃縮工場、原子炉燃料工場を備え、海洋上で捕集したウランで製造した燃料を原子力発電所に配給し、代わりに使用済み燃料を受け取り、再処理工場に運ぶ。このような燃料サイクルシステムは夢としていかがでしょうか。このようなシステムができれば、わが国はエネルギー自立上、きわめて有利になることでしょう。しかも、すでにその技術的基盤は、わが国産技術としてできあがっています。海は広いな 大きいな 夢も果てなく 広々と。(了)
第268号(2011.10.05発行)のその他の記事
- 津波の科学的な記録とそれに基づく津波防災のあり方 東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻教授◆佐藤愼司
- 原子力と海 公益財団法人原子力安全研究協会会長◆松浦祥次郎
- 海への礼、水族への恩を返す場としての水族館 海の中道海洋生態科学館 館長◆高田浩二
- インフォメーション 「21世紀の海洋教育に関するグランドデザイン」が完成
- 編集後記 ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・研究科長)◆山形俊男
