Ocean Newsletter
第265号(2011.08.20発行)
- 神戸大学 大学院海事科学研究科 名誉教授◆井上欣三
- 東北大学大学院農学研究科 教授◆佐藤 実
- 日本郵船株式会社 CSR推進グループ◆宮本亜矢子
- 2011年「海の日」(第3回)懸賞論文入選作品の発表
- ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所・教授)◆秋道智彌
日本郵船ネイチャーフェローシップ
[KEYWORDS]日本郵船ネイチャーフェローシップ/海洋環境調査ボランティア/生物多様性日本郵船株式会社 CSR推進グループ◆宮本亜矢子
日本郵船(株)は、世界各地の野外調査を支援する国際NGOアースウォッチ・ジャパンと協働で「日本郵船ネイチャーフェローシップ」を立ち上げ、世界各地の海洋環境調査・研究の現場に国内の大学生と当社グループ社員を派遣している。
世界中から集まる科学者やボランティアとともに調査に携わることを通じて、参加者の環境意識や国際感覚を向上・啓発することを目的としている。
日本郵船ネイチャーフェローシップ設立のきっかけ
2005年、当社は環境に対する取り組みが評価され、「コンティキ号」で有名な探険家トール・ヘイエルダール博士とノルウェー船主協会によって創設された「トール・ヘイエルダール国際海洋環境賞」を受賞した。これを記念して2006年に世界各地の野外調査を支援する国際NGOアースウォッチ・ジャパンと協働で「日本郵船ネイチャーフェローシップ」を立ち上げ、世界各地の海洋環境調査・研究の現場に国内の大学生と当社グループ社員を派遣している。
本プロジェクトは、世界中から集まる科学者やボランティアとともに調査に携わることを通じて、参加者の環境意識や国際感覚を向上・啓発することを目的としている。
大学生およびグループ社員の応募者は、「日本郵船ネイチャーフェローシップの参加経験を活かして取り組みたいあなたの『チャレンジ』」というテーマの論文審査を経た後、社内および社外有識者の面接等により選考される。
海洋環境調査へいよいよ出発

■「コククジラの回遊」調査の様子
「コククジラの回遊」調査の場合は、およそ1 週間の海洋環境調査を実施。毎年カナダとメキシコの間29,000kmを回遊するコククジラの行動の謎を解き明かし、クジラの保護計画を立案するための生態調査を手伝う。
以下、調査の手順・プロセスを概観する。
(1)参加者決定後、参加要領とともに調査内容をまとめたブリーフィング資料(50~60頁)を参加者は必ず熟読しておくことが求められる。
(2)集合場所となるカナダの埠頭で、研究者9名と世界各地から来たボランティア約10名が初対面する。
(3)宿泊拠点となるキャンプ地へ。船上や研究所内等調査内容に応じて参加者はそれぞれ移動する。
(4)研究者より調査に関するレクチャーとデータ収集方法について説明を受ける。
(5)フィールドでの調査では、シーカヤックに乗り、クジラを探す。水中音波探知装置や海底サンプル収集機器を使った生物学的データの収集、写真による個体識別、データの記録、航法の補助などを行う。各作業は事前にトレーニングを受けるため、専門知識がなくても円滑に行えるものとなっている。
(6)研究所に戻り、データを整理する。調査地で撮影したクジラの写真データを分析・照合し、個体の同定などを確認する。
(7)研究者から最新の調査結果の説明を受ける。
(8)ボランティアと研究者が交代で食事や掃除を分担し、あわせて異文化交流を実現する。
(9)調査終了後、集合場所と同じ埠頭で解散。
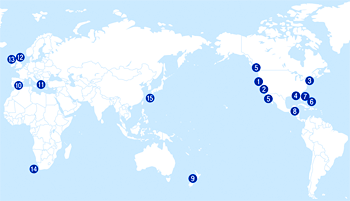
■日本郵船ネイチャーフェローシップ実績
「2006年から2010年までに15調査に44名が参加」
調査一覧
(1)カリフォルニアのラッコとイルカ(アメリカ/モントレー湾)
(2)カリフォルニアのサメとエイ(アメリカ/モントレー湾・エルクホーン湿地)
(3)バーネガット湾のキスイガメ(アメリカ/バーネガット湾)
(4)野生イルカの社会(アメリカ/サラソタ)
(5)コククジラの回遊(メキシコ/ラグナ・サン・イグナシオン)(カナダ/ブリティッシュ・コロンビア)
(6)バハマのサンゴ礁(バハマ/サンサルバドル島)
(7)アバコ島のクジラとイルカ(バハマ/グレート・アバコ島)
(8)ベリーズのマナティとイルカ(ベリーズ/ドゥロウンド・キーズ)
(9)ニュージーランドのイルカ(ニュージーランド/アドミラルティ湾)
(10)スペインのイルカ(スペイン/アルボラン海)
(11)ギリシャのバンドウイルカ(ギリシャ/アンフラキコス湾)
(12)モーレイ湾のクジラとイルカ(イギリス/モーレイ湾)
(13)ヘブリディーズ諸島のクジラとイルカ(イギリス/ヘブリディーズ諸島)
(14)南アフリカのペンギン(南アフリカ/ロベン島)
(15)沖縄のサンゴ礁
調査後のフィードバック
より良い地球社会の実現に向けて参加者が海洋環境調査や異文化交流を通して得た知識・経験を社会に還元してもらうため、社内や日本郵船歴史博物館、アースウォッチ・ジャパン主催の報告会で体験談を語ってもらう。
参加した学生および社員たちからは、「ボランティア活動を行うということについて改めて考えさせられた」「ボランティア活動は何かをしてあげるということではなく、こちらの方が貴重な体験をさせてもらっている、ということを自然に感じることができた」「皆誰が言うともなく行動し、自ら進んで協力し合うことができたことで本当に快適で素晴らしい日々を送ることができたと思う」「メンバーとの船上での生活からチームワークの重要性を学ぶことができた」などの報告があり、彼らが参加前よりもひとまわり大きくなった姿は印象的である。
パートナーとして―アースウォッチ・ジャパンの想い
海外では企業による次世代へのフェローシップ事業は多く、その教育的効果も高い。しかし、日本で学生を海外のアースウォッチのプロジェクトに派遣している企業は、日本郵船(株)ただ一社である。日本郵船は、以前より「次世代の人材育成」と「海洋環境保全」をテーマに社会貢献活動を実施しており、2005 年にネイチャーフェローシップが実現して以来、アースウォッチ・ジャパンの良きパートナーとして、共に多くの若者を育てきた。
第一線の研究者のもとで、人生観が変わるような体験をした参加者は、一回りも二回りも大きくなって帰国してくる。彼らは、その体験を自分だけのものとせず、報告会で子どもたちや一般の大人たちにその体験を語って共有している。
ネイチャーフェローシップに参加する前は、どことなく頼りなく思えた若者たちが、世界中から集まったボランティアや研究者にもまれ、自らの体験を堂々と自分の言葉で語る様は、まさに感動の一言であり、是非とも多くの方に知っていただきたいと考えている。
おわりに
参加者には本プロジェクトを通して得た知識や経験を自分自身に留めるのではなく、社会に還元して、より良い地球社会の実現に向けて取り組んでいただきたいと願っている。当社グループは本プロジェクトのみならず、地球社会とともに生きる「良き企業市民」として、今後も積極的にさまざまな活動に取り組んでいきたい。(了)
第265号(2011.08.20発行)のその他の記事
- 災害時医療支援船構想~船を活用した被災地の医療福祉支援~ 神戸大学 大学院海事科学研究科 名誉教授◆井上欣三
- 海の恵み・海藻から作りだすバイオエタノール 東北大学大学院農学研究科 教授◆佐藤 実
- 日本郵船ネイチャーフェローシップ 日本郵船株式会社 CSR推進グループ◆宮本亜矢子
- インフォメーション 2011年「海の日」(第3回)懸賞論文入選作品の発表
- 編集後記 ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所・教授)◆秋道智彌
