Ocean Newsletter
第265号(2011.08.20発行)
- 神戸大学 大学院海事科学研究科 名誉教授◆井上欣三
- 東北大学大学院農学研究科 教授◆佐藤 実
- 日本郵船株式会社 CSR推進グループ◆宮本亜矢子
- 2011年「海の日」(第3回)懸賞論文入選作品の発表
- ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所・教授)◆秋道智彌
災害時医療支援船構想~船を活用した被災地の医療福祉支援~
[KEYWORDS]災害関連死/ホテルシップ/ドクターシップ神戸大学 大学院海事科学研究科 名誉教授◆井上欣三
透析患者、難病患者、在宅患者、要介護者等の被災者には支援の手が後回しになることが多い。この人たちに忍び寄るのが災害関連死である。東日本大震災では災害関連死は既に100人を超えたといわれている。
このような災害弱者をストレスフルな避難所で、完全でない医療環境、貧弱な福祉環境のもとで災害関連死に至らしめないためにも、海・船・港をフル活用した医療支援を現実のものにしなければならない。
船の生活機能の活用
船は、それ自体、人や物を運ぶ道具であるだけでなく生活の場でもある。船内には電気、水、食料、風呂、トイレ、洗濯、冷暖房、厨房設備、宿泊設備といった生活に必要なすべてのものが整っている。これら自己完結的小社会の機能を利用することにより、緊急時にはそのまま被災者の避難所としての活用が可能である。また、被災者への食事、給水、風呂、トイレ、洗濯など生活と健康維持のための設備供与が可能である。さらに、被災者だけでなく被災地復旧要員のためのホテルシップとしての利用や、医療関係者と連携して船を医療活動の拠点としたドクターシップとして活用することも可能である。
阪神・淡路大震災における船の活用事例の全貌を調査した結果※1によれば、震災から2~3日目あたりから船の輸送機能が、そして、船の生活機能は震災から3~4日目あたりから積極的に活用され始めた。このたびの東日本大震災でも津波被害から復旧した港湾を使って政府艦船や民間船舶が支援物資や人員輸送に、また、風呂や食事の提供などに活躍したことは誰しもが知るところである。
しかし、被災地での医療面や福祉面での支援に目を向けるとき、残念ながら船が効果的に活用されたわけではない。週に2~3回人工透析を受けなければ生きられない慢性腎疾患患者、難病を抱える患者、人工心肺にたよる在宅患者、酸素や特定の薬を必要とする患者、高齢者、要介護者等々には支援の手が後回しになることが多い。この人たちに忍び寄るのが災害関連死であり、こういう人たちにこそいざという時に駆けつけてくれる病院船的な医療施設を備えた専用船がわが国にもあれば被災者には心強い。
まずソフト面で支援を実現
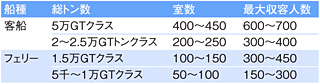
■想定される支援船のイメージ
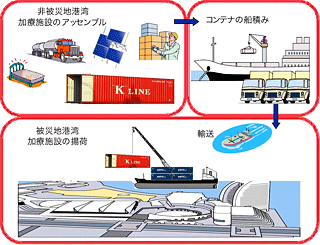
■港頭加療の概念
しかし、巨額のコストがかかる専用船の建造を悠長に待つわけにはいかない。被災者はいますぐにでも利用できる船の生活機能の医療支援や福祉支援への活用を必要としているのである。将来の立派なハードウエアの建造を期待しつつも、まずは現存する船をうまく運用するソフトウエア重視の視点が先ではないだろうか。例えばフェリーや客船などが医療と福祉の観点から被災者に避難と医療の場を提供するといったように、事前に専用の船を用意しなくても特別の装備がないふつうの船を災害発生時に即座に組織化する有事即応型の医療と海の社会連携を通じて被災者に支援の手をさしのべる、そういった海からの支援を実現するという発想が重要なのではないだろうか。
災害時に透析医療界から患者搬送・資機材輸送の要請をうけて支援船隊が海上ルートで搬送するというコンセプトに基づく「災害時医療支援船構想」(表参照)の取り組みは、筆者が中心となって10年が経過し、船の輸送機能に重点をおいた大阪湾域内民・民共助のしくみとして根付いてきた。昨年来、医療支援活動の枠を透析患者のほかに難病患者にもひろげたのを機に今後は「運ぶ」から「泊める」へ船による海からの支援を強化し、「ホテルシップ・ドクターシップ構想」のもと、域内共助体制から域外相互支援を可能とする体制作りを具体化しようとした矢先、東日本大震災がおこった。
東日本大震災では災害関連死は既に数百人を超えるといわれている。このような災害弱者をストレスフルな避難所で、完全でない医療環境、貧弱な福祉環境のもとで災害関連死に至らしめないためにも、また、次の災害で多くの被災者が設備環境に乏しい体育館などで我慢をしのばなくてもよいように、海・船・港をフル活用した医療支援を現実のものにしなければならない。そして、今後災害がどこで起こっても海からの支援を確実に組織化できる社会的しくみをソフト面から構築しておくことが急がれる。
ホテルシップ構想
災害が発生した際に、継続的な維持透析を必要とする患者、介護が必要な高齢者や障害者、難病患者など、いわゆる災害弱者に忍び寄るのが災害関連死である。劣悪な生活環境、行き届かない医療・福祉環境からくる災害関連死を防ぐためにも、体育館などの避難所生活があたりまえであるかのような発想から離れて、冷暖房、食事、風呂、ベッドなどが整った船が被災者に対しホテルシップとして生活機能を提供する発想が求められる。このような災害弱者の生活環境の改善には船が最適であることをよく知る海事の業・官の関係者に対して、医師、患者の悲痛な思いをホテルシップ構想の具体化にむすびつける発想と意識をこの機会にあらためて求めたい。
ドクターシップ構想
ホテルシップ構想は、船の自己完結的生活機能を活用して被災者の避難・救護生活の環境改善を図ることにより災害関連死を防ごうとするものである。また、この構想では、フェリーや客船など特別な装備がなくても現存の船を災害発生時に即座に組織化して運用する業・官連携の有事即応型支援体制を整えることを念頭においている。ホテルシップの運用にあたっては、災害弱者に生活環境を提供するだけでなく、良好な医療・福祉環境を同時に提供できることが望まれる。そのためには船内に医師、看護師、臨床技士、薬剤師、介護福祉士などが乗り込んで被災者に必要な医療・福祉環境を提供できるように、医療と海とが船を核に社会連携することが望まれる。これを具体的な形で実現するアイデアがドクターシップ構想である。
必要な医療設備や医薬品などについては、船内に持ち込めるものは可能な範囲で運び込み船内での加療に供する一方、例えば透析のための医療機材や設備などはコンテナに事前にアッセンブルしてコンテナ(医療施設)ごと船またはバージ(台船)で被災地の港に搬入し、コンテナ自体をも臨時の処置室として港頭での加療に使用する。このように船内加療と港頭加療を組み合わせた海からの医療支援活動をシステマティックに運用することは、透析医療から救急医療まで、船を用いた海からの医療支援に新たな道を開くものと期待される。(了)
第265号(2011.08.20発行)のその他の記事
- 災害時医療支援船構想~船を活用した被災地の医療福祉支援~ 神戸大学 大学院海事科学研究科 名誉教授◆井上欣三
- 海の恵み・海藻から作りだすバイオエタノール 東北大学大学院農学研究科 教授◆佐藤 実
- 日本郵船ネイチャーフェローシップ 日本郵船株式会社 CSR推進グループ◆宮本亜矢子
- インフォメーション 2011年「海の日」(第3回)懸賞論文入選作品の発表
- 編集後記 ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所・教授)◆秋道智彌
