Ocean Newsletter
第265号(2011.08.20発行)
- 神戸大学 大学院海事科学研究科 名誉教授◆井上欣三
- 東北大学大学院農学研究科 教授◆佐藤 実
- 日本郵船株式会社 CSR推進グループ◆宮本亜矢子
- 2011年「海の日」(第3回)懸賞論文入選作品の発表
- ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所・教授)◆秋道智彌
海の恵み・海藻から作りだすバイオエタノール
[KEYWORDS]褐藻マコンブ/再生可能エネルギー/地球環境東北大学大学院農学研究科 教授◆佐藤 実
原子力発電所の事故により、自然エネルギーや再生可能エネルギーの利用についてより効率的な生産技術の開発が確実に求められる。海藻から作るバイオエタノールは再生可能エネルギーとして地球環境の維持に貢献すると考える。
今後はエタノール発酵に適した海藻の探索と養殖、より効率的な発酵微生物の探索や、培養条件、精製方法などの検討を進めることが必要と考える。
大震災を経験しながら海を生かして生きる必要性
3月11日の東日本大震災にともなう大津波で沿岸部は甚大な被害をうけ、街は復旧の道半ばというより緒に就いたばかりの状態である。とりわけわが国自然災害史上最大級の津波被害については、歴史的に繰り返されてきたものと思われ、せめて人的被害だけでも現代のハイテク情報通信手段を生かして防げなかったものかと思う。
"にくき海"であるが、海は私たちにさまざまな恵みをもたらす、なくてはならない場である。海は水の源であり、多様な食料の宝庫であり、温度変化の少ない穏やかな地球環境をもたらし、食料や工業製品などを効率良く運ぶ船を浮かべてくれ、エネルギーや医薬品など有用物質も提供してくれる。いずれも私たちの生活に欠かせないものである。
今回の津波の高さは10mとも50mともいわれ、日常的にはあり得ない大波であるが、太平洋の平均深度約4,000mを考えると、津波の高さは海の深さの0.25%~1.25%だけのわずかな変化である。私たちが凪の海を前提に水際での生活を営んでいることが背景にあり、危険と隣りあわせの生活になっていることを自覚し、いざという時の避難方法を確保しつつ生活する必要があるといえる。
化石燃料とバイオエタノールの問題点
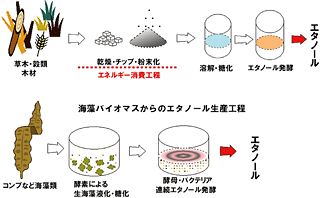
■図1:陸上バイオマスからのエタノール生産工程
私たちの生活をエネルギー面から支えている化石燃料の石油は、埋蔵量に限りがあるとともに、燃焼時に発生する二酸化炭素が地球温暖化の元凶とされ、石油からの脱却が求められている。代替エネルギーの主役と目されてきた原子力発電が東日本大震災と津波による福島第一原子力発電所の爆発事故で極めて深刻な事態を招き、今後の原子力発電所建設はもとより既存の原子力発電所の運転にも変化や、見直しが求められる可能性が考えられる。わが国民には、現実味をおびた電力不足にそなえ、一段の省エネ、省電力スタイルの生活が求められる一方、太陽光、水力、風力などの自然エネルギーのさらなる活用と、バイオマスから生産されるバイオエタノールなどの再生可能エネルギーの利用を進めるための効率的な生産技術の開発が確実に求められる。
バイオエタノールは現在、トウモロコシ、サトウキビなどを原料に製造がおこなわれているが、穀類の利用が食料価格の高騰をもたらしており、非食料バイオマスの利用が求められる。非食料バイオマスとしては、雑草、稲ワラ、廃材木などのリグノセルロース系バイオマスと、アオサ、マコンブやホンダワラなどの海藻がある。このうち、リグノセルロース系バイオマスは、セルロースを覆い抽出の妨げになっているリグニンの除去、難分解性セルロースの糖化(高分子多糖類を低分子化、単糖化し微生物が利用しやすいようにすること)、使用する硫酸などの薬品の処理などが大きな壁になり、広がりがみられない。海藻は一部食料として利用されるものはあるが、ほとんどは食料としての利用はなく、エタノール原料としては手つかずのバイオマスといえ、近年、各方面で盛んに研究がなされている。
海藻から再生可能なバイオ燃料、エタノールを作ろうとする試みは古く、緑藻アオサからのエタノール製造に成功している。緑藻は含まれる多糖が陸上植物に似たセルロースやデンプンであり、比較的容易に製造が可能といえよう。ただし、緑藻、褐藻、紅藻の大型海藻全体を見渡した場合、資源量はコンブやワカメ、ホンダワラなどが属する褐藻が圧倒的に多い。しかし褐藻は、残念ながら緑藻と異なり、炭水化物としてセルロース系多糖も含むが、マンニトール、ラミナラン、アルギン酸など、複雑な成分を含んでおり、エタノール発酵は困難とされ、実用化が遅れている。
海藻から効率良いエタノール製造技術
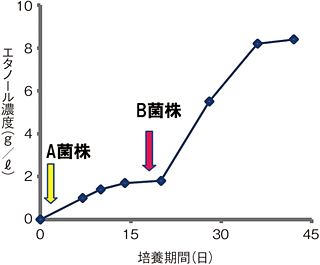
■図2
私たちの研究室と東北電力(株)が取り組んだ海藻は、発電所の取水口に集まる海藻である。取水口に集まる海藻は主に春はマコンブ、夏はホンダワラ、秋はアマモなどのように季節により変化する。集まった海藻はゴミであり、産業廃棄物として有償で引き取られ、処分されている。
私たちはモデル海藻としてマコンブを用い、バイオエタノール製造技術の開発に着手した。海藻の前処理として、陸上バイオマスで行われているエネルギー大量消費工程の乾燥工程、チップ化と粉末化工程を省略することとし、生海藻から直接に液化(細胞を破壊し成分を取り出すこと)と糖化を進め、エタノール発酵にいたる工程を確立することを目指した(図1参照)。
海藻は生では柔らかいが乾燥すると堅くなることから、生海藻を乾燥することなくセルラーゼやアルギン酸リアーゼなどの酵素類を用い液化と糖化を同時に行うこととした。褐藻には複雑な炭水化物が含まれており、それらを複数の微生物、酵母や研究室で独自に単離した細菌類を段階的に作用させることでバイオエタノールを効率的に製造する方法である(図2参照)
私たちの方法は、原料海藻が発電所取水口に集まるマコンブなどの海藻で、いわば"ゴミ"であり、収集にかかるコストはなく、むしろ産業廃棄物処理コストを低減できること、前処理で多くのエネルギーを必要とする乾燥や微粉末化を省略したことでエネルギー収支を大幅に改善させたこと、複雑な海藻成分を複数の微生物を利用してエタノール発酵する流れである。この方法で、生マコンブ1kgから22gのエタノール製造を確認しており、試験管レベルながら高効率的なエタノール製造技術と言えよう。
今後は、マコンブからのエタノール発酵のスケールアップを図るとともに、再生可能エネルギー生産を推進するために、エタノール発酵に適した海藻の探索と養殖、より効率的な発酵微生物の探索や、培養条件、精製方法などの検討を進めることが必要と考える。
エタノール発酵に適した海藻の養殖は震災被害を受けた漁業の再建に役立つ可能性があり、それから作るバイオエタノールは再生可能エネルギーとして地球環境の維持に貢献すると考える。(了)
第265号(2011.08.20発行)のその他の記事
- 災害時医療支援船構想~船を活用した被災地の医療福祉支援~ 神戸大学 大学院海事科学研究科 名誉教授◆井上欣三
- 海の恵み・海藻から作りだすバイオエタノール 東北大学大学院農学研究科 教授◆佐藤 実
- 日本郵船ネイチャーフェローシップ 日本郵船株式会社 CSR推進グループ◆宮本亜矢子
- インフォメーション 2011年「海の日」(第3回)懸賞論文入選作品の発表
- 編集後記 ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所・教授)◆秋道智彌
