Ocean Newsletter
第25号(2001.08.20発行)
- 東京大学海洋研究所教授◆徳山英一
- よこすか市民会議代表◆片桐信治
- edutainments.net 代表、東海大学海洋学部研修員◆堀口瑞穂
- ニューズレター編集委員会編集代表者 (横浜国立大学国際社会学研究科教授)◆来生 新
自前エネルギー、メタンハイドレート
東京大学海洋研究所教授◆徳山英一日本はエネルギー資源の乏しい国と考えられていた。しかし、わが国周辺海域にはメタンガスを大量に含むメタンハイドレートが大量に存在することが明らかにされつつある。これを受けて、わが国ではメタンハイドレートの資源化を視野に入れた、研究・開発を世界に先駆けて推進している。
はじめに

メタンハイドレートをすでにご存知の読者も多数いらっしゃるものと思います。昨今は日本周辺海域に大量の埋蔵量が予測され、日本が世界に先駆けて探査から生産までの研究・開発を開始したことが新聞等で報じられています。メタンハイドレートは、メタンガスと水から構成された固体であり、結晶構造を持っています。この固体は氷と異なり燃えて、炭酸ガスと水になることから(図1)、未来の資源としての可能性が指摘されています。
メタンハイドレートとは?
それではメタンハイドレートとはどのような性質を持っているのでしょうか? 水が結晶構造を持つといえば、氷を連想しますが、メタンハイドレートも塊状や、シャーベット状の産状を示します。また、氷は1気圧では摂氏0度以下で存在可能ですが、メタンガスと水は、圧力が数十気圧以上の場合、摂氏数度までハイドレートとして安定に存在します。この条件、つまり圧力が数十気圧以上であり、温度が数度の条件は、水深が数百m以上の海底では一般的に満足されています。海底には当然海水が存在するので、もし十分な量のメタンガスが存在すればメタンハイドレートがごろごろと海底に転がっていることが期待されるわけです。
事実、クリミア半島が面する黒海の海底には、メタンハイドレートがごろごろと海底に転がっていることが確認されています。その理由は黒海が水深2000mを越す深い海で、また陸に取り囲まれて外海との水の交換が極めて少なく、さらにドナウ川に代表される河川から大量の有機物が供給されることから、海底でメタンガスが多量に発生するためです。有機物を分解してメタンガスを発生する反応は微生物が担っていると考えられています。実は、この状態は日本が先進国の仲間入りをするために突っ走っていた時代、河川が汚れて夏季にメタンガスが川底から発生した状態と共通点を持っています。しかし、日本の場合は、河川であることから、圧力が低く、かつ温度が高いために、メタンハイドレートが形成される環境ではありませんでした。
日本周辺海域のメタンハイドレートの特徴
それでは日本周辺の海域の場合はどのような特徴が見られるのでしょうか? 実は日本周辺ではプレートの沈み込みによる地殻変動と密接に関連しています。プレートの沈み込みといえば、地震や火山を引き起こす原因と理解されていますが、実は資源の面でわれわれにお返しをしてくれているのです。つまり、日本周辺海域では急峻な河川から供給される堆積物は、直接沈み込みの境界に供給されるか、あるいはその途中で砂防ダムのような地形でせき止められるかのいずれかです。実は砂防ダム地形もプレートの沈み込みにより形成されたものです。
日本周辺の場合、陸から供給される堆積物そのものに含まれる有機物は黒海と比較すれば極めて少ないのですが、プレートの沈み込みに伴う地殻の変形の結果、透水性の高い地層中から断層に沿って、あたかも雑巾を絞るように、ぶよぶよの堆積物から水が搾り取られ、その水とともにメタンガスも移動して表層地殻に濃集するためです。この場合も多くのメタンガスは微生物が作り出していると考えられています。また、日本周辺海域の場合、黒海のように海底面にメタンハイドレートの分布は確認されていません。黒海の例が極めてまれなのかもしれません。
前述したように、数百mを越す海底面ではメタンハイドレートが安定に存在可能と述べましたが、例えば水深が400mを越す深海では、海底面から下の堆積物中でもメタンハイドレートが安定な状態は満たされています(図2)。しかし、地下深くなるにつれ、圧力は増しますが、地温が上昇する効果が圧力の効果を上回り、ある深度より深くではメタンハイドレートは存在できなくなります。この境界より上の堆積物中にメタンガスが十分に存在する場合にはメタンハイドレートが含まれ、下の堆積物にはメタンガスと水が分離して含まれることになります。このような堆積物の状態の違いをあらわす境界は、リモートセンシングで知ることができます。
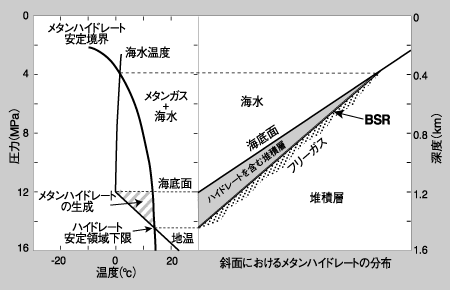
メタンハイドレートを探す
メタンハイドレートを探り当てるリモートセンシングの体表的な手法は音波探査法です(図3)。本探査法は、舟で海釣に出たことのある方であれば使用した経験のある魚群探知機による魚の群れの探査法と類似しています。図3の上図は音波探査の概念図ですが、音波探査法ではパワーのある音源を使用するため、音波は地殻内まで貫入し、それが反射する境界面を描くことができます。一般に反射面は地層を表現しますが、上述したメタンハイドレートの安定境界の下限が極めて特徴のある反射面として表されます。この境界を、BSRと呼びます。このBSRの分布からメタンハイドレートの存否を知ることができるのです。図3の下図は音波探査記録の実例で、地殻の表面を表しています。縦軸は水深に対応し、1秒間は750mに相当します。したがって、5秒は水深が3750mの深海を示します。
メタンハイドレートの開発に向けて
これまでに実施された音波探査の記録をもとに、日本周辺海域のBSRの分布を調べてみると、四国沖から御前崎沖の太平洋の海底に顕著にBSRが発達することが明らかにされています。メタンハイドレートの埋蔵量はBSRの分布域に、堆積物の単位体積に含まれるメタンハイドレートの量比を仮定することによって推定できます。その結果ではメタンハイドレートの埋蔵量は日本が消費するメタンガスの約100年分に達するという推計も出されています。
このような状況のもと、わが国では資源エネルギー庁の主導のもと探査から生産までの一貫した開発計画が昨年度立案されました。上述したようにメタンハイドレートは深海の堆積物中に存在することから、その開発には困難が伴うことが予想されますが、今年度から十数年にわたって継続する本研究は、世界のメタンハイドレート開発の先駆となるものであり、その成果が期待されます。(了)
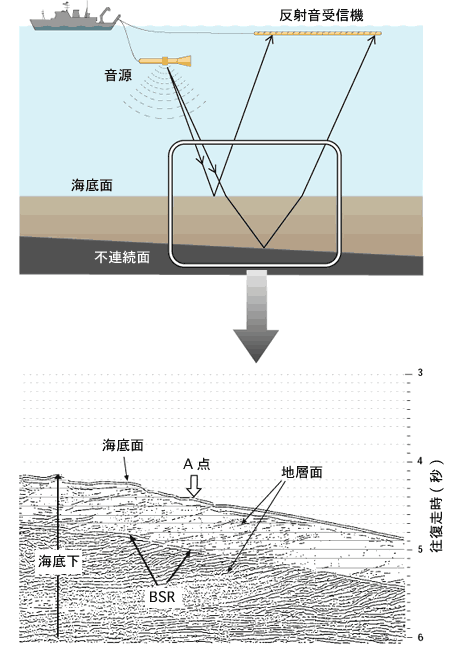
第25号(2001.08.20発行)のその他の記事
- 自前エネルギー、メタンハイドレート 東京大学海洋研究所教授◆徳山英一
- 読者からの投稿 海洋文化を地域から ~国際海の手文化都市・横須賀の「よこすか市民会議」の活動~ よこすか市民会議代表◆片桐信治
- 読者からの投稿 海岸での体験学習に向けて edutainments.net 代表、東海大学海洋学部研修員◆堀口瑞穂
- ニューズレター編集部に届いた読者からのご意見
- 編集後記 ニューズレター編集代表 (横浜国立大学国際社会学研究科教授)◆来生 新
