Ocean Newsletter
第241号(2010.08.20発行)
- 日本財団 海洋グループ長◆海野光行
- 東京海洋大学 海洋環境学科 教授、東京海洋大学江戸前ESD協議会 共同代表◆河野(こうの) 博
- 社団法人日本海難防止協会 常務理事◆濱野勇夫
- インフォメーション
2010年「海の日」(第2回)懸賞論文入選作品の発表 - ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所副所長・教授)◆秋道智彌
江戸前の研究と江戸前ESDリーダーの養成
[KEYWORDS] 東京湾/沿岸域の総合的管理/文理融合東京海洋大学 海洋環境学科 教授、東京海洋大学江戸前ESD協議会 共同代表◆河野(こうの) 博
江戸前の海を自然科学的に解明し、その自然および人との関わりを地域の方々といっしょに学ぶという、二つの調査研究を紹介する。これらによって「江戸前ESDリーダー」の養成ができ、さらに「江戸前の海の総合的管理」を目指している。
江戸前の海の総合的管理をめざして
東京湾の湾奥部である江戸前の海は、高度経済成長にともなう凄まじいまでの開発が一段落し、少し余裕のある時代になってきました。ウォーターフロントと呼ばれるおしゃれな場所が整備され、私たちも江戸前の海を「憩いの海」と感じ始めています。しかし私は、今こそ、「江戸前の海を持続的に利用することができるかどうかの関頭に立っている」という認識をもっています。
いろいろな人が江戸前の海を利用し始めると、いろいろな摩擦も生じてきます。しかし、江戸前の海の利用に関しては、多様な関係者の協議による意思決定がなされていない状態、すなわち「総合的な沿岸域管理がなされていない」といえます。そこでここでは、自然科学的な研究「羽田周辺水域環境調査研究委員会(以下、羽田調査)」と、社会科学的な活動「東京海洋大学江戸前ESD協議会(江戸前ESD)」を紹介し、「江戸前ESDリーダー」の養成による「江戸前の海の総合的管理」の可能性を探ります。なお、ESDというのはEducation for Sustainable Developmentで、「持続可能な開発のための教育」※1です。
江戸前の海の変貌
江戸前の海は目まぐるしく変化しました。100年ほど前には、広大な干潟にハマグリなどが多く生息し、打瀬船がシバエビなどを漁獲していました※2。第二次世界大戦が終わって高度経済成長の時代には、江戸前の海の埋め立てと浚渫、港湾の整備がどんどん行われました。しかし、20年ほど前のバブル景気の崩壊後には、私たちの江戸前の海に対する感覚も変化しています。そこで私には疑問がありました。本当に江戸前の海は穏やかな「憩いの海」なのか? ひょっとしたら、海の中ではかつての「死の海」が広がっているのではないのか? 私の研究室は「魚類学研究室」です。それならば東京湾の魚類を研究しようと考えたのは、当時の東京水産大学に赴任してから2年後の平成5(1993)年のことでした。それ以来、魚類が江戸前の海の沖合や干潟などをどのように利用しているのか、といった研究を続けています。とくにこの10年ほどは見た目もきれいになり、「最近の江戸前の海は、きれいになりましたね」という声もよく聞かれるようになりました。しかしその一方で、沖合にでると赤潮に遭遇し、人工の干潟に行くと波打ち際では泡だった水が腐臭を放っていたりして、魚類の研究からだけでは見えてこない何かが江戸前の海でおこっているのではないかといった不安感を持っていました。
江戸前の海を知るための二つの視座
こうした、漠然とした江戸前の危機を感じていたときに、二つの調査研究に携わることになりました。一つは羽田調査で、もう一つは江戸前ESDの活動です。
羽田調査は、新滑走路の建設工事にともなう環境への影響調査が目的で、平成17(2005)年に国交省関東地方整備局横浜港湾空港技術調査事務所に設置されました。これまでに3回のシンポジウムと13回の研究委員会などを行い、多摩川河口域を総合的に捉えることがほぼ可能になってきました。その中には、江戸前の海にはかなりの栄養塩が存在し、夏季には広範囲の底層域で無酸素水塊が形成されることなど、やはり魚類の研究からだけでは見えてこない貴重なものが多く含まれています※3。
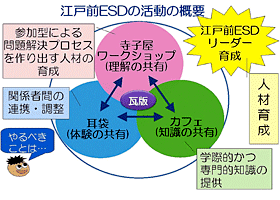
江戸前ESD設立のきっかけは、東京海洋大学の学生だけではなく、首都圏の若い世代の人たちが地先の海である江戸前の海を知っていないこと、あるいは知っていてもその重要性を認識していないことでした。そこで、本学の持つ江戸前の海に関する知を提供し、地域の方々と共同して江戸前の海について考えてみようということで、平成18年に教職員の有志で協議会を結成しました。目的は、江戸前の海の持続可能な開発と利用を考える能力を備え、それに基づいて関係者と協議をして合意形成へと展開することができる「江戸前ESDリーダー」の養成です。方法は、寺子屋(ワークショップ:理解の共有)を中心にして、カフェ(江戸前の海の環境や生物などについて学ぶこと:知識の共有)、耳袋(江戸前の海を訪れそこで生活している人たちの話を聞くこと:体験の共有)の三つの要素を組み合わせた活動を行うことです。結成から今年の6月30日までに50回近くの活動を行っています※4。主な活動としては、附属図書館との共催によるカフェ「江戸前を知ろう ―「むかし」と「いま」の東京湾 ―」、大森海苔のふるさと館との共催によるカフェ+寺子屋の「江戸前マイスター講座」(月に1回、連続6回)などがあります※5。また広報誌「瓦版」を出版し、これらの活動の一部については報告をしています※6。
江戸前ESDリーダー養成の仕組み作り
この5年近く、学生や地域住民の方々とともに多彩な活動を繰り広げてきました。参加してくださった学生や地域住民の方々も積極的に議論に参加し、江戸前の海のあるべき姿というものもボンヤリと形になりつつあります。江戸前ESDの活動はほぼ成功しているといってもいいのでしょう。しかし「江戸前ESDリーダーの養成」という人材育成については、何かモヤモヤとして達成感がなく、あまり得心していません。その理由を考えてみました。
一つは正式な教育課程ではないということです。正式な教育課程である必要はないのですが、やはり何らかの資格のようなものを授与することができれば、学生のモチベーションもあがります。地域住民の方々に対しては、例えば大学に生涯学習の制度を設けて人材育成を行うということも可能なのですが、その整備もまだできていません。もう一つは羽田調査のような自然科学的研究との連動(文理融合)です。何人かの先生は両方の調査に携わっていますが、羽田調査そのものは江戸前ESDとは関係がありません。現在行っている江戸前ESDの活動は、私たちが江戸前の海を対象にして独自に開発した規模の小さなプログラムに基づいています。羽田調査のような大規模かつ最新の研究結果をサイエンスカフェで披露してもらったりワークショップの場として利用させてもらったりすると、さらにしっかりとしたプログラムが作成できるのではないかと考えています。
こうした難題を一つ一つ片付けることによって「江戸前ESDリーダー」が育ち、さらに「江戸前の海の総合的な沿岸域管理」もできるようになると期待されます。(了)
第241号(2010.08.20発行)のその他の記事
- 海の世界の人づくり 日本財団 海洋グループ長◆海野光行
- 江戸前の研究と江戸前ESDリーダーの養成 東京海洋大学 海洋環境学科 教授、東京海洋大学江戸前ESD協議会 共同代表◆河野(こうの) 博
- 海運関係者と水産関係者の相互理解の場 社団法人日本海難防止協会 常務理事◆濱野勇夫
- インフォメーション 2010年「海の日」(第2回)懸賞論文入選作品の発表
- 編集後記 ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所副所長・教授)◆秋道智彌
