Ocean Newsletter
第191号(2008.07.20発行)
- 民主党 衆議院議員◆前原誠司
- 前国土交通省海事局海運基盤強化政策準備室長◆藤田礼子
- 女優◆岸 ユキ
- 第1回海洋立国推進功労者表彰の受賞者決定
- ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所副所長・教授)◆秋道智彌
高坂正堯が描いた「海洋国家日本の構想」
[KEYWORDS] 高坂正堯/海洋国家/フロンティア民主党 衆議院議員◆前原誠司
いまから40年も前に、高坂正堯先生はその著書の中で「海は残された最大のフロンティア」と述べられ、漁業資源や海の鉱物資源のみならず、自国の防衛にも資すると指摘されている。
わが国に必要なのは、「広大なフロンティア」を開発することへの国家としての覚悟である。
日本の未来を切り開いていくために、政治家である限り「広大なフロンティア」開拓の努力を続けていきたい。
高坂正堯先生との出会い
私が「海洋」という言葉を初めて意識したのは、大学時代だ。司馬遼太郎さんの『竜馬がゆく』にも感銘を受けたが、何と言っても高坂正堯先生の影響が大きい。浪人時代に読んだ先生の『国際政治』(中公新書、1966)という新書本で、私はすっかり高坂正堯という国際政治学者が好きになり、京都大学法学部に進学後、当然のように先生の国際政治学を受講し、ゼミも高坂ゼミに所属した。国際政治学の講義後、何度か授業内容の説明を求めて先生の下を訪れたが、ある時、自著である「『海洋国家日本の構想』を読んでみろ」とのアドバイスを受けた。何軒かの本屋を廻ってみたが、ない。その旨を先生に伝えたところ、先生は本棚から一冊を取り出し、私に下さった。それが今でも私が大切にしている、昭和44年に第4版で出版された『海洋国家日本の構想』である。ちなみに、この本の初版は昭和40年だ。
繰り返し読んでみると、高坂先生の先見性には、改めて驚かされる。そう言えば、冷戦時代の真っ只中の授業で、「将来、アメリカとソ連は仲良うなるかもしれんで。アメリカという国は、戦った国と不思議に仲良うなっとる。日本がそうや。そやけど、その時にはソ連という国の名前は、ロシアに変わってるかもしれんで」と仰っていた。その時は別に気にも留めていなかったが、その後の歴史は先生が予想されたとおりに推移している。
同時に、日本の政治が大事な問題点を先送りにしてきたことにも驚かされる。昭和40年に先生が指摘されていた政策課題は未だに達成されておらず、今も重要なテーマのままだ。
『海洋国家日本の構想』
高坂先生は『海洋国家日本の構想』の中で、海洋国家として政府にしか出来ない長期的な政策課題を二つ、挙げておられる。一つは「低開発諸国の開発」であり、もう一つは「海の開発」である。先生がポイントとして示しておられる文章を、少し長くなるが引用する。
―しかし、低開発諸国の開発とならんで、私は海の開発の重要性を強調したい。いままで、海は資源としての価値をあまり持たなかった。海は極めて多様な資源を秘めながら、人間にその門戸を開放してこなかった。しかし、最近潜水技術の進歩、原子力などの巨大なエネルギーの開発、種々の海洋調査技術の進歩によって、その開発の可能性を示し始めた。
まず、すでに開発されている漁業資源が問題になるだろう。何故なら、今後十数年間に、世界の人口が十数億増加するものと予測されるし、彼らに必要な蛋白質資源がどこかに求められなくてはならないからである。それだけでもたいへん問題であるのに、それに続いて、海の鉱物資源の開発も次第に実用化してくるであろう。そして、それとともに国際法の原則であった海洋の自由という原則は不十分になり始めるであろう。この原則は、海洋が軍事的な意味と貿易のための公道という意味しか持たないときには妥当した原則であった。しかし、今や海は資源としての意味を持ち始め、その重要性を増していくであろう。それは今までの海洋の国際法秩序に衝撃を与えるものである。それは現に、漁獲高の制限や大陸棚の問題で、我々に難しい問題を投げかけているのだ。
それは、国際秩序の問題であると同時に、日本の国民的利益の問題である。海は残された最大のフロンティアとして、今後重要性を増大させてくるであろう。その場合、日本がその国民的利益を守るにも、国際秩序の建設に参与するにも、海洋の開発に積極的に参加しなくてはならないのである。
そして、そのためには大規模な科学的基礎調査を必要とする。しかし、海洋の開発にあたっては、他の場合とは比較にならないほど多額で、私企業の投資ではとうてい不可能な調査投資が要求されるのである。何故なら、海は誠に広大で、その調査には著しい費用と人材を必要とするからである。
しかし、海洋調査は間接的には防衛にもつながっていることが注意されなくてはならない。自らの周囲の環境を知ることこそ、防衛の要諦だからである。したがって、次の三つを提案したいと思う。
- 現在の自衛隊の予算の3分の1程度を海洋調査に回すこと。
- 日本近海については海上自衛隊が中心となって調査すること。
- 世界の海については、国際協力を原則として、科学者が調査をおこなうこと。
それはかなり思い切ったことではあるが、10年後にはその効果を現し始めているにちがいない。そして、それは決して日本の防衛を不十分にはしないのである。
これら、広範にわたる施策の必要性と効果は、現在はそれほど明らかではないかもしれない。たしかに、それは未知の要因を含んで入る。しかし、我々に現在最も必要なのは、この未知のものを求める視野の広がりなのである。(『海洋国家日本の構想』高坂正堯、中央公論社(1965))―
この著書には、珠玉のメッセージが幾つもちりばめられている。この本は国連海洋法条約が批准される、はるか前に書かれているが、高坂先生は海が持つ意味の変容を的確に予言されている。つまり、海の持つ資源性に注目が集まり、「自由な公道」ではなくなる、と。著書には「海は残された最大のフロンティア」と述べられ、漁業資源や海の鉱物資源のみならず、自国の防衛にも資すると指摘されている。自らの周辺の環境を知ることは防衛の要諦である、と。
日本の未来にむけて
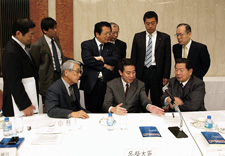
海洋基本法フォローアップ研究会にて(2007年11月28日)
先生がこの著書を世に問われてから約40年の年月が経った。日本を取り巻く周辺環境は大きく変わった。北朝鮮の核・ミサイル開発による地域の不安定さや経済的発展を背景とした中国の目覚しい軍事力の増強などを考えるとき、自衛隊予算の3分の1を海洋調査にまわすことは現実的ではないが、先生が仰りたかったことは、それぐらいの投資と国家の覚悟がなければ「広大なフロンティア」を開発することはできないということだろう。
食糧自給率はカロリーベースで約39%。水産資源に限っても50%を割り込んでいる。エネルギーの自給率は原子力を除けば約4%、原子力を含めても20%足らずだ。世界人口の増大と新興国の経済発展で、食糧とエネルギーの需給は逼迫し、さらなる価格の高騰が予想される。食糧・エネルギーの安全保障という観点からも、海の開発は不可欠なのである。
同時に、世界第6位の海洋国家として、領土・領空・排他的経済水域・大陸棚といった日本の主権を、しっかりと守り抜く国家としての意志も確固として持ち続けなければならない。特に沖ノ鳥島、尖閣諸島など、日本の主権を守る上で離島の保護・管理は、最重要の課題の一つだ。
日本の英知を結集し、広大なフロンティアを開発することが、技術や産業、学術の面でも、日本の新たな発展の原動力にもなるだろう。海洋国家日本の偉大さを引き出すのが、「慎重さと冒険、『非英雄主義』と『英雄主義』をつなぐことができる政治の技術であり、さらに慎重さを単なる慎重さに終らせない視野の広さなのである」と高坂先生は指摘され、「そこに日本の未来がある」と喝破された。40年遅れではあり、財政的にも厳しい現況ではあるが、日本の未来を切り開いていくために、政治家である限り「広大なフロンティア」開拓の努力を続けていきたい。(了)
第191号(2008.07.20発行)のその他の記事
- 高坂正堯が描いた「海洋国家日本の構想」 民主党 衆議院議員◆前原誠司
- トン数標準税制の導入~外航海運政策の新時代の幕開け~ 前国土交通省海事局海運基盤強化政策準備室長◆藤田礼子
- 海に想いをよせて 女優◆岸 ユキ
- インフォメーション 第1回海洋立国推進功労者表彰の受賞者決定
- 編集後記 ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所副所長・教授)◆秋道智彌
