Ocean Newsletter
第11号(2001.01.20発行)
- 九州大学応用力学研究所教授・力学シミュレーション研究センター長◆柳 哲雄
- 金沢工業大学環境システム工学科助教授◆敷田麻実
- (財)神戸国際観光コンベンション協会見本市事業部推進課長◆中西理香子
- インフォメーション
- ニューズレター編集委員会編集代表者 (横浜国立大学国際社会学研究科教授)◆来生 新
沿岸海域の富栄養化機構
九州大学応用力学研究所教授・力学シミュレーション研究センター長◆柳 哲雄沿岸海域に流入する生活廃水や工場廃水の急増により、頻発する赤潮・貧酸素水塊。現在世界中の閉鎖性海域で、窒素・リンの陸岸からの負荷量を減少させて、赤潮・貧酸素水塊の発生を防止する富栄養化対策が考えられているが、どのような対策が最も有効であるかは、各湾の栄養物質輸送特性をきちんと理解した上で決められなければならない。
閉鎖的内湾では表層で赤潮が、底層で貧酸素水塊が発生する。
その原因は陸岸から窒素やリンなどの栄養塩が過剰に流入することにある。
毎年夏季になると、東京湾、伊勢湾、三河湾、大阪湾、洞海湾、博多湾など富栄養化した日本の閉鎖的内湾では表層で赤潮、底層で貧酸素水塊が発生する。赤潮とは特定の植物プランクトンが異常に増殖して海水の色が変色する現象、貧酸素水塊とは表層の植物プランクトンの死骸などが沈降して、光の届かない底層でバクテリアにより分解され酸素を消費して、海水中の溶存酸素濃度が減少することで、底棲生物などが死滅する現象を指す。
赤潮や貧酸素水塊が発生する主な原因は陸岸から窒素やリンなどの栄養塩が過剰に流入することにある。植物プランクトンは栄養塩と光と二酸化炭素を使って光合成を行い、無機物から有機物を合成する。さらに光のあたる表層で多量に発生し、底層に沈降した植物プランクトンの死骸など多量の有機物が分解されるとき、底層で過剰に酸素を消費して貧酸素水塊が発生するからである。
沿岸海域にはもともと栄養塩が現在ほど多量には存在しなかったので、植物プランクトンも多くの種類が適当な密度で存在し、底層に沈降する有機物も多くはなく、赤潮や貧酸素水塊の発生はほとんど見られなかった。しかし、日本では1960年代以降、沿岸海域に流入する生活廃水や工場廃水の急増により、大量の栄養塩が沿岸海域に流入するに及び、沿岸海域が富栄養化して、赤潮や貧酸素水塊が頻発するに至った。このような状況は世界中で見られ、アメリカのチェサピーク湾、ヨーロッパのバルト海や黒海、東南アジアのタイランド湾などの閉鎖性海域でも赤潮や貧酸素水塊の頻発に悩まされている。
富栄養化の度合いは、陸岸からの栄養塩の流入量に比例しない。
表層を外洋に、底層を湾奥に向かって流れる密度流が、湾内の富栄養化を進める。
それぞれの閉鎖性海域の富栄養化の度合いは陸岸からの栄養塩の流入量に比例するかというと、実はそうではない。表1に東京湾・三河湾・洞海湾・博多湾の容積、全窒素負荷量、単位容積当たりの全窒素負荷量、湾内の全窒素濃度、全窒素の平均滞留時間、淡水の平均滞留時間を示す。これを見ると、まず単位容積当たりの全窒素負荷量が最も大きい洞海湾の全窒素濃度が最も高い(最も富栄養化している)ことがわかる。しかし、単位容積当たりの全窒素負荷量が最も少ない三河湾の全窒素濃度は負荷量の多い博多湾より高い。これは三河湾の全窒素の平均滞留時間が40日で、博多湾の16日よりはるかに長いためである。
| 容積 (X10 9 m 3 ) | 全窒素負荷量 (ton/month) | 単位容積当たりの全窒素負荷量 (X10 -9 ton/month m -3 ) | 全窒素濃度 (μg/l) | 窒素の平均滞留時間 (days) | 淡水の平均滞留時間 (days) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京湾 | 7.34 | 9,000 | 1,230 | 1,123 | 27 | 13 |
| 三河湾 | 0.70 | 229 | 327 | 440 | 40 | 40 |
| 洞海湾 | 0.09 | 313 | 3,597 | 2,008 | 13 | 7 |
| 博多湾 | 0.42 | 384 | 906 | 243 | 16 | 8 |
平均滞留時間とは湾内に負荷された物質が平均的にどの位の時間その湾内に留まるかを示す指標で、平均滞留時間が長いほど負荷された物質が長く、したがって、大量に湾内に留まり、富栄養化が進みやすいことを意味する。
博多湾より三河湾の全窒素の平均滞留時間が長い主な理由は、淡水の平均滞留時間が三河湾の方が長いことにある。三河湾に流入した淡水(主に河川水)は博多湾と比較すると5倍も長く湾内に留まる。この理由は潮流、吹送流、密度流など淡水を湾外に輸送する流動が博多湾では活発で、三河湾では不活発なことにある。特に、表層を外洋に、底層を湾奥に向かって流れる密度流(河口循環流と呼ばれる)が博多湾でより発達することが、博多湾の短い淡水の平均滞留時間の理由になっている。
一方、三河湾では淡水と全窒素の平均滞留時間が両方とも40日でほぼ等しい、すなわち、全窒素は淡水とほぼ同様な挙動を示すのに対して、東京・洞海・博多湾の全窒素の平均滞留時間は淡水のそれのほぼ2倍になっている。これは淡水とともに陸岸から流入した無機溶存態窒素(栄養塩)がまず表層で植物プランクトンに取り込まれ有機化して粒子(有機懸濁態窒素)となり、動物プランクトンに食べられ糞として底層に沈降し、底層の密度流により湾奥に運ばれながら、分解されて無機溶存態(栄養塩)となり、表層に湧昇して再び植物プランクトンに取り込まれるので、表層の密度流にのってすみやかに湾外に輸送される淡水と比較すると、長く湾内に留まるためである。このような機構によって窒素などが沿岸海域に長く留まる過程を栄養物質のトラップ機構と呼ぶ(図1)。
■図1 河口循環流が卓越する閉鎖性沿岸海域における栄養物質のトラップ機構
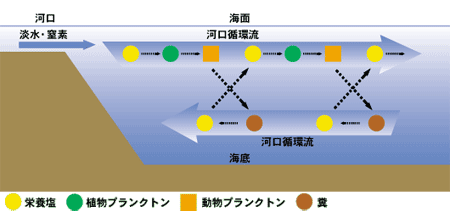
現在世界中の閉鎖性海域で、窒素・リンの陸岸からの負荷量を減少させて、赤潮・貧酸素水塊の発生を防止する富栄養化対策が考えられているが、どのような対策が最も有効であるかは、以上述べたような各湾の栄養物質輸送特性をきちんと理解した上で決められなければならない。例えば、図1のような機構が卓越する沿岸海域では、陸岸からの栄養塩の負荷量を相当量削減しても、底層を通じて外洋から流入する栄養塩の影響により、湾内の富栄養化は簡単には解消しない。
第11号(2001.01.20発行)のその他の記事
- 沿岸海域の富栄養化機構 九州大学応用力学研究所教授・力学シミュレーション研究センター長◆柳 哲雄
- 第三の沿岸域危機と沿岸域の未来 金沢工業大学環境システム工学科助教授◆敷田麻実
-
海の大切さを子供たちに伝える~ペットボトルの潜水艇が教えてくれた、海洋教育の可能性~
(財)神戸国際観光コンベンション協会見本市事業部推進課長◆中西理香子
- 中央省庁再編に伴う海洋関係行政機構の改編について解説1●国土交通省 インフォメーション
- 編集後記 ニューズレター編集代表 (横浜国立大学国際社会学研究科教授)◆来生 新
