Ocean Newsletter
第32号(2001.12.05発行)
- 日本大学名誉教授◆佐久田昌昭
- 横浜国立大学 国際社会科学研究科 教授◆来生 新
- 琴引浜の鳴り砂を守る会◆松尾省二
- インフォメーション
- ニューズレター編集委員会編集代表者((社)海洋産業研究会常務理事)◆中原裕幸
「アクアポリス」の教訓
~トータルライフサイクルコストの議論を~
日本大学名誉教授◆佐久田昌昭沖縄海洋博の「アクアポリス」の建造から解体までの一生を概観し、鎮魂の思いを踏まえ、在野の一技術者から自分自身を含めての反省の弁を述べる。四分の一世紀前のわが国の巨大プロジェクト企画推進力がいかに付け焼刃的な、虚なものであったか。建造から解体までのコスト対費用効果を吟味することは、環境問題の「トータルライフサイクルコスト」を議論することでなければならない。
沖縄海洋博のシンボル「アクアポリス」
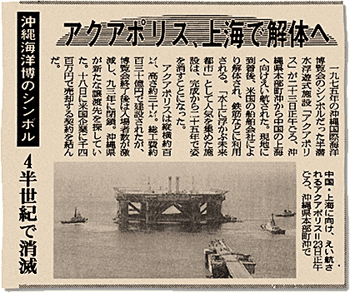
クリックすると拡大表示でご覧いただけます
去年の10月末のことで旧聞になるが、「アクアポリス」が沖縄本部町沖から中国・上海へ曳航、現地で解体されたとの報道が一部の新聞で報じられた。「アクアポリス」というと、読者諸賢ご存知のように、四分の一世紀前の1975年(昭和50年)沖縄返還記念の「沖縄国際海洋博覧会」のシンボルとして、当時の建造費130億円以上を投じた半潜水式構造物で、一辺100m四方の広大な最上階デッキと内部の居住・展示空間を売り物にした、文字通り「アクアポリス」(aqua-polices=海洋都市)で、宇宙・原子力開発と並ぶ人類共通の開発テーマ=海洋開発のシンボルとして、その中に発電設備他一切の必要設備を持つ独立した都市機能を包含する世界に誇る海洋構造物であった。
この「アクアポリス」誕生については、関係者は多数にわたり、もちろん運営についても、現役の方々は第一線でご活躍中であることは承知しているが、古希を過ぎた一技術者として、この新聞記事の副題"沖縄海洋博のシンボル・アクアポリス、四半世紀で消滅"に触発されて、以下、率直な自分自身を含めた反省の弁をつづりたい。
「アクアポリス」に反対した筆者の予想的中と落胆
沖縄国際海洋博覧会(以下海洋博)が正式決定されたのは、確か1972年5月の沖縄復帰実現の直後であったと記憶している。武力による占領地域が平和裡に返還された一大快挙を記念して国際的に認知された海洋博であったが、すでに1970年の日本万国博覧会(大阪)の経験もあって、順調な手続きのもと、世界初の海洋博としてどのようなコンセプトの海洋博を目指すか、当時の識者を集め、総合的なプロデューサーとして若き通産官僚の堺屋太一氏と海洋建築の第一人者、菊竹清訓氏が関係したことも記憶が鮮明である。
この海洋博の目玉として「アクアポリス」が誕生したのであるが、数多くの候補案からこのアクアポリス案を採用した時に、筆者は(在野の一技術者として)最後まで反対した記憶があり、思い出すのも重苦しい感を否定することができない。
主として、海洋博後のアクアポリスの利用法について、非常に漠とした説明から、この巨大な構造物の将来に対し責任ある回答を得られないまま、大手造船企業で分担建造され、最終的に三菱重工(当時、広島造船所の仮設ドック)内でアッセンブルされた。この型式の構造物は、「半潜水型移動式海洋石油掘削装置」として発展した歴史があり、欧米で研究開発されて来たが、すでにわが国では、海外のコンサルタントエンジニアリング企業の技術指導も得ながら、大手造船所の手で直接建造され、その建造技術は世界的に定評があった。企画設計から建造までわが国で一貫して実施するのは、正式にはこれが第1号であったことも記憶している。
このような掘削装置をその中心に据付けることを想定した構造物様式を、沖縄本島の沿岸浅海域に係留し人間居住・施設に利用することは、いろいろ識者の間で、あるいは専門家グループの間で検討されたことであろうが、陸上生物の人間が浮遊式海洋構造物で生活を営む不自然さを数多く体験した筆者には、例え海洋博という期間に限ったにせよ、不特定多数の一般客の方々を対象にした「アクアポリス」構想との間に根本的な差異があると指摘せざるを得なかった。この差異は、作業空間内で高能率の作業に従事する特定作業員の感覚と、生活空間内で心身の安息を目的とする家庭人の感覚とはまったく異質なものであると説明すれば、ご理解いただけるだろう。しかし、建造後本部沖まで無事曳航、係留され、固定された桟橋を歩いてアクアポリスを訪問した時は、さすがに、堂々たる正面外観とその内部のコンパクトにまとまった設備に複雑な感動を覚えたことも思い出される。しかし、海洋構造物全体のボリュームのうち、10%の居住生活利用空間率に、半潜水式構造物の空間利用の限界を知り、ある面で予想が的中した確認と、落胆したことも思い出される。
"この複雑な感動、予想的中の確認と落胆"は、今から反省すると、海洋博の目玉施設にこの様式(半潜水型移動式)を採用したことの基本的な失態を簡潔に表現している。従来の(石油掘削装置を中心に据付けた大水深荒天時設計条件を加味した)半潜水式構造物と異なる、新しい「アクアポリス」型の構想・設計条件の設定・施工・据付け稼動(万博の主海上施設として利用)、さらにその後の補完・維持・跡利用のための改造も考慮し、20年~30年ほどの利用期間(償却)後の解体までを、企画者側は予想・期待したはずである。しかし、「アクアポリス」の海洋博終了後の"航跡"を見ると、残念ながらまったくこれを裏切っているとしか評価できない。
建造から最終処理までのトータルライフサイクルコストの検討を
ご存知のように海洋博終了後の「アクアポリス」は、管理財団・開発公社・株式会社・第三セクター・台湾企業への売却等、話題は豊富で、それ相応の経緯があったことは事実だが、結果としては、実に虚しい実りの少ない結末であった。もちろんそこには、国から県への有償譲渡、県から公社への無償譲渡、公社から株式会社への無償貸付・譲渡、株式会社の第三セクターへの吸収合併、破産宣告・県への無償譲渡、そして今回のスクラップとなっての米国企業への売却というプロセスの節々には、関係者の方々の苦渋の決断があったことも逐一報道されてきた。
しかし、われわれはここで反省しなければならないことは以下の一点あることを強調しなければならない。海洋構造物を計画する場合は、コミッショニング(commissioning:就役)からデコミッショニング(decommissioning:退役)までを考えたコストパーフォーマンス(コスト対効果)を想定・確立し、その評価を厳正に行い、稼動中も絶えず要所要所でチェック補正・利用目的変更などの対応を間違いないようにしなければならないことである。しかし、このことは18世紀の産業革命が、英国の農業革命から始まった時から資本主義下での鉄則として繰り返し説かれていたことであるにもかかわらず、1970年代のわが国の通産省中心の海洋博企画スタッフには、この初歩的な鉄則を理解・実行した人は皆無であったという評価は避けられない。
わが国は、「科学技術基本法」が制定され、明治以来の富国殖産政策から、平成時代の「科学技術創造立国」にまで成長、変貌して来た。世界の中でこれを国是として指導国家の一員として活躍するためには、上記「アクアポリス」の企画から就役(建造)・退役(解体)、そして消滅までの経緯は、諸先輩の苦渋の決断を含め、"他山の石"として貴重な教訓を残してくれたといえよう。(了)
第32号(2001.12.05発行)のその他の記事
- 「アクアポリス」の教訓 ~トータルライフサイクルコストの議論を~ 日本大学名誉教授◆佐久田昌昭
- 公共性と岸壁の専用使用 横浜国立大学 国際社会科学研究科 教授◆来生 新
- 読者からの投稿 琴引浜の鳴き砂を後世へ ~海岸を取り巻く環境について~ 琴引浜の鳴り砂を守る会◆松尾省二
- インフォメーション 欧州における沿岸管理政策統合の動き
- 編集後記 ニューズレター編集代表((社)海洋産業研究会常務理事)◆中原裕幸
