招へい報告 バンコク都関係者が新宿区と横浜市の多文化共生の取組みを視察
移住労働者の児童の就学促進事業では、周辺諸国からの移住者を多く受け入れているタイで、移住労働者の子どもたちがタイの公教育を継続的に受けられるように、制度の周知やタイ語学習の支援を行っています。日本の多文化共生に向けた教育経験を参考にしていただくため、パイロット地域の1つであるバンコク都の関係者に、日本における外国につながる子どもたちへの教育の取組みを、新宿区と横浜市で見学していただきました。
経済発展を続ける東南アジア諸国では、起業家女性の活躍が目立つ。最大の理由は日本と異なり企業などに雇われて働く機会が少ないことだ。特に農村部では、起業は女性が経済力を持つための唯一の選択肢と言える。 笹川平和財団は、インドネシア、ミャンマー、カンボジア、フィリピンの東南アジア諸国で、女性起業家の支援を行っている。今回はインドネシアの首都ジャカルタとその郊外で現地取材を行い、この地域で働く女性起業家や、彼女達を支援するエンジェル投資家、起業家支援の仕組みを取材した。


Co-founderのダイアン・ウランダリーさん(D): 私たちは、ビジネスを通じて社会の問題を解決に導く「社会起業家」の支援をしています。中でも初期の起業家を支援しています。もともと、自分たちの活動にジェンダー視点が必要だという意識は、さほどありませんでした。
なぜなら、インステラ―は、もともと女性が多い組織だったからです。 ただし、GLIAの内容を学んだおかげで、自分たちが持っている「暗黙バイアス」に気づくことができました。バイアスは男性だけでなく女性も持っている。皆が持っているものなのですよね。
シニア・企業開発オフィサーのエルヴィラ・ソウファニ・ロザンティさん(E):
GLIAツールキットは紙ベースで100ページ以上あったので、まず私が読んでCEOに要旨を伝えました。インステラ―の活動に役立ちそうだと思い、GLIAパイロットプログラムへの参加を提言し、参加が決まりました。
私たちが提供している起業家養成のインキュベーションプログラムにおいてジェンダー視点をもってより包摂的なものにしたい、と思ったからです。このプログラムは男女ともに社会起業家を支援するためのもので2014年から5年以上続いています。
これまで社会起業家を支援してきた経験から、男性起業家の率いる企業の方が成長しやいように思えました。そこで、過去にプログラムに参加した起業家にアンケートをとってみたところ、男性の方が野心的で交渉をすること、女性は交渉スキルを学びたいと思っていることが明らかになりました。
こうした課題について、GLIAを機に気づき専門家を招いてインステラ―内部で研修をしたのです。
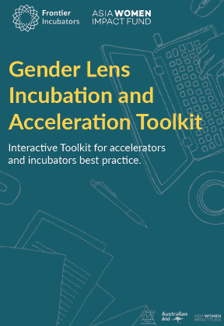
E: 特に役立ったのはGLIAツールキットの中でも、マーケティング資料の作り方に関する項目です。起業家支援プログラムに女性の応募を増やしたい場合は、写真やイラストに女性のイメージを使うと良いそうです。私たちはこれまで、特に意識せず「男性のイメージ」をフリー素材の中から選んで起業家支援プログラムの告知ウェブやSNSを作っていました。そこでは、投資家はスーツの男性、消費者は女性の姿で描かれることが多かったのです。確かに、そういうイメージを見せられたら「これは男性向けのプログラム」と思い女性から敬遠されてしまっていたかもしれません。
面白いのは、ジェンダー視点をもって視覚的な発信を心がけるようにしたところ、私たちの起業家支援プログラムに会社員女性も応募してくるようになったことです。

D:まず、起業家に研修機会を増やしたいです。たとえば、研修に参加する起業家が子育て中であれば、そのような起業家のために安心して研修に参加できるように託児サービスを用意したり、自宅でも必要なスキルを学べるようにオンライン学習の機会なども増やしていきたいです。
インドネシアの働く女性や女性起業家を支援するエコシステムを作る必要があります。これは、多くのインドネシア企業が必要としていることで、女性が主要顧客なのに女性のことが分かっていない企業も、まだたくさんあるんです。自分も起業して思うのは、女性は他の女性に影響を与えて社会を変えることができると思います。
GLIAツールキットは包括的にジェンダーについて学ぶことができ、自分の組織に合うものから取り入れられて使いやすいです。
ダイアンさんとエレヴィアさんの話は、日本で働く女性の経験ともつながる。日本でも女性管理職を増やしたり、起業家女性を支援したりする取り組みが全国で行われている。インタビューに出てきた自信を巡る男女差、募集広告の表象をいかに選ぶかといった実践的な改善策が必要とされている日本で、インステラ―の経験から学ぶことは多くありそうだ。インステラ―で活用されたツールキットは、2月13日から、下記インターネットサイト(英語・ミャンマー語、インドネシア語、カンボジア語)で公開される予定である。
https://toolkits.scalingfrontierinnovation.org/
(写真 Agus Sanjaya撮影)