Ocean Newsletter
第88号(2004.04.02発行)
- 市立酒田病院飛島診療所長・医学博士◆杉山 誠
- 独立行政法人 航海訓練所理事◆小川吾吉
- (株)ゼネシス エンジニアリング事業部◆實原定幸
(株)ゼネシス エンジニアリング事業部◆桜澤俊滋 - ニューズレター編集委員会編集代表者(横浜国立大学国際社会学研究科教授)◆来生 新
海洋温度差発電の胎動
(株)ゼネシス エンジニアリング事業部◆實原定幸(株)ゼネシス エンジニアリング事業部◆桜澤俊滋
海洋温度差発電は、自然エネルギーの切り札としてその行方が大きく注目されている。そのブレークスルーは日本の技術が中心となっている。今、世界各地で実用化に向けた動きが進む中、これまで以上に多くの分野の技術集約が必要となってくる。
なぜ今海洋温度差発電か?
近年、温室効果ガスによる地球温暖化および化石資源の枯渇がますます懸念される中、「持続可能なエネルギーシステムへの転換」がグローバルな流れとなっている。また、エネルギー供給に関してその8割以上を海外に依存しているわが国においては、「安定したエネルギー供給の確保」は以前より最重要の命題とされてきた。今後アジア地域を中心とした開発途上国におけるエネルギー需要の増大、北米、北海地域における石油の供給能力の減少等、石油需要の逼迫が予想されることを考えれば、石油代替エネルギーの開発・導入を一層推進し、石油依存度を低減することが不可欠である。
これら課題に対し、わが国においても様々な自然エネルギー技術の開発及び導入が進められている。しかしながら、自然エネルギーの多くは再生利用が可能で環境に与える負荷が少ない反面、不安定性と負荷変動への対応が難しいという面を持ちあわせている。
一方、海洋温度差発電(OTEC; Ocean Thermal Energy Conversion)は、安定性と負荷変動への対応性の点で非常に優れた特徴を持っていることから、石油代替エネルギー源の中心的な役割を担う技術としてその実用化を急ぐ必要がある。以下に、OTECのしくみやその開発の経緯、現状と今後の展望について述べる。
海洋温度差発電(OTEC)開発の経緯
OTECとは、地球上の約7割を占める海洋の表面を太陽が温めることで蓄えられた膨大な熱量と冷たい深層水との温度差を利用するもので、海と太陽がある限り利用可能な再生可能エネルギーである。OTECに関する研究の歴史は意外に古く、1881年に、フランスの物理学者ダルソンバール(J. D'Arsonval)が考案したものが最初である。そのアイデアは、同じくフランスのクロードに引き継がれ、OTECの実用プラントの建設に執念を燃やしたが、クロードはその実現を見ることなく1960年にこの世を去った。その後、1973年の第一次オイルショックをきっかけにして、OTECは石油の代替エネルギー候補として日本と米国で本格的な研究が行われるようになった。
温度差発電の実用化へ向けたブレークスルー

「そんな小さい温度差を利用できるのか?」という疑問を持たれるかもしれない。それを可能にしたのが、佐賀大学の上原教授を中心とした研究グループが開発したウエハラサイクルである。作動流体に純物質を用いる従来のランキンサイクルに対し、ウエハラサイクルではアンモニアと水の混合媒体を用いる。このことで、相変化(蒸発および凝縮)中に温度変化を伴うために、サイクルで得られる仕事量が増加し熱効率が向上するのである。
また、上原グループは、サイクルの研究と並行してOTECの心臓部ともいえる熱交換器の研究にも力を注ぎ、高性能なプレート式熱交換器を開発導入した。これら技術の開発が温度差発電の実用化へ向けた大きなブレークスルーになっている。
当社(株)ゼネシスは、いち早く佐賀大学の研究に参加し、自社工場内においてプレート熱交換器の開発、製造を行うなどOTECの実用化に向けた開発を実施している。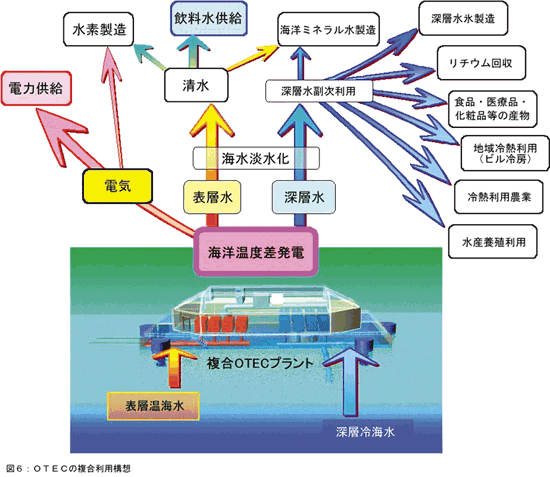
深層水のカスケード利用
深層水を汲みあげて発電するとなると、その経済性に疑問を持たれるかもしれない。
ここで、OTECを深層水の有効利用という視点で捉えてみる。深層水には、低温性、富栄養性、清浄性という三つの主要な特徴(ポテンシャル)がある。現在、日本各地で深層水の利用および商品化が始まっているが、これらのほとんどは清浄性を利用したものである。また、相模湾においては、富栄養性を利用した漁場生成システムの実証実験も始まっている。
一方、OTECは低温性というポテンシャルの一部を利用するものである。また、低温性ポテンシャルでは、地域冷房、スプレーフラッシュ方式の海水淡水化システムへのカスケード利用も可能である。もちろん、低温性を発電等に利用した後でも富栄養性、清浄性が損なわれることはないため、上記の漁場生成、深層水商品等との複合利用は十分可能である。このように、深層水の持つポテンシャルを余すことなく利用することにより、経済性が飛躍的に向上するとともに、水問題、食糧問題の解決に大きく貢献することができる。
将来を見すえたOTEC開発
OTECは、エネルギー需要が増大しつつある熱帯・亜熱帯地域の開発途上国に最適のエネルギーシステムであることから、すでに多くの国で計画および検討が進められている。中でも太平洋に浮かぶパラオ共和国では、3MW級の発電プラントの建設を皮切りに、今後10年間で国内の発電をディーゼルからOTECへ全面的に切り替える計画が進行中である。
日本国内においては、佐賀大学海洋エネルギー研究センターが伊万里に新設された。同施設には、30kWのウエハラサイクル海洋温度差発電実験装置を中心に、海水淡水化実験装置、水素製造・貯蔵実験装置、リチウム回収実験装置、海洋深層水環境模擬実験装置などの実験装置が置かれ、より高性能な発電技術と複合利用技術の確立を目指すものである。この研究センターはOTEC研究をリードして、新たな産業が発信される国際的な拠点となることが期待されている。また当社では、利用価値が低いためにこれまで捨てられていた低温の工場排熱を利用した発電、海水淡水化システムにも取り組み、OTEC実用化のための技術基盤の整備、確立を行っている。
今後は、有限な化石資源への依存度を低減させるためにも、日本の持ち味である技術開発力、豊かな海に囲まれた地形的特性を活かしながら、海洋エネルギーの有力な技術としてOTECの開発に取り組むことが重要である。また、本システムに関わる技術分野は非常に多岐にわたることから、さらに多くの技術の集約が必要となってくる。将来、日本が海洋に関してたくわえてきた豊かな知見と技術力を活かして、エネルギー輸出国となることも十分可能であると考える。(了)
第88号(2004.04.02発行)のその他の記事
- <日本の島から>山形唯一の有人離島"飛島(とびしま)"~高齢過疎とともに消え去るもの~ 市立酒田病院飛島診療所長・医学博士◆杉山 誠
- 21世紀における航海訓練のあり方 (独) 航海訓練所理事◆小川吾吉
-
海洋温度差発電の胎動
(株)ゼネシス エンジニアリング事業部◆實原定幸
(株)ゼネシス エンジニアリング事業部◆桜澤俊滋 - 編集後記 ニューズレター編集代表(横浜国立大学国際社会学研究科教授)◆来生新
