Ocean Newsletter
第88号(2004.04.02発行)
- 市立酒田病院飛島診療所長・医学博士◆杉山 誠
- 独立行政法人 航海訓練所理事◆小川吾吉
- (株)ゼネシス エンジニアリング事業部◆實原定幸
(株)ゼネシス エンジニアリング事業部◆桜澤俊滋 - ニューズレター編集委員会編集代表者(横浜国立大学国際社会学研究科教授)◆来生 新
21世紀における航海訓練のあり方
独立行政法人 航海訓練所理事◆小川吾吉民間商船で働く船員になるための教育訓練については、国の政策により座学教育は商船系大学・海洋学校等の教育機関で行う一方、実技訓練は航海訓練所で行うこととされている。航海訓練所は平成13年に独立行政法人化され、海運国日本のこれからを担う船員を育てるため、よりいっそうの業務運営の効率化と業務の質の向上に取り組んでいる。
1.航海訓練所の役割
21世紀は海洋の世紀と言われている。その海洋を舞台に民間商船で働く船員になるための教育訓練については、国の政策として座学教育は商船系大学、商船高専、海技大学校、海員学校等の教育機関で行う一方、実技訓練については航海訓練所で行うこととされている。これは、海運国日本を担う優秀な船員を確保するためには、各教育機関でバラバラに訓練するよりは、海運業界のニーズに対応した多様な形態の練習船、例えば外航・内航の航海形態や、船の規模、エンジンの種別などに応じた練習船を保持し、しかも効率的、効果的で安全な訓練ができる専門的な機関が必要であるとの国の方針によるものである。
航海訓練所は平成13年4月省庁再編に伴い国から分離され、独立行政法人として発足し、現在帆船2隻、ディーゼル船2隻、タービン船2隻計6隻の練習船により、国土交通大臣の定めた「中期目標」に従って策定した「中期計画」(平成13年度?17年度)と年度計画に基づいて業務を実施、推進している。
これらの年度計画と「中期計画」の達成状況については、他の独立行政法人と同様に、国土交通省独立行政法人評価委員会の評価を受けることとされており、「職員の意識改革、即応性の確保、独自の工夫」の3点に重点をおいて役職員一丸となって計画の達成に取り組んでいる。
練習船による航海訓練や研究は、船員資質の涵養、船舶運航に関する知識と技能の教育、乗船履歴の付与に重要な役割を果たしており、ひいてはわが国の海上輸送の安全と安定に大きく貢献している。
2.21世紀における航海訓練の展開
独立行政法人として求められているのは、一般に、業務運営の効率化を図ることと国民に対して提供するサービス等の業務の質の向上を図ることである。航海訓練所においては、海運船社・船員教育機関との意見交換を行うことにより、ニーズの把握に努めているが、その要望の中で最も強く求められているのが海事英語訓練の強化、内航即戦力化等への対応、船員資質の涵養である。船員資質の涵養については、帆船を活用するなど訓練全体を通して育成に努めている。また、利用者のサービスに対応しつつ業務運営の効率化を図るため、練習船の隻数を減らすことや管理費の削減を図ることとしている。

(1)海事英語訓練の強化
現在の日本外航商船の外国人船員との混乗実態に鑑み、平成13年度から(財)日本海運振興会と(財)練習船教育後援会(本年3月から(財)船員教育振興協会に変更)のご支援のもとに、ネイティブ・スピーカーである米国人のアシスタント・アドバイザーを乗せた海事英語訓練実験事業を開始した。生活を共にすることで実習生の英語力も向上し、外航海運業界にも評判が良く大きな成果を上げている。16年度までに実験調査を行い、17年度以降は航海訓練所として本格実施すべく検討している(図参照)。
(2)内航即戦力化への対応
内航海運における即戦力となる船員の育成を図るため、内航海運の実態に応じて、練習船の瀬戸内海等狭水域・狭水路航行及び出入港訓練の回数を大幅に増やす(図表参照)など訓練の充実に取り組んでいる。また、新たに内航船の現役の船長・機関長に練習船に乗船していただき、その的確なアドバイスを訓練に反映している。さらに内航海運会社の経営者や役員に練習船に乗船していただき、実習訓練についての理解を深めていただいている。
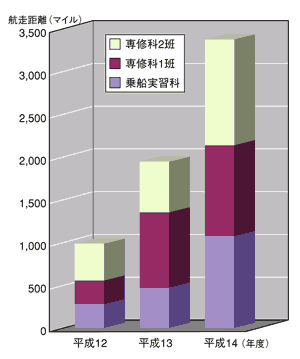
(3)国際協力・海事教育等の推進
現在日本商船隊の船員の約9割はアジア人などの外国人船員である。これらの諸国では練習船を保持していない場合や、保持していても小さな船だったり、老朽船だったりして十分な訓練ができない場合がある。このため、ODAの一環としてアジア諸国の船員の訓練を実施するとともに、専門家派遣などの協力を行っているが、笹川フェローシップの一員として航海訓練所の職員を世界海事大学へ派遣させていただき、帰国後国際海事教育の面でも大きな成果を上げている。
また、練習船が日本各地に寄港した際の一般公開や小中学生等への見学会の実施、(財)船員教育振興協会主催による海王丸体験航海・海洋教室の支援などにより、広く一般国民に親しんでもらう「生きた海事教育の普及」に取り組んでいる。
(4)6隻から5隻体制へ
船隊規模の見直しを行い、6隻のうちタービン船1隻を廃止するとともに、老朽化したディーゼル船1隻に代えて、最新の船舶技術とITを導入した訓練器材等を装備した次世代対応練習船(ディーゼル船)を本年6月から供用開始すべく建造中であり、昨年12月皇太子殿下ご臨席の下に命名・進水式が行われたところである。
この結果、帆船2隻及び標準練習船3隻の計5隻とすることで、利用率を向上させるとともに、効果的な配乗計画となるよう見直しを進めている。
3.今後の課題
上述の「中期計画」における当面の課題としては、(1)16年度における6隻から5隻への船隊再編・整理に向けた着実な計画の推進、(2)自己収入としての受託料確保の努力、(3)船員法完全適用に伴う体制の整備 などが上げられる。いずれも利用者等関係者の理解と協力が不可欠であり、それに全力を挙げているところである。
優秀な船員の確保は、今後ともわが国海運・海事産業の発展の重要な要素であり、そういう中で実習訓練業務を推進する航海訓練所の果たす役割は大きい。21世紀における航海訓練教育のあり方を見据え、国民のニーズの把握や業務の効率化に努めつつ、船齢が古くなった練習船のあり方などを中心に、次の「中期計画」に向けた検討を進めていく所存である。(了)
第88号(2004.04.02発行)のその他の記事
- <日本の島から>山形唯一の有人離島"飛島(とびしま)"~高齢過疎とともに消え去るもの~ 市立酒田病院飛島診療所長・医学博士◆杉山 誠
- 21世紀における航海訓練のあり方 (独) 航海訓練所理事◆小川吾吉
-
海洋温度差発電の胎動
(株)ゼネシス エンジニアリング事業部◆實原定幸
(株)ゼネシス エンジニアリング事業部◆桜澤俊滋 - 編集後記 ニューズレター編集代表(横浜国立大学国際社会学研究科教授)◆来生新
