Ocean Newsletter
第7号(2000.11.20発行)
- 東海大学海洋学部教授◆酒匂敏次
- 横浜市立大学教授(国際海洋法)◆布施 勉
- 大島商船高等専門学校商船学科教授◆三原伊文
- ニューズレター編集委員会編集代表者 (横浜国立大学国際社会学研究科教授)◆来生 新
ニューズレター編集部宛に届いた読者のご意見
ニューズレターで興味のあった記事
●「街のゴミが海を汚す」(第3号:小島あずさ氏)の記事のように、私も海岸漂着の膨大、継続的なことに寒心を捨てられない。特に外国のゴミは意図的に毒物汚染を受ける危険もあり、関心大だ。
●宮澤昭一小笠原村長(第4号)の投稿文を興味深く拝見した。太平洋上の島々の重要性を痛感。
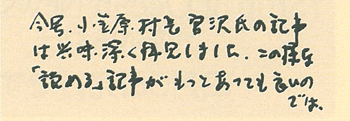
●「今なぜ、捕鯨が問題か?」(第5号:森下丈二氏)は、欧米の指摘事項に対する反論が判りやすくまとめられていた。ただし、鯨類に対する海洋生物の捕食については、(1)鯨が大量に活動していた昔にもバランスをとっていたこと、(2)そもそも人間が自然の生態系を管理すること(人間の食べる魚の捕獲量を確保するために鯨の数を管理すること)に無理があるのではないかという印象をもっている。編集後記に指摘があるように、日欧のライフスタイル、文化の違いを感じる問題である。
●興味深く読ませてもらっている。特に「日本海の循環」(第5号:尹 宗煥氏)に関心を持った。
●「海観が育つ環境を」(創刊号:濱田隆士氏)の趣旨にまったく同感である。子供たちや市民にとって海が常に身近に感じられるような方向でのNewsletterの発展を期待する。
ニューズレターに希望すること
●海洋問題は21世紀の重要問題。中国は太平洋でアメリカと覇を競うようなので、中国の海洋進出(意図と実績)を重点的に掲載してもらいたい。
●21世紀の課題である。IT活用と戦略的概念について、海洋開発及び船舶輸送システムについてまとめてもらいたい。あるいは指針的なもの。
●読者の参加型の企画を多くしてほしい。工学、理学、社会・文化、文学、遊び等の視点も含める。
●取り扱う対象範囲がかなり広いようなので、各号毎のテーマを明確にした誌面作りを期待したい。海洋をめぐる議論は抽象的指摘が多すぎるので、具体論を望みたい。
●海洋に対するイメージは欧米とアジアでは大きく異なる。何故、海洋を「持続可能な開発」の対象とするのかは、アジアにとって大きな課題である。アジアの視点から議論展開を期待する。
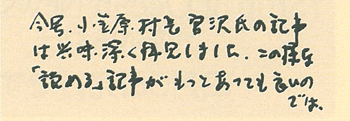
●個別海域の沿岸域環境問題など、東京から見ているだけでは本質や具体的対応の動きが見えにくい問題も多々あると思う。編集・取材における各地域との連携が望まれる。
●NGOの活動、市民団体の取り組み等を取り上げていただきたい。
●日本国安全保障保持のためにの船員政策、船舶政策が現状ほぼゼロであり、今後の対応、考え方について議論したい。
●海洋開発シナリオが判りにくい。海洋から得られるすべてのエネルギー源の開発が重要である。
●海の祭りや、行事についての記事を期待します。
●海洋と水産資源に関すること。増加する人口(2050年には百億人とか)と海洋との関わり。物資輸送手段として船舶は将来とも必要か等。
●海洋でも特に航路となる海域の汚染が際立っていると聞いた。海洋の汚染状況とそれに対する対策として、どんなことが行われているか知りたい。
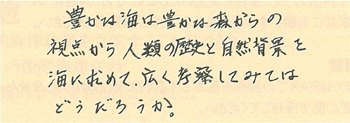
ニューズレターへの意見
●記事が難しい。親しみのもてるテーマで、日本人の海洋意識を高めるような論文がほしい。
●海に関する解析、DATA、統計等なんでもよいが、図表入りで載せて欲しい。
●問題点、取り扱う分野のカテゴライズが必要ではないか。
●外国の論文や世界の情報も採用したらどうか。
●全般的に社会科学的研究が不足しているように思うので、英語のMarine Policyのような雑誌の方向を目指すべきであると考える。
本誌に対する多数のご意見をありがとうございました。寄せられたものの中から、一部ですが、貴重なご意見、批判等をご掲載させていただきました。これらをもとに、これからもよりよい誌面を作っていきたいと考えております。なお、本誌に対するご意見・投稿については、随時募集しています。本誌への積極的なご参加をお待ちしております。(編集部)
第7号(2000.11.20発行)のその他の記事
- ダイアローグ「竜馬と乙姫」 東海大学海洋学部教授◆酒匂敏次
- 国際海洋法の新しい思想 横浜市立大学教授(国際海洋法)◆布施勉
- 海と船が、人を育てる 大島商船高等専門学校商船学科教授◆三原伊文
- ニューズレター編集部宛に届いた読者のご意見
- 編集後記 ニューズレター編集代表(横浜国立大学国際社会学研究科教授)◆来生新
