Ocean Newsletter
第51号(2002.09.20発行)
- Ship & Ocean Newsletter編集部
- (社)日本海洋開発建設協会◆(社)日本埋立浚渫協会
- (社)日本造船工業会
- ニューズレター編集委員会編集代表者 ((社)海洋産業研究会常務理事)◆中原裕幸
「メガフロート工法」の主張
(社)日本造船工業会浮体(メガフロート)工法は、地震に強く、環境にも優しい、また工期も短く、経済性が高いなどの優れた特徴を持っている。羽田空港の再拡張事業では、数多くのすばらしい特徴を持ち、わが国の最先端技術を結集して開発された、世界に誇れる先端技術である浮体工法こそが最適と考える。
日本造船工業会が提案している浮体方式は、滑走路島全体を浮体(メガフロート)工法で継ぎ目のない一体構造で建設する方式です。この浮体工法は、地震に強く、環境にも優しく、また短工期、高い経済性が特徴のわが国が開発した世界に誇れる工法で、「メガフロート」の名前でご存じの方も多いと思います。平成7年から6年の歳月をかけて、造船・鉄鋼の両業界の最先端技術を結集して完成させたメガフロート技術は、次のような様々な優れた特徴をもっており、私たちが羽田空港の再拡張に最適であると考える理由もここにあります。
浮体工法の優れた特徴
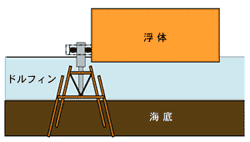
(1)地震がきても影響を受けません。
浮体はドルフィンと呼ばれる「やぐら」にしっかりと繋がれて水に浮いているため、地震による震動はほとんど伝わらず、直下型の大地震がきてもびくともしません。飛行機が着陸しようとしているとき万一地震が発生したらどうなるでしょう。大震災が心配されている首都圏ではとても重要なことです。
(2)環境に非常にやさしい工法です。
浮体は海を潰しません。海が環境に与える恵みは計り知れません。東京湾のような閉囲された湾の中では、海の水が都心の気温上昇や大気汚染の抑制に大きな影響をもっている可能性が指摘されています。これ以上東京湾の水域を減らして良いものなのでしょうか。
浮体の下の海中には、太陽光線は届きませんので、一般の海中の水深数十メートルより深いところと同じような状態になりますが、潮流などにより海水が常に移動・交換されますので環境影響もほとんどありません。
(3)海底の地質が悪くても影響を受けません。
メガフロートは浮いていますので、その下の海底の地質がどんなに悪くてもほとんど影響を受けません。今回滑走路の計画されている場所は40mもの厚さでヘドロ状の層があると聞いております。関西空港でいまだに完成後も発生しているような地盤沈下の問題は、浮体では全く心配要りません。

(4)工事期間が非常に短くてすみます。
メガフロートは多数のユニットと呼ばれる小さな浮体、と言っても長さ300mくらいで大型のタンカー程の大きさはありますが、そのユニットを各地の造船所で分散して建造し、予定の海域に集結して接合・合体させて、巨大な構造物を作っていくため、とても短い時間で完成させることができます。羽田空港再拡張事業では、一日も早い滑走路の使用開始が重要な条件となっています。今回の浮体工法による工期の試算では、4週で6日の休日や1日8時間労働といった余裕の十分ある条件で、2年半ほどの工期を見込んでありますが、仮にいわゆる突貫工事を前提とすれば、さらに1年近い工期の短縮も可能になります。しかも、工事のほとんど(約80%)が造船所などでの工場製作のため、天候や海象などの影響をほとんど受けず、確実に工期が守れることも大きな特徴です。同じように工費も途中で増大するような恐れはありません。
この他にも、メガフロートは、鋼鉄製の箱ですので、内部に大きな空間が存在し、表面は滑走路として、また、内部空間は、倉庫やオフィス、イベント会場など多くの用途に利用可能となり、高い経済性も期待できます。
安全で安心な浮体工法
今回、日本造船工業会は浮体工法を提案いたしましたが、世界初の工法であるため当初、以下のような質問も寄せられましたが、これまでの技術の蓄積をもとに、一つずつ丁寧に説明し、ご理解を得てまいりました。
(1)大きな波で折れることはないのか?漂流しないのか?
東京湾では起こりえないような大波を想定しても、びくともしない強度になるよう設計しています。また、仮にドルフィンがテロなどで故意にすべて破壊されたとしても、非常用のアンカー(錨)が浮体を流さないようにしますので安心です。
(2)多摩川にかかる部分には川の流れを妨げないよう「櫛型」という新しい形の浮体が採用されているが、安全性は大丈夫か。
メガフロート開発の段階では、安全性を確認するための多くの計算プログラムが開発されていますが、浮力によって構造物を支えるという基本原理が同じであれば浮体の形状に関係なく計算ができるよう工夫されており、今回の櫛形部についても、そのいずれのプログラムを使って計算しても十分安全なことが確認されています。また、櫛形のような形状の構造物は北海油田のリグなどで多数の実績があります。
(3)浮体は鋼鉄製なので、錆びることはないか。
船などで多くの実績のある電気を使った錆止め技術とさらに特に錆びやすいところには、錆びない金属といわれる「チタン」で巻いてしまう技術を併用することで、100年以上の使用に全く問題ないように計画しています。
(4)浮体工法の優れた点は理解できるが、実績がないから不安だ。
昭和50年代、新関西空港の工法を検討した際も「浮体工法は実績がない」との理由で埋立工法に決まり、現在にいたっています。そこで、航空、港湾及び造船の各分野の学識経験者、関連業界等が一体となって平成7年度から、技術はもとより、安全性や空港としての機能性についても検討するため、実際にメガフロート空港を建設し、飛行機を離発着させるという壮大な実証実験が行われました。何百回と言う飛行実験を繰り返し、膨大な技術データをもとに様々な科学的評価も行われ、また、プロのパイロットの方々による感覚的検証まで実施しました。その結果を国の委員会「メガフロート空港利用調査検討会」に報告したところ、平成13年3月、「4000m級の滑走路を有する浮体式のメガフロート空港が技術的には十分可能である」との結論が委員会によりまとめられ、国として、巨大空港をメガフロートで建設することについての安全性についてお墨付きをいただきました。
●
このような数多くのすばらしい特徴を持ち、かつ、日本の高い技術力に裏付けられた浮体工法(メガフロート工法)が、今回の羽田再拡張工事における重要な条件(緊急性、地震に強いこと、海底はヘドロの軟弱地盤であること、現在の空港を利用しながら側で工事を行うため現場工事は極力少ないことなど)を考えると最適な工法であると考え提案させていただいています。(了)
第51号(2002.09.20発行)のその他の記事
- 羽田空港再拡張建設工法をめぐる論議について Ship & Ocean Newsletter編集部
- 「埋立/桟橋ハイブリッド方式」について (社)日本海洋開発建設協会◆(社)日本埋立浚渫協会
- 「メガフロート工法」の主張 (社)日本造船工業会
- 編集後記 ニューズレター編集代表 ((社)海洋産業研究会常務理事)◆中原裕幸
