Ocean Newsletter
第262号(2011.07.05発行)
- 北海道大学名誉教授◆池田元美
- 全国漁業協同組合連合会漁政部◆田中要範(としのり)
- 小豆島町長、元厚生労働省政策統括官◆塩田幸雄
- ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・研究科長)◆山形俊男
水産業・漁村の復興と漁業協同組合(JF)の役割について
[KEYWORDS]東日本大震災/漁業再開への取り組み/漁業協同組合(JF)全国漁業協同組合連合会漁政部◆田中要範(としのり)
震災で被害を受けた地域には、日本を代表する水産基地が多く存在している。多くの尊い人命が失われ、漁業関係者も被災した。
また、漁船や養殖施設、漁港、市場施設、加工場、造船所など、地域で水産業を形成するために必要な資産が失われた。漁業関係者は、JFを核にして、懸命に再起に取り組んでいる。
はじめに
東日本大震災では、多くの尊い人命や財産が失われた。震災で被害を受けた方々に心からお見舞い申し上げますとともに、被災団体の一員として、ともに連携して復興に向かって歩んでいきたい。また、国内外からさまざまな形で、大きな支援が被災地に寄せられている。とりわけ漁業・漁村は、甚大な被害を受けた立場として、誠に大きなご支援をいただいている。温かいお気持ちを寄せていただいた皆さまに、被災地の漁業者に代わって、まずは心から感謝の気持ちをお伝え申し上げます。
水産業・漁村の被害状況
4月、被災地の一部、宮城と岩手の沿岸地帯に行った。はじめ現場を目の当たりにした瞬間、グッと喉が詰まり、文字通り言葉にならなかった。沿岸域が壊滅的な被害を受けたのは、地震もさることながら、大津波の巨大な力によるところが大きい。波の力で湾口の巨大なケーソンが横倒しになった岩手県田老地区、町が丸ごと消滅した陸前高田。気仙沼では、自衛隊員と重機が寡黙に働き続ける音以外は、カラスの鳴き声が響くのみで、かつての人の賑わいが絶えていた。「地元で生まれて慣れ親しみ、何回も通った町なのに、風景が変わってしまっていて何度も道に迷ってしまう」という宮城県漁業協同組合(JFみやぎ)幹部の言葉がすべてを物語っている。
さて、水産庁※1によると、わが国の東側沿岸15道県で、養殖物・養殖施設に1,293億円の津波被害があった。このうち特に被害の大きい北海道から千葉の7道県では、漁船被害は約2万隻、特に岩手、宮城では9割以上の沿岸漁船が失われた。漁港被害は319漁港、隣接する市場の大半も被災した。加工施設は777施設が全半壊等の被害を受けた。水産全体では、6月9日現在で1兆664億円もの被害にのぼっている。漁業協同組合(JF)関連では、青森から茨城までの5県で、128のJF事務所等施設が全半壊した(JF全漁連調べ)。組合員(漁業者)の安否については未だ全容は不明だが、百人単位の甚大な人的被害を受けたJFもある。
また、造船業、漁業用機械製造業など、漁業を行うために必要な工場等の施設や、水産卸売・小売業、ホテル・旅館、飲食業施設など、地域経済を形成するために必要な多くの資産が失われた。
漁業生産・水産物流通への影響

■現場指揮をとる漁協組合長(岩手県宮古市)
岩手、宮城、福島3県の漁船漁業で獲れるものは、オキアミ類、サメ類、キチジ、アワビ類、サンマ、カジキ類、イカナゴ、マダラ、サケ・マス類、ウニ類、マグロ類、スルメイカ、アナゴ類、タコ類、カツオ類など※2。養殖物では、ホヤ類、ワカメ、コンブ、カキ、ホタテ、ノリなど。これら水産物の水揚げが一時的に停滞し、流通が減少する可能性が高い。漁業種類ごとに受けた被害状況によって、それぞれの魚種に影響が出る。ただ、今後、漁船等の復旧のスピードや漁期の到来の違いがあるものの、水揚げは順次再開されていく動きだ。カツオ一本釣り漁業では、漁期の到来を迎え、釣餌や資材の調達など、関係者が急ピッチで操業準備を進め操業開始にこぎつけた。ワカメ養殖業者は、夏に行うワカメの種付け(メカブから胞子を種糸に付着させる作業)を行うべく準備を進め、来春の出荷を目指している。
JFみやぎが県内漁業者に実施したアンケートによると、被災前の水揚額の8割以上の生産高を担うに相当する漁業者が、漁業継続の意志を示した。JFみやぎ幹部によると、「生産手段が整った場合、被災前と同等の生産を行うことは可能」とのことで、意気は高い。多くの漁業者は、自ら漁場のガレキ撤去を行い、漁場が再生したら、故郷の海で漁を再開したいと考えている。すでに漁業者による漁場ガレキ撤去は岩手、宮城、福島の3県で精力的に実施されており、漁船の修理や新船増産体制もスタートした。
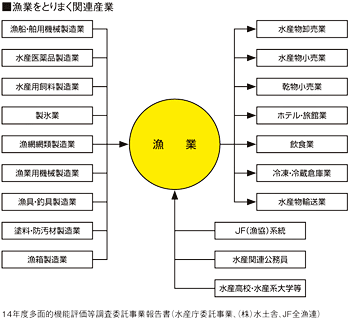
JFの役割と水産業の復興に向けて
集団を導くことはもともと困難な仕事だが、とりわけ独立意識の強い漁業者一人一人が集まった漁業者集団を、一つの方向に導いていくことはなかなか難しい。ここで、JFが機能する。JFは、漁業者との日ごろの関係性の中で、経済的・精神的に深く漁業者と結びついている。JFと漁業者は一体であるとも言って良い。漁業者は、何か課題があればJFに集い、意見を戦わせ、一つの方向性を見出して、それをJFが実行する。この震災でも、JFが被害状況の把握、漁業継続の意志確認、行政との連絡、復旧事業の実施など、必要な全ての取り組みのとりまとめと実務を行っている。このように、JFは、震災復興にあたって、必要不可欠な拠点として存在し役割を担っているのである。
現在、国や被災県、研究者や企業等が、さまざまなで形で、復興構想にかかる会議や議論を行っている。水産分野でも同様だが、議論を行うなかで、われわれが忘れてはならないのが被災者の存在だ。どのような素晴らしい構想・提案であれ、それを実行するのは被災地域住民である。むろん急ぐ必要はあるが、人々の納得に至るステップをないがしろにしてはならない。当事者の納得がない形で進めたとしても、結局人心が離れれば構想は無意味となり、コミュニティは分解し、投下資本の無駄にもつながりかねない。復興構想は持続性が担保されねばならず、そのためには住民の納得が不可欠だ。また、被災地を自らの構想の実験場とみなし、主張やアイデアを押し付けるのは論外である。被災者へ支援と議論の素材を提供しつつ、産官学の関係者とともに議論する姿勢で取り組みたい。
さて、震災対策のため編成された国の第一次補正予算では、水産関係として2,153億円が措置された。現在、関係者は、漁業生産活動の再開を目指して、漁港の復旧、漁場のガレキ撤去や漁船の共同利用事業など、予算の活用による当面の復旧に取り組んでいる。
今後は、本格的な復興に向け中長期的な視点での取り組みが必要となってくる。水産物加工・流通業をはじめ、関連産業の再興は大きな課題の一つである。水産業は、関連産業が一体となって発動する巨大なメカニズムであり、水産業の復興にあたっては、関連産業の再興が不可欠だ。漁船などの生産手段の確保は、地域経済をリスタートさせるきっかけにすぎない。今後、関連産業の再興と相まって地域の水産経済が循環し、多くの水産物が全国の消費者に再び届けられるようになることが目標である。この目標に向かって、今後、私たちは復興のあり方を含め、政策的運動を展開していきたい。(了)
第262号(2011.07.05発行)のその他の記事
- 東日本大震災の苦境を乗り越え、国際社会に敬意をはらわれる民に 北海道大学名誉教授◆池田元美
- 水産業・漁村の復興と漁業協同組合(JF)の役割について 全国漁業協同組合連合会漁政部◆田中要範(としのり)
- 海と島の復権 小豆島町長、元厚生労働省政策統括官◆塩田幸雄
- 編集後記 ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・研究科長)◆山形俊男
