Ocean Newsletter
第260号(2011.06.05発行)
- 海上保安庁長官◆鈴木久泰
- 日本内航海運組合総連合会広報室長◆野口杉男
- 長崎大学水産・環境科学総合研究科教授◆中田英昭
- ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・研究科長)◆山形俊男
東日本大震災と内航海運
[KEYWORDS] 緊急物資輸送/災害時国内輸送/内航海運日本内航海運組合総連合会広報室長◆野口杉男
内航海運業界は、3月11日に発生した大震災に際して、海上輸送という交通機関の特性を生かした支援活動を行なってきた。震災当初は、岸壁等の損傷、浮遊物による障害等により、太平洋岸の港がほとんど使用不可能な状態であったが、燃料油、畜産飼料、緊急生活物資および車両等を被災地にむけて輸送してきた。
これからも内航海運は海洋国家日本の産業活動や国民の生活を支えるとともに、災害時の緊急輸送に大事な役割を果たしていくつもりである。
はじめに
3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震は、日本の観測史上最大のマグニチュード9.0を記録し、東北、関東地方に大規模な地震と過去に例のない大津波によって、多くの方々が被災されました。また福島原発事故は、チェルノブイリ原発事故に匹敵するような過去最大レベルの原子力発電所事故となってしまいました。内航船員およびその家族も226名の死者・行方不明者がいます。今回の東日本大震災で亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げるとともに、被災された皆様に心よりお見舞いを申し上げます。
内航海運業界の東日本大震災への対応
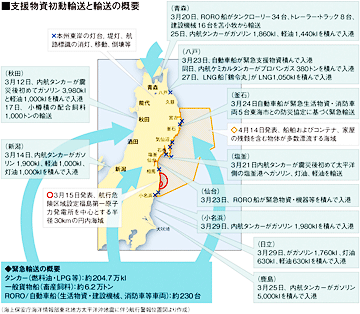
大震災の発生を受けて、日本内航海運組合総連合会(以下、内航総連)は、当日ただちに「東北地方太平洋沖地震災害対策本部」(4月1日より「東日本大震災対策本部」に名称変更)を設置して、被災地に向けて緊急物資の輸送対策に取り組みました。
具体的には、3月12日に国土交通省より今後発電用燃料油および緊急輸送用の軽油の大量の緊急輸送需要が想定されるとしてその対応要請がありました。同日に国土交通省から災害地向け緊急救援物資輸送を想定して配船可能な候補船を提出してほしいとの要請もありました。これを受けて内航総連は、関係事業者と至急調整し、3月13日には対応可能船舶としてRORO船、コンテナ船、ガット船19隻をリストアップして提出しました。他方、3月15日農水省より被災地の11飼料工場の生産停止にともなう緊急事態のため全国各地からの畜産飼料緊急輸送用の船腹提供するよう協力要請がありました。このため、輸送手配協力要請を各海運組合を通じて行い、対応しました。震災当初は、岸壁等の損傷、浮遊物による障害等により、太平洋岸の港がほとんど使用不可能な状態でした。4月28日時点においても65%の岸壁(238バース)等の施設が依然使用不能となっています。
(1)燃料油の緊急輸送
燃料油については、まず被災地における深刻な燃料不足に迅速に対応するため、港湾機能が維持されている日本海側の秋田、酒田、能代、新潟に加え青森経由で、緊急物資として燃料、LPガス等を運び、そこから陸路トラック輸送等と連携し、被災地に運ぶこととなりました。3月14日、内航タンカーが震災後初めて新潟港へガソリン、軽油、灯油を輸送して以来、3月18日までに18万5千kl(キロリットル)、その後延べ320隻燃料油約116万2千kl、原油4万5千kl、LPG等1万5千klを日本海側の東北諸港へ輸送しました。また、港湾関係者、消防、自衛隊、海上保安庁やアメリカ軍等の尽力により、3月21日以降は、太平洋側の港に入港、部分的に着岸できるようになったため、図の通り震災後はじめて塩釜港に、そしてその後鹿島港、日立港、小名浜港へ順次入港できるようになりました。4月28日までに太平洋岸諸港へ延べ79隻によりガソリン、灯油、軽油等燃料油約78万4千kl、プロパンガス等約4千8百トンの輸送を行いました。
(2)畜産飼料の緊急輸送
畜産飼料は、大型のフレキシブル・コンテナと呼ばれる袋入りの荷姿により一般貨物船で輸送されるため揚地側の倉庫が必要であることと一般貨物船用の岸壁及び荷役設備の復旧が遅れていることもあり、日本海側諸港中心に酒田港、秋田港、青森港、能代港、八戸港、新潟港揚げの順に約6.2万トン(平均1,000トンのロットで約62航海)の船腹の確保が確認できました。3月16日小樽積酒田揚げ1,000トンの輸送をはじめとして、一部は東京経由で自動車船等により以降順次輸送されました。4月中旬までにほぼ必要量は輸送されました。現在は、鹿島、八戸等の飼料工場も生産開始され、一段落したとの荷主からの報告を受けています。
(3)緊急生活物資および車両等の輸送
大型RORO船については、3月20日、北海道庁の要請により震災後初めて苫小牧から青森港へガソリン・灯油積載のタンクローリー、生活物資、建設機械を、そして22日東京港から仙台港向け機材、マイクロバス等車輌、建設機械の緊急輸送をしました。大型自動車船については、3月23日名古屋より八戸港へ支援物資等5台、24日名古屋より東海市要請により釜石港向けに飲料水、食料、消防車両物資等トレーラー5台、消防車1台、被災地用仮設住宅仙台港22台、東京港53台の輸送をそれぞれ実施しました。
この他、3月だけでも沖縄県の各種8団体および企業からのコンテナ・車両59台分の支援物資を沖縄/東京間無償輸送するなど全国各地から東京経由で被災地への輸送が実施されました。
今回の緊急輸送実績については、実施海運事業者からの報告のあった4月28日までの輸送のみを集計したものですが、燃料油、畜産用飼料、緊急生活物資・車両の全輸送量は約210万トン/kl(10トン車21万台分)に達しています。海上に多くの浮遊物や福島原発の放射線問題等のリスクのあるなか多くの船が良く頑張ったと思います。
また長距離フェリーは多くの自衛隊員、警察官、消防員およびその車両輸送等に活躍したと仄聞しております。今後とも、内航海運業界挙げて、生活支援物資はもとより避難者用仮設住宅資材、セメント・鋼材等復旧資材、瓦礫等の輸送要請に応えて行く所存です。
内航海運の役割
今回の大地震は、何にも増して物流の重要性を再認識させたと感じております。平成7年の阪神・淡路大震災に際して、内航業界は、率先して188航海約10万トンの救援物資、115航海20万トンの瓦礫等の輸送活動を行いました。また、同年のサハリン北部大地震の際には救援物資の輸送、平成12年の有珠山噴火災害時にはJRコンテナ代替輸送等を行いました。このように内航海運業界は、大規模自然災害に際して、海上輸送という交通機関の特性を生かした支援活動を行なってきました。
内航海運は、海洋国家日本の産業活動や国民の生活を支えるとともに、災害時の緊急輸送に大事な役割を果たしています。最近、国内の海上輸送について、日本の船でなければならないという制度(カボタージュ制度)を廃止して国内輸送に外国人船員が運航する外国船の利用を図ることを提案している一部の学者もいますが、国の生命維持に不可欠である内航海運の活動を外国の手にゆだねることはいかがなものでしょうか?内航海運には、災害時における国内輸送の確保という役割もあることに、ご理解とご協力をお願いします。(了)
第260号(2011.06.05発行)のその他の記事
- 東日本大震災における海上保安庁の活動について 海上保安庁長官◆鈴木久泰
- 東日本大震災と内航海運 日本内航海運組合総連合会広報室長◆野口杉男
- 貧酸素化が進行する内湾の環境修復:大村湾における実証実験 長崎大学水産・環境科学総合研究科教授◆中田英昭
- 編集後記 ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・研究科長)◆山形俊男
