Ocean Newsletter
第259号(2011.05.20発行)
- 横浜国立大学名誉教授 放送大学教授◆來生 新
- (独)海洋研究開発機構 上席研究員、日本海洋学会教育問題研究会長◆市川 洋
- 横浜国立大学統合的海洋教育・研究センター研究教員◆Compel Radomir
- ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所・教授)◆秋道智彌
トルコ海峡に見る近代海洋外交~ある昭和初期外交官の視点から~
[KEYWORDS] 海洋外交/トルコ海峡/海洋ガバナンス横浜国立大学統合的海洋教育・研究センター研究教員◆Compel Radomir
1920年代後半にイスタンブールに駐在した外交官で後に総理大臣となった芦田 均は、トルコの海洋外交の変遷を海峡通航制度の形成に照らし合わせ、来るべき海洋外交への期待を託して『君府海峡通航制度史論』をまとめあげた。
いま再び、日本が新たな海洋外交の方向性を模索するにあたり、彼の視点に学ぶべき事柄はよりたくさんある。
「海洋外交」と海峡問題
「海洋外交」という用語から、どのような外交や人物を思い浮かべるであろうか。そもそも海洋と外交というふたつの用語を接合することに、違和感を抱くかもしれない。なぜなら、高坂正堯の言葉を借りれば、島国日本には海洋国イギリスのような積極的な「海洋外交」はかつてなかったとさえいわれるからである。日本の「海洋外交」について検討するにあたって、何年にまで遡ればよいのか。一つの手がかりを残した人物が戦後初期に首相となった芦田均である。1920年代後半、外交官であった芦田はイスタンブールに駐在している。その時分からトルコの海峡制度に注目し、トルコの「海洋外交」の変遷を海峡通航制度の形成に照らし合わせてみていたのである。
トルコ海峡の「アンシャン・レーグル」
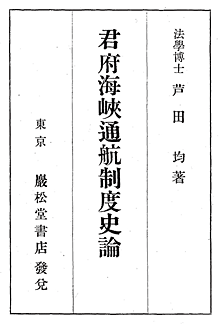
■『君府海峡通航制度史論』芦田均著(巖松堂書店、1930年)
芦田は、アジアとヨーロッパの結節点とされるトルコ海峡※1に焦点をあて、その通航制度の歴史を大著にまとめ上げた。1930 年に上梓された『君府海峡通航制度史論』がこれにあたる。同書の叙述に沿って、まず第一次世界大戦後に至るまでのトルコ海峡の制度的な変遷を追ってみたい。1453年、メフメト二世がコンスタンチノープルを攻略し、千年にわたるビザンツ帝国の歴史に終止符が打たれた。地中海にまで手を伸ばしていたオスマン帝国は、ボスポラスとダーダネルスのトルコ両海峡を閉鎖し、黒海をトルコ湖にした。こうして海峡閉鎖というオスマン帝国の「アンシャン・レーグル」※2が幕を開ける。トルコ海峡および中東各地を経由したシルク・ロードはオスマントルコの支配下に陥り、キリスト教ヨーロッパのアジアとの交易は思うように進まなくなったために、イタリア、ポルトガルとスペインが新航路の開拓に乗り出し、世界は大航海時代を迎える。まさにトルコ海峡の閉鎖がその後の日本を含めた世界史の転機をもたらしたことになる。またトルコ海峡をめぐる覇権争いはその後、オスマントルコの東欧、近東、北アフリカ地域への勢力拡大と、第二次ウィーン包囲以降東欧からの反撃、英仏の地中海進出、そしてロシア帝国の南下政策に左右されていくのである。英国とオランダおよびフランスに与えられたカピチュレーションと呼ばれる特恵および1774 年のロシア帝国とのクチュク・カイナルジー条約により、オスマントルコは次第に海峡を異国の商船に開放するに至った。これは「アンシャン・レーグル」という全面的な通航禁止体制から、商船への通航を許容しながら軍艦の通航を拒むという体制へと移り変わることを意味した。
軍艦の通航を禁止する「アンシャン・レーグル」は、ナポレオン戦争最中の1809 年に明文化され、その後、トルコによる「アンシャン・レーグル」の独自な運用は地域覇権国を目指すエジプト事件時のイギリス、およびクリミア戦争時のロシアから反撃を受けたが、1841年のロンドン海峡協約および1878年のベルリン講和会議で「アンシャン・レーグル」が再度確認される。ちなみに1904 年の日露戦争時、商船偽装巡洋艦三隻を除けば、ロシアの黒海艦隊は黒海に閉じこめられたまま身動きがとれず、極東で出番を迎えることはなかった。このようにトルコ海峡の「アンシャン・レーグル」は19世紀のヨーロッパにおける勢力均衡を保証するという旧外交の重要な手段となり、第一次世界大戦まで維持されてきた。芦田は、このトルコ海峡の通航をめぐる列強の政治駆け引きの経緯を踏まえ、その上で1923年に成立した新体制を大戦後の世界平和の新秩序形成の好機と捉えたのである。
トルコ海峡通航の新体制

■最も狭い地点でのボスポラス海峡
第一次世界大戦中、またその後のヨーロッパ列強の外交は、秘密主義を象徴するものであり、勢力均衡の伝統的外交への信頼の喪失をもたらした。その中で期待を託されたのが国際安全保障を担う国際機構であった。
ローザンヌ条約では、トルコ海峡の新たな通航制度の成立が講和の支柱の一つに据えられた。芦田は、この通航制度に三つの提言を行い、来るべき「海洋外交」への期待を託していた。まず一つは、「アンシャン・レーグル」を捨て、各国の海峡通航の自由を最大限に保障することであった。第二に、海峡の非武装地帯の中立化であった。芦田はトルコの要望に同調し、非武装地帯を中立地帯に引き上げることにより、すべての加盟国が海峡沿岸国の安全を共同的に保障するべきと説いた。第三に、安全な海峡通航を保障するために、イスタンブールにある国際海峡委員会の権限を強化すべきとした。この芦田の提言の背景には、国際連盟へ寄せられた信頼が垣間見える。芦田は、偏狭的なナショナリズムに基づく封建的全体主義を排除し、国際連盟下における政治的協調と自由貿易による経済拡大によって、将来の展望を見出した。とはいうものの、芦田の普遍的政治観の根底にあったのは、自由主義的な秩序における各国の積極的な集団安全保障への志向であり、ある意味では楽観的な前提であった。
近代国家として再建をはかったトルコは、1936年に締結されたモントルー条約において、加盟国の積極的な集団安全保障観の欠如を理由として、海峡の再武装と管理の国営化に踏み切る。モントルーでの講和条件の再交渉について、芦田はトルコ政府による海峡通航の自由の保障という国際的な道義的責任に留意しながらも、トルコによる限定的な条件の下で海峡通航の管理と再武装に賛同する見解を述べた。通航国のより自由な通航権の要求と、沿岸国の通航により派生する不都合への懸念との板挟みになった国際海峡の通航制度の明確なルール作りの必要性を見越した上での賛同であろう。
第一次世界大戦後のヴェルサイユ・ローザンヌ体制に「海峡通航の自由」という新たな概念が加わったことによって、「アンシャン・レーグル」は名実ともに瓦解し、新海洋秩序の形成へと一歩前に進んだといえる。また国際連盟を介した新海洋秩序の構築は、外交の形態の変容を促した。なぜなら、海峡協約をめぐる交渉において伝統的外交の限界が露呈し、多国間外交および共同安全保障を軸にした「新外交」の時代を迎えることになったからである。芦田の『君府海峡通航制度史論』は、トルコの海峡制度の変遷を詳述したものであるが、同時に「新海洋外交」の到来への期待をここに込めたものだったのである。
日本にはトルコと同様、大隅海峡、対馬海峡、津軽海峡および宗谷海峡といった世界的にも重要な海峡が存在する。今日の国際海洋法では、トルコとの関係に限れば現行のモントルー条約しか紹介されないことが多いが、日本の新たな「海洋外交」の方向性を模索するためにも、トルコが経験した「海洋外交」の源流とその変容から参照すべきものはより多くあるのではないだろうか。(了)
第259号(2011.05.20発行)のその他の記事
- 東日本大震災と総合的海洋管理の具体化~排他的経済水域と大陸棚~ 横浜国立大学名誉教授、放送大学教授◆來生 新
- 海のサイエンスカフェ~海洋科学研究者と市民との双方向の交流~ (独)海洋研究開発機構 上席研究員、日本海洋学会教育問題研究会長◆市川 洋
- トルコ海峡に見る近代海洋外交~ある昭和初期外交官の視点から~ 横浜国立大学統合的海洋教育・研究センター研究教員◆Compel Radomir
- 編集後記 ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所・教授)◆秋道智彌
