Ocean Newsletter
第259号(2011.05.20発行)
- 横浜国立大学名誉教授 放送大学教授◆來生 新
- (独)海洋研究開発機構 上席研究員、日本海洋学会教育問題研究会長◆市川 洋
- 横浜国立大学統合的海洋教育・研究センター研究教員◆Compel Radomir
- ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所・教授)◆秋道智彌
東日本大震災と総合的海洋管理の具体化~排他的経済水域と大陸棚~
[KEYWORDS] 東日本大震災/一元的行政組織/総合的海洋管理横浜国立大学名誉教授 放送大学教授◆來生 新
わが国が東日本大震災からの復興を果たすためには、世界に冠する豊かな排他的経済水域と大陸棚を、他の諸国家に先駆けて活用する、新たな総合的管理を積極的に開始しなければならない。
海の統合管理をめぐる法的措置を実現するための道のりはけっして平坦ではないが、いまこそ国の総力をあげて海洋国家日本の将来を確保するための新たな一歩を踏み出すべきである。
はじめに
前稿では、東日本大震災からの復興事業を行うに際して、現在の時点で想定されるいくつかの課題を整理し、被害にあった各自治体が「沿岸域の総合的管理」による復興を行うことの重要性を指摘した。本稿では、排他的経済水域および大陸棚の管理に関する立法論の形で、海洋の総合的管理の新たなシステムを提唱したい。
排他的経済水域および大陸棚の総合的管理と日本の復興
少子高齢化の中で、かつての活力を失いつつあるわが国の経済が、大震災前の水準に復活し、いっそうの成長と発展を実現することは決して容易なことではない。日本の未来に対する国民の視線が、将来に対する希望や信念を失うことをおそれるものである。それだけに、わが国の政治的・経済的指導者が、今、何よりもなさねばならぬことは、これまでの財政赤字の深刻化という桎梏の中で、社会全体として未来に明るい展望を欠きつつあった日本国民に、日本の国土の持つ潜在的可能性の豊かさを十分に認識させ、前向きに希望を持って生きることの重要性を確信させることであろう。いかに困難であろうとも、国民が、その課題に挑戦し、将来世代のために、世界を再びリードする気概と国力を持つ将来の国家像、日本人像を明確に打ち出し、国民意識を高揚させる具体的な施策を展開することが喫緊の国家的課題なのである。
海洋関係者にはよく知られているように、排他的経済水域と大陸棚を合わせると、日本は世界第6位の広大な空間を持つ巨大領域国家である。しかもわが国の海は、世界においてもまれに見る生物資源と、未開発の鉱物資源の豊かさを誇る海でもある。
海は、今回の悲劇のように、人からすべてを奪い去る残酷な死をもたらす存在でもあるが、逆に、人に生命を与え、それを育む豊かで優しい母にも譬えられる存在である。海からそのいずれの側面を引き出すかは、まさにわれわれの決断と取り組みにかかっている。わが国は、自らの21世紀の命運を、このように矛盾して多面的な海との共生に賭け、世界に冠する豊かな排他的経済水域と大陸棚を、他の諸国家に先駆けて活用する、新たな総合的管理を積極的に開始しなければならない。その意思を今こそ鮮明に内外に宣言し、それによってこの未曾有の海洋大災害によって打ちひしがれた国民の精神を鼓舞し、そこから生ずるであろう富を、膨大な費用を要する沿岸地域の災害復興に役立てる技術を開発せねばならない。
海に関する規制権限を一元化する行政組織の創設を
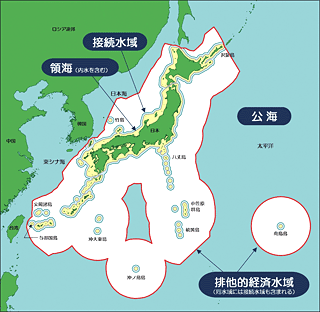
■わが国のEEZと領海
海上保安庁HPより
このような排他的経済水域・大陸棚の積極的な管理のために、何よりも必要なことは、総合的な海洋の管理を行うための権限を単一の行政主体に集中させた、新たな行政組織の創設である。
わが国の海に関する行政権限は、多くの省庁に分散し、縦割り行政の弊害を指摘されるものであった。平成19年の海洋基本法の制定により、内閣官房に総合海洋政策本部が設置され、従来の縦割りの海洋政策を統合する政治的なメカニズムができあがった。それは大きな前進であったと評価されるが、総合海洋政策本部は個別の規制権限を持つ各省庁間の権限行使の調整をする組織に過ぎず、何らの規制権限を持つものではない。
領海を超えた排他的経済水域および大陸棚は、国連海洋法条約によって国に管轄権が認められた空間で、その管理には国が直接的な権限行使を行うことが国際的に求められる空間である。しかるに、現行の海洋管理法制の多くは、都道府県知事が許認可権を持つものとなっている。その一事のみでも、従来の個別法の適用を前提とする現行の排他的経済水域および大陸棚に関する法律には限界があることは明らかであり、この海域の物理的、社会的特性にふさわしい新たな総合的管理を可能にする立法が求められるところである。
総合的な海洋の管理とは、法的に見れば、従来の個別法の個別規制基準の単なる寄せ集めを超えた、関連する規制基準の積極的な統合による新たな海洋活動の規制体系の構築に他ならない。そのためには、個別法の所管庁の枠を超えた、積極的で能動的な視点を持つ単一主体が、関連空間の諸特性に応じて、環境の保全と開発と科学的知見の増大を積極的に図る意欲を持って、従来の諸規制基準の統合と再整理を図らねばならない。新たな主体の創出なしに、新たな視点での規制基準の創出と明確化は不可能なのである。
新たな規制主体をどのような組織形態で創出するか、選択肢は多様である。しかし、イギリスのMMO(海洋管理機関)※の創設等、海外ではすでにそのような動きが現実化しつつある。また、その選択肢には、白地に近くやりやすい排他的経済水域および大陸棚から始めて、領海・沿岸域に漸進的に及ぼすことも含まれる。
今こそ、国の総力をあげて海洋国家日本の将来を確保するための新たな一歩を踏み出すべきであり、その具体化に不可欠なのが排他的経済水域と大陸棚の総合的な管理を行う規制権を持つ行政組織の創出であることを再度述べて、本稿のまとめとしたい。(了)
第259号(2011.05.20発行)のその他の記事
- 東日本大震災と総合的海洋管理の具体化~排他的経済水域と大陸棚~ 横浜国立大学名誉教授、放送大学教授◆來生 新
- 海のサイエンスカフェ~海洋科学研究者と市民との双方向の交流~ (独)海洋研究開発機構 上席研究員、日本海洋学会教育問題研究会長◆市川 洋
- トルコ海峡に見る近代海洋外交~ある昭和初期外交官の視点から~ 横浜国立大学統合的海洋教育・研究センター研究教員◆Compel Radomir
- 編集後記 ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所・教授)◆秋道智彌
