Ocean Newsletter
第254号(2011.03.05発行)
- 財団法人神戸港埠頭公社理事長◆片桐正彦
- 海洋政策研究財団客員研究員、韓国 東義大学 流通管理学科副教授◆具 京模(グキョンモ)
- 海洋ジャーナリスト、日本レクリエーショナルカヌー協会理事◆内田正洋
- ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・研究科長)◆山形俊男
神戸港埠頭公社の民営化と今後の港湾経営について
[KEYWORDS] 国際コンテナ港湾/港湾経営/神戸港財団法人神戸港埠頭公社理事長◆片桐正彦
神戸港のコンテナターミナルの整備運営を行ってきた神戸港埠頭公社が、民間の人材や資本の積極的な活用を図るべく、株式会社として新たなスタートを切ることになった。
課題は山積しているが、国が進める国際コンテナ戦略港湾に阪神港(神戸港)として選定されたことを契機に、神戸港の発展に貢献する新たな港湾経営主体となるべく努力していることを紹介したい。
埠頭公社の解散
神戸港埠頭公社は、東京湾、大阪湾の主要なコンテナターミナルの整備、運営を行ってきた国の京浜、阪神の両外貿埠頭公団の解散を契機に、神戸港に存在する公団の財産を承継して、神戸市が100%出捐した財団法人として1982年に設立された。神戸港で取り扱われるコンテナ貨物量の実に9割以上を公社のターミナルで扱っている。
一時期は、世界のコンテナ取扱港のランキングで4位に位置し、文字通り東アジアのハブ港として広く韓国、中国などからの貨物も神戸港においてトランシップ※して欧米に輸送していた神戸港であるが、1995年1月の阪神淡路大震災による壊滅的な打撃を受けた。国を挙げての迅速な復旧に努めたものの、その後の韓国、中国の港湾におけるコンテナターミナルの急速な整備や、貿易貨物量の急拡大に伴って、これら諸国の港湾におけるコンテナ取扱量が急激に増加し、相対的に神戸港の地位は低下していくことになった。今や神戸港でのコンテナ取扱量は、震災後最大となった2008年でも256万TEU(20ftコンテナ換算個数)と世界では44位、日本国内でも東京、横浜、名古屋に次ぐ順位に甘んじている状況である。
現在、神戸港ではコンテナターミナルの経営をより積極的かつ効率的に進めていくために、2011年4月1日をもって公社を解散し、株式会社化した神戸港埠頭株式会社として新たにスタートすべく、その準備を鋭意進めているところである。
埠頭公社制度の課題
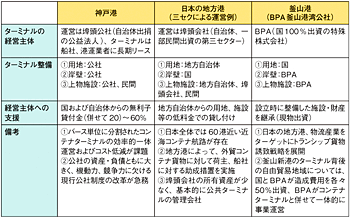
■表1: 神戸港と他港湾とのターミナル比較
このような事態に至った要因はいろいろあるが、神戸港にとっての一番の競合港である韓国の釜山港や日本の地方の港湾と比べたものを表1に示す。公社のターミナル運営が施設や用地の整備費も含めた完全な独立採算制となっていることや、個々のターミナル単位で船会社等に長期リースしているために埠頭の一体運営や共同利用などターミナルの効率的な運用が進まないなどの理由から、港湾コストが釜山港などに比べて高く、港湾としての国際競争力の低下をもたらしている。
これは、一概に神戸港に限ったことではなく、日本の主要港全体でも、北米・欧州の大型コンテナ船の基幹航路数が10年前に比べて、釜山港では1.5倍となっているのに対し、平均で8割程度に減少していることを見ても、世界のコンテナ輸送網における日本の港湾全体の地盤沈下が表れている。
また、日本の地方港でのコンテナターミナルの整備が進み、韓国、中国等との近海航路が今や日本全体では60港あまりに及んでいることから、日本のコンテナ貨物の分散化が進んでおり、そこでは、地方港から相手国への直接貿易貨物だけではなく、北米・欧州等へのトランシップ貨物までもが流出している現状がある。
貿易立国である日本にとっては、北米・欧州等への直行便が無くなり、中国や韓国の港湾経由での航路しかなくなることは、経済面、安全保障面などから極めて憂慮せざるを得ない問題である。
国際コンテナ戦略港湾としての阪神港の選定
このような危機感の中で、2009年秋以降、日本のコンテナ港湾の選択と集中の必要性が大きく取り上げられるようになり、国土交通省において、北米・欧州などの基幹航路を取り扱う港湾を、国際コンテナ戦略港湾として1港もしくは2港に限定し、国の支援を集中し、より効率的なターミナル運営を目指すべきとの方針が示された。
2010年3月には、広域連携も考慮した、東京湾、伊勢湾、大阪湾、北部九州の4地域の港湾が応募し、委員会での厳しい審議を経て、8月には、京浜港(東京、川崎、横浜)と阪神港(大阪、神戸)が国土交通省から選定された。阪神港として提出した計画においては、神戸港、大阪港の両埠頭公社を2011年4月に同時に株式会社化し、2015年を目途に両社の経営統合を目指すことにより、民の視点から阪神港のコンテナターミナル全体を一元的に経営する港湾経営主体を確立することにしている。更に、経営トップへの民間人材の登用はもとより、ポートセールス部門の主要役職などにも民間の人材を積極的に活用すると共に、早期の民間資本の導入を進めることとしている。また、瀬戸内海の内航フィーダー網の拡充による西日本地域からの集荷機能の強化や、インランドポートの設置による北陸エリアからの集荷機能強化などを図り、従来、海外の港湾でトランシップされていたコンテナ貨物を阪神港に取り戻すことを意図している。
新たな港湾経営主体の構築
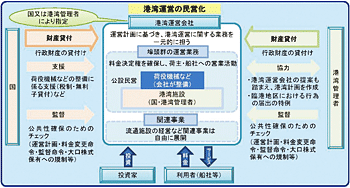
■図1: 港湾経営会社のイメージ
国土交通省では、国際コンテナ戦略港湾の議論と並行して、日本の港湾の国際競争力向上には、港湾経営の効率化・活性化が必要不可欠であるとして、従来、港湾管理者が行なってきた業務のうち、埠頭の運営(経営)については、民間が参画した港湾運営会社が担うことで効率的な事業運営を行えるようにするとの主旨で、1951年の港湾法施行以来の抜本的な改正を行おうとしている。そこでは、図1に示すように、公設民営方式、すなわち、岸壁や埠頭用地などの基盤施設は国・港湾管理者が整備し、指定された港湾運営会社に長期低料金価で貸付け、ガントリークレーンなどの荷役機械は港湾運営会社が整備する方式を打ち出している。
埠頭公社の株式会社化も、この国の政策を踏まえて進めようとしているところである。神戸港においては、160ヘクタールを超える埠頭用地を資産として所有し、資産額では1,000億円近いものの、震災の影響等もあり600億円を超える巨額な債務を有する神戸港埠頭公社が、どうすればうまく港湾運営会社のスキームに乗って、将来の神戸港の港湾経営主体として神戸港の発展に貢献できるかが、現在問われているところである。そこには、埠頭公社(埠頭株式会社)の自助努力に加えて、国や港湾管理者からの支援はもとより、神戸港のユーザーや広く関西全体からの支援・協力も重要である。
引き続き、西日本のゲートウェイとしての神戸港(阪神港)の重要性と、その経営主体としての埠頭株式会社の健全経営の必要性を強く訴えていきたい。(了)
第254号(2011.03.05発行)のその他の記事
- 神戸港埠頭公社の民営化と今後の港湾経営について 財団法人神戸港埠頭公社理事長◆片桐正彦
- 日中韓の近海物流市場の発展を目指す政策協調について 海洋政策研究財団客員研究員、韓国 東義大学 流通管理学科副教授◆具 京模(グキョンモ)
- シーカヤックがもたらす海洋国家への道 海洋ジャーナリスト、日本レクリエーショナルカヌー協会理事◆内田正洋
- 編集後記 ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・研究科長)◆山形俊男
