Ocean Newsletter
第252号(2011.02.05発行)
- 東京海洋大学海洋政策文化学科准教授◆佐々木 剛
- (独)海洋研究開発機構客員研究員、東京大学特任教授◆鳥海光弘
- 東海大学名誉教授◆酒匂敏次
- ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・研究科長)◆山形俊男
水圏環境教育推進リーダーの育成
[KEYWORDS] 総合的な海洋の理解/水圏環境リテラシー/水圏環境教育推進リーダー東京海洋大学海洋政策文化学科准教授◆佐々木 剛
2007年に制定された海洋基本法第28条では、海洋に関する教育の推進の必要性が謳われている。
東京海洋大学は、水圏環境リテラシー教育推進プログラムをスタートさせ、国民の「総合的な海洋の理解」を推進する「水圏環境教育推進リーダー」の育成に取り組んでいる。
本プログラムを通し、関係諸機関や関係各位のご協力やご助言を賜り国民の「総合的な海洋の理解」促進に貢献できればと願っている。
はじめに
ご存知のとおり、私たち人類にとって水圏(海洋、河川等)は必要不可欠な存在である。世界四大文明は大河のもとに築かれ、現在でも多くの人口は沿岸部に集中している。しかしながら、水産資源の減少、海ゴミ、地下水汚染、海洋汚染等、世界的規模で水圏の環境問題は深刻化している。一方で、私たちは水圏環境の重要性や問題を認識できる機会を十分に持っていないだけでなく、問題の解決を図ることが困難な状況にある。また、水圏環境に関する教育・普及を推進するリーダーや教育・普及のシステムが確立されていないことも大きな問題の一つである。
こうした中、2007年に海洋基本法が制定され、国民の海洋に関する理解を深める必要性が指摘された。これを受け2007年より東京海洋大学は、水圏環境リテラシー教育推進プログラムをスタートさせ、国民の「総合的な海洋の理解」を推進する「水圏環境教育推進リーダー」の育成に取り組んでいる。ここでは水圏環境リテラシー※、水圏環境教育、水圏環境教育推進リーダー育成プログラム、海洋リテラシー推進部門について紹介する。
水圏環境リテラシーとは
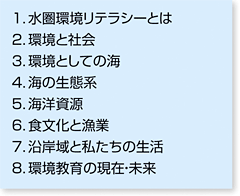
■図1:水圏環境リテラシー基本原則
私たちは、「総合的な海洋の理解」を「水圏環境リテラシー」と定義し、すべての人々が「水圏環境リテラシー」を持ち、責任ある決定と行動をすることが、現代の水圏環境の諸問題解決につながると考えている。
水圏環境リテラシー基本原則は、私たち人類が海洋から受ける影響と、人類が海洋に与える影響を理解するために必要な知識を定めたもので、水圏環境の科学的な知見と日本の伝統・文化等を盛り込み8つの大原則と66の小項目から構成されている(図1)。
水圏環境リテラシー基本原則が作成されたことによって、各学問分野間の横断的なつながりが可能となっただけでなく、学習指導要領と海洋に関する学問の関連付けが明確となり、学校教育と地域での社会教育活動とがより円滑に連携できるようになった(図2)。

■図2:さんりくESD(持続発展教育)閉伊川大学校「わくわく自然塾」
水圏環境教育の定義
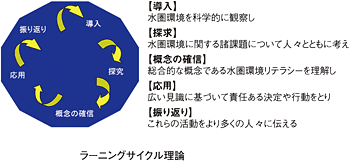
■図3:ラーニングサイクルによる水圏環境教育
水圏環境リテラシーを普及・推進するためには、一般市民が自ら進んで学習できる環境を整えることが必要である。私たちは、ラーニングサイクル理論に基づいた問題解決型学習を提唱している。ラーニングサイクル理論は、導入→探究→概念の確信→応用→振り返りの5つの学びのステップを踏みながら学習を進める理論である。ラーニングサイクル理論に基づいて水圏環境教育を実践する場合、水圏環境教育は「水圏環境を科学的に観察し(導入)、身近な水圏環境に関する諸問題について人々とともに考え(探究)、総合的概念である水圏環境リテラシーを理解し(概念の確信)、広い見識に基づいて責任ある決定と行動をとり(応用)、これらの活動をより多くの人びとに伝える(振り返り)ことができる人材の育成」と定義される(図3)。ラーニングサイクル理論に基づいた水圏環境教育を実践することで、水圏環境の問題解決に自らすすんで取り組むことができる国民を育成することが可能となるであろう。
水圏環境教育推進リーダー育成科目
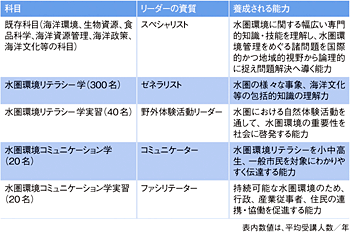
■表1:水圏環境教育推進リーダー育成科目
水圏環境教育を実践していくためには、水圏環境教育の指導者である「水圏環境教育推進リーダー」の育成が欠かせない。本プログラムでは、リーダーの目指すべき姿として5つの資質を掲げ、既存のスペシャリスト育成科目に加え新たに4科目を設置した(表1)。
これらの能力を備えた水圏環境教育推進リーダーが実践的な教育活動を行うことで、全国各地域において「水圏環境教育」が活発に行われるものと期待される。
水圏環境リテラシー推進のための組織の構築
次に、育成された水圏環境教育推進リーダーが大学と連携しながら地域社会において活躍するためには、全国の各地域のリーダーの活動を支援する組織が必要である。そこで、水圏環境教育推進リーダーの地域への派遣等を通じた大学と社会をつなぐインターフェース的役割を担うことを目的とし、2010年4月に本学の産学・地域連携推進機構内に海洋リテラシー推進部門が設置された。海洋リテラシー推進部門の設置によって、水圏環境教育推進リーダーがそれぞれの地域のみならず、全国的規模で「国民の総合的な海洋の理解」の促進に向けた水圏環境教育に取り組むことが期待される。
まとめ
本紙面をお借りして水圏環境教育推進リーダー育成プログラムの内容を紹介した。今後、全国の水産海洋系高校・大学等の関係諸機関や関係各位のご助言とご協力を賜り、本プログラムがより良い方向に発展し、国民の「総合的な海洋の理解」促進に貢献できればと願っている。(了)
