Ocean Newsletter
第246号(2010.11.05発行)
- 金沢大学理工研究域環境デザイン学系教授、第3回海洋立国推進功労者表彰受賞◆石田啓(はじめ)
- 東京大学大学院理学系研究科 附属臨海実験所 所長、海洋基礎生物学研究推進センター センター長◆赤坂甲治
- 東京大学大学院人文社会系研究科 附属北海文化研究常呂実習施設 准教授◆熊木俊朗(としあき)
- ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・研究科長)◆山形俊男
環オホーツク海地域をめぐる古代の交流
[KEYWORDS] オホーツク文化/考古学/海洋民東京大学大学院人文社会系研究科 附属北海文化研究常呂実習施設 准教授◆熊木俊朗(としあき)
オホーツク海の沿岸地域では、5世紀から12世紀のあいだ、独特の古代文化である「オホーツク文化」が拡がっていた。この文化の担い手は海での生業を基盤とする海洋民であると同時に、大陸と日本列島を北回りのルートで仲介する交易民でもあった。このルートでの交流はそれまで約6,000年間も途絶えていたのだが、オホーツク文化は、それを復活させるという交流史上きわめて重要な役割を果たした。
古代のオホーツク海洋民の文化
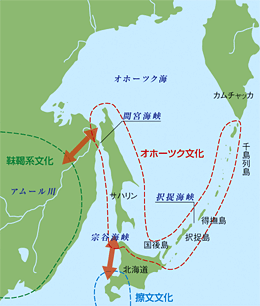
■図1: オホーツク文化の拡がりと周辺の文化
日本列島を囲む四つの海のなかで最北に位置するのがオホーツク海であり、この海に接している北海道の東北部沿岸は、冬期に流氷が漂着することで知られている。オホーツク海を取り囲んでいる陸地の「環」の南半、すなわち北海道・サハリン(樺太)・千島列島では、紀元後5世紀から12世紀のあいだに突如として出現した、独特の古代文化が存在した。考古学で「オホーツク文化」とよばれる海洋民の文化である。
彼らオホーツク人の残した遺跡は北海道のオホーツク海沿岸でも数多く発見されているが、その出自や暮らしぶりは、札幌など同時期の北海道に展開していた文化とは全く異なっていた。人々の顔かたちは現在の大陸のアムール川下流域の人々のそれに近く、金属製品など大陸産の品を携えた外来の文化であり、巨大な竪穴住居に複数の家族が同居し、海獣狩猟や漁撈など、海での生業を生活の基盤としていた。クマをはじめとする動物を信仰の対象としていたこともわかっている。オホーツク人は「謎の海洋民族」とよばれることもあるが、その発見から100年以上に及ぶ考古学の調査によって、北海道へと移住してきた一派についてはその実像が次第に明らかにされつつある。
オホーツク文化は、5世紀に宗谷海峡を挟んだサハリン南部から北海道北端部にかけての局所的な地域で成立したのち、7世紀になると大陸の文化要素を多く取り込みながら分布域をアムール河口部から千島列島まで大きく拡げた(図1)。この拡大期の文化内容は斉一的で地域色は少なかったが、その後、8世紀の後半になると各地の文化との交流が深まって地域毎の差が大きくなり、やがて各地の文化に吸収されるようなかたちでオホーツク文化は分断され、消滅する。オホーツク文化の変遷過程はおおよそこのように判明しているが、北海道以外の詳しい状況、すなわち彼らの故地とみられるサハリンや、大陸のアムール川河口やその北部、北海道を経由した先の千島列島に展開していた集団については、ロシア連邦との共同調査が進展しつつある現在でも資料が少なく、実態には不明な点が多い。使用されていた土器や骨角器などの共通性からみて同様の文化が拡がっていたことは明らかだが、生活の詳細や、文化の形成から消滅に至るまでの背景については、未だに多くの「謎」が残っている。
交易民としてのオホーツク人

■図2: オホーツク文化の遺跡から出土した大陸系の青銅製帯金具
この地域にオホーツク文化が突如として現れ、拡散し、消滅していった背景には何があるのだろうか。従来からいわれてきたのが、温暖化や寒冷化といった気候変動や、資源や人口の配分を最適化するための戦略など、環境への適応とそれに伴うヒトの移動という観点からの説明である。それらに加えて最近では、交易の仲介者という社会経済的な側面が特に重要視されている。オホーツク人が携えていた大陸産の製品(図2)は、当時のアムール川中流域を中心に拡がっていた「靺鞨(まつかつ)」※1 系の文化からもたらされたものだが、おそらく、オホーツク人はその対価としてクロテンなどの毛皮や海産物を靺鞨の側に渡していた。この靺鞨系の集団は当時、唐の王朝へと盛んに朝貢しており、オホーツク文化からの産品も靺鞨系集団を介して唐に献上されていた可能性が高い。しかし8世紀後半以降、唐への朝貢が下火になるのと同時にオホーツク人と靺鞨系集団の関係は弱まり、大陸製品の移入は減ってゆく。一方で北海道のオホーツク人はそれを補完するかのように、当時の北海道に展開していた「擦文(さつもん)文化」※2 との交流を強化し、擦文人を介して本州産の鉄製品などを盛んに入手するようになる。このような過程を経て、北海道のオホーツク人は擦文文化のなかに取り込まれてゆくことになった。
高度な海洋適応を果たしたといわれるオホーツク人であるが、それは単に海獣狩猟や漁撈といった生活技術の面のみに注目しているわけではない。海を舞台として、大陸と日本列島を仲介していた交易民としての側面も含めた評価なのである。この、オホーツク文化の時期に開発されたアムール河口からサハリン・北海道へと至る「北回りの」交流ルートが、その後の中世から近世にかけてどの程度機能していたのかは未だ判然としていないが、交流そのものは維持されていたとみられている。そして18~19世紀には、清朝と本州をつなぐ北回りの交易として隆盛を極めた山丹交易※3 が、このルート上で展開されることになる。
文化の境界としての宗谷海峡・択捉海峡
オホーツク海は島や半島に囲まれた大陸の縁海であり、この「閉じた海」のかたちや、ここに紹介したオホーツク文化の存在などは、「環オホーツク海地域」という歴史地理的な単位がそれ以前から続いていたことを想像させるかもしれない。しかし、この地域を一つのまとまりとするような広域的な相互交流は、約7,500年前の縄文時代の早期からオホーツク文化の出現前夜まで、実におよそ6,000年もの間、途切れた状態が続いていた。すなわち、最終氷期が終わって間宮海峡や宗谷海峡が成立した後は、宗谷海峡と択捉海峡(択捉島と得撫(うるっぷ)島の間)がいわば文化的な境界線となる状況が続き、この線を越えて日本列島の縄文文化とサハリンや大陸の新石器文化とが交流することは、縄文時代早期などの一時的な例外を除き、全くおこなわれなくなった。この境界線を越えて日本列島の北方と大陸との密な交流を復活させたのがオホーツク文化であり、これは日本列島の交流史上、画期的な出来事だったと評価できるだろう。
筆者の所属する東京大学常呂実習施設は主に考古学と博物館学の研究・教育をおこなっている。北海道での発掘調査のほか、近年ではロシア連邦の研究機関との交流を深め、極東ロシアでの共同調査も実施している。古代のオホーツク人と現代のわれわれとでは交流の背景にある社会政治的な状況が大きく異なるが、海峡を挟んで接した隣人との交流が社会経済上不可避であり、それは同時に文化的な豊かさをもたらす、という点では共通すると日々実感している。現在、極東ロシアとの交流を進展させるにはまだ様々な障壁があるが、環オホーツク海を舞台とした海洋交流を実現させたオホーツク人の存在が、現代のわれわれを勇気づけることになればと願っている。(了)
第246号(2010.11.05発行)のその他の記事
- 海洋の環境保全と開発が人類を救う 金沢大学理工研究域環境デザイン学系教授、第3回海洋立国推進功労者表彰受賞◆石田啓
- 海洋教育に不可欠な地域密着型教材の開発 東京大学大学院理学系研究科 附属臨海実験所 所長、海洋基礎生物学研究推進センター センター長◆赤坂甲治
- 環オホーツク海地域をめぐる古代の交流 東京大学大学院人文社会系研究科 附属北海文化研究常呂実習施設 准教授◆熊木俊朗
- 編集後記 ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・研究科長)◆山形俊男
