Ocean Newsletter
第244号(2010.10.05発行)
- 一般財団法人函館国際水産・海洋都市推進機構 推進機構長◆伏谷 伸宏
- 日本福祉大学子ども発達学部教授◆磯部 作
- 海上保安大学校教授◆山地哲也
- ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・研究科長)◆山形俊男
海底ゴミ問題の法整備を
[KEYWORDS] 小型底曳網漁業/海底ゴミ回収・処理体制/海洋ゴミ発生抑制日本福祉大学子ども発達学部教授◆磯部 作
瀬戸内海の海底には大量のゴミが沈積しており、漁業などに被害を与えている。漁業者が小型底曳網漁業などにより日常的に海底ゴミを回収し、沿岸自治体などで処理を行うが、回収・処理の体制はまだ未整備の地域が多い。
今後、国や府県などが責任をもって回収・処理体制の確立や、ゴミの発生抑制を行う必要がある。
海底ゴミ問題の状況

■小型底曳網により回収した海底ゴミ(上)
漁獲物と混獲した海底ゴミ(下)
(岡山県寄島町漁協)
瀬戸内海や東京湾や伊勢湾などの海底には多くの海底ゴミが沈積しており、小型底曳網漁業などの操業時に大量のゴミが網にかかり問題になっている。
瀬戸内海では、小型底曳網漁業の網にかかる海底ゴミは、ポリ袋やペットボトルや食品トレイなど、石油化学製品であるプラスチック類が80%以上を占めている。次いで飲料などの空き缶が多く、冷蔵庫などの電気製品や自転車、タイヤ、それに自動車やボートなどが網にかかることもある。漁具などの漁業系のゴミは数%にすぎない。
瀬戸内海の海底ゴミの量は、小型底曳網漁業によって回収可能な海底数十cmまでに沈積している海底ゴミで約13,000トン以上ある。海底ゴミは瀬戸内海全域に沈積しているが、人口が多く河川が流入する海域や、淡路島東部や燧灘(ひうちなだ)東部などのように潮流などの影響でゴミが集まりやすい海域に多く沈積している。また海底には、小型底曳網漁業では回収不可能な不法投棄された建設廃材や大型船の錨など、数トンもある巨大な物も沈んでいる。さらに漁網にかからない網目より小さいゴミもある。ビニールシートなどの海底ゴミは海底を被覆することなどにより海域環境の悪化をもたらす。また、小型底曳網漁業などでは、操業時に海底ゴミが漁網に入ることによる漁獲効率の低下や揚網時の労力負担増、混獲した海底ゴミと漁獲物とを分別するための時間の損失、魚体の損傷、鉄板やワイヤーなどの海底ゴミによる漁網の破損などが問題である。巨大な海底ゴミが漁網にかかることによる漁船転覆の危険性もある。
海底ゴミの回収・処理
海底ゴミを減少させるためには、まず海底に沈積しているゴミを回収して処理する必要がある。しかし、海底ゴミの回収・処理体制はまだ未整備の地域が非常に多い。このため現状では、小型底曳網漁業などを営んでいる漁業者が、海の日を中心にした時期に海底清掃活動を行っている場合が多い。ただ、一時期だけの清掃活動では、毎年同じように海底ゴミが沈積しており、海底ゴミをあまり減少させることにはなっていない。
これに対して、瀬戸内海では、日常的に海底ゴミの回収を行う漁協も少しずつではあるが増えてきている。岡山県の日生(ひなせ)町(現備前市)や寄島町(現浅口市)、広島県の尾道市、大分県の日出町(ひじ)などでは、小型底曳網漁業の漁業者が、通常の操業時に網にかかった海底ゴミの回収を行い、漁港に設置した海底ゴミ専用のゴミステーションに一時保管し、それを沿岸自治体のゴミ処理場に運搬して処理をしている。岡山県では、県の「瀬戸内海環境美化推進事業」により、まだモデル地区ではあるが、瀬戸内海沿岸の7市すべてに海底ゴミ専用のゴミステーションが設置されており、重い家電製品などの運搬費用は県が負担している。尾道市では、回収した海底ゴミを入れる網袋代や、焼却場へのゴミの運搬費用などを市が負担している。岡山県日生町漁協の操業海域では、20年以上にわたって日常的に海底ゴミを回収しており、洪水による出水時などを除いて、海底ゴミが大幅に減少している。
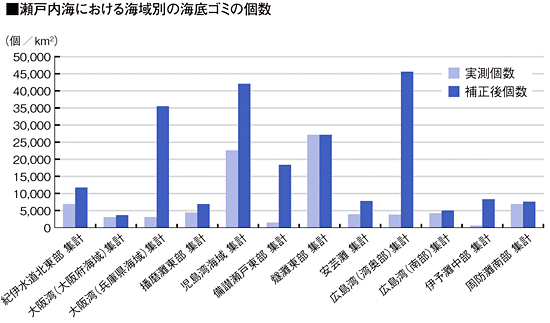
注)環境省中国四国地方環境事務所の瀬戸内海海底ゴミ対策検討会実態把握専門部会(部会長 筆者)が、2007年度冬に瀬戸内海の紀伊水道から周防灘までの12海域53地点において実施した小型底曳網漁業による海底ゴミの実態調査の実測値と、各海域での漁法や漁具の違いを考慮して筆者が補正をしたもの。
海底ゴミ問題解決の課題
海底ゴミの回収は一般市民などでは不可能であり、巨大なゴミを除いて、海底などの海域環境を熟知している漁業者が小型底曳網漁業などによって行うことが有効である。ただ、漁業系の海底ゴミは非常に少ないため、海底ゴミを漁業の産業廃棄物とするのではなく、一般廃棄物として扱い、行政が責任をもって、回収・処理体制の整備や費用負担などを行う必要がある。一般廃棄物は沿岸市町村で処理されるが、海底ゴミは河川などを通じて陸上から流入したものが多く、潮流などによって県境を越えて移動することも多いため、市町村だけでなく、国や府県が責任をもつことが重要である。現に、小型底曳網漁業は府県の許可漁業であり、海面の浮遊ゴミは国土交通省がゴミ回収船で回収している。
また、小型底曳網漁業で回収可能な瀬戸内海の海底ゴミは、瀬戸内海沿岸の一自治体平均は100トン強であり、人口数十万人の市では年間の一般廃棄物の0.1%程度であり処理可能であるものの、海底ゴミの集中しやすい海域のある自治体や小規模自治体などでは大きな負担となるため、国や府県の費用負担などは欠かせない。また、港湾区域内や海上交通安全法の航路内など、通常小型底曳網漁業の操業ができない海域における海底ゴミ回収や、漁業では回収不可能な巨大な海底ゴミに対しても、国や府県などによる回収体制の確立が必要である。さらに不法投棄された海底ゴミに対しては、発生源を明らかにし、発生源者に回収・処理費用の負担を含めて、違法に対する責任を取らせなければならない。
海底ゴミ問題を解決していくためには、海底ゴミの回収・処理体制の確立とともに、新たなゴミを発生させないことが重要である。海底ゴミの大半が自然分解しない石油化学系の製品などであるため、流入する河川流域の地域を含めた、啓発などの消費段階における対策だけでなく、拡大製造者責任や自然分解が可能な製品の製造など、製造段階も含めたゴミの発生抑制が必要である。さらに、大量生産、大量流通、大量消費、大量廃棄などの社会システムの見直しがなされなければならない。また、金属製の海底ゴミを回収業者に販売して稚魚購入資金の一部にしている尾道市の吉和漁協にみられるように、回収された海底ゴミの再資源化も考えられなければならない。
環境省中国四国地方環境事務所では、2006年度から「瀬戸内海海ゴミ対策検討会」を設置して、海底ゴミの実態把握や回収・処理、発生抑制に取り組んできた。今後は、近畿から九州にかけての海域、さらに伊勢湾や東京湾など、全国的に拡大して取り組んでいくことが求められる。とりわけ、漂着ゴミに対しては2009年に国の法律が制定されている※ため、今後は海底ゴミの回収・処理体制の確立などを推進させるための法律の整備が必要である。(了)
第244号(2010.10.05発行)のその他の記事
- 函館の「水産・海洋」による"まちおこし" 一般財団法人函館国際水産・海洋都市推進機構 推進機構長◆伏谷 伸宏
- 海底ゴミ問題の法整備を 日本福祉大学子ども発達学部教授◆磯部 作
- 海上保安大学校学生の国際対応力向上について 海上保安大学校教授◆山地哲也
- 編集後記 ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・研究科長)◆山形俊男
