Ocean Newsletter
第239号(2010.07.20発行)
- 民主党衆議院議員、海洋基本法フォローアップ研究会 代表世話人◆髙木義明
- (社)日本経済団体連合会海洋開発推進委員長、三井造船株式会社会長◆元山登雄
- 東京大学大学院工学系研究科教授◆荒川忠一
- インフォメーション
『「新たな海洋立国の実現」に関する提言』提出 - ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所副所長・教授)◆秋道智彌
風力エネルギーは「海」を目指す
[KEYWORDS] 海洋再生可能エネルギー/洋上風車/実証実験東京大学大学院工学系研究科教授◆荒川忠一(ちゅういち)
日本のエネルギー政策は太陽光に重点がおかれているが、世界では再生可能エネルギーの優等生である風力へとシフトしており、ヨーロッパのみならず今や中国や韓国でも大規模な洋上風車の設置の動きが明らかになっている。海洋王国日本の優れた海洋技術を活用し、わが国にも、大きな産業を育てるために洋上風車の国家プロジェクトとしての展開を強く期待するところである。
洋上風車を取り巻く現状

■図1: 世界一美しいと言われるコペンハーゲンの着底式洋上ウィンドファーム
コペンハーゲン空港に着陸する直前、機内の窓から右手下方に、弓型に並んだ20基の洋上風車が優雅に回転する姿を眺めることができる(図1)。およそ10年前に運転を開始し、専門家が「世界一美しいウィンドファーム」と賞賛する風車群である。美観ばかりでなく、これらの洋上風車群は、陸上の風車に匹敵する低コストでクリーンな電力を供給している。ヨーロッパ大陸最西端のポルトガル・ロカ岬には、15世紀に新世界を求めて船出した航海者らを記念した「ここに陸終わり、海始まる」という碑文が立っていると聞くが、風力エネルギーの先進地域であるヨーロッパは、まさに今、陸上の風車から海上の風車へという新たな船出の時代を迎えているのである。
国際エネルギー機関のロードマップでは、2050年までに、世界全体における地球温暖化ガスの50%削減を目ざしている。この目標を実現するために、日本をはじめとする先進国は80%以上の削減を期待されている。そのうち21%を再生可能エネルギーが担当することになっているが、風力は水力と同等の規模を占め、太陽光によるエネルギーを圧倒的に凌駕している。洋上風車については、4000kW機4,000基/年の新設が求められている。ちなみに現在、世界の風力エネルギーの総量は1億6,000万kW、うち洋上風車は200万kWである。ヨーロッパでは2020年までに、洋上風車2,000万kW導入を計画している。

■図2: 大深水の海域に設置されるノルウェーの浮体式洋上風車(Oyvind Hagen / Statoilによる)
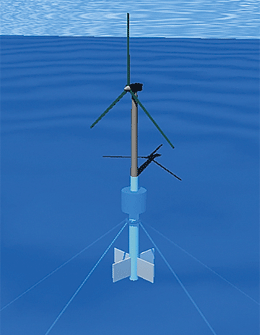
■図3: スパー型浮体式洋上風車の模式図(東大・鈴木英之教授による)
翻って日本はどうであろうか。昨年9月の国連総会で、鳩山前首相は2020年地球温暖化ガス25%削減を目指すと宣言した。しかし現在の政府の試案では、コストの高い太陽光に重点がおかれ、再生可能エネルギーの優等生である風力は、いまだ国内で大きな位置を占めるに至っていない。日本の風力エネルギーは現在200万kWであり、たとえ従来の政府目標である600万kWまで引き上げたとしても、温暖化ガス削減目標を満たすには到底不十分である。世界の基準に照らし合わせるならば、2,000万kW以上を目指す必要があるが、陸上の風車だけでそれを賄うのはきわめて難しい。一方、海洋に目を転じてみれば、排他的経済水域世界6位という数字も示すとおり、四方を海に囲まれた日本は豊富な海洋エネルギーに恵まれ、洋上風車が発展する可能性も果てしなく大きい。賦存量に関してはさまざまな見積りが試みられているが、浅い海に展開する「着底式」の風車では3,000万kW以上、深い海での利用に対応する「浮体式」の場合はその10倍を超えることは疑いない。
日本の洋上風車は、現在、港湾地域や陸上のごく近い場所に10数基存在するものの、本格的なものは皆無といってよい。経済産業省・NEDOは、浅い海を想定した着底式洋上風車について、6カ所で基礎調査をスタートさせたほか、昨年から2カ所で風況観測のプロジェクトを開始した。本年度は、1カ所1基という単位で風車を設置するプロジェクトの公募を行っている。とはいえ、冒頭で触れたコペンハーゲン沖の大規模洋上風車群などと比較すれば、ゆうに10年以上の遅れを取っていることは否定しようもない。
世界では今、将来的に海洋エネルギーの中心的役割を担うものとして、深い海のうえに浮かべた風車、すなわち浮体式洋上風車が注目されている。昨年ノルウェーにおいて、200m水深の海上に2,000kW風車が短期間で設置され、世界中を驚嘆させたことは記憶に新しい(図2)。日本では、東大・東電らのグループ(図3)、京大・佐世保重工らのグループなどの基礎研究があるものの、実証試験を行うまでには至っておらず、本年度、環境省がフィージブル・スタディを開始すると聞くにとどまっている。
低炭素社会の構築に向けて、先進国の一員としての責務を果たすためにも、日本の持つ海洋技術の粋を集めた先端的な洋上風車の開発と、数多くある離島の活用や漁業との協調など、日本の環境に適合した風力エネルギーシステムの実証試験を推進することが今や急務となっている。以下に、具体的なプロジェクト案を示していこう。
洋上風車プロジェクトの提案
1)漁業協調型洋上風車
日本において、洋上風車をはじめ海洋エネルギーを導入する場合、漁業との調和が必須となる。従来、漁場として利用していた場所に設置する際、建設後に再び漁場として利用できる工夫を施した、漁業協調型洋上風車を開発する。具体的には、風車を支える構造物を漁礁として利用できるように工夫するとともに、将来大量に風車を導入することも想定したさまざまな漁礁設備の研究を行う。なお、浅い海で利用される着底式を基本とするものの、50m程度の水深にも耐えられる「ジャケット式」※など、日本の海洋事情に適合した方式の研究開発が望まれる。
2)離島におけるエネルギーの地産地消型洋上風車
離島地域においては、現在も電力価格の高いディーゼル発電などを利用している。洋上風車を導入することにより、地域として電力をカーボンフリーで地産地消することを目指す。環境、観光、地域活性を兼ね備えた地産地消型洋上風車の導入となる。このとき、深い海での浮体式洋上風車との組み合わせを提案する。現在、世界唯一の浮体式大規模洋上風車はノルウェーのみであり、日本での基礎研究を組み合わせることによって、台風などの厳しい自然環境下でも機能する実用的な浮体式システムを構築することができる。
3)ハイブリッド型海洋エネルギー基地、および実証試験サイト
海洋エネルギーは、洋上風車をはじめ、波力、潮流、温度差など、これから発展が期待できるさまざまな手法がある。特に、洋上風車と波力の組み合わせは構造物を共有できるメリットがあり、その将来が有望である。これらの複合的な実証研究サイトがイギリスに2カ所建設されており、日本にもその規模を拡大した海洋エネルギー実証サイト建設が、上記の洋上風車の実証試験に続くことが望まれる。
低炭素社会の構築と海洋利用の促進を図るため、洋上風車の本格的導入を目ざした実証試験を開始すべき時期はすでに到来している。洋上風車の先頭を走るヨーロッパのみならず、今や中国や韓国でも大規模設置の動きが明らかになっている。海洋王国日本の優れた海洋技術を活用し、大きな産業を育てるためにも、国家プロジェクトとしての展開を強く期待するところである。(了)
第239号(2010.07.20発行)のその他の記事
- 海洋への国民的関心と理解を深めよう 民主党衆議院議員、海洋基本法フォローアップ研究会 代表世話人◆髙木義明
- 海洋立国への成長基盤の構築に向けて (社)日本経済団体連合会海洋開発推進委員長、三井造船株式会社会長◆元山登雄
- 風力エネルギーは「海」を目指す 東京大学大学院工学系研究科教授◆荒川忠一
- 編集後記 ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所副所長・教授)◆秋道智彌
- インフォメーション 『「新たな海洋立国の実現」に関する提言』提出
