Ocean Newsletter
第239号(2010.07.20発行)
- 民主党衆議院議員、海洋基本法フォローアップ研究会 代表世話人◆髙木義明
- (社)日本経済団体連合会海洋開発推進委員長、三井造船株式会社会長◆元山登雄
- 東京大学大学院工学系研究科教授◆荒川忠一
- インフォメーション
『「新たな海洋立国の実現」に関する提言』提出 - ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所副所長・教授)◆秋道智彌
海洋立国への成長基盤の構築に向けて
[KEYWORDS] 成長基盤としての海洋/海洋産業振興/総合的な推進体制(社)日本経済団体連合会海洋開発推進委員長、三井造船株式会社会長◆元山登雄(たかお)
日本経団連では、政府の新成長戦略に向けて、「海洋立国への成長基盤の構築に向けた提言」を取りまとめた。新たな海洋産業の創出を通じた豊かな国民生活の実現に向けて、海洋資源など国家権益の確保、海洋の安全・安心の確保、低炭素社会への貢献などの重要課題に取り組むべきである。総合的かつ一元的な海洋政策の推進を図るために、総合海洋政策本部にリーダーシップの発揮が求められる。
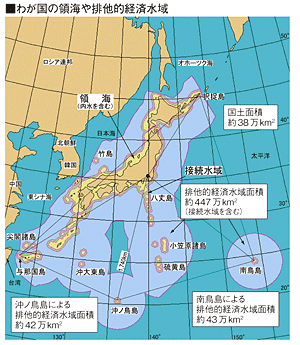
海上保安庁資料をもとに作成
わが国の国土面積は世界第61位の約38万km2であるが、領海と排他的経済水域(EEZ:Exclusive Economic Zone)を合わせた面積は世界第6位の447万km2と広大である。現在、国連で審査中である大陸棚の延長申請が認められれば、最大で国土面積の約2倍に及ぶ74万km2の大陸棚が確保でき、経済社会の新たな成長基盤となる。
日本経団連では、海洋政策を総合的かつ一元的に推進することの重要性を訴えてきた。こうしたなか、わが国では、2007年4月に海洋基本法が成立し、それに基づき2007年7月に総合海洋政策本部が設置されるなど、推進体制は着実に整備され、2008年3月に海洋基本計画が策定された。
政府は6月に「新成長戦略」※1、来年春に「第4期科学技術基本計画」を策定することから、海洋基本計画の施策の実現に向けて、4月20日に日本経団連では「海洋立国への成長基盤の構築に向けた提言」※2を公表した。
海洋開発利用をめぐる環境変化
わが国の海洋開発利用をめぐる環境変化としては、次の3つが挙げられる。
第1は資源獲得競争の激化である。中国やインドなど新興国の発展や、世界の人口増加により、陸上資源が不足・枯渇することが危惧されている。こうした環境のもとで、原油、天然ガス、石炭、鉄鉱石など主要な資源の大部分を輸入に依存するわが国にとって、鉱物・エネルギー資源を十分に確保できなくなるおそれがある。
第2は安全保障環境の変化である。日本近海で外国の不審船などが出没しており、200海里を超える大陸棚の延長により海洋権益が拡大すれば、安全・安心の確保のため海上保安の一層の強化が不可欠になる。国際的には、アデン湾・ソマリア沖において海賊によるハイジャック事件が多発しており、海賊対策に向けた自衛隊の海外派遣による国際協力の必要性が高まっている。
第3は地球規模の環境問題の深刻化である。異常気象の頻発や海面上昇などによる被害が収まっておらず、海洋分野における施策に期待が寄せられている。
重要課題の解決に向けた海洋開発利用
海洋開発利用は投資コストとリスクが大きく、実用化・商業化に向けて政府が果たす役割は大きい。そこで、政府は、産学官の連携による自主技術の開発や実証、パイロットプロジェクトの実施、適正な予算の投入による海洋産業の振興に取り組むべきである。また、海洋産業は国民生活に密着しており、総合海洋政策本部の調査によると、産業規模は16.5兆円、従業者は101.5万人となっている。活動領域の拡大や技術開発等によって、新たな海洋産業の創出を通じた雇用の拡大や豊かな国民生活の実現につながる。そこで、次の重要課題に対応すべきである。
第1は海洋資源など国家権益の確保である。わが国は、2008年11月に国連に大陸棚の延長申請を行い、現在は審査中である。この申請が認められれば、わが国の大陸棚が大幅に拡大する。
EEZや大陸棚を管理・保全するためには、重要な拠点となる離島を活用する法整備が必要である。提言では特定離島の整備に関する法案の早期成立を求めたところ、5月26日に国会で成立し、高く評価している。特に、わが国の最南端の沖ノ鳥島と最東端の南鳥島のEEZはわが国の国土面積より広く、この2つの島の港湾の国による直轄管理などの施策を実施すべきである。
また、離島や海域の管理の保全のため、洋上プラットフォームを構築し、鉱物・エネルギー資源開発のための実証実験などを実施することも有効である。これに加え、メタンハイドレート、石油・天然ガス、海底熱水鉱床、コバルトリッチクラスト等の量や規模などの調査や、資源探査船の開発とデータ整備、海上保安の維持・強化が求められる。
第2は安全・安心の確保である。まず、海上輸送については、世界貿易の重要なシーレーンであるアデン湾・ソマリア沖における海賊問題への対応がある。具体的には、海賊対処法に基づく自衛隊の護衛活動の頻度の増大や、ソマリアや対岸のイエメンへの支援が必要である。また、防災・減災については、地球深部探査船の「ちきゅう」による地球深部の観測・探査や、災害対応へのネットワークシステムの整備が具体的課題として挙げられる。
第3は低炭素社会への貢献である。まず、再生可能エネルギーについては、洋上風力、波力、海洋温度差、海流・潮流などの発電の技術開発と実証実験を推進する必要がある。次に、海上輸送については、CO2排出量の少ないエコシップの研究開発や導入推進が有効である。さらに、海底下の地層にCO2を貯留するCCS(CO2分離・回収・貯留)の研究開発や実証実験を推進することが重要と考える。
総合的な推進体制の確立
海洋政策は幅広く、関連省庁が多い。総合的かつ一元的な海洋政策の推進を図るための司令塔として総合海洋政策本部には、海洋基本計画を強力に推進するとともに、海洋関係予算の一括管理や、関係省庁の連携強化、海洋産業の振興に向けた研究開発、海賊問題など国際的な取り組みの強化に向け、リーダーシップの発揮が求められる。また、人材育成は重要な課題である。まず、子どもに対する海洋教育の充実が不可欠である。次に大学等における専門教育を強化し、研究者や技術者の育成を行う必要がある。産業界としても、技術開発力の向上等を通じて人材育成に努めたい。
4月7日には、政産学の有識者で構成される「海洋基本法フォローアップ研究会」において、この提言の考え方について、私が説明した。また、4月23日には、前原誠司海洋政策担当大臣に私が提言を建議した。その後、6月18日に閣議決定された「新成長戦略」には、経済成長に資する施策として、洋上風力開発の推進が位置付けられた。また、環境・エネルギー大国戦略としては、海洋資源や海洋再生エネルギー等の開発・普及の推進が盛り込まれ、日本経団連としても高く評価している。
今後、何よりも重要なのは、スピード感をもって実際にプロジェクトを実行していくことである。わが国の海洋開発利用を進めるために、産業界としても関係方面との連携強化に努めていく。(了)
第239号(2010.07.20発行)のその他の記事
- 海洋への国民的関心と理解を深めよう 民主党衆議院議員、海洋基本法フォローアップ研究会 代表世話人◆髙木義明
- 海洋立国への成長基盤の構築に向けて (社)日本経済団体連合会海洋開発推進委員長、三井造船株式会社会長◆元山登雄
- 風力エネルギーは「海」を目指す 東京大学大学院工学系研究科教授◆荒川忠一
- 編集後記 ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所副所長・教授)◆秋道智彌
- インフォメーション 『「新たな海洋立国の実現」に関する提言』提出
