Ocean Newsletter
第238号(2010.07.05発行)
- 横浜国立大学環境情報研究院教授◆松田裕之
- 三重県志摩市産業振興部水産課 水産資源係長◆浦中秀人
- NPO法人鞆まちづくり工房 代表理事◆松居秀子/東京大学大学院工学系研究科博士課程◆P. Vichienpradit
- 東京大学大学院理学系研究科 研究科長・教授◆山形俊男
海が問われる生物多様性条約
[KEYWORDS] 生物多様性条約(CBD)/2020年目標/CoP10横浜国立大学環境情報研究院教授◆松田裕之
2010年10月、名古屋で生物多様性条約(CBD)第10回締約国会議(CoP10)が開かれる。
「生物多様性の喪失速度を顕著に減らす」という2010年目標が検証され、中長期目標が議論される節目の年である。
その場では海洋保護区など、さまざまな海の議論が予定されている。
2020年目標
生物多様性条約(CBD: Convention Biological Diversity)はUNEP(国連環境計画)による国際条約で、生物多様性の保全、持続可能な利用、利益の公正な配分を3原則とする。利益の公正な配分は海洋問題と並んでCoP10(第10回締約国会議)でも主要議題になる予定である。CBDを批准していない米国はこれを強く批判していると言われる。
2002年ハーグのCoP6で、「2010年までに生物多様性喪失速度を顕著に減速させる」という2010年目標が合意された。CBD事務局が2010年5月に公表した地球生物多様性観測の第3版(GBO3)では、残念ながらこの目標は達成されていない。これは、日本国内の評価も同様である。
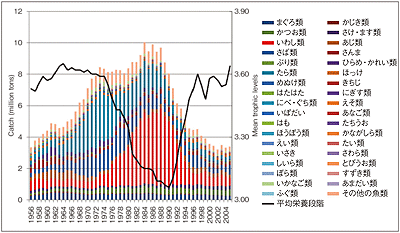
日本の漁獲量と海洋栄養段階指数(折れ線)。農水省、水産総研センター資料より作図
実は、生物多様性喪失速度の測定・評価手法は決まっていない。この点は温室効果ガスの数値目標とは大きく異なる。定量的指標も一部にあるが、妥当性が疑わしい。たとえば漁獲物の平均栄養段階(海洋栄養段階指数、MTI)を海洋生態系の健全性の指標としている。この指標を見る限り、日本の海洋生態系は半世紀前と変わらず、しかも世界平均の3.3より高く、模範的である(図1)。漁業によって海洋生態系が壊滅しているという指摘があるが、陸上よりも人間活動の影響が大きいとは言いがたく、また沿岸域の主要な劣化要因は漁業というより埋め立て、河川改修による流砂量減少などである。
CoP10で議論される2020年目標の事務局案※で海に関する目標のいくつかは、漁業の乱獲阻止を掲げている。目標6では、乱獲と破壊的漁業をなくすこと、漁獲圧の半減、資源量を最大持続生産量(MSY)水準に回復させることなどが謳われている。目標10ではサンゴ礁など脆弱な海洋生態系を気候変動と酸性化から守ることが謳われ、目標11では陸や海の各生態系の面積の15%を保護区などの手段で保護することが謳われている。
生物多様性と生態系サービスの政府間プラットフォーム(IPBES)の枠組み


2009年5月8日東京大学での日本生物多様性観測ネットワーク(J-BON)設立総会(上)と同年10月16日ケープタウンでのDIVERSITAS公開科学者会議のパネル討論。右から2番目が筆者(下)。
国連気候変動枠組条約(UNFCCC)では、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が設置されて多くの科学者の意見が集約されている。2007年にIPCC事務局はアル・ゴア氏とともにノーベル平和賞を受賞した。CBDは事務局とともにSBSTTA(生物多様性条約の科学技術助言補助機関)と呼ばれる科学技術的助言を行う会合を持ち、そこで議題や原案を作成する。しかしIPCCに匹敵する科学者の常設組織がない。自主的な科学者組織が内外で結成されているが、少なくとも海洋の専門家はごくわずかである。
CoP10では生態系サービスの政府間プラットフォーム(IPBES)と呼ばれる組織を作る準備をしている。3月に名古屋で開かれたCoP10事前会合では、上記2020年目標への科学者からの意見がまとめられた。私は、MTIが乱獲の指標としては妥当ではないこと、短期間に水産資源をMSY水準に回復させるという目標は禁漁しても物理的に不可能な魚種があること、そもそもMSYという概念自体が生態系サービス全体の最大化を求めない古い概念であること、保護区には地元が自主的に定めたものも含めるべきことなどを提言した。MTI批判以外は、事前会合全体の意見に取り入れられた。ワシントン条約と同じく、CBDの目標も環境団体の意見が色濃く反映されていると見られるが、CBDにかかわる科学者(国際生物多様性科学研究計画:DIVERSITAS)も、実現不可能な目標を掲げることには批判的である。
しかし、IPCCに匹敵するIPBESを作っても、問題が解決するとは限らない。そもそも、UNFCCCもワシントン条約も、締約国間の対立が激化して新たな提案の多くが否決された。CBDのCoP10事前会合に参加した限りでは、締約国の意見分布を省みていないように見える。2010年5月にナイロビで開かれたCoP10の事前会合であるSBSTTAでは、陸海それぞれの保護区面積を全海域の15%などとする事務局案に対し途上国から異論が噴出したという。私は事前会合の場で、先進国のエコロジカルフットプリント(生態学的負荷)は途上国よりはるかに高く、持続可能な水準の2~4倍であるから、これを持続可能な水準まで下げる目標を立てるべきだと主張したが、無視された。先進国の負荷をそのままに、途上国の開発を一方的に妨げるような「理想」が合意されるとは考えられない。
これらの環境諸条約は、先進国と途上国の対立が激化し、国際捕鯨委員会のような機能不全に陥る恐れがある。必要なことは、科学者が合意できない提案に固執せず、先進国が途上国よりはるかに大きな環境負荷をかけているという現実を見据えて、締約国の意見を理解するよう変わることだろう。誰が正しいかが問題ではない。大切なのは一歩でも合意して実行することである。(了)
松田裕之・井嶋浩貴(2009) エコロジカルフットプリントとミレニアム生態系評価. 林希一郎編『生物多様性・生態系の経済の基礎知識』中央法規出版. 124-146.
環境省生物多様性総合評価検討委員会(2010) 生物多様性総合評価報告書. 環境省:1-279
Secretariat of the Convention on Biological Diversity(2010). Global Biodiversity Outlook 3. Montreal Canada, pp.1-94
第238号(2010.07.05発行)のその他の記事
- 海が問われる生物多様性条約 横浜国立大学環境情報研究院教授◆松田裕之
- 英虞湾における新しい里海の創生に向けた取り組み 三重県志摩市産業振興部水産課 水産資源係長◆浦中秀人
-
鞆の歴史から瀬戸内海の観光まちづくりを展望する
NPO法人鞆まちづくり工房 代表理事◆松居秀子/
東京大学大学院工学系研究科博士課程◆P. Vichienpradit - 編集後記 ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・研究科長)◆山形俊男
