Ocean Newsletter
第192号(2008.08.05発行)
- 文部科学省研究開発局海洋地球課長、現科学技術・学術政策局調査調整課長◆近藤秀樹
- 西南学院大学法学部教授◆古賀衞(まもる)
- ヨットデザイナー、「ベンガル」セーリングチーム所属◆大橋且典
- ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・副研究科長)◆山形俊男
太平洋を走る3本のヨットレース
[KEYWORDS] クルーザー/外洋ヨットレース/太平洋航行ヨットデザイナー、「ベンガル」セーリングチーム所属◆大橋且典
北アメリカ西海岸からハワイに向けて走るヨットレースは3本ある。このレースに挑むのは、太平洋を縦横に駆けるベンガルチーム。アメリカ西海岸から飛び出し、太平洋高気圧を大きく回り込み、時には20ノット以上のハイスピードで、南の楽園ハワイをめざす。こんな大洋生活、あなたもいかがですか。
外洋ヨットレース

「ベンガル7」、2007年レース中の艇上風景(前列右端が筆者)(写真:ベンガル7/矢部洋一)
セーリングヨットには、大別して2つの種類がある。一つはオリンピック競技で良く見かける小型のもので「ディンギー」と呼ばれる種類である。これは居住キャビンを持たず、転覆を防ぐための復原力を乗員の動作に依存するスポーツ用具であり、艇種別に多くのクラスがある。もう一つは外洋航行を目的とするヨットで「クルーザー」と呼ばれる。これらは艇内に宿泊できる居住設備を有し、船底にバラストキールを備え堪航性に優れ、通常エンジンも搭載している。
外洋ヨットレースとはクルーザーによるもので、例えば神奈川県三浦をスタートし、黒潮を越え八丈島を回って帰る約480kmのレース等、昼夜兼行のセーリングを行い、航海術を競うものである。結果は艇の大きさを基本としたハンディにより、各艇の所要時間を修正し順位を決める。
筆者が所属するベンガルチーム※の旧艇、クルーザーの「ベンガルII」(全長16m、筆者設計)は、メルボルン―大阪レース、香港―沖縄―鹿児島―大阪レースなど多くの外洋レースに、すべて自力回航で参加してきた。新艇「ベンガル7」(全長13.85m、筆者設計)も同様に2007年のロサンゼルス―ホノルルレースに自力回航で参加している。「ベンガル」チームの航跡は太平洋を南北に3往復、東西に2往復、その走破距離は合計で8万マイルを超えている(地球一周=約2万マイル)。
※ 「ベンガル」セーリングチーム(代表:邨瀬愛彦)は、市民レベルで外洋ヨットレースを楽しむグループ。
ベンガル通信 URL (http://www.bengal7.com/)にて、活動が報告されている。
太平洋を走る3本の外洋ヨットレース
北アメリカ大陸からハワイまでの外洋ヨットレース3本を紹介しよう。
1.ビクトリア・マウイレース: レースは1965年から開催され、コースはカナダ・バンクーバー島のビクトリアからハワイのマウイ島ラハイナまでの2,308マイルである。最近は西暦偶数年に開催され、2006年の参加艇数は17であった。
2.パシフィックカップレース: 1980年6月15日、第1回が40艇の参加でスタートした。現在のコースはサンフランシスコからハワイのオアフ島カネオヘまでの2,070マイル。西暦偶数年に開催。前出のビクトリア・マウイレースもそうだが、2000年までは日本艇が参加した形跡はない。わがチームは2002年に「ベンガルII」で参加。同年は77艇が出走した。「FUN RACE TO HAWAII」というキャッチフレーズどおり、外洋セーリングそのものを楽しむチームが半分を占め、残りの半分はその合言葉に遠慮しつつも、勝敗を強く意識して走るレース派だ。コースレコードは1998年にRoy Disney(ウォルト・ディズニーの甥でディズニー社幹部) の「Pyewacket」が出した6日と14時間23分。
3.トランスパックレース: 距離はロサンゼルスからホノルルまでで2,225マイル。第1回1906年のレースのスタートはドラマティックであった。本来はサンフランシスコからスタートする予定だったが、その直前にサンフランシスコ大地震が発生。レース艇はそのままロサンゼルスに移動し、そこからスタートした。以後このレースはロスからスタートしている。戦後は西暦奇数年に開催。日本艇は1963年の「コンテッサ III」から始まり、昨年の「タキオンIII」「夢ひょうたん」「ベンガル7」まで多数参加している。筆者自身は1975年「DIC-CHITA」で、2001、03、05年は「ベンガルII」で、2007年は「ベンガル7」で出場、73艇の参加があった。
太平洋レースの常道
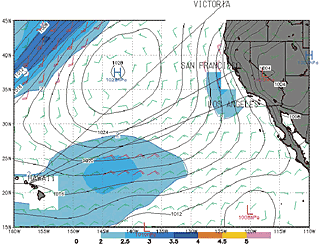
太平洋レース時の典型的気圧配置。図中直線は上から、ビクトリア・マウイレース、パシフィックカップレース、トランスパックレースの各コース。矢印は、風向と風力を表す。
外洋ヨットレースの攻略には、気象研究が必須となる。各レースはスタート地点もフィニッシュ場所も違うので、コースのディテールは大いに異なる。しかし中間の主要部分は皆同じで、そこに登場するのが太平洋高気圧である。夏場の北米大陸の西側の海上には、概して図のように大きな高気圧が居座っている。太平洋高気圧は例年春から初夏にかけて位置、勢力ともに激しく変動するが、7月の初旬から中旬、各レースが開催される頃には落着いてきて安定する。当然ながらこの高気圧の中心付近は風が弱い。ところが、各レースのコースは直線でも大圏でも、その中心近くの微風域を通る形になっている。
南へ迂回するコース: 目的地へ向かってまっすぐ進めば、微風域につかまり止まってしまうので、これをどのように避けて走るかが各太平洋レースの勘所となる。具体的に言えば、スタート後しばらくしてから吹出す北からの強風に乗って南下し、気圧の尾根付近で徐々に向きを変えて東進するという迂回コースが常道となる。そしてその東進の道を北寄りに取るか南寄りにするかで前段の勝負が決まるとされている。北側の風が弱ければ、大回りでも南側の勝ち。その逆ならば北の勝ちである。
実際、太平洋レースのベテランたちはどんな状況でもある程度は南下するようだ。過去、太平洋高気圧に突っ込んでベタなぎにあった例は多く、その恐怖が身に染み付いているのであろう。また、追風用のボート(太平洋レースは全体に追風なので、この種のボートが多い)は、軽量で復原力が小さくセールが大きいので、この強風では支えきれず、必然的に南下する。つまり大方はより南下する傾向にあり、それがひとつのセオリーにまでなっている。
ギャンブル性の高い北寄りの直線コース: しかし法則のあるところには例外がある。われわれ「ベンガルII」は2001年のレースでその例外的幸運にめぐり会った。レース前の気象解析では、どうみても北寄り直線コースの方が南迂回コースよりも有利である。この結論に従って、われわれただ一艇が直線コースをばく進した。他の全艇は常道の南コースである。結果は、「ベンガルII」の勝利。所属クラス1着修正3位外国艇1位を獲得した。おまけに「最も北へ行った」賞までいただいた。
逆の例もある。2007年の「ベンガル7」だ。レース前のコンピュータシミュレーションでは、例年と違い、わずかながら北寄りのコースがよいという結論が出た。しかし、われわれはあえて南を大きく迂回するコースを取った。結果は無残な敗北となった。微風が何日も続き、あわや表彰式にも間に合わないという程に遅れてしまった。ただし、最後の1日はよい風と波に恵まれて、同艇最高の22ノットオーバーという艇速をたたき出した。成績は悪かったものの、快速を十分に堪能できて一同大いに溜飲を下げた。
おわりに
日本においては、最近このような外洋レースに参加する艇が極端に減少し、クルーザーでありながら、沿岸に設置したブイを回る等の操船技術のみを競うレースが多くなっている。しかし、クルーザーの本来の楽しみは「外洋航行」にあり、真の海の楽しさ、恐ろしさを理解するためにも、できるだけ多くの人達に外洋でのセーリング体験を切に望むものである。(了)
第192号(2008.08.05発行)のその他の記事
- 海洋資源の利用促進に向けた基盤ツール開発プログラム 文部科学省研究開発局海洋地球課長、現科学技術・学術政策局調査調整課長◆近藤秀樹
- 大陸棚延伸問題の背景 西南学院大学法学部教授◆古賀衞(まもる)
- 太平洋を走る3本のヨットレース ヨットデザイナー、「ベンガル」セーリングチーム所属◆大橋且典
- 編集後記 ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・副研究科長)◆山形俊男
