Ocean Newsletter
第192号(2008.08.05発行)
- 文部科学省研究開発局海洋地球課長、現科学技術・学術政策局調査調整課長◆近藤秀樹
- 西南学院大学法学部教授◆古賀衞(まもる)
- ヨットデザイナー、「ベンガル」セーリングチーム所属◆大橋且典
- ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・副研究科長)◆山形俊男
大陸棚延伸問題の背景
[KEYWORDS] 大陸棚縁辺部/陸性地殻/大陸棚限界委員会西南学院大学法学部教授◆古賀衞(まもる)
沿岸国は、200海里までの海底を一律に大陸棚とすることができる。そして、200海里を超える海底を自国の大陸棚と主張する場合は、大陸棚の定義に基づいてその証拠を示すことが要求される。これは大陸棚延伸の「挙証責任」である。大陸棚の延伸を主張することはもちろん条約で認められた権利ではあるが、むしろわが国の大地の果てを確かめるための国家としての手続きと考えるべきである。
大陸棚は移動する大陸の外端
「ひょっこりひょうたん島みたいですね」―1977年夏のニューヨーク、第3次海洋法会議での話。私は、深海底制度を取り扱う第1委員会を傍聴していた。大陸棚については隣の第2委員会が取り扱っていて、通産省から派遣されていた地質専門家から交渉の様子を聞いた。「ひょっこりひょうたん島」は、団塊の世代には懐かしいテレビ番組。キャラクター豊かな人形たちの住む小さな島が波の間に間に漂い、着いた所でいろいろな事件が起こる物語。島が動くという発想が、おもしろかった。
当時、海洋法会議では、大陸棚の定義(範囲)をめぐる交渉が暗礁に乗り上げていた。大陸棚は、1958年条約で水深200mまで、または天然資源の開発が可能なところまでの海底およびその下と定義されていたが、排他的経済水域の出現で、200海里までの海底を含む大陸縁辺部(コンチネンタル・マージン)までとする案が支持を得て、交渉用草案に採用された。その結果、議論は「大陸縁辺部」をどう定義するかという点に集中した。
そこで登場したのが、「大陸漂移説」。大陸は毎年数cmずつ移動しているという学説である。それによれば、海底は、地質学上「陸性」と「海性」の地質に分けることができ、陸性の海底は移動する陸塊の一部をなすという。大陸棚が陸地の「自然の延長」という意味なら、大陸棚の範囲は、大陸漂移説でいう陸性海底の外端を定義すればいいということになった。
もともと大陸棚とは、氷河期に陸地であったとされる水深200m前後のなだらかな海底をいう。1945年に米国トルーマン大統領が大陸棚に対する管轄権の帰属を宣言した時には、水深200m以内にある海底の資源(石油)を想定していた。同宣言は、「大陸棚は沿岸国の陸地の自然の延長であって、それに自然に付随するものとみなされ」と述べている。この時から、大陸棚は陸地の一部であると意識されていたことが分かる。
大陸棚は、その後、南米諸国によって200海里領海の主張に変えられた。南米の太平洋側海底は急勾配で、ほとんど大陸棚が存在しない。資源も、海中の漁業資源しかなかった。そこで1947年、チリ大統領は「大陸棚に関する宣言」を発し、深度にかかわりなくチリ海岸に接続する海底の上、中および下にある天然資源を保存開発するために「大陸棚」に対する国家主権を確認し、そこにおける漁業と捕鯨活動を政府の管理下におくと宣言したのである。韓国でも、李承晩大統領が大陸棚宣言を発し、広い主権水域を設定した(李ライン)。
このように、大陸棚制度は、他方で上部水域に広がり、沿岸国による資源保存管理と伝統的漁業権の調和を模索しながら、排他的経済水域の制度へと変わって行った。
陸地領土の自然の延長として
資源を囲いこむ管轄権拡大の動きは、深海底資源の登場によって変質し、第3次国連海洋法会議の開催を促す契機となった。海洋法会議は1973年から1982年の条約採択まで丸10年間続けられ、大陸棚を越えた所に深海底制度を生み出した。深海底制度は大陸棚の無限の拡大を食い止めるために、その先の海底を人類の共同の財産と位置づけ、国際管理制度を設けたものである。
海洋法会議の前に、特筆すべき判決が出された。西ドイツ(当時)とオランダ、デンマークが国際司法裁判所で争った「北海大陸棚事件」判決(1969年)である。裁判所は、境界を示すことではなく、隣接する3国間の境界画定交渉に用いられる原則と方法を示すことを求められたのだが、それは結果として大陸棚制度の本質を論じることになった。裁判所は、当事国間で衡平の原則に従って誠実に交渉することを第一原則として判示したのであるが、同時に、大陸棚はその国の「陸地領土の自然の延長」でなければならない、という基準を示した。
このように、経済水域も深海底も、大陸棚制度との関わりで発展してきた。そして、大陸棚帰属の根拠とされたのは一貫して陸地領土との一体性であった。
海洋法会議では、地質学の専門家グループが世界の海底について大陸縁辺部の特徴を分析した。その結果、大陸縁辺部はいくつか異なる成因を基準に分類され、単一の規定では定義できないことが分かった。大陸が分裂または拡大している海底や、プレートが沈み込んでいる海底などさまざまである。またアイスランドのように海底隆起の上にある島の場合は地形学的な定義が適用できない。専門家グループは、それらに共通に適用できる法的かつ一義的な定義を模索した。その結果、比較的見つけやすい地形(大陸斜面脚部)を基点として、そこからの距離と堆積岩の厚さの比率を基準にするか、60海里という距離を基準にする規定を設けた。その上で、その定義ではカバーできない特殊な地質・地形についてさまざまな例外と制限を設けた。例外を主張する国々に配慮しつつ、全体としてコンセンサス・パッケージを作ろうとしたため、海洋法条約第76条は、とりわけ難解な規定になった。
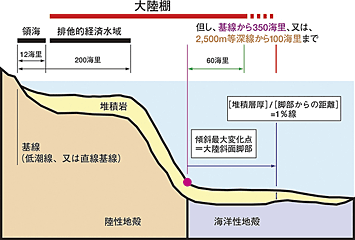
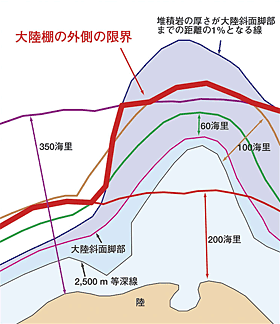
大陸棚延伸手続の成立
大陸棚延伸問題は、この流れの延長線上にある。沿岸国は、一律に200海里までを大陸棚とすることができる。そして、200海里を超える海底を自国の大陸棚と主張する国は、大陸棚の定義に基づいてその証拠を示すことが要求される。いわば「挙証責任」転換の制度である。
そして、海洋法会議は、第76条適用のためにもう一つユニークな仕組みを用意した。すなわち、200海里を超える海底を自国大陸棚と主張する国について、その申し立てを審査する制度である。大陸棚の定義はそれ自体客観的であるが、データ適用の段階で沿岸国の主観的な操作が行われる可能性がある。そのため、海洋法条約附属書IIで専門家からなる「大陸棚の限界に関する委員会」を設け、200海里を越える海底の主張を審査することにした。
審査制度は、「陸地領土の自然の延長」の限界を客観的に確定するための方策であり、「陸」と「海」の境目を法的に確定する手続である。日本がこの制度に基づいて大陸棚の延伸を主張することは、条約上の権利として当然のことであるが、それは、大陸棚の長い歴史の末にたどり着いた陸と海の境目を確定する手続でもあることを、あらためて思い返したい。(了)
第192号(2008.08.05発行)のその他の記事
- 海洋資源の利用促進に向けた基盤ツール開発プログラム 文部科学省研究開発局海洋地球課長、現科学技術・学術政策局調査調整課長◆近藤秀樹
- 大陸棚延伸問題の背景 西南学院大学法学部教授◆古賀衞(まもる)
- 太平洋を走る3本のヨットレース ヨットデザイナー、「ベンガル」セーリングチーム所属◆大橋且典
- 編集後記 ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・副研究科長)◆山形俊男
