Ocean Newsletter
第109号(2005.02.20発行)
- 北海道大学大学院水産科学研究科教授、日本海洋学会教育問題研究部会世話人◆岸 道郎
- 北九州市立大学文学部人間関係学科助教授◆竹川大介
- シップ・アンド・オーシャン財団海洋政策研究所主任研究員◆秋元一峰
- ニューズレター編集委員会編集代表者(総合地球環境学研究所教授)◆秋道智彌
新しい海洋安全保障の概念"海を護る"
シップ・アンド・オーシャン財団海洋政策研究所主任研究員◆秋元一峰"海を護る"、それは、海洋の平和維持と環境保護に統合的に取り組む新たな安全保障の概念である。
SOF海洋政策研究所が3年にわたって主催した国際会議「地球未来への企画"海を護る"」の研究メンバーは、2004年12月の最終国際会議において、「東京宣言"海を護る"」を採択した。
宣言は、新たな海洋安全保障によって、国連海洋法条約・アジェンダ21体制の求めるオーシャン・ガバナンスを促進することを提唱している。
海洋に新しい安全保障
海洋に新しい安全保障の概念が生まれた。"海を護る"とは、軍事、平和利用、資源、環境などに関する海洋の様々な管理が総合的に行われることを求める新たな安全保障の概念である。防衛・外交および治安維持によって国民と国家の安全を確保する旧来の狭義の安全保障観から脱皮して、資源管理や環境保護もまた人類の生存と発展のための基盤的要件であるとの認識に基づく広義の総合的な安全保障概念である。それは、海洋の問題全体に総合的、かつ、統合的なアプローチを提供し、これまでの縦割りで限定的な取り組みを大きく改善するものであり、安全保障を通したオーシャン・ガバナンスへの貢献である。
海洋管理の現状
人類は、海洋を利用し海洋の恵みを得て発展し繁栄を得てきた。海上交通路、漁業資源、海底資源、産業と生活のための沿岸域と、地球表面の70%を占める海洋とその資源に大きく依存してきた。これからも、海洋の持続的利用なくして平和と発展はあり得ない。さらに言えば、海洋こそが地球メカニズムを支えており、海洋環境の維持なくして地球生命の存続はあり得ない。
しかし、今、資源・エネルギーを求めて、あらゆる国家や主体が海洋へのアクセスを増大させており、そのような状況の中で、海洋の開発と利用を巡る国家間の対立が顕在化し、軍事的緊張を呼ぶ紛争が生じている。また、冷戦終結後、世界の主要な海洋路に沿った沿岸国・地域において、宗教や民族的対立あるいは貧困に端を発する武力紛争やテロが多発し、深刻さを増す海賊・武装強盗と併せて海洋の利用環境を不安定化させている。一方、経済活動の活発化の中で、大量生産、大量消費、大量廃棄の生活様式と無秩序な沿岸域開発によって陸上起因の海洋汚染が広がり、また、人口増大と食生活の向上が海洋資源の乱獲を招き、海洋における自然環境の悪化、生態系の破壊と資源の枯渇が深刻化している。
1994年に国連海洋法条約が発効し、沿岸国の領海は12海里に拡大し、さらに沿岸国が主権的権利・管轄権を持つ排他的経済水域・大陸棚が設けられ、その管理が沿岸国に委ねられた。その結果、それまで海洋自由のパラダイムの下で利用されてきた海洋のおよそ40%を占める広大な海域が、沿岸国の管理下に入った。この国連海洋法条約と、その2年前の地球サミットで採択されたAgenda21とによって、海洋の総合的管理と持続可能な開発を目指す新たな取り組みの体制がスタートした。
しかし、海洋のかなりの部分が各国の管轄海域として分割されたことにより、他方で、海に引かれた沿岸国の管轄海域の境界線がかえって海上犯罪に対する取り締まり当局の追跡を遮断してその逃亡を助け、また、人為的に引かれた各国の境界線が一体性の強い海洋環境や自由に動き回る生物資源の管理を難しくしている、などの新たな問題が出てきている。
各国は、このような現実を直視し、その広大さ故に本来国際的性格を持っている海洋の管理には、海洋全体の総合管理を念頭においた沿岸国による適切な管理とともに地域各国間の協調と協力が必要であることを再確認して、海洋の総合管理のための協働関係を強化する必要がある。新たな海洋安全保障の概念"海を護る"はこのようなニーズに応えようとするものである。
"海を護る"ための取り組み
シップ・アンド・オーシャン財団(SOF)海洋政策研究所は、「人類と海洋の共生」の基本理念に基づき、日本財団の支援を受けて、海洋の総合管理の研究を行っている。その一環として、2002年から3年計画で、「地球未来への企画"海を護る"」というテーマで新しい海洋の総合安全保障概念"海を護る"の提唱とそれを社会的に実現するための政策提言について研究をしてきた。
昨年12月、SOF海洋政策研究所は、東アジアを中心に世界の9カ国および国際機関から海洋法および海洋政策の専門家を東京に招いて、最終の国際会議を開催し、そこで、参加者の総意として、『東京宣言"海を護る"』を採択した。この東京宣言では、新たな安全保障概念"海を護る"を実現するための政治的意思の形成とその実行について、国際的な海洋シンクタンクの設立、"海を護る"国際会議の定期的開催、紛争予防・環境保護システムの構築、情報の共有、利用国による応分の負担など10項目にわたる具体的措置を講じることを提言している。提言の概要は表を参照されたい(全文は、シップ・アンド・オーシャン財団ホームページ https://www.spf.org/topics/pdf/041220_1.pdfに掲載)。
SOF海洋政策研究所では、東京宣言に盛り込まれた提言を実行することが重要であると考え、機会あるごとに関係方面にそのことを訴えていくこととしている。そして、その中核として「海を護る政策提言グループ」を組織して東京宣言の政策提言を実行に移すための活動を推進していきたいと考えている。人類の生存基盤である海洋の総合管理を促進させるために、皆様にもご理解、ご協力いただければ幸いである。(了)
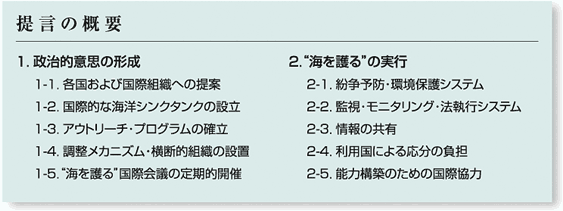
第109号(2005.02.20発行)のその他の記事
- 小中学校の「海」の教育を考える 北海道大学大学院水産科学研究科教授、日本海洋学会教育問題研究部会世話人◆岸 道郎
- 海はだれのものかを考える-実践知識と環境への権利- 北九州市立大学文学部人間関係学科助教授◆竹川大介
- 新しい海洋安全保障の概念"海を護る" シップ・アンド・オーシャン財団海洋政策研究所主任研究員◆秋元一峰
- 編集後記 ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所教授)◆秋道智彌
