Ocean Newsletter
第109号(2005.02.20発行)
- 北海道大学大学院水産科学研究科教授、日本海洋学会教育問題研究部会世話人◆岸 道郎
- 北九州市立大学文学部人間関係学科助教授◆竹川大介
- シップ・アンド・オーシャン財団海洋政策研究所主任研究員◆秋元一峰
- ニューズレター編集委員会編集代表者(総合地球環境学研究所教授)◆秋道智彌
小中学校の「海」の教育を考える
北海道大学大学院水産科学研究科教授、日本海洋学会教育問題研究部会世話人◆岸 道郎小中学校の理科の教科書に「海」はほとんど出てこない。
海洋国日本、と言いながらどうしてそうなったのか? その原因を探り今後の課題を考える。
とにかく教科書を見てください!
皆さんのお子さんやお孫さんが学校に通っていたら、理科や社会の教科書を5分間でいいのでご覧ください。表紙の裏などに海の写真やイルカの写真が載っていませんか? 一安心? でも、騙されてはいけません。教科書の中身を見てください。小学校と中学校の教科書には「海」のことは単元としてはまったく登場しません。写真は「海」を入れたいなぁ......と考えた執筆者や会社の人の茶目っ気か抵抗か、はたまた「海を入れないことへの罪滅ぼし」?
そればかりか、「海」について何らかの記述がある、という場所は、小学校の理科ではまったくないといってよいのです。社会でも「私たちの国土(5年)」というところで、「太平洋、日本海」が記述されていますが、「黒潮や親潮」は指導要領からはずされているので、「あたたかい海の流れ、冷たい海の流れ」と書かれています(「あたたかい海の流れ」という熟語に違和感はありませんか? 「海」は流れるのか? 流れるのは海水でしょうが!)。魚についての記述はさすがに社会科の「食料生産(5年)」で少しだけ出てきますが、「黒潮や親潮」と書くと文科省の検定で改訂させられるわけですから、黒潮域・親潮域でどんな魚が獲れるかとか、回遊とかそんなことは記述されていません。
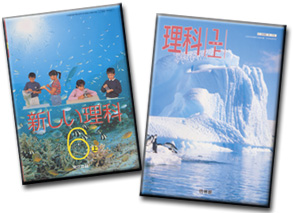
中学の教科書を見てください。ほとんどが小学校で学んだことの繰り返しである、ということが分かります。よく西洋の人たちが「どうして日本人はそんなに星が好きなんだ?」って驚くように、天体や地層の話はこれでもか、これでもかというくらい出てきます。日本は地震の国だから、地震の起こるメカニズムまで、簡単ではあるものの書いてあるわけです(しかし、津波についてはまったく書いてありません。念のため)。理科では魚の体の構造について、他の脊椎動物と比較した記述がありますが、海の魚のことはまったく書いてありません。プランクトンも淡水性のものがほとんどです。二酸化炭素の吸収に海の植物プランクトンが果たす役割は陸上の植物に匹敵するのに、そのようなことはどこを捜しても書いてありません。これで「海洋国日本」の教科書と言えるでしょうか?
どうして「海」がないの?
文部科学省が出している小学校学習指導要領解説理科編と、中学校学習指導要領解説理科編を見てみます。ご承知の方も多いと思いますが、「日本をつぶすのか?」学校教育、「円周率は3」の学校教育、「子供をバカにしている」学校教育、と批判のある改訂版です(1998年12月に学校教育法施行規則と学習指導要領が改訂され、この新学習指導要領に沿った教育が、小学校と中学校では2002年度から全面的に実施されていたものです)。当然ですが、「海」という文字が項目はおろか、それの説明文の中にさえまったく登場しません。だから教科書に「海」がないのです。「海を体系だって教えないこと」は国の方針だ、といっても過言ではないような気がします。しかも、これは今回の改訂でそうなったというよりは、以前からその傾向があったのです。
なぜ日本の理科の初等教育から海が欠落してしまったのでしょうか? それは、もとをたどれば、大学の理学部の体制に行きつくことはわれわれの間では周知の事実なのです。最近環境問題が入ってきて少し崩れてきはしましたが、大学の理学部は、物理、化学、生物、地学と分かれ、教科書もそれにぴたりと対応してきました。最近、大学でも「環境」の大学院教育をするところができ、それに呼応して教科書に「環境」の単元が登場し、あるいは高校に総合理科という科目が生まれ、その中に環境問題の単元ができたようです。しかし、総合的な海洋学が理学部にないので、高校の理科にもありません。小中学校の理科は、高校の理科に発展するようになっているので、高校にないものは、小中学校にもないのです。わずかに、海洋物理は理学部地球物理学科の中にあるので、高校の地学の中に海洋物理がありますが、歴史が浅いので、大気(気象)よりずっと軽い取り扱いしか受けず、小中学校では扱ってもらえません。海がなくて、地質や天体の入っている小中学校の理科の教科書は、理学部の勢力地図から生じた結果といえましょう。
海を理解するには?
「理科」には、物理、化学、生物という3大分野があり、この3つの基礎学問をもとに高校の教科書が構成されているのは、上に述べたとおりです。でも、小学校で大学教育にエンエンと続くこの3大分野に立脚した理科教育が必要でしょうか? 海を学ぶ、ということの基本に「物理」「生物」「化学」の知識が必要だ、というのは大学教育や研究においてではないでしょうか。「海を学ぼう」で、海にはこんな不思議(今、はやりの「へぇ」ですね)がある、こんな生き物がいる、津波もあるし、潮の満ち引きもある、などを「知る」「学ぶ」のに物理も化学も生物も要らないではありませんか(「なぜ?」を追求しなければ......ですが)。「なぜ」を知りたくなったら、大学へ行って勉強しよう! でいいのです。海が果たす役割を子供のうちに学ぶこと、これが海洋国を名乗る国民の教育である、と考えます。そしてそれは「魚嫌い」を減らし(?)、長寿国日本を続けることにもつながります。
日本海洋学会の取り組み
私の属する日本海洋学会では、少しでも高校生や小中学生に海に興味をもってもらうために、各地の「海洋の家」の行事を支援したり、本を出版したりしています。「海を学ぼう」(東北大学出版会)は、高校生の夏休みの自由研究の手引きのつもりで作りました。現在は小中学校の先生が、海の単元がなくても海のことに授業で触れることができるようにするための、新しい発想の本を作成中です。(了)
【参考文献】
角皆静男、「島国日本の学校で海の教育は?」、Ship & Ocean Newsletter No.81 (Dec.20)、 2-3 (2003)
第109号(2005.02.20発行)のその他の記事
- 小中学校の「海」の教育を考える 北海道大学大学院水産科学研究科教授、日本海洋学会教育問題研究部会世話人◆岸 道郎
- 海はだれのものかを考える-実践知識と環境への権利- 北九州市立大学文学部人間関係学科助教授◆竹川大介
- 新しい海洋安全保障の概念"海を護る" シップ・アンド・オーシャン財団海洋政策研究所主任研究員◆秋元一峰
- 編集後記 ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所教授)◆秋道智彌
