Ocean Newsletter
第38号(2002.03.05発行)
- 海洋生物学者◆ジャック T.モイヤー
- (社)海洋産業研究会常務理事、東海大学・北海道東海大学講師◆中原裕幸
- ニューズレター編集委員会編集代表者 ((社)海洋産業研究会常務理事)◆中原裕幸
21世紀に向けた海洋・沿岸域の環境管理
~Oceans & Coasts at Rio+10パリ会議からWSSDヨハネスブルグ・サミットへ~
(社)海洋産業研究会常務理事、東海大学・北海道東海大学講師◆中原裕幸昨年12月のRio+10パリ会議、そして2002年8月ヨハネスブルグで開催されるWSSD「持続可能な開発に関する世界首脳会議」。地球環境サミット(リオ、92年)が採択した「AGENDA 21」の実施状況の検証と今世紀における効果的な実施に向けて国際的な動きが進んでいるが、海洋・沿岸域の重要性にもかかわらず、その取り組みの立ち遅れが目立つ。
60ヶ国、約430人参加のRio+10パリ会議
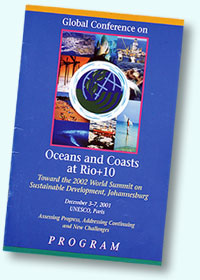
1992年リオデジャネイロで開催されたいわゆる『地球環境サミット』、国連環境開発会議(UNCED:UNConference on Environment &Development)は、"持続可能な開発(SustainableDevelopment)"という思想をその後の世界中に浸透、定着させるとともに、21世紀に向けた環境と開発の共存を目指した行動計画、「AGENDA 21」を採択したことで歴史的に意義の深い会議として知られる。そのリオ会議から10年経った時点での国際的な取り組み状況を点検し、今世紀の方向を討議しようとの趣旨で、2002年の今年8月26日から9月4日まで、南アフリカのヨハネスブルグで「持続可能な開発に関する世界首脳会議」(WSSD:World Summit on Sustainable Development)が開かれる。
このヨハネスブルグ・サミットに先立って、昨年12月3日から7日まで、パリのUNESCO本部で開催された、GlobalConference on Oceans & Coasts at Rio+10:Toward the 2002 World Summit on Sustainable Development,Johannesburg(以下、Rio+10パリ会議)という国際会議に参加する機会を得た。
このRio+10パリ会議は、国連UNESCO傘下のIOC(政府間海洋学委委員会:Intergovernmental Oceanographic Commission)とそのサポート研究調査活動に当たったアメリカのデラウェア大学海洋政策研究センター(Center for the Study of Marine Policy, Univ. of Delaware)の呼びかけになるものである。その趣旨は、上記の「AGENDA 21」(全40章)の第17章が海洋・沿岸域における環境と開発の共存を扱った部分であり、まさしく世界の環境と開発に関する問題の重要部分を占めるのがこの海洋・沿岸域での問題である、との考え方にもとづいて開催されたものといってよい。
この会議は、政府関係者、NPO・アカデミア、国際機関・地域機関の三つのセクターからの参加者で構成されたが、政府関係機関からは164名の専門家、NPO・アカデミアから162名、国際機関等から98名の参加があった。会議の出資者(patronと表示されていた)はブラジル政府、カナダ漁業海洋省、フランス政府、韓国海洋水産部、アメリカ政府NOAA等にならんで日本財団が加わっていた。Sponsorとして表示されていたのは、InternationalOceanInstitute(IOI)、国連環境計画(UNEP)、WorldBankなど5機関である。
日本でもWSSDに向けて積極的取り組み、しかし海洋・沿岸域は......
ところで、わが国はこのヨハネスブルグ・サミットに向けては非常に積極的な取り組みをしている。昨年10月に東京で開かれたエコアジア会議で民間有識者会議「アジア太平洋環境開発フォーラム」を設立することとし、1月12日より2日間バンコックで同フォーラムを立ち上げた。議長は橋本龍太郎元総理で、川口環境相(当時)も出席。国連環境計画(UNEP)の事務局長らも参加という本格的なものである。また、この4月には横浜で環境省、神奈川県などの主催によりヨハネスブルグ・サミットに向けた国際環境シンポジウムも開催される運びで、中国、韓国、タイ、マレーシア、フィリピンなどからの出席のほか、NGOにも参加が呼びかけられている。
このようなわが国の取り組みは賞賛に値すると言えようが、こと海洋・沿岸域の環境と開発に関する視点からみると、いささか首を傾げざるをえない。というのは、このRio+10パリ会議には、公式の日本政府関係者の参加は全くなく、しかもわが国からの参加者は日本財団、東大海洋研究所、早大、JAMSTEC関係者、シップ・アンド・オーシャン財団のほか、現地からUNESCO・IOC勤務の日本政府職員とJETROパリ事務所関係者のみで、総勢10名に満たない状況にとどまっている。
また、そもそもメディアでは、橋本元総理が参加する上記フォーラムは報道されることがあっても、海洋・沿岸域の環境と開発問題を扱うこのRio+10パリ会議については、事前の紹介も全くといってもいいほどなされず、ましてや産官学すべての海洋関係者の間でもほとんど知られていなかったというのが実情である。さらに言えば、わが国ではAGENDA21に対する認識さえもが十分浸透していないのではなかろうか。海洋国家日本の面目と立場、取り組みは一体どこにいったのであろうかと残念でならない。
その点、上記のように政府高官を派遣してきた国々は海洋・沿岸域に関する取り組みのPRにこれ努め、なかでも韓国は海洋水産部次官がオープニングセッションの議長を務めたうえ、初日夜のパーティも主催してそのプレゼンスを最大限にアピールしたといってよい。また、最終日にはWSSD開催国を代表して南アフリカ政府の女性の環境省副大臣が締めくくりの演説を、通り一遍の挨拶ではない内容で見事に発表していたのが印象的であった。
健全なる海洋・沿岸域なくして持続的開発はなしえない
Rio+10パリ会議の議長声明によれば、「われわれは、地球表面の70%を占める海洋の持続的な開発をWSSDの中心的な課題とすべきである」としている。なぜなら、WSSDの事前AGENDAでは"海洋・沿岸域"問題は他のテーマの影に隠れたかたちになってしまっているからである。ちなみに、その10のAGENDAとは以下のものである。
- 持続的開発に向けた国際化作業の推進
- 貧困の撲滅と持続的な生活様式の確立
- 非持続的な消費と生産パターンの変革
- 持続的開発を通じた健康、衛生の向上
- エネルギー源へのアクセスとエネルギー効率
- 生態系および生物多様性の持続的管理
- 世界の淡水資源の管理
- 財政問題と技術移転
- アフリカのための持続的開発イニシアチブ
- 持続的開発のための国際的管理システムの強化
そこで、今年1月28日から2月8日までアメリカで全世界からおよそ1,000名が参加して開かれた第二回準備会合(Prep.Com.II)ほかの機会を通じて、海洋・沿岸域における持続的開発の重要性を訴え、WSSDでの主要議題になるよう積極的な活動を展開しているというわけである。(第三回Prep.Com.は3月に開催とのこと。)
「海洋・沿岸域における適切なる行動なくしてWSSDは成り立たない」し、「持続的開発と貧困の減少は、健全なる海洋・沿岸域なくしては達成できないのである」とも述べる上述の議長声明は、まさに当を得たものであるといえる。そして約40ページの議長報告本文は、海洋・沿岸域における持続的開発の重要性を訴え、その一層の推進に向けて「行動を呼びかける(ACall to Action)」と題されているのである。同報告は7つの提言(Discussion)をまとめているが、それは次のようである。
- 貧困の減少とより健全な沿岸地域社会の実現
- 国際協定の実施と遵守
- 海洋・沿岸域に関するすぐれた管理能力の構築
- 海洋・沿岸域の健全性と河川流域圏の適切な管理
- 海洋・沿岸域およびその生物多様性の保護
- 海洋環境のモニタリングとアセスメント
- 開発途上の島しょ国の諸問題
いずれも海洋・沿岸域の持続性ある開発のうえで重要かつ本質的な議論といえる。どちらかといえば途上国や島国などを念頭に置いた内容であるようにも見受けられるが、Cに掲げられている海洋・沿岸域管理能力の向上・確立は、わが日本においてもそのまま自問しなければならない課題であるといえよう。
なお、本稿執筆中に、Rio+10パリ会議にも出席していた国際海洋法の権威の一人であり、前出のIOI創立者でもあるElizabeth Mann Borgese女史が2月8日に逝去されたとの悲報が届いた。内外の国際会議で幾度も遠め近めにお見かけしていたが、わが国にも知己が多く、哀悼の意を表する気持ちが広がっているところであろう。本誌面をかりて心から冥福をお祈り申し上げて、締めくくりとしたい。(了)


※関連サイト:
第38号(2002.03.05発行)のその他の記事
- 無知が海を壊す!~海の現状と「海の環境教育」の必要性~ 海洋生物学者◆ジャック T.モイヤー
- 21世紀に向けた海洋・沿岸域の環境管理~Oceans & Coasts at Rio+10パリ会議からWSSDヨハネスブルグ・サミットへ~ (社)海洋産業研究会常務理事、東海大学・北海道東海大学講師◆中原裕幸
- 編集後記 ニューズレター編集代表 ((社)海洋産業研究会常務理事)◆中原裕幸
