Ocean Newsletter
第365号(2015.10.20発行)
- 駐日パナマ共和国特命全権大使◆Ritter DIAZ
- 富山県氷見市長◆本川祐治郎
- (株)サーフレジェンド代表取締役社長◆加藤道夫
- ニューズレター編集代表(国立研究開発法人海洋研究開発機構上席研究員/東京大学名誉教授)◆山形俊男
漁村文化をリードするまち氷見の新たな試み~まちづくりが生まれる「ひみ漁業交流館魚々座」~
[KEYWORDS] 越中式定置網/市民協働/社会命題富山県氷見市長◆本川祐治郎
富山湾に面した能登半島の付け根に位置する氷見市は、漁村文化の歴史を連綿と受け継いできた魚のまちである。
新たに誕生した地域交流施設『ひみ漁業交流館魚々座』は、世界にも有名になった越中式定置網の技術など、漁村文化を未来に伝え、目に見えない社会資本や人と人の絆を網上げていく拠点を目指している。
越中式定置網が育んだ魚のまち、氷見
富山湾に面した能登半島の付け根に位置する氷見市は、縄文時代から豊かな海の恵みを受けてきました。万葉集にも数々の歌に詠まれた海のまち、漁村文化の歴史を連綿と受け継いできた魚のまちです。そして、今日に至るまで、その漁業の中心を成してきたのが「越中式定置網」※1です。かつて富山湾では「台網」と呼ばれ、天正年間にはじまったとされる定置網が大きな変化を遂げたのは明治時代でした。宮崎県で豊漁が続いた「日高式定置網」を、氷見において、さらにさまざまな改良を加え、越中式大敷網へと発展させ、現在の越中式大型定置網に至っているのです。
こうした歴史の中で、海洋資源に優しい定置網を大切に守り育ててきた氷見の海には、40カ統以上もの定置網が仕掛けられ、日本屈指、いや、世界トップクラスの定置網の名所となっているのです。実際に、氷見の越中式定置網の技術は、JICAなどを通じて、東南アジアや中南米各国での技術指導を行い、世界にも広がっています。
ハードからソフトへ、市民協働の施設を目指して
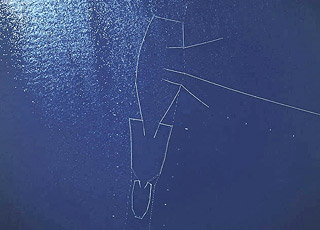
■越中式定置網

■古くからの歴史をもつ氷見の定置網
こうした歴史を持つ「漁村文化をリードするまち氷見」において、2015年4月、新たな拠点が誕生しました。地域交流施設『ひみ漁業交流館魚々座(ととざ)』です。この施設は、単なる観光施設ではなく、漁村文化を未来に伝え、目に見えない社会資本や人と人の絆を網上げていく拠点を目指しております。物見遊山の観光と訣別し、緊急ではないが重要なことに、人々が目を向けるきっかけとなるソーシャルな観光※2、自らが当事者となって食や文化、漁村の家並みや風景を守っていく"最先端の地域づくり拠点"と位置づけ、市民協働で開館に向けて準備を進めてまいりました。本川市政において常に掲げております「ハードからソフト、ソフトからハートへ」という言葉通り、魚々座は、単なるハード面の魅力だけでなく、ハートに響く人と人との意味ある交流と地域の絆作りを育むソフト面の充実を重要視しております。基本設計ができた段階から市民参加による座談会やワークショップを開催し、大学生による漁労具集めの民家訪問を行うなど常に地域と一体となったプロセスを重視して参りました。また、さまざまなセミナーやシンポジウム、そして本物の漁師さんとの語らいの場など、4月のオープン以来、数多くの市民参加型の事業を展開してまいりました。例えば、まちづくりの事例として全国的に注目を集めている島根県海士町のまちづくり会社「巡りの環」代表・阿部裕志氏をお招きしたオープニング記念セミナーには、氷見市民を含めて、全国から約80名の皆様にご参加いただきました。
アートを通して地域の絆を網上げる、ということから、市民が集まって大きな網を網んでいく『そらあみ』というアートプロジェクトには、これまで600人以上の人たちが関わり、でき上がったそらあみは、魚々座の入口に飾られ、館に彩りを添えるシンボルとなっております。魚々座の館内では、現在も、来館するお客様にそらあみづくり体験にご参加いただいており、プロジェクトの輪は、さらに広がっています。
また、パプアニューギニアの水産庁職員の皆様による視察や、ベトナム総領事のご来館など、国際的なお客様にも数多くお越し頂いております。

■魚々座の展示資料
海と魚のまち氷見の未来を見すえて
魚々座においては、社会課題を解決し永きにわたって漁村文化をリードする交流拠点という点が大きな特徴となっております。ここに関わる人たちは、ボランティアの方や、毎日立ち寄って下さるご近所の漁師さんなど地域の方が集まって新しいアイデアを持ち寄って下さいます。ですから、魚々座では、突然、魚さばきワークショップが始まることがあります。朝、漁師さんが魚を持ち込んで下さったりするので、それを調理しながらお客様と一緒に魚のさばき方や調理方法を語り合う、そんな時間が自然に生まれているのです。現代の食生活における魚食率の低下は、漁業界のみならず、社会的に見ても重要な課題となっています。魚食の啓発・普及は、魚々座の取り組むべき大切なテーマのひとつですが、このように日常的な交歓の場の中で、そのことについて自然な語り合いが生まれる、それが「魚々座的社会課題アプローチ」ではないかと考えます。
魚々座の館内には、約3,000点もの漁具や民具を触れられる状態で展示しております。介護施設のお年寄りが気分転換にお越しになった際には、民具に触れて昔の記憶を呼び覚まし、表情が明るくなり、脳の活性化にもつながったというようなことがあるそうです。これを仕組み化する回想法という認知症の改善方法について、魚々座では博物館と一緒に取り組みをはじめております。漁村文化を未来に伝えるという魚々座の目指す未来には、こうした形での社会課題の解決を支援していくということも重要な要素となっているのです。
海のまち氷見の未来に向けて、魚々座を通してさまざまなチャレンジに今後も取り組んでまいりたいと考えております。漁村文化をリードする海のまち氷見の新しい試みである魚々座に、皆様もぜひお越しください。(了)
第365号(2015.10.20発行)のその他の記事
- パナマ運河~拡張完成と新しいビジネスチャンスの到来に向けて~ 駐日パナマ共和国特命全権大使◆Ritter DIAZ
- 漁村文化をリードするまち氷見の新たな試み~まちづくりが生まれる「ひみ漁業交流館魚々座」~ 富山県氷見市長◆本川祐治郎
- 海洋スポーツと天気予報について (株)サーフレジェンド代表取締役社長◆加藤道夫
- 編集後記 ニューズレター編集代表(国立研究開発法人海洋研究開発機構上席研究員/東京大学名誉教授)◆山形俊男

