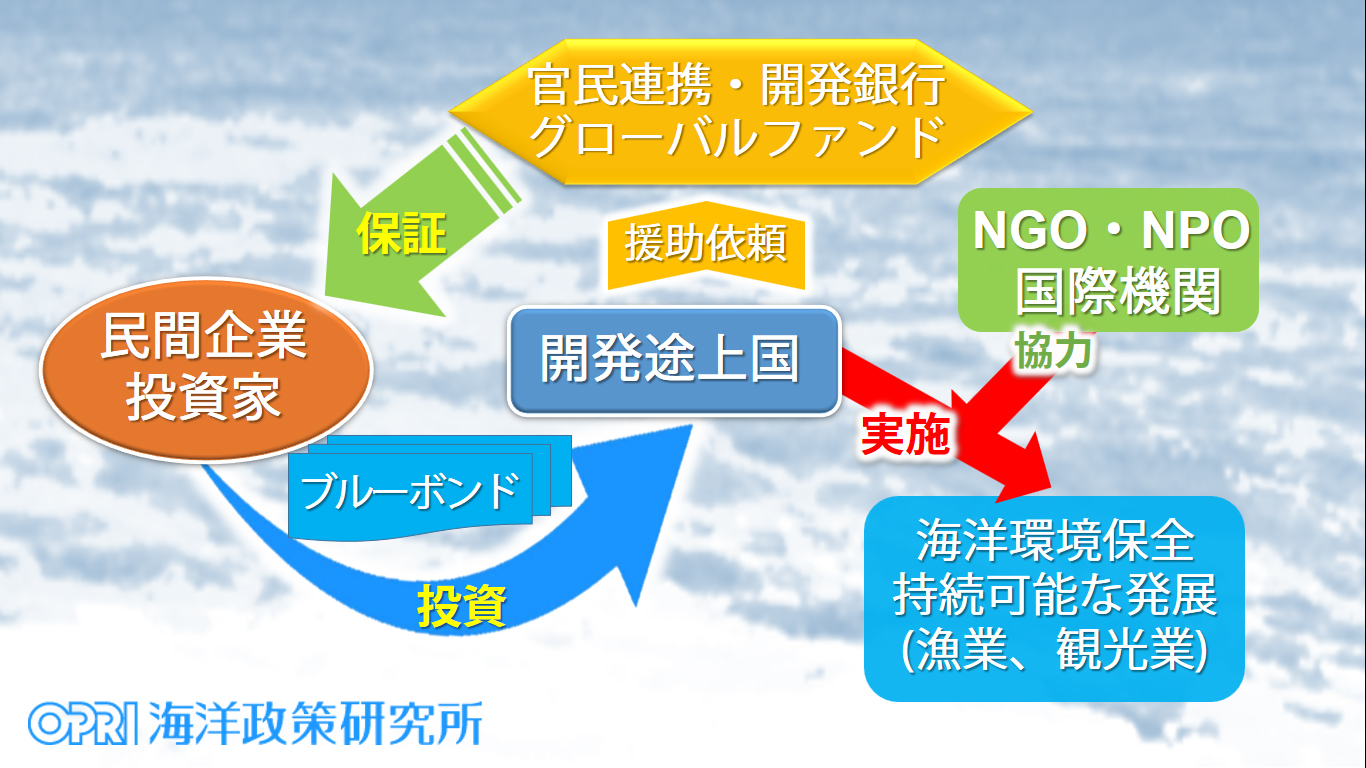グローバル戦略トレンド(GST):リチャード・ジョンソン氏を迎えて2055年までを展望する
グローバル戦略トレンド(GST)第7版をテーマに、英国国防省「Defence Futures(旧 Development, Concepts and Doctrine Centre)」チームのリチャード・ジョンソン氏が2055年までの世界を展望します。本動画では、GST 6(2019年版)からGST 7(2024年版)への主な変更点、分析の中心となる6つの主要変化要因、そして各国における受け止め方の違いを取り上げます。さらに、新たに導入された「5つの未来への道筋と将来像」について、政策立案に活用できる視点を紹介します。最後に、英国政府と日本政府の協力強化にも希望を語ります。 聞き手は笹川平和財団の西田一平太上席研究員です。