第1グループ(戦略対話・交流促進担当)
第1グループ(戦略対話・交流促進担当)
【開催報告】
総選挙後のインド情勢と日印関係の展望
登壇者発表要旨
2024.08.27
38分
主催:笹川平和財団
開催日時:2024年7月2日(火)15:00-17:15 (JST)
会場:笹川平和財団国際会議場・オンライン(Zoom)配信
開会挨拶
笹川平和財団常務理事 安達一

笹川平和財団 常務理事 安達一
笹川平和財団は、アジア地域の平和と安定、並びに、世界共通課題の解決に向けたアジア諸国との対話や協働を通じ、アジアの諸国と日本の戦略的関係の強化を図るため様々な人物交流事業、開発協力事業、調査研究事業を実施しています。当財団は、2004年から日印の国会議員の交流事業を展開して参りました。そして、当財団は継続して、独自の立ち位置・ネットワークを活用して、今年から日本・インド両国の戦略的対話・交流を促進する「日印戦略的ネットワーク強化」事業を実施します。このような両国の国民を代表するリーダー同士の人的な交流と相互理解の深化は極めて重要なものと捉えております。そして、今後はさらに裾野の広い人的交流が必要だと考え、当財団の活動を通じて、引き続きそのような両国の取り組みをサポートして参りたいと思います。
近年、インドは世界的にその存在感を高めており、人口は中国を抜いて世界第一位、インドの名目GDP(国内総生産)が2025年に日本を抜いて世界4位に浮上するとの見通しも示されています。インドはG20の議長国としての手腕を発揮し、自身を「グローバル・サウス」のリーダーたらんと標榜しています。インドの安定的な発展は世界的にも、地域安全保障の観点からも大変重要であることは言うまでもありません。
日印両国にとって、政治・経済・外交・安全保障・技術・人材等いくつもの分野で、相手国の重要性が目に見えて増大するなか、官民ともに、固定観念や印象論ではなく、事実に基づく研究成果に依拠し、相手国の現状を正確に理解し、そのうえで長期的な関係を模索することが大切だと、当財団は考えております。そのような考えに基づき、当財団では、日印両国のリーダーの対話に加えて、特に日本と歴史的なつながりが深いインド北東部において重点的に事業を行ってきました。インド北東部は、バングラデシュやミャンマー、中国と国境を接し、多様な文化と民族性を有する地域です。第2次世界大戦中に日本軍による「インパール作戦」が展開された地域でもあります。2019年に日本財団の資金援助により、マニプール州インパールの地に、インパール平和資料館が設立され、当財団はソフト面での支援を行いました。今年は、インパール作戦から80年、インパール平和資料館設立5周年にあたる年でもあります。また、当財団は、インド北東部の多様な文化やアイデンティティに光をあてそれらを記録し、共有する事業にも取り組んでまいりました。
本日のセミナーでは、先月、6月4日に開票が実施されたインドの第18期下院議員選挙の結果を踏まえ、政治・経済・外交・安全保障の各分野において日本を代表する5名のインド専門家の先生方をお招きしております。選挙前の多くの予想に反して、政権与党のインド人民党(BJP)が議席を大幅に減らしたかたちで、第三期モディ政権が発足しました。今回の選挙結果は、何を意味するのか。そこから、インドの今後、また、日本・インドの二国間関係についてどのような示唆を読み取ることができるのか。本日は、先生方のお話しを伺い、躍動するインドの実情について学び、今後の日印関係について考えて参りたいと思います。
では、最後になりますが、皆さまのご参加に改めて感謝申し上げ、開会のご挨拶とさせて頂きます。どうもありがとうございました。
近年、インドは世界的にその存在感を高めており、人口は中国を抜いて世界第一位、インドの名目GDP(国内総生産)が2025年に日本を抜いて世界4位に浮上するとの見通しも示されています。インドはG20の議長国としての手腕を発揮し、自身を「グローバル・サウス」のリーダーたらんと標榜しています。インドの安定的な発展は世界的にも、地域安全保障の観点からも大変重要であることは言うまでもありません。
日印両国にとって、政治・経済・外交・安全保障・技術・人材等いくつもの分野で、相手国の重要性が目に見えて増大するなか、官民ともに、固定観念や印象論ではなく、事実に基づく研究成果に依拠し、相手国の現状を正確に理解し、そのうえで長期的な関係を模索することが大切だと、当財団は考えております。そのような考えに基づき、当財団では、日印両国のリーダーの対話に加えて、特に日本と歴史的なつながりが深いインド北東部において重点的に事業を行ってきました。インド北東部は、バングラデシュやミャンマー、中国と国境を接し、多様な文化と民族性を有する地域です。第2次世界大戦中に日本軍による「インパール作戦」が展開された地域でもあります。2019年に日本財団の資金援助により、マニプール州インパールの地に、インパール平和資料館が設立され、当財団はソフト面での支援を行いました。今年は、インパール作戦から80年、インパール平和資料館設立5周年にあたる年でもあります。また、当財団は、インド北東部の多様な文化やアイデンティティに光をあてそれらを記録し、共有する事業にも取り組んでまいりました。
本日のセミナーでは、先月、6月4日に開票が実施されたインドの第18期下院議員選挙の結果を踏まえ、政治・経済・外交・安全保障の各分野において日本を代表する5名のインド専門家の先生方をお招きしております。選挙前の多くの予想に反して、政権与党のインド人民党(BJP)が議席を大幅に減らしたかたちで、第三期モディ政権が発足しました。今回の選挙結果は、何を意味するのか。そこから、インドの今後、また、日本・インドの二国間関係についてどのような示唆を読み取ることができるのか。本日は、先生方のお話しを伺い、躍動するインドの実情について学び、今後の日印関係について考えて参りたいと思います。
では、最後になりますが、皆さまのご参加に改めて感謝申し上げ、開会のご挨拶とさせて頂きます。どうもありがとうございました。
総選挙後のインド情勢と日印関係の展望
岐阜女子大学客員教授/インド政治外交史専攻 堀本武功氏

堀本武功氏
Ⅰ.今回の総選挙結果
インドの第18総選挙は、2024年6月4日に一斉開票され、インド人民党(BJP)を中心とする与党連合(国民民主同盟)が過半数を確保し、2014年と2019年に引き続いて三期連続して国政与党となった。
しかし、人民党は240議席で単独過半数(272議席)を得られず、与党連合全体で過半数を維持したに止まり、辛うじて3期で与党連合を継続することができた。与党連合では、南部アーンドラ・プラデーシュ州のテルグ・デサム党(18議席)と北部ビハール州のジャナタ党12議席の支持が不可欠となった。新内閣の主要閣僚(内務、財務、外務、防衛)は、いずれも留任した。インドは「連合政権時代」に回帰したようにも見える。
これに対して国民会議派(会議派)を中核とする野党連合は議席数を2倍以上に拡大させた。会議派は大きく躍進した。会議派のラフル・ガンディーは、公的な「野党リーダー」(leader of opposition)の地位確保に成功した。
インド識者の多くは、選挙結果に安堵しているように見受けられる。ノーベル受賞者のアマルティア・センは選挙結果について、「インドが(人民党の主張する)ヒンドゥー国家ではないことを証明した」と指摘し[1]、メータも「インドの有権者がどのようにモディを抑制し、インドの民主主義を救出したことでインドの危機から一歩後退した」とコメントした[2]。
Ⅱ.総選挙後のインド情勢
1.総選挙結果の背景
インド人民党は後退したが、同党が過去10年間に推進した「ヒンドゥー至上主義」が必ずしも否定されたことを意味しない。2024年1月に盛大に執り行われた北部・アヨーディヤーにおけるラーム寺院建立は、ヒンドゥー教徒が8割を占めるインド人には歓迎されたのは事実である。
しかし、インド国民にとって最大関心事であるインフレ、雇用、貧困の状況改善が期待したほどには、進展しなかった[3]。国際NGOによれば、インドでは、全人口の上位1%の富裕層が国内資産の40%以上、人口の半分に相当する約7億人が国内資産の3%を保有しているに過ぎないという[4]。インドの農村問題専門家によれば、過去20年間にインドの農民の自殺人数が31万人に及ぶ[5]。
2.インドの経済大国化と経済構造
インフレや雇用と密接不可分の関係にあるのがインド経済である。今やインドは世界最大の人口を擁している。インド経済の成長率は、2004〜2014に7.7%の成長率、その後の10年間が5.7%と推計されている。2027年には、GDP世界第3位に到達すると予想されている。
しかし、経済規模が拡大しても、膨大な約14億の人口を抱えるインドでは、経済成長の果実を均霑的に配分できていない。世界の1人当たり名目GDP 国別ランキング(IMF 2023)によれば、インドは144位の2500米㌦に留まっている。中国は、74位の12,670米㌦である。
経済発展を実現できてはいても、一人当たりの経済状況が低位に留まっているさまざまな要因があるが、なんと言っても、製造業が振るわない点が大きいだろう。モディ首相は2014年の首相就任時、「Make in India」を掲げ、GDPに占める製造業の比率を25%まで引き上げるとしたが、実現できなかった。世銀データ(2022年)の比率は13.3%で、中国(27.7%)よりもはるかに低い。人口増に雇用創出が追いつけない。
その結果、依然として、農業の比率が高い状態にある。GDPに占める農業比率は独立時に50%だったが、2011年には約3分の1まで退行した。一方で農業人口は1951年の69.7%から2011年の54.6%に減少しているが、少ない農業所得パイを多くの農民が奪い合う状態になっている。毎年誕生する新しい就業者には、毎年、1000万人〜1200万人の雇用が必要と言われる。農業は、依然として、就業調整機能を果たしている。
日本がかって経験した高度経済成長は、人口ボーナスの結果とも言われる。一般的には、生産年齢人口(15~64歳)に対する従属人口(14歳以下の年少人口と65歳以上の老年人口の合計)の比率が低下すると、経済成長を促すと言われる。インドの人口ボーナス期は、2040年には、終了に向かうととも言われる[6]。
3.「縁故資本主義」が構造的な要因か
英国エコノミスト誌[7]は、縁故資本主義(Crony Capitalism)の観点からインド経済を分析している。縁故資本主義は資本主義の根幹となる市場経済による効率的な資源配分、競争力の向上、技術革新を阻害する一方では、特定階層による経済支配を固定化することで経済的格差を助長する、政府官僚、政治家、大企業、富農との癒着による経済支配を意味する。
同誌は、インドが世界43カ国中、10位にランク付けし、インド経済が発展するが、満遍なく、全国民が発展を享受しにくいという見方を示しているが、インド経済が今後も発展することの見方を否定しているわけではない。
4.インドの強権的な権威主義化はどうなるか
インドの宗派別人口は、ヒンドゥー教徒が80%、ムスリム(イスラーム教徒)が約15%である。ムスリムはインドのマイノリティ宗派というが約2億人という大規模である。
宗派比率から、インドが独立時に施行した憲法は、政教分離主義(世俗主義)、単純化すれば、政治が宗教に係わらないと言う理念に立ち、「世界最大の民主主義国」を誇ってきた。
会議派や憲法がこの考え方を打ち出したのは、インドでは、宗派に加え、人種、言語など極めて多様性に富む以上、一元的な価値をもって新国家を統治できないと考えたからである。そこで打ち出したのが「多様性の中の統一」である。むろん、統一に重点が置かれている。
一方、1925年に創設された民族義勇団は、ムガル帝国・英国によって虐げられたインド、多数派のヒンドゥー教徒を抱えるインドはヒンドゥー国家となるべきだという発想から活動を開始した。1951年には民族義勇団の政治部とも言うべき大衆連盟、続いて1980年にインド人民党(BJP)を結成した。2014年からは国政与党となっている。BJPがヒンドゥー国家化を進めれば進めるほど、インドが権威主義国化しているとの見方が次例のように噴出している。
今後のBJPを考えて見ると、なんらかの内部対立が浮上する可能性もある。
①2014年に国政与党になってからは、BJPと母体だった民族義勇団との力関係が徐々にBJP>民族義勇団となってきたが、今回の総選挙で退行したため、民族義勇団が両者間の対等な関係性を要求し、両者間の緊張が表面化する可能性がある。
②モディ首相の求心力低下に伴う政策決定のスピード鈍化や与党連合内における対立が表面化する可能性もあろう。
③ポピュリスト的な政策運営も選択肢の一つとなる。大衆迎合的な財政支援に加え、与党連合に加盟する政党のムスリム政策との調整も必要なろう。
Ⅲ.戦略的自律外交(実利外交)の方向性
インドは、2010年代から外交理念として戦略的自律性を掲げているが、実態的には実利外交と見て間違いない。実利面から見れば、かつての非同盟と相当程度まで共通するだろう。
モディ政権は独立から100年目の2047年には、先進国となるとの考え方を持っている。言いかえれば、G3(世界3大国)である。しかし、米中並みのランクにインドが到達するのは容易なことではない。
名目GDPの上位5カ国(IMF 2023)/兆ドル
Ⅳ.どんな行方になりそうか。
インドが経済大国化する可能性は大きい。政権与党がインド人民党であるか否かに関わりなく、インドが国内外の政策でどのように自由と平等とのバランスを取るのか、対ムスリム政策をどのように進めるかが焦点になるだろう。
インドが注視し続ける国は中国であるが、米国(特にトランプ政権が誕生した場合)の出方も大きなカギを握る。日印関係は、今後も経済要因と中国要因の関係で継続することは間違いない。しかし、インドは、カースト制に見られるように、上下観で相手(国)を認識し、行動する傾向が顕在的にも潜在的にも存在する。インドがさらに大国化した場合、日印関係は中国要因がある以上、存続するのは間違いないが、現在のモードのまま存続するとは思えない。決めるのは、インドであるが、日本も相応の対応を考慮しておく必要もある。
おそらく、今後のインドは、民主主義による経済発展がどのような方向性をとるかが大きな要因となろう。歴史的見れば、諸々は「時計の振り子」のように左右に振れながら進むことになろう。
インドの第18総選挙は、2024年6月4日に一斉開票され、インド人民党(BJP)を中心とする与党連合(国民民主同盟)が過半数を確保し、2014年と2019年に引き続いて三期連続して国政与党となった。
しかし、人民党は240議席で単独過半数(272議席)を得られず、与党連合全体で過半数を維持したに止まり、辛うじて3期で与党連合を継続することができた。与党連合では、南部アーンドラ・プラデーシュ州のテルグ・デサム党(18議席)と北部ビハール州のジャナタ党12議席の支持が不可欠となった。新内閣の主要閣僚(内務、財務、外務、防衛)は、いずれも留任した。インドは「連合政権時代」に回帰したようにも見える。
これに対して国民会議派(会議派)を中核とする野党連合は議席数を2倍以上に拡大させた。会議派は大きく躍進した。会議派のラフル・ガンディーは、公的な「野党リーダー」(leader of opposition)の地位確保に成功した。
インド識者の多くは、選挙結果に安堵しているように見受けられる。ノーベル受賞者のアマルティア・センは選挙結果について、「インドが(人民党の主張する)ヒンドゥー国家ではないことを証明した」と指摘し[1]、メータも「インドの有権者がどのようにモディを抑制し、インドの民主主義を救出したことでインドの危機から一歩後退した」とコメントした[2]。
Ⅱ.総選挙後のインド情勢
1.総選挙結果の背景
インド人民党は後退したが、同党が過去10年間に推進した「ヒンドゥー至上主義」が必ずしも否定されたことを意味しない。2024年1月に盛大に執り行われた北部・アヨーディヤーにおけるラーム寺院建立は、ヒンドゥー教徒が8割を占めるインド人には歓迎されたのは事実である。
しかし、インド国民にとって最大関心事であるインフレ、雇用、貧困の状況改善が期待したほどには、進展しなかった[3]。国際NGOによれば、インドでは、全人口の上位1%の富裕層が国内資産の40%以上、人口の半分に相当する約7億人が国内資産の3%を保有しているに過ぎないという[4]。インドの農村問題専門家によれば、過去20年間にインドの農民の自殺人数が31万人に及ぶ[5]。
2.インドの経済大国化と経済構造
インフレや雇用と密接不可分の関係にあるのがインド経済である。今やインドは世界最大の人口を擁している。インド経済の成長率は、2004〜2014に7.7%の成長率、その後の10年間が5.7%と推計されている。2027年には、GDP世界第3位に到達すると予想されている。
しかし、経済規模が拡大しても、膨大な約14億の人口を抱えるインドでは、経済成長の果実を均霑的に配分できていない。世界の1人当たり名目GDP 国別ランキング(IMF 2023)によれば、インドは144位の2500米㌦に留まっている。中国は、74位の12,670米㌦である。
経済発展を実現できてはいても、一人当たりの経済状況が低位に留まっているさまざまな要因があるが、なんと言っても、製造業が振るわない点が大きいだろう。モディ首相は2014年の首相就任時、「Make in India」を掲げ、GDPに占める製造業の比率を25%まで引き上げるとしたが、実現できなかった。世銀データ(2022年)の比率は13.3%で、中国(27.7%)よりもはるかに低い。人口増に雇用創出が追いつけない。
その結果、依然として、農業の比率が高い状態にある。GDPに占める農業比率は独立時に50%だったが、2011年には約3分の1まで退行した。一方で農業人口は1951年の69.7%から2011年の54.6%に減少しているが、少ない農業所得パイを多くの農民が奪い合う状態になっている。毎年誕生する新しい就業者には、毎年、1000万人〜1200万人の雇用が必要と言われる。農業は、依然として、就業調整機能を果たしている。
日本がかって経験した高度経済成長は、人口ボーナスの結果とも言われる。一般的には、生産年齢人口(15~64歳)に対する従属人口(14歳以下の年少人口と65歳以上の老年人口の合計)の比率が低下すると、経済成長を促すと言われる。インドの人口ボーナス期は、2040年には、終了に向かうととも言われる[6]。
3.「縁故資本主義」が構造的な要因か
英国エコノミスト誌[7]は、縁故資本主義(Crony Capitalism)の観点からインド経済を分析している。縁故資本主義は資本主義の根幹となる市場経済による効率的な資源配分、競争力の向上、技術革新を阻害する一方では、特定階層による経済支配を固定化することで経済的格差を助長する、政府官僚、政治家、大企業、富農との癒着による経済支配を意味する。
同誌は、インドが世界43カ国中、10位にランク付けし、インド経済が発展するが、満遍なく、全国民が発展を享受しにくいという見方を示しているが、インド経済が今後も発展することの見方を否定しているわけではない。
4.インドの強権的な権威主義化はどうなるか
インドの宗派別人口は、ヒンドゥー教徒が80%、ムスリム(イスラーム教徒)が約15%である。ムスリムはインドのマイノリティ宗派というが約2億人という大規模である。
宗派比率から、インドが独立時に施行した憲法は、政教分離主義(世俗主義)、単純化すれば、政治が宗教に係わらないと言う理念に立ち、「世界最大の民主主義国」を誇ってきた。
会議派や憲法がこの考え方を打ち出したのは、インドでは、宗派に加え、人種、言語など極めて多様性に富む以上、一元的な価値をもって新国家を統治できないと考えたからである。そこで打ち出したのが「多様性の中の統一」である。むろん、統一に重点が置かれている。
一方、1925年に創設された民族義勇団は、ムガル帝国・英国によって虐げられたインド、多数派のヒンドゥー教徒を抱えるインドはヒンドゥー国家となるべきだという発想から活動を開始した。1951年には民族義勇団の政治部とも言うべき大衆連盟、続いて1980年にインド人民党(BJP)を結成した。2014年からは国政与党となっている。BJPがヒンドゥー国家化を進めれば進めるほど、インドが権威主義国化しているとの見方が次例のように噴出している。
| ―米フリーダムハウス『世界自由度報告』(2021年):従来の自由から一部自由へ。 ―The Economist(EIU):民主主義度を2014年の7.92→2020年に6.61に引き下げ。 ―独立機関V-Demo(Sweden):2022年報告で政治状況を「選挙独裁」に分類。 ―Index RSFによる「報道の自由」(180カ国)では、2019年が140位(日本67位) ☞2023年が161位(日本68位) |
今後のBJPを考えて見ると、なんらかの内部対立が浮上する可能性もある。
①2014年に国政与党になってからは、BJPと母体だった民族義勇団との力関係が徐々にBJP>民族義勇団となってきたが、今回の総選挙で退行したため、民族義勇団が両者間の対等な関係性を要求し、両者間の緊張が表面化する可能性がある。
②モディ首相の求心力低下に伴う政策決定のスピード鈍化や与党連合内における対立が表面化する可能性もあろう。
③ポピュリスト的な政策運営も選択肢の一つとなる。大衆迎合的な財政支援に加え、与党連合に加盟する政党のムスリム政策との調整も必要なろう。
Ⅲ.戦略的自律外交(実利外交)の方向性
インドは、2010年代から外交理念として戦略的自律性を掲げているが、実態的には実利外交と見て間違いない。実利面から見れば、かつての非同盟と相当程度まで共通するだろう。
モディ政権は独立から100年目の2047年には、先進国となるとの考え方を持っている。言いかえれば、G3(世界3大国)である。しかし、米中並みのランクにインドが到達するのは容易なことではない。
名目GDPの上位5カ国(IMF 2023)/兆ドル
| 1 | 米国 | 27.4 |
| 2 | 中国 | 17.7 |
| 3 | ドイツ | 4.5 |
| 4 | 日本 | 4.2 |
| 5 | インド | 3.7 |
Ⅳ.どんな行方になりそうか。
インドが経済大国化する可能性は大きい。政権与党がインド人民党であるか否かに関わりなく、インドが国内外の政策でどのように自由と平等とのバランスを取るのか、対ムスリム政策をどのように進めるかが焦点になるだろう。
インドが注視し続ける国は中国であるが、米国(特にトランプ政権が誕生した場合)の出方も大きなカギを握る。日印関係は、今後も経済要因と中国要因の関係で継続することは間違いない。しかし、インドは、カースト制に見られるように、上下観で相手(国)を認識し、行動する傾向が顕在的にも潜在的にも存在する。インドがさらに大国化した場合、日印関係は中国要因がある以上、存続するのは間違いないが、現在のモードのまま存続するとは思えない。決めるのは、インドであるが、日本も相応の対応を考慮しておく必要もある。
おそらく、今後のインドは、民主主義による経済発展がどのような方向性をとるかが大きな要因となろう。歴史的見れば、諸々は「時計の振り子」のように左右に振れながら進むことになろう。
[1] The Economic Times, Jun 27, 2024.
[2] Pratap Bhanu Mehta, “India Steps Back From the Brink How Indian Voters Constrained Modi—and Saved Their Democracy, Foreign Affairs, June 14, 2024.
[3] India Today誌(24年2月実施のMood of Nation)。Mood of the Nation 2024 Latest News, Photos, Videos and Analysis - Indiatoday
[4] 国際NGOオックスファム(2023年1月24日)公表。
[5] 「サイナート×堀本対談」『中央公論』2024年1月。
[6] EastAsiaForum, May 11, 2024。
[7] The Economist, May 2,2023.
経済大国インドの機会と挑戦
神戸大学経済経営研究所 佐藤隆広氏

佐藤隆広氏
(インド経済の「機会」と「挑戦」)
インド経済の「機会」が注目される背景には、主要国の中で際立って高い水準で推移してきた経済成長率があり、2027年までに、インドは、日本、ドイツをGDPで抜いて世界第三の経済大国になる見通しである。
次いで、過去10年間でのモディ政権下で実施された経済政策を振り返りながら、インド経済の「挑戦」的課題を評価してみたい。2014年5月の第一次モディ政権発足当時、インドは、景気後退、インフレ、国際収支赤字を同時に抱え、1991年経済自由化開始以来といってよいほどの危機的状況を迎えていた。モディ政権が政権発足からわずか二年でスタグフレーションを解決したことは、国際的にも際立った素晴らしい成果と評価できる。その後の破産・倒産法制度(2016年)、物品サービス税(GST)導入(2017年)、エア・インディアの民営化(2022年)などは、経済改革の取り組みとして高く評価できるものであるが、残念ながら、これら、経済改革路線の成功事例は数少ない。一方、準備もなく突然断行された高額紙幣廃止(2016年)や世界最強のロックダウン(2020年)は、経済合理性では到底説明できない経済政策であった。さらに、2015年以降、基本関税の引き上げによる保護貿易政策が顕著になり、しかも、ハイテク産業・技術/知識集約的産業ではなく、競争力のないローテク労働集約的産業の保護が指向された。日・中・韓・ASEAN・オーストラリア・ニュージーランドからなる包括的経済連携RCEPからの突然の離脱はその典型例といえる。また、土地収用法の再改正も実現されず、せっかく議会を通過した四つの労働法典も施行されずに今に至っている。また、農業近代化のために施行した農業関連三法も、激しい反対にあって最終的には廃止された。モディ首相は、権威主義の独裁者と評価されることが多いが、経済的にみると実は経済改革に対する抵抗勢力に屈服を強いられる10年間だったと総括できる。
(モディ政権下インド経済の実績評価)
インド経済の過去10年の実績を客観的に評価するために、先進国や中国ではなく、インドとよく似た経済状況の国との比較を通して考えてみたい。そこで、同じ元英領インドで、かつては世界の最貧国でもあったバングラデシュと比較してみると、実は、一人当たりGDPは、モディ政権下の10年間で、インドはバングラデシュに逆転されてしまった。バングラデシュ経済の成功の好例はアパレル産業で、同国は、非常にレベルの高い縫製技術を養い、輸出志向でグローバル・バリューチェーンに参入することで、中国に次ぐ世界第二位のアパレル製品輸出国へと成長した。一方で、インドは、ローテクの労働集約産業を保護する「後ろ向き」な保護政策を採用した。この違いが、インドとバングラデシュの「差」をうみだしたと考えられる。
(選挙からの考察)
失業、インフレ、貧困の三重苦をまったく解決できなかったことが、モディ政権が選挙で大勝できなかった要因であり、これらの問題への対処が第三期モディ政権にとっての挑戦的課題となる。若年層失業率は、世界最強のロックダウン当時、約35%まで悪化した。直近では、2019年の第二次モディ政権発足時よりも約4ポイント改善しているが、それでも長期間高い失業率が延々続いてきた状況であり、失業問題解決のための雇用創出は非常に深刻な課題と評価せざるを得ない。次に、インフレに関しては、インド政治の有名な経験則として、「選挙前年のインフレ率が10%を超えると現職政権が敗北する」というものがある。昨年のインフレ率は8%と、10%には届かないながら高水準であり、これもモディ政権苦戦の原因となった。さらに就業者全体で大きな割合を占める農業労働者の実質賃金を見ると、この5年間で下落しており、つまり労働者の貧困が悪化していることが読み取れる。これらの課題解決のために、まず、後ろ向きの保護貿易主義から、経済改革路線に復帰することが必須である。試金石になるのは、施行を待つだけの状態になっている労働法典を速やかに施行できるかどうかである。さらに、農産物物流の近代化により物流過程で生じている食品ロスを低減することでインフレを抑制することや、スピーディなインフラ開発のために土地収用法を改正すること、セーフティネットの整備などが、課題解決のために必要な施策になる。
(インド経済の見通し)
仮に第三次モディ政権が経済合理性に欠ける政策をとったとしても、年率6%程度の経済成長は続いていくと考えられる。注視すべき重要ポイントは労働法典の施行であり、野党が反対している状況を踏まえると政治争点になる可能性が高いものの、本法典は、植民地時代から蓄積してきた44もの労働法を四つの法典にまとめ、現代的な労働法制を実現する非常に意義深いものである。内容としては、雇用の柔軟化、労働者の社会保障への包摂などが含まれている。インドに進出している日本企業においても、本労働法典の施行をめぐる動向について注視し、内容を勉強することが望ましい。
(インド経済における日本企業の役割)
日本企業がインドで果たしている役割を見るためには日印間の貿易だけを見ても全貌は掴めない。インドに進出している日本企業の経済活動を見る必要があり、実は、後者の経済規模は前者の五、六倍の水準に達している。さらにインドに進出している日本企業は約1兆円もの第三国向け輸出を生んでおり、インド進出日本企業によるグローバルな生産活動が、インドのグローバル・バリューチェーン参入を大きくサポートしているという視点が重要であると考える。
インド経済の「機会」が注目される背景には、主要国の中で際立って高い水準で推移してきた経済成長率があり、2027年までに、インドは、日本、ドイツをGDPで抜いて世界第三の経済大国になる見通しである。
次いで、過去10年間でのモディ政権下で実施された経済政策を振り返りながら、インド経済の「挑戦」的課題を評価してみたい。2014年5月の第一次モディ政権発足当時、インドは、景気後退、インフレ、国際収支赤字を同時に抱え、1991年経済自由化開始以来といってよいほどの危機的状況を迎えていた。モディ政権が政権発足からわずか二年でスタグフレーションを解決したことは、国際的にも際立った素晴らしい成果と評価できる。その後の破産・倒産法制度(2016年)、物品サービス税(GST)導入(2017年)、エア・インディアの民営化(2022年)などは、経済改革の取り組みとして高く評価できるものであるが、残念ながら、これら、経済改革路線の成功事例は数少ない。一方、準備もなく突然断行された高額紙幣廃止(2016年)や世界最強のロックダウン(2020年)は、経済合理性では到底説明できない経済政策であった。さらに、2015年以降、基本関税の引き上げによる保護貿易政策が顕著になり、しかも、ハイテク産業・技術/知識集約的産業ではなく、競争力のないローテク労働集約的産業の保護が指向された。日・中・韓・ASEAN・オーストラリア・ニュージーランドからなる包括的経済連携RCEPからの突然の離脱はその典型例といえる。また、土地収用法の再改正も実現されず、せっかく議会を通過した四つの労働法典も施行されずに今に至っている。また、農業近代化のために施行した農業関連三法も、激しい反対にあって最終的には廃止された。モディ首相は、権威主義の独裁者と評価されることが多いが、経済的にみると実は経済改革に対する抵抗勢力に屈服を強いられる10年間だったと総括できる。
(モディ政権下インド経済の実績評価)
インド経済の過去10年の実績を客観的に評価するために、先進国や中国ではなく、インドとよく似た経済状況の国との比較を通して考えてみたい。そこで、同じ元英領インドで、かつては世界の最貧国でもあったバングラデシュと比較してみると、実は、一人当たりGDPは、モディ政権下の10年間で、インドはバングラデシュに逆転されてしまった。バングラデシュ経済の成功の好例はアパレル産業で、同国は、非常にレベルの高い縫製技術を養い、輸出志向でグローバル・バリューチェーンに参入することで、中国に次ぐ世界第二位のアパレル製品輸出国へと成長した。一方で、インドは、ローテクの労働集約産業を保護する「後ろ向き」な保護政策を採用した。この違いが、インドとバングラデシュの「差」をうみだしたと考えられる。
(選挙からの考察)
失業、インフレ、貧困の三重苦をまったく解決できなかったことが、モディ政権が選挙で大勝できなかった要因であり、これらの問題への対処が第三期モディ政権にとっての挑戦的課題となる。若年層失業率は、世界最強のロックダウン当時、約35%まで悪化した。直近では、2019年の第二次モディ政権発足時よりも約4ポイント改善しているが、それでも長期間高い失業率が延々続いてきた状況であり、失業問題解決のための雇用創出は非常に深刻な課題と評価せざるを得ない。次に、インフレに関しては、インド政治の有名な経験則として、「選挙前年のインフレ率が10%を超えると現職政権が敗北する」というものがある。昨年のインフレ率は8%と、10%には届かないながら高水準であり、これもモディ政権苦戦の原因となった。さらに就業者全体で大きな割合を占める農業労働者の実質賃金を見ると、この5年間で下落しており、つまり労働者の貧困が悪化していることが読み取れる。これらの課題解決のために、まず、後ろ向きの保護貿易主義から、経済改革路線に復帰することが必須である。試金石になるのは、施行を待つだけの状態になっている労働法典を速やかに施行できるかどうかである。さらに、農産物物流の近代化により物流過程で生じている食品ロスを低減することでインフレを抑制することや、スピーディなインフラ開発のために土地収用法を改正すること、セーフティネットの整備などが、課題解決のために必要な施策になる。
(インド経済の見通し)
仮に第三次モディ政権が経済合理性に欠ける政策をとったとしても、年率6%程度の経済成長は続いていくと考えられる。注視すべき重要ポイントは労働法典の施行であり、野党が反対している状況を踏まえると政治争点になる可能性が高いものの、本法典は、植民地時代から蓄積してきた44もの労働法を四つの法典にまとめ、現代的な労働法制を実現する非常に意義深いものである。内容としては、雇用の柔軟化、労働者の社会保障への包摂などが含まれている。インドに進出している日本企業においても、本労働法典の施行をめぐる動向について注視し、内容を勉強することが望ましい。
(インド経済における日本企業の役割)
日本企業がインドで果たしている役割を見るためには日印間の貿易だけを見ても全貌は掴めない。インドに進出している日本企業の経済活動を見る必要があり、実は、後者の経済規模は前者の五、六倍の水準に達している。さらにインドに進出している日本企業は約1兆円もの第三国向け輸出を生んでおり、インド進出日本企業によるグローバルな生産活動が、インドのグローバル・バリューチェーン参入を大きくサポートしているという視点が重要であると考える。
総選挙後のインドの外交・防衛政策
防衛研究所地域研究部アジア・アフリカ研究室主任研究官 伊豆山真理氏

伊豆山真理氏
はじめに、今回の総選挙の意味をまとめるならば、第1に一定の社会層が政権への不満を表明したものであり、選挙民主主義が機能していると評価できる。第2に、BJPの一党優位の時代が終わり、州レベルでのカースト集団間政治を基盤とした連合政治への回帰と位置付けたい。
BJPの後退要因を構造的要因と戦術的要因に分けてみていく。構造的要因として、モディ政権の「ワン・ネーション」ナラティブが、多様なコミュニティからなるインドの社会構造と不適合になりつつあることをあげたい。モディ政権は、「ワン・ネーション(一国家)」を冠した国家一律の政策を推進してきた。「一国家一税制」、「一国家一食糧配給カード」、「一国家一選挙」などである。
モディ首相は2024年1月末、アヨーディヤに建立したラーマ寺院の祝典を行い、ヒンドゥー・ナショナリズムの高揚を得票につなげることを企図したが、ラーマ寺院は挙国一致の物語にはなれなかった。実際ラーマ寺院が存するファイザバード選挙区で、BJPの現職議員が落選している。
「ワン・ネーション」ナラティブは、なぜ機能しなかったのか。事前の予想では、ヒンドゥー・ナショナリズムに賛同しない有権者であっても、民主主義、セキュラリズムといった「価値」よりも「日々の暮らし」に直結する経済発展の実績を重視して、BJPに投票するだろうとみられていた。しかし、「ヒンディー・ベルト」と言われる北部の要衝地域で、モディ政権下の経済発展の恩恵を受けられない層が野党に投票したことが明らかとなった。農民がその代表である。また、北部の指定カースト(SC)、その他後進階層(OBC)は、BJPが議会で多数派をとって憲法改正を企図していると懸念した。憲法が保障する優遇措置が廃止されることに対する危惧である。
野党連合の選挙戦術もBJP後退の要因である。モディ政権による複数の野党指導者の拘束は、野党を結束させた。特にウッタル・プラデーシュ州では、会議派と社会主義党(SP)との候補者調整が功を奏し、社会主義党(SP)がBJPを凌ぐ37議席を獲得して第1党となった。BJPは議席数を62から33へと大幅に減らした。また、野党側はSNSを有効に活用した。SNS上に拡散する政権への批判的意見をくみ取りながら「憲法尊重」というカウンター・ナラティブを形成し、発信することに成功したのである。
こうした選挙結果を受けて、モディ首相のBJPは、連合政党との協議に加え、強くなった野党と対峙する必要に迫られることになるため、第3次モディ政権の政策、政権運営は、これまでとは異なるものとなろう。しかし外交・防衛政策については継続性が予測される。その理由は、主要閣僚が再任されていること、連合政党であるテルグ・デーサム党(TDP)とジャナター・ダル統一派(JD(U))の外交・防衛政策への関心は限定的であること、国際社会におけるインドの地位向上は、有権者にも支持されていることである。内務、外務、財務、防衛の4大臣は全て留任である。この4大臣は、軍の海外派遣や防衛装備調達などの重要な決定を行う「内閣安全保障委員会」のメンバーである。また、中国との国境交渉を任されるドーバル国家安全保障顧問(NSA)も再任されている。基本的には、これまでと同様、大国化あるいは国際的地位の向上と、戦略的自立あるいはマルチ連携とが、外交・防衛政策の2本柱となろう。
外交・防衛政策で野党による争点化があり得る分野としては、以下が考えられる。第1に、インドの人権問題が外交に波及する分野である。会議派の選挙マニュフェストでは、BJPによる市民的自由の抑圧が、インドの国際的威信を傷つけていると述べる。第2は、対中政策である。会議派は、2020年6月のガルワン危機における「情報の失敗」、中国に対する政府の不必要な強硬姿勢などを批判している。しかし会議派も総合的な対中国政策を提示できているわけではない。第3は、軍の人事政策である。モディ政権が2022年に導入した任期付採用「アグニパト(Agnipath)」制度は、軍への就職が多い各地で若者の抗議行動につながり、選挙では不利に作用した。会議派だけでなく連合政党であるジャナター・ダル統一派(JD(U))も「アグニパト」撤回を主張しており、モディ政権は軍人の給与・年金支出の抑制か、若者への雇用提供かという困難な課題を抱える。この問題は軍の人事政策全般に及び、国防機構改革論議を湧き起こす可能性をもつ。
BJPの後退要因を構造的要因と戦術的要因に分けてみていく。構造的要因として、モディ政権の「ワン・ネーション」ナラティブが、多様なコミュニティからなるインドの社会構造と不適合になりつつあることをあげたい。モディ政権は、「ワン・ネーション(一国家)」を冠した国家一律の政策を推進してきた。「一国家一税制」、「一国家一食糧配給カード」、「一国家一選挙」などである。
モディ首相は2024年1月末、アヨーディヤに建立したラーマ寺院の祝典を行い、ヒンドゥー・ナショナリズムの高揚を得票につなげることを企図したが、ラーマ寺院は挙国一致の物語にはなれなかった。実際ラーマ寺院が存するファイザバード選挙区で、BJPの現職議員が落選している。
「ワン・ネーション」ナラティブは、なぜ機能しなかったのか。事前の予想では、ヒンドゥー・ナショナリズムに賛同しない有権者であっても、民主主義、セキュラリズムといった「価値」よりも「日々の暮らし」に直結する経済発展の実績を重視して、BJPに投票するだろうとみられていた。しかし、「ヒンディー・ベルト」と言われる北部の要衝地域で、モディ政権下の経済発展の恩恵を受けられない層が野党に投票したことが明らかとなった。農民がその代表である。また、北部の指定カースト(SC)、その他後進階層(OBC)は、BJPが議会で多数派をとって憲法改正を企図していると懸念した。憲法が保障する優遇措置が廃止されることに対する危惧である。
野党連合の選挙戦術もBJP後退の要因である。モディ政権による複数の野党指導者の拘束は、野党を結束させた。特にウッタル・プラデーシュ州では、会議派と社会主義党(SP)との候補者調整が功を奏し、社会主義党(SP)がBJPを凌ぐ37議席を獲得して第1党となった。BJPは議席数を62から33へと大幅に減らした。また、野党側はSNSを有効に活用した。SNS上に拡散する政権への批判的意見をくみ取りながら「憲法尊重」というカウンター・ナラティブを形成し、発信することに成功したのである。
こうした選挙結果を受けて、モディ首相のBJPは、連合政党との協議に加え、強くなった野党と対峙する必要に迫られることになるため、第3次モディ政権の政策、政権運営は、これまでとは異なるものとなろう。しかし外交・防衛政策については継続性が予測される。その理由は、主要閣僚が再任されていること、連合政党であるテルグ・デーサム党(TDP)とジャナター・ダル統一派(JD(U))の外交・防衛政策への関心は限定的であること、国際社会におけるインドの地位向上は、有権者にも支持されていることである。内務、外務、財務、防衛の4大臣は全て留任である。この4大臣は、軍の海外派遣や防衛装備調達などの重要な決定を行う「内閣安全保障委員会」のメンバーである。また、中国との国境交渉を任されるドーバル国家安全保障顧問(NSA)も再任されている。基本的には、これまでと同様、大国化あるいは国際的地位の向上と、戦略的自立あるいはマルチ連携とが、外交・防衛政策の2本柱となろう。
外交・防衛政策で野党による争点化があり得る分野としては、以下が考えられる。第1に、インドの人権問題が外交に波及する分野である。会議派の選挙マニュフェストでは、BJPによる市民的自由の抑圧が、インドの国際的威信を傷つけていると述べる。第2は、対中政策である。会議派は、2020年6月のガルワン危機における「情報の失敗」、中国に対する政府の不必要な強硬姿勢などを批判している。しかし会議派も総合的な対中国政策を提示できているわけではない。第3は、軍の人事政策である。モディ政権が2022年に導入した任期付採用「アグニパト(Agnipath)」制度は、軍への就職が多い各地で若者の抗議行動につながり、選挙では不利に作用した。会議派だけでなく連合政党であるジャナター・ダル統一派(JD(U))も「アグニパト」撤回を主張しており、モディ政権は軍人の給与・年金支出の抑制か、若者への雇用提供かという困難な課題を抱える。この問題は軍の人事政策全般に及び、国防機構改革論議を湧き起こす可能性をもつ。
第3次モディ政権と今後の日印関係
拓殖大学名誉教授 小島眞氏
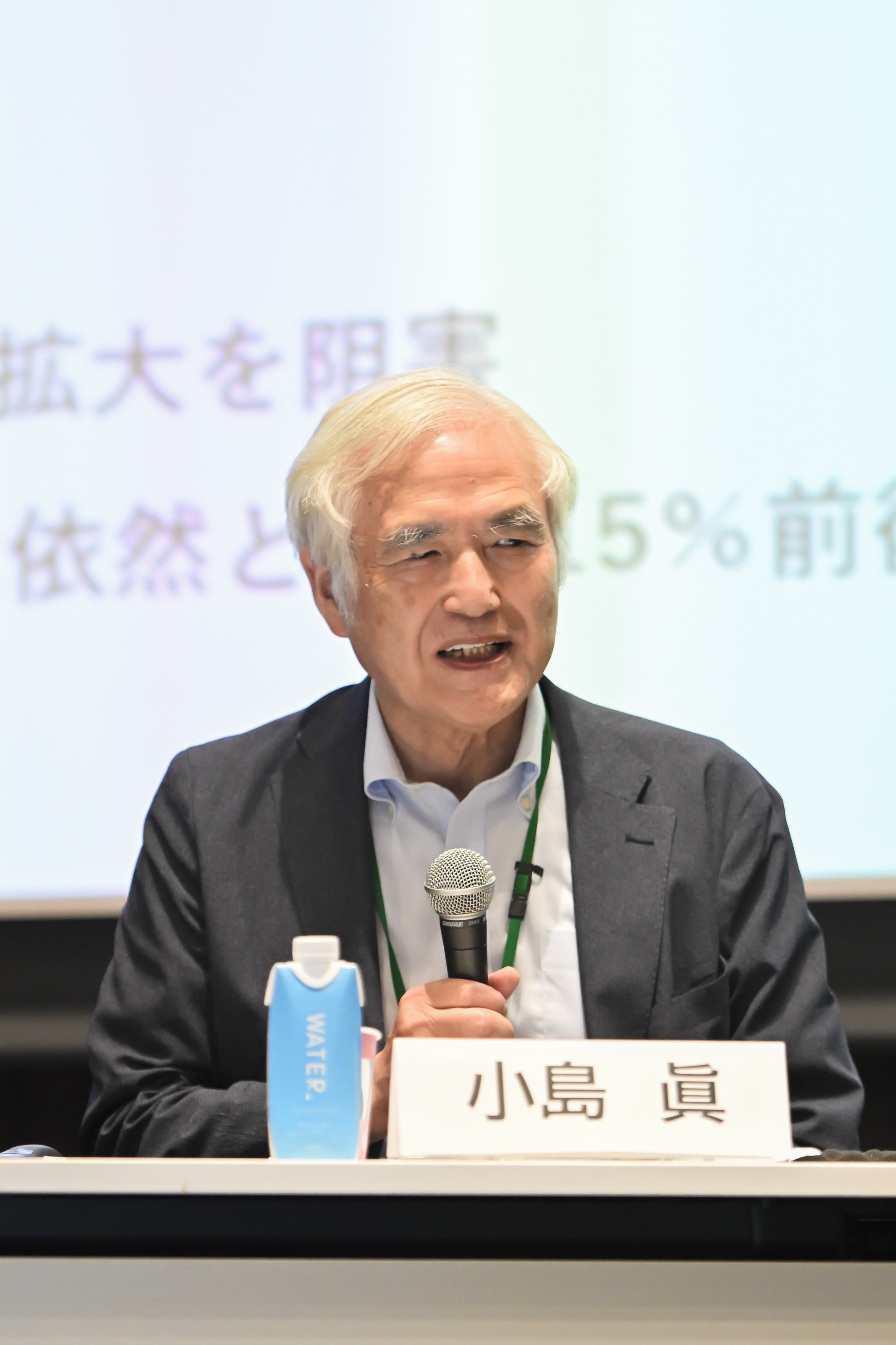
小島眞氏
(モディ政権下のインド経済)
経済改革が導入された1990年代以降、インドのこれまでの経済成長はIT産業を含む
サービス部門主導型であった。人口大国としてインドは労働力が豊富な国であることを考えれば、本来、労働集約的製造業に比較優位があって然るべきであるが、硬直的な労働法、住民に有利な土地収用法、工業用に割高な電力料金制度などが阻害要因として立ちはだかっていた。
2014年にインド人民党(BJP)のモディ政権が成立し、そこで目指されたのは、ガバナナス改革と堅実なマクロ経済運営を図りつつ、インド社会の変革と底上げを伴った力強い経済成長の実現であった。第1次モディ政権下ではデジタル・インディアや各種社会政策の推進、さらには「倒産・破産法」、「財サービス税」の制定が図られる中、”Make in India”が提唱されたものの、総花的で尻すぼみに終わり、経済成長も2016年度をピークに減速するに至った。
第2次モディ政権(2019~24年)では、20年度にはコロナ渦の下で全土封鎖が断行され、大幅なマイナス成長を余儀なくされたが、他方、中長期的な発展を見据えた一連の構造改革を目指した「自立したインド(インド自立化)」ミッションの下で、生産連動型インセンティブ(PLI)スキーム、大規模インフラ開発、デジタル公共インフラ、グリーン・エネルギー戦略などが打ち出され、21年度以降、7%を優に超える高レベル成長が実現している。
2024年5~6月の総選挙では与党BJPが単独過半数に及ばなかったものの、地域政党の参加を得て、第3次モディ政権が発足し、主要閣僚はほぼ全員留任となっている。総選挙直前に発表された選挙マニフェストに照らしてみても、そこでの経済政策の方向性は基本的に第2次モディ政権下の場合と同様と想定される。
(インド製造業の新局面)
近年、インドの製造業は新たな拡大局面を迎えつつあるが[1]、そうした拡大に弾みを与えたのが、“Make in India 2.0” として、2020年4月に14部門を対象に導入された1兆9700億ルピー(240億ドル)規模のPLIスキームである。エレクトロニクス産業が本格的な拡大を示す中で、急務とされるのが半導体産業の立ち上げである。21年12月に7600億ルピー(100億ドル)規模の「インド半導体プログラム」が打ち出され、プロジェクト・コスト全体の50%相当の資金的支援が発表された。24年2月、「修正半導体プログラム」の下で、タタ・エレクトロニクスと力晶積成電子製造の合弁によるチップ製造工場を含む3件のプロジェクトが承認され、半導体産業実現に向けて大きな一歩を踏み出した。
(拡大する中間層)
中間層は、一国経済のバックボーンを形成する存在である。インド消費者経済国民研究所(PRICE)によれば、中間層とは経済的安全性を確保し、裁量的消費が十分可能となるような所得階層だということで、世帯年収(2020年度価格)は50万~300万ルピー(6,700~40,000ドル)とされる。インドの人口に占める中間層のシェアは2015年の26%から21年には31%に拡大し、今後31年には38%(富裕層を含めれば56%)、さらに47年には60%に拡大すると見込まれている。
(日印関係拡大への期待)
日印両国は特別戦略的グローバル・パートナーシップの間柄にあり、安全保障、経済両面で広範な関係を形成しているが、貿易面に関しては、経済連携協定(EPA)が発効したにもかかわらず、停滞した状況が続いている。他方、2004年度以降、インドは日本のODAの最大の供与先であり、デリー・メトロに続いて、デリー・ムンバイ産業大動脈、貨物専用鉄道西線、高速鉄道建設など日印共同プロジェクトとしてインドの大規模インフラ開発に深くコミットしている。
注目されるのは、直近の日系企業の対印直接投資の動向である。JBICの製造業企業を対象にした海外事業展開調査によれば、インドは長期展望に続いて、中期展望においても有望事業展開先の第1位にランクされている。またJETROの日系企業実態調査によれば、日系企業の4分の3はインドでの事業展開を「拡大」と回答しており、日系企業の全世界平均を大きく上回っている。実際、日本の対印直接投資は顕著な拡大を示しており、増加しており、2023年度の場合、他の主要国の対印投資が足踏みする中、日本の対印直接投資は31億7700万ドルを記録し、前年度を77%上回る勢いであった。
こうした背景にあるのは、インドでは中長期的に高レベル成長が見込まれ、中間層の拡大を伴う巨大な国内市場の拡大が見込まれること、さらにはPLIスキームや半導体振興策が功を奏する形で、エレクトロニクス産業や半導体産業を巻き込みつつ、インドでは一大グローバル製造業ハブが形成されつつあり、生産拠点・輸出拠点としての重要性が確実に高まっていることが挙げられる。
経済改革が導入された1990年代以降、インドのこれまでの経済成長はIT産業を含む
サービス部門主導型であった。人口大国としてインドは労働力が豊富な国であることを考えれば、本来、労働集約的製造業に比較優位があって然るべきであるが、硬直的な労働法、住民に有利な土地収用法、工業用に割高な電力料金制度などが阻害要因として立ちはだかっていた。
2014年にインド人民党(BJP)のモディ政権が成立し、そこで目指されたのは、ガバナナス改革と堅実なマクロ経済運営を図りつつ、インド社会の変革と底上げを伴った力強い経済成長の実現であった。第1次モディ政権下ではデジタル・インディアや各種社会政策の推進、さらには「倒産・破産法」、「財サービス税」の制定が図られる中、”Make in India”が提唱されたものの、総花的で尻すぼみに終わり、経済成長も2016年度をピークに減速するに至った。
第2次モディ政権(2019~24年)では、20年度にはコロナ渦の下で全土封鎖が断行され、大幅なマイナス成長を余儀なくされたが、他方、中長期的な発展を見据えた一連の構造改革を目指した「自立したインド(インド自立化)」ミッションの下で、生産連動型インセンティブ(PLI)スキーム、大規模インフラ開発、デジタル公共インフラ、グリーン・エネルギー戦略などが打ち出され、21年度以降、7%を優に超える高レベル成長が実現している。
2024年5~6月の総選挙では与党BJPが単独過半数に及ばなかったものの、地域政党の参加を得て、第3次モディ政権が発足し、主要閣僚はほぼ全員留任となっている。総選挙直前に発表された選挙マニフェストに照らしてみても、そこでの経済政策の方向性は基本的に第2次モディ政権下の場合と同様と想定される。
(インド製造業の新局面)
近年、インドの製造業は新たな拡大局面を迎えつつあるが[1]、そうした拡大に弾みを与えたのが、“Make in India 2.0” として、2020年4月に14部門を対象に導入された1兆9700億ルピー(240億ドル)規模のPLIスキームである。エレクトロニクス産業が本格的な拡大を示す中で、急務とされるのが半導体産業の立ち上げである。21年12月に7600億ルピー(100億ドル)規模の「インド半導体プログラム」が打ち出され、プロジェクト・コスト全体の50%相当の資金的支援が発表された。24年2月、「修正半導体プログラム」の下で、タタ・エレクトロニクスと力晶積成電子製造の合弁によるチップ製造工場を含む3件のプロジェクトが承認され、半導体産業実現に向けて大きな一歩を踏み出した。
(拡大する中間層)
中間層は、一国経済のバックボーンを形成する存在である。インド消費者経済国民研究所(PRICE)によれば、中間層とは経済的安全性を確保し、裁量的消費が十分可能となるような所得階層だということで、世帯年収(2020年度価格)は50万~300万ルピー(6,700~40,000ドル)とされる。インドの人口に占める中間層のシェアは2015年の26%から21年には31%に拡大し、今後31年には38%(富裕層を含めれば56%)、さらに47年には60%に拡大すると見込まれている。
(日印関係拡大への期待)
日印両国は特別戦略的グローバル・パートナーシップの間柄にあり、安全保障、経済両面で広範な関係を形成しているが、貿易面に関しては、経済連携協定(EPA)が発効したにもかかわらず、停滞した状況が続いている。他方、2004年度以降、インドは日本のODAの最大の供与先であり、デリー・メトロに続いて、デリー・ムンバイ産業大動脈、貨物専用鉄道西線、高速鉄道建設など日印共同プロジェクトとしてインドの大規模インフラ開発に深くコミットしている。
注目されるのは、直近の日系企業の対印直接投資の動向である。JBICの製造業企業を対象にした海外事業展開調査によれば、インドは長期展望に続いて、中期展望においても有望事業展開先の第1位にランクされている。またJETROの日系企業実態調査によれば、日系企業の4分の3はインドでの事業展開を「拡大」と回答しており、日系企業の全世界平均を大きく上回っている。実際、日本の対印直接投資は顕著な拡大を示しており、増加しており、2023年度の場合、他の主要国の対印投資が足踏みする中、日本の対印直接投資は31億7700万ドルを記録し、前年度を77%上回る勢いであった。
こうした背景にあるのは、インドでは中長期的に高レベル成長が見込まれ、中間層の拡大を伴う巨大な国内市場の拡大が見込まれること、さらにはPLIスキームや半導体振興策が功を奏する形で、エレクトロニクス産業や半導体産業を巻き込みつつ、インドでは一大グローバル製造業ハブが形成されつつあり、生産拠点・輸出拠点としての重要性が確実に高まっていることが挙げられる。
[1]直近のインド製造業の成長率は、21年度の10.0%から22年度には一転してマイナス2.2%に落ち込んだものの、23年度には再び9.9%という高水準を記録した。
インド北東部と日印関係
岐阜女子大学南アジア研究センター特別客員准教授 笠井亮平氏

岐阜女子大学南アジア研究センター特別客員准教授 笠井亮平氏
1.インド北東部という地域
パネルディスカッションにおいて、「インド北東部と日印関係」と題し報告を行った。近年インド北東部に対する関心がインド国内でも日本でも急速な高まりを見せている。その一方で、これまで北東部に関する情報はきわめて限られているか、あっても断片的なものだったことを踏まえ、まずインド全体における北東部の位置づけ、各州の歴史や宗教、地理といった基本的背景を解説し、多様なインドの中でもとりわけ多様性に富んだ地域であることを指摘した。
2.北東部の総選挙結果
次に、北東部における今次連邦下院総選挙の結果について概要を説明した。北東部は各州の政治的背景が大きく異なるため、全体に共通した傾向を見出すことは容易ではない。今回の報告では、かなり単純化した見方であることを断った上で、「アッサム州」と「その他の諸州」に二分するとある程度の状況が浮かび上がってくることを指摘した。すなわち、前者ではBJP主導のNDAが過半数の選挙区で勝利したのに対し、後者では野党連合のINDIAブロックや地域政党が勝利した州もあることを示した(時間の都合上踏み込まなかったが、州の中でも部族間の関係や平野部・丘陵部の違いといった個別の様子があることを付記しておく)。
3.日本とのかかわり
北東部は日本にとって歴史的に深い関わりを持つ地域である。日本軍は太平洋戦争中の1944年3月にインパール作戦を発動したが、その舞台となったのはインド・ビルマ(現ミャンマー)国境およびインド北東部(特に現在のマニプル州およびナガランド州)だった。同作戦で日本軍は作戦の見通しの甘さや補給不足等の要因により甚大な被害を出し、撤退することになる。しかしこの作戦は日本軍だけでなく、現地の住民にも計り知れない被害をもたらした。折しも今年はインパール作戦から80周年という節目の年であり、日本が支援するかたちでナガランド州コヒマのかつての激戦地に「鎮魂」と刻まれた慰霊碑が建立され、5月8日に除幕式が行われたことを紹介した。
慰霊碑は日本と北東部の間に生じた過去に思いを馳せるためのものと解されるが、それだけにとどまらず、この場所一帯を「エコパーク」として文化施設やステージ等を整備する計画が進行中である。日本と北東部のかかわりについて、過去を振り返るだけでなく、現在そして未来に向けて発展させていく上でのシンボルという位置づけではないかとの報告者の受け止めを示した。これに関連して、ナガランド州で行われたJICAの森林管理プロジェクトをはじめ、日本は北東部に対して多くの経済協力案件を行っていることも紹介した。
4.インド北東部が直面する課題と日本の役割
2014年にインドがそれまでの「ルック・イースト」政策をさらに強化するものとして「アクト・イースト」政策をローンチしたことで、ミャンマーやバングラデシュ等と国境を接する北東部はそのゲートウェイと位置づけられた。「フロンティア」という言葉には「辺境」と「最先端、未開拓」という二つの意味があるが、北東部はまさに前者から後者へと性格を変えたのである。
しかし、北東部がそのポテンシャルを発揮するためにはクリアしなくてはならない課題がある。ひとつはコネクティビティ(連結性)で、①北東部域内の交通インフラ整備と②東南アジアへのアクセス向上に大別される。前者は峻険な山と深い谷の多い地形やモンスーン期の豪雨といった地理・自然条件をいかに克服するか、後者は2021年にミャンマーで発生したクーデターのような地域情勢にも左右される。
もうひとつの課題は、経済開発と人材活用である。北東部はアッサムを除くと平野部が限定的であり、大規模な工場を建設するには制約が多く、産業開発も進んでいない。一方で、若年層は高校や大学を卒業してもそのスキルに見合った職に就きにくいという現実がある。
こうした課題に対して日本が担える役割——そして期待も——は非常に大きい。産業開発においては、JICAの支援で竹資源を活用するプロジェクトがあることにも言及しながら、北東部の特質を活かすことの重要性を指摘した。また、同地域のコネクティビティ改善については、単に北東部の住民の移動や生産・商業活動の活発化に寄与するだけでなく、「自由で開かれたインド太平洋のための新たなプラン」に言及されており、北東部さらにはベンガル湾との接続という観点からも大きな意味を有していることを強調した。最後に、北東部は「日本からもっとも近いインド」であり、この地域に対する多方面からの関心と理解が深まることを願っている旨述べて報告を締めくくった。
5.その他
質疑応答では、カシミール情勢に関する出席者からの質問に対応した。カシミールについては、インドにおける宗教や自治をめぐる問題という国内的側面と、パキスタンや中国との主権や領土にかかわる問題という国際的側面があり、整理して考える必要性があることを指摘した。
最後の締めくくりの発言では、インド側が「ルック・イースト」から「アクト・イースト」へと東方への関与を増大させていることを引き合いに、日本側もインドにおいてこれまで以上に積極的に活動を展開させていくべきであるとして、「アクト・インディア」、「アクト・ノースイーストインディア」が求められていると提唱した。
パネルディスカッションにおいて、「インド北東部と日印関係」と題し報告を行った。近年インド北東部に対する関心がインド国内でも日本でも急速な高まりを見せている。その一方で、これまで北東部に関する情報はきわめて限られているか、あっても断片的なものだったことを踏まえ、まずインド全体における北東部の位置づけ、各州の歴史や宗教、地理といった基本的背景を解説し、多様なインドの中でもとりわけ多様性に富んだ地域であることを指摘した。
2.北東部の総選挙結果
次に、北東部における今次連邦下院総選挙の結果について概要を説明した。北東部は各州の政治的背景が大きく異なるため、全体に共通した傾向を見出すことは容易ではない。今回の報告では、かなり単純化した見方であることを断った上で、「アッサム州」と「その他の諸州」に二分するとある程度の状況が浮かび上がってくることを指摘した。すなわち、前者ではBJP主導のNDAが過半数の選挙区で勝利したのに対し、後者では野党連合のINDIAブロックや地域政党が勝利した州もあることを示した(時間の都合上踏み込まなかったが、州の中でも部族間の関係や平野部・丘陵部の違いといった個別の様子があることを付記しておく)。
3.日本とのかかわり
北東部は日本にとって歴史的に深い関わりを持つ地域である。日本軍は太平洋戦争中の1944年3月にインパール作戦を発動したが、その舞台となったのはインド・ビルマ(現ミャンマー)国境およびインド北東部(特に現在のマニプル州およびナガランド州)だった。同作戦で日本軍は作戦の見通しの甘さや補給不足等の要因により甚大な被害を出し、撤退することになる。しかしこの作戦は日本軍だけでなく、現地の住民にも計り知れない被害をもたらした。折しも今年はインパール作戦から80周年という節目の年であり、日本が支援するかたちでナガランド州コヒマのかつての激戦地に「鎮魂」と刻まれた慰霊碑が建立され、5月8日に除幕式が行われたことを紹介した。
慰霊碑は日本と北東部の間に生じた過去に思いを馳せるためのものと解されるが、それだけにとどまらず、この場所一帯を「エコパーク」として文化施設やステージ等を整備する計画が進行中である。日本と北東部のかかわりについて、過去を振り返るだけでなく、現在そして未来に向けて発展させていく上でのシンボルという位置づけではないかとの報告者の受け止めを示した。これに関連して、ナガランド州で行われたJICAの森林管理プロジェクトをはじめ、日本は北東部に対して多くの経済協力案件を行っていることも紹介した。
4.インド北東部が直面する課題と日本の役割
2014年にインドがそれまでの「ルック・イースト」政策をさらに強化するものとして「アクト・イースト」政策をローンチしたことで、ミャンマーやバングラデシュ等と国境を接する北東部はそのゲートウェイと位置づけられた。「フロンティア」という言葉には「辺境」と「最先端、未開拓」という二つの意味があるが、北東部はまさに前者から後者へと性格を変えたのである。
しかし、北東部がそのポテンシャルを発揮するためにはクリアしなくてはならない課題がある。ひとつはコネクティビティ(連結性)で、①北東部域内の交通インフラ整備と②東南アジアへのアクセス向上に大別される。前者は峻険な山と深い谷の多い地形やモンスーン期の豪雨といった地理・自然条件をいかに克服するか、後者は2021年にミャンマーで発生したクーデターのような地域情勢にも左右される。
もうひとつの課題は、経済開発と人材活用である。北東部はアッサムを除くと平野部が限定的であり、大規模な工場を建設するには制約が多く、産業開発も進んでいない。一方で、若年層は高校や大学を卒業してもそのスキルに見合った職に就きにくいという現実がある。
こうした課題に対して日本が担える役割——そして期待も——は非常に大きい。産業開発においては、JICAの支援で竹資源を活用するプロジェクトがあることにも言及しながら、北東部の特質を活かすことの重要性を指摘した。また、同地域のコネクティビティ改善については、単に北東部の住民の移動や生産・商業活動の活発化に寄与するだけでなく、「自由で開かれたインド太平洋のための新たなプラン」に言及されており、北東部さらにはベンガル湾との接続という観点からも大きな意味を有していることを強調した。最後に、北東部は「日本からもっとも近いインド」であり、この地域に対する多方面からの関心と理解が深まることを願っている旨述べて報告を締めくくった。
5.その他
質疑応答では、カシミール情勢に関する出席者からの質問に対応した。カシミールについては、インドにおける宗教や自治をめぐる問題という国内的側面と、パキスタンや中国との主権や領土にかかわる問題という国際的側面があり、整理して考える必要性があることを指摘した。
最後の締めくくりの発言では、インド側が「ルック・イースト」から「アクト・イースト」へと東方への関与を増大させていることを引き合いに、日本側もインドにおいてこれまで以上に積極的に活動を展開させていくべきであるとして、「アクト・インディア」、「アクト・ノースイーストインディア」が求められていると提唱した。
