【開催報告】
日・イランオンライン学生交流プログラム
中東・イスラム事業グループ(*1)では、イラン外務省付属の大学院大学である国際関係学院(School of International Relations、以下SIR)との共催で、東海大学の協力のもと、2021年12月21日、22日に日・イランオンライン学生交流プログラムを開催しました。
このプログラムでは、21日はSIRが、22日は東海大学がホスト役を務め、4つのテーマ(Geopolitics、Governance、Economics、Society &Culture)に基づいた発表と、意見交換を行いました。SIRからは10人、東海大学からは計15人の参加がありました。
12月21日 イランデー
この日はSIRがホストとなり、以下の発表が行われました。
「イランの南北回廊における地政学的利点と経済的能力」(Geopolitics)
「外交政策の分野におけるイラン・イスラム共和国の統治の原則」(Governance)
「エネルギー効率の政治経済学と温室効果ガス削減に関する世界の動きへのイランの参加」(Economics)
「イラン社会における建築芸術の反映」(Society & Culture)
発表は外交・国際関係を中心に現代イランの状況が分かる構成になっており、東海大学の学生たちも真剣に聞き入っていました。また、環境問題などについての質問や意見交換が交わされました。
またこの日は冬至(ペルシア語で”シャベヤルダー”)前日であり、イラン文化におけるこの日の持つ意味や、この日の過ごし方についての紹介もありました。
12月22日 日本デー
「日本における相対的貧困」(Economy)
「安楽死に対する賛否両論」(Society & Culture)
「日本が核兵器禁止条約に署名しない理由」(Governance)
「最悪の状況:COVID-19、地政学的、世界的な半導体危機」(Geopolitics)
東海大学側は教養学部や情報理工学部など3学部 から学生が参加し、それぞれの専攻に即したバラエティに富む発表になりました。またプログラム2日目で、双方の緊張がほぐれたこともあり、日本人の結婚・離婚観、女性の社会進出、日本の外交戦略や、コロナが社会に与えた影響など、発表に関連した意見交換も活発に行われました。
日本とイラン両国の間で5時間半の時差があり、すでにそれぞれの学校で講義やゼミナールの日程が組まれている中、イランデーと日本デーを半日ずつ、2日間にわたって実施することは容易ではありませんでした。しかし、昼食休憩を調整したり、ゼミ単位で参加したりするなどSIRと東海大学双方の協力の下、実施することが出来ました。また、参加者の学生の専門は様々でしたが、どの発表も、それぞれの大学の先生方のご指導の下、客観的事実と各主題に関する多様な見解を盛り込んだ大変優れた発表でした。参加者は、2日にわたる発表と意見交換を通じて、相手の国の課題について多くのことを学んだことと思います。
当グループは、今後もこのような活動を通じて、日・イランの若者同士の交流を促進していきます。
*1 2022年1月よりアジア・イスラム事業グループに再編。
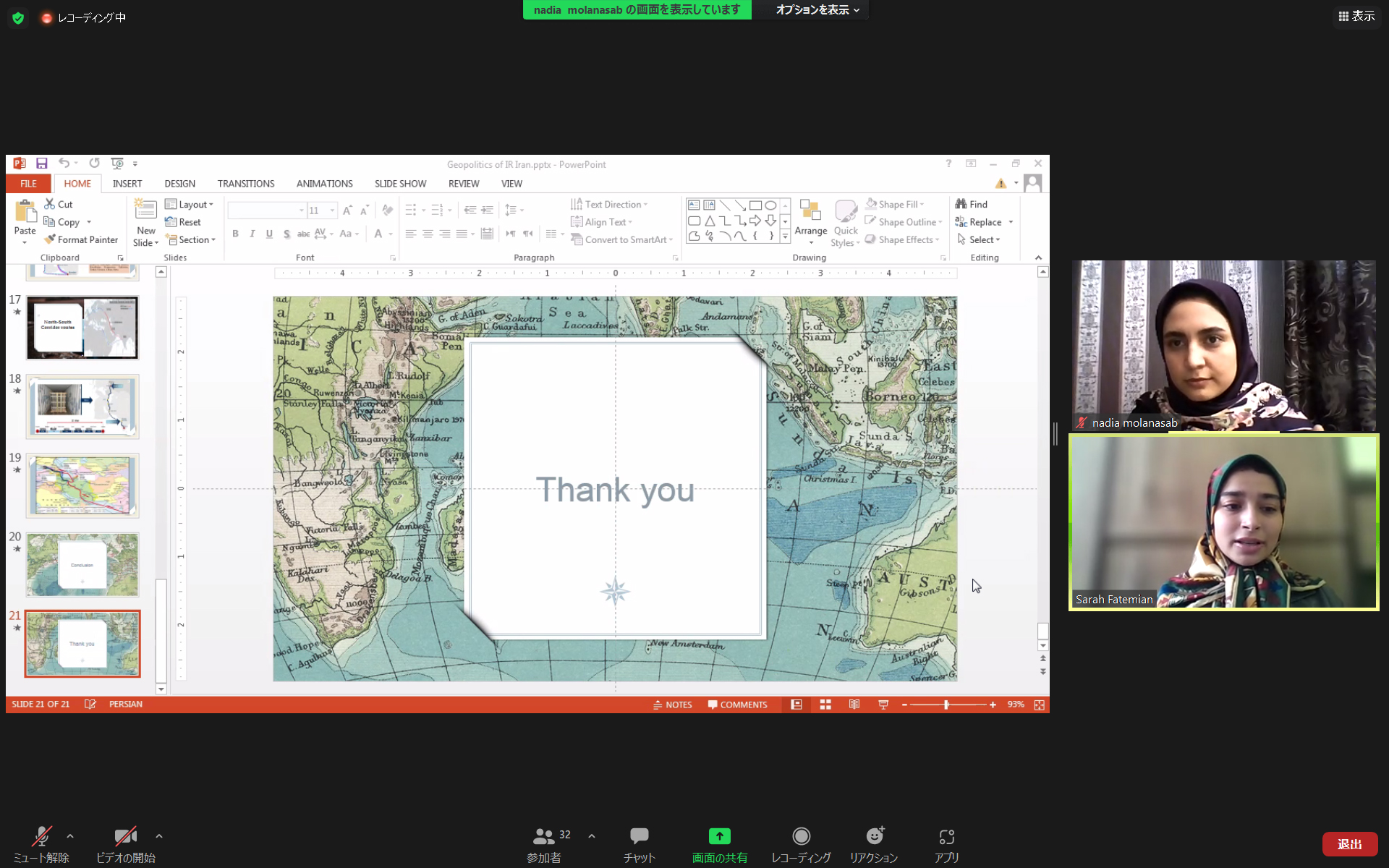
イランデーの発表の様子
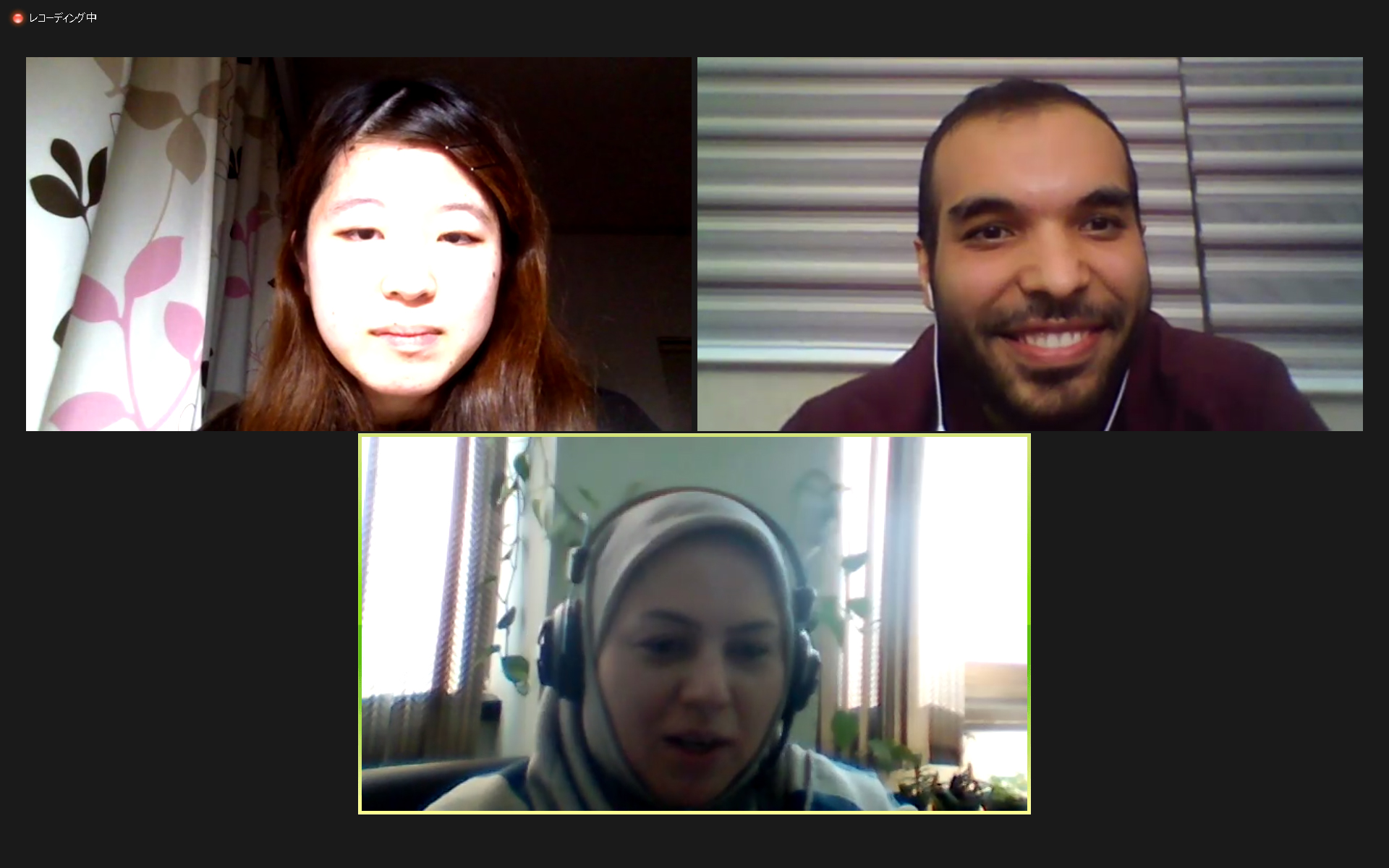
日本デーの質疑応答の様子
 参加者の様子
参加者の様子