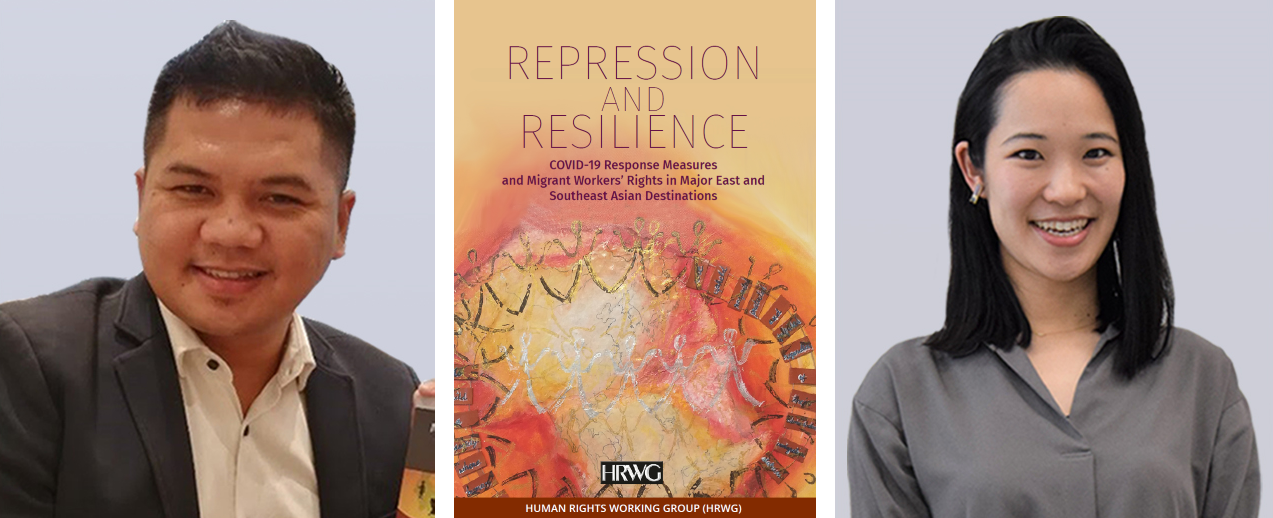――なぜこの共同研究プロジェクトを行うことになったのでしょうか。また、特に新型コロナウィルス感染症の世界的流行を踏まえ、検討の必要があると思われた最も重要なテーマや問題は何ですか ダニエル・アウィグラ氏 この研究は東・東南アジアの特に移住労働者の人権保護に対する地域間連携に向けたイニシアチブの一環として実施したものです。ヒューマンライツ・ワーキンググループと笹川平和財団との連携は2018年に始まりました。近年、東アジアにおける移住労働者の需要が以前にもまして高くなっており、東南アジアと東アジアの国家や地域間で労働移住の相互依存が増しています。高齢化社会、女性のさらなる社会参画、経済成長や経済発展が移住を誘引する要因の一部となっています。こうした状況の中で、この二つの地域の間の対話と協調のための広域プラットフォームがますます重要になってきました。
また、世界的傾向であるポピュリズムやナショナリズムの台頭は東・東南アジアにも及んでいます。移民はよそ者とみなされ、時としてスケープゴート化され、差別の対象になることがあります。移住労働者とその家族が直面する問題の本質の一つは、移住労働者が、母国と受入れ国双方の国益に強く基づいて打ち出された政策で規制されているという点です。しかし、二地域間の移住の増加にも関わらず、特に、移住労働者のニーズに応え、移住労働者を支援するうえで重要な役割を果たしている市民社会、非国家主体間の地域間協調が、依然として欠如しています。
新型コロナウィルス感染症の世界的流行下で、多くの国は弱者である移住労働者に背を向け、支援の手を差し伸べないばかりか、この感染症の拡大を移住労働者のせいにしようとしています。移住労働者の多大な貢献よりも、移住の負の影響のほうが取り沙汰される頻度が高いのです。また、社会的に周縁化された人々の窮状に対する懸念を声にし、社会の意識を高める役割を持つ我々市民社会の活動が、パンデミックにより困難に直面し、移住労働者は最も影響を受けやすい脆弱な集団の一つとなってきています。こうした移住労働者の人権に関する状況をより深く理解するために、この共同研究を実施することにしました。
調査をするうえで最大の課題は、パンデミック下で移住労働者のもとを直に訪ね、彼らの状況に関する情報を収集したうえで、国家・地域・国際レベルで彼らを擁護することが非常に難しくなっているということです。しかし、この研究では、私たちがすでに構築していた東・東南アジアを網羅する市民社会ネットワークのおかげで、影響を受けた移住労働者自身の証言を含む非常に豊富なデータと情報を収集することができました。この地域の主要な受入れ国・地域に焦点を当て、広域にわたって移住労働者の保護の改善を図るべく、新型コロナウィルス対応措置とそれが移住労働者の生活に及ぼす影響に関する共同研究を実施できたのです。
――そうして実施した調査結果の報告書が、2020年12月に刊行された「抑圧とレジリエンス:~コロナ禍と移住労働者: 東・東南アジア各国の施策と当事者の声から考える~ 」ですね。研究結果の概要や研究で取り上げた地域全体の傾向や共通点について、教えてください。
林茉里子氏 この研究はアウィグラ氏の述べた問題意識の下、3つの主要な目的で行われました。第一の目的は、新型コロナウィルスのパンデミック下で、感染症対策と既存の移住政策が、移住労働者の権利に及ぼす影響を評価することです。第二の目的は、移住労働者の脆弱性が実体験としてどのような形で表れてくるのか、また、移住労働者が直面する課題に国家主体や非国家主体がどのように対応するのかを明らかにすることです。そして第三の、最も重要な目的は、影響を受けている人々の声を広め、国家レベル・地域レベルで多くのステークホルダーにこうした声を届けることでした。
この研究は、7つの移住労働者受入れ国・地域の状況に焦点を当てており、香港、日本、マレーシア、シンガポール、韓国、台湾、タイを対象としています。私たちはこの7カ国・地域のフィールド・リサーチャーと連携して調査を行いました。彼/彼女らは、移住労働者コミュニティに対する直接支援を行う実務家や、コミュニティを拠点とした研究者です。主に2020年7月から9月まで、またこの報告書が作成されるまでの期間に様々なデータを収集しました。
私たちは、感染症に関する情報収集や分析よくみられる統計的な数字を強調した議論ではなく、移住労働者の実体験や事情を知り、伝えたいと思いました。フィールド・リサーチャーはすでに移住労働者と信頼関係を構築していましたから、パンデミック下でもこうした情報を得るのは可能でした。彼らは現地に根差しているので、現地語でのみ入手可能な情報源から得た情報やデータを分析に含めることもできました。
パンデミック下で移住労働者が直面する共通の課題には、移動の制限、医療や個人用防護具(PPE)へのアクセスが制限されていること、失業による生活苦、国の支援サービスを利用できないこと、国の資金支援を受ける資格がないことが含まれますが、これに限定されません。職場での搾取や不当な扱いも共通の課題であり、パンデミック下で人身取引のリスクが増してきています。情報の不足や情報へのアクセスが困難だといったことも大きな課題で、その結果、こうした移住労働者の権利、特にパンデミック下で健康への権利や、労働者としての権利も侵害されています。
移住労働者特有の脆弱性として、例えば、多くの移住労働者、特に滞在許可証を持たない者や非正規滞在である者にとっては、強制退去や収容等の移民法や出入国管理法の執行対象になるのではないかという恐怖が、必要不可欠なケアや支援を受ける際の障壁となりました。ほとんどの移住労働者のビザは雇用主に紐づけられていたり、雇用主が提供する居住施設で暮らしていたりしますから、失業してしまうとビザ、あるいは家をなくすことになりかねません。こうした恐怖、生活苦、精神的苦痛、移動制限、搾取、雇用主による監視の強化からくる不安感は、移住労働者のメンタルヘルスの悪化につながっています。
移住労働者が直面するこうした課題は、パンデミックの発生以前から移住労働者が置かれてきた社会的立場や扱われ方に起因していると、私たちは結論付けました。パンデミック下で移住労働者が弱者となったもう一つの理由は、国籍、市民権、在留資格が、必要なサービスと支援を受けるうえでの基準として使われたことです。移住労働者がどのような在留資格を有しているかによって、社会に包摂されるか、排除されるかが決まってしまいました。パンデミック下であっても、出入国管理の延長線上で支援やケアの利用可能範囲が制限されているのです。
こうした状況の中で、現地のNGOや自助グループは、人道支援、理解しやすい形での情報の発信、文化的に配慮した支援、より専門的なサービスやケアの提供などで重要な役割を果たしました。
――研究結果を踏まえて、どのようなことを提言されたのでしょうか。いくつかご提示いただけますか
林氏 この研究では、協同イニシアチブとして、新型コロナウィルス感染症のような公衆衛生上の危機下における移住労働者の権利保護に関するガイドラインを提示しました。このガイドラインは、先ほどお話しした移住労働者の特定の脆弱性の再確認を含む一般原則から始まり、コミュニティ・レジリエンスや社会参画などの重要性にも言及しています。一般原則では、必要不可欠なサービスにおいて差別しないことや、移民法や出入国管理法の執行と公衆衛生サービスの提供とを明確に分離する必要性も提唱しています。
このガイドラインの主要部分は、移住労働者にとって重要な7つの権利領域について述べています。これには保健医療、情報、ディーセントワーク(働き甲斐がある人間らしい仕事)と社会保障、安全で公正な移住プロセス、人身取引からの保護を受ける権利や安全な生活環境を確保する権利のほか、支援が行き届きにくい場所で働く移住労働者の権利が含まれます。
このガイドラインの最終部分は、移住労働者とその支援者を含む市民社会のレジリエンスを支援することや、母国と受入れ国との継続的な協調も提唱しています。私たちは政府、国際組織、援助機関などに対し、移住労働者や支援者コミュニティの草の根運動に協力し、より多くの財源を彼らに配分してくださるようお願いしています。
例えば、一部の国で開始されているワクチン接種プログラムに対する勧告として、各国に対し国籍、市民権、在留資格をワクチン接種の基準としないようお願いしたいのです。これは公衆衛生上の危機ですから、最も影響を受けやすい弱者を保護せずして社会全体の保護はありえません。すべての人が安全を確保するまで、誰一人安全とはいえないのです。
――ダニエルさんは報告書の冒頭で、世界中に大きな衝撃を与え生活を一変させた新型コロナウィルス感染症の世界的流行は、変革の重要な局面としての役割も果たしうるという理論を展開していますね。この研究から導かれた結論を踏まえると、新型コロナウィルス感染症の世界的な流行に対応する際、移住労働者保護を目的としたよりレジリエントなシステムを構築するために、ネットワークを再評価し強化する機会をどのような形で提供できると思いますか アウィグラ氏 新型コロナウィルス感染症の世界的流行は、物事の普遍性がいかに重要かということを私たちに示してくれています。ウィルスには、国籍も宗教も人種も関係ありません。ウィルスはすべての人を攻撃するだけです。今日ほぼすべての政府は、憲法に則って市民や国民を守る姿勢を示しています。もちろん、これだけでは十分でありません。といいますのも、それぞれの国には自国の市民だけではなく、移住労働者や旅行者、非正規滞在者、難民、難民申請者らも住んでいるからです。
この新型コロナウィルス感染症の世界的な流行は、宗教、国籍、人種、その他のアイデンティティなどの特定基準に基づく対応ではなく、普遍性に基づく対応がいかに重要であるかを伝える機会を提供しています。ほぼすべての政策を根本的に見直し、これらの政策がすべての人々にとって包摂的なものであるのかどうかを検討することが、大いなる推進力につながると思います。政策が包摂的ではない場合、政策に不備があるのです。
新型コロナウィルス感染症の世界的流行に対する各国・地域の対処方法を決定する確固たる枠組みはありません。今回、非常に短期間で多数の実験的な政策がとられていることがわかりました。この緊急事態下の選択肢は非常に限られています。あきらめるのか、立ち向かうのか。国の権限を強化して孤立する道を選ぶのか、あるいは国際協調による対応を推進するのか、社会をエンパワーしていくのか。こうしたことが選択肢になります。
研究結果が示唆しているのは、この状況に単独で立ち向かえる国はないということです。パンデミックに屈服するのではなく、社会をエンパワーし、国際協調を構築して、対抗するということです。最も影響を受けやすいグループを保護するには、人権と民主主義の原則を支持するという発想が必要なのです。私たちは団結、協調、そして包括的な政策によってのみ、この状況に対処できると信じています。
今こそ、移住労働者を保護するための制度を再評価するだけでなく、あらゆる意思決定プロセスへの移住労働者の参加を促進するということを含む、民主主義的な課題に触れることが非常に重要である理由は、ここにあります。
――地域全体でこうした広範な連携を支援するために講じる必要がある重要な措置には、どのようなものがあると思いますか アウィグラ氏 ASEAN(東南アジア諸国連合)地域では、新型コロナウィルス感染症の世界的な流行に対し多くの取り組みをしてきましたし、共同の政治的コミットメントを示してきました。政治的コミットメントが実施されてきたかどうか、あるいはそれが紙に書かれた政治的コミットメントにすぎないのかどうか、私たちは厳しい目で見届けなければなりません。これはASEAN地域におけるプロセスを確認するうえで必要なことなのです。他方、東アジアでも、公衆衛生上の危機への対処の経験が豊富であり、それなりのリソースがあることが分かってきています。
東南アジアでは、さまざまな課題を議論する特定の手段としての、ASEANの地域主義が非常に強固ですが、東アジアでは、地域を超えた協調以上に豊富な財源を持ち合わせています。こうした協調領域で地域間連携を可能にする一つのプラットフォームを、例えばASEAN+3のプラットフォームの下に強化することができるでしょう。
昨年、「新興疾患及び公衆衛生上の緊急事態に対するASEAN地域センター(ASEAN感染症対策センター)」を設立する施策が、ベトナムの議長国の下、公表されました。この施策に対して最近、日本政府による資金援助がありました。ASEANには公衆衛生上の緊急事態に対するセンターができたということですので、これは私たちが地域を超えて連携できる分野だと思います。
また、意思決定における移住労働者の参加も呼び掛けているGlobal Compact for Migration(安全で秩序ある正規
移住のための
グローバル・
コンパクト)等の二国間協調や国際協調のプラットフォーム等を活用する方法もあるでしょう。
林氏 日本からも、移住労働者の権利保護に関して、国家主体と非国家主体に、国境を越えた広域の施策にいっそう関与していただければと思っています。移住は継続的なプロセスであり、移住労働者の母国での採用や出発前のプロセスから、日本での生活、そして帰国、母国への再統合までがすべてつながっています。
移住労働者が直面する課題は関連する国双方、母国と受入れ国、場合によっては移住の途中で一時的に滞在する場所も含めた国々の状況に起因しています。また、人権の観点からいえば、国家の移住労働者管理を考える際、両国間の覚書(MOU)に基づいている二国間関係だけにとらわれないことが重要です。ある特定の国からの移住労働者の搾取を排除することに成功したとしても、人権の普遍性に基づいて地域・国際的に移住労働者の権利保護の改善に取り組まなければ、別の移住労働者が搾取される姿を今後も目にすることになるのです。
日本でも、この公衆衛生上の危機下において、移住者コミュニティは、生活している人間としてではなく、あくまで一時的な労働力として政府から扱われてきたことにより、甚大な影響を受けました。移住者コミュニティが利用できない、あるいはアクセスできない公的支援のギャップを埋めてきた市民社会団体は、パンデミックの長期化で疲弊しつつあります。
私たちはすべての人にとって、よりレジリエントで持続可能な社会にしていくために、日本だけではなく隣国とも手を取り合い、移住労働者の権利を保護するために力を合わせて提言をしていく必要があります。特に移住者の権利保護の領域において、日本からアジア域内連携への関与は依然として限られています。私たちは引き続き、笹川平和財団のこれまでの取り組みを踏まえながら、そして既存のプラットフォームとも連携しながら、東・東南アジアの市民社会間でさらに強力なネットワークや協調を構築する取り組みを推進していきたいと考えています。