Ocean Newsletter
第505号(2021.08.20発行)
持続可能な社会を支える生態系インフラストラクチャー
[KEYWORDS]生物多様性/防災/Eco-DRR東京大学名誉教授◆鷲谷いづみ
生物多様性の保全に寄与し、将来世代の選択肢を狭めることなくコストの小さい「生態系インフラストラクチャー」は、自然環境の保全・再生をめざす研究者によって提案された。「自然にもとづく問題解決」として、国際的にも気候変動適応策や防災の手法として重視されるようになったその考え方を、日本の海辺にも取り入れることを奨めたい。
コンクリート構造物と植栽がつくる景色
生態学や進化学の研究者は、生態系や生物多様性の「目」で景色を眺める習慣が身についている。私もその一人であり、最近は、どこに行っても少し「残念な」景色が目に入るため国内旅行を楽しめなくなってきた。コンクリート構造物と園芸植物の植栽によるインフラ整備は、欧米諸国ではすでに時代遅れとなりつつあるが、日本では未だ隆盛をきわめている。かつては地域毎に個性的な自然もそれと関わる人の営みも豊かだった海辺も、今では、画一的で単調な人工的な風景が広がる場所が多くなった。
茨城県ひたちなか市に関東地方ではすでに珍しくなった砂丘が残されており、国営公園として整備されている。海岸沿いに建設された道路のため砂の移動動態は変化しているが、砂丘らしい地形が残されている。しかし、人気スポットでは砂丘植生が取り除かれ、広大な面積一面に園芸植物が植えられている。砂丘を覆い尽くす園芸植物の花が開花すると決まってマスコミが取り上げ、アプローチ道路が渋滞するほど多くの人々が訪れる。日本では、多くの人々が、場所を問わず植栽でつくれる人工的な風景を「素晴らしい」と感じ、かつてその場所を特徴づけていた自然にはほとんど関心を示さないようだ。それは、幼少期から大人になるまで、自然誌(Natural history)の学習の機会をほとんどもつことがないからかもしれない。
自然環境保全再生分科会の提言
 写真1 大津波に見舞われた10か月後の北上川河口付近の茅場でのヨシ採集(2012 年1月)
写真1 大津波に見舞われた10か月後の北上川河口付近の茅場でのヨシ採集(2012 年1月)
 写真2 生態系インフラストラクチャーの代表例ともいえる治水のための湿地再生事業が進められている渡良瀬遊水地
写真2 生態系インフラストラクチャーの代表例ともいえる治水のための湿地再生事業が進められている渡良瀬遊水地
東日本大震災の後に国の防災の政策となった「復興・国土強靱化」は、将来世代に多大な債務という経済的な負担を残しながら日本列島の陸と海の狭間を急速に変容させつつある。大震災から10年を経た東北地方の沿岸には、「コンクリートと造成・植栽でつくられた景色」が目立つ。
震災後しばらくして、自然環境の保全や再生にかかわる研究者が参加する日本学術会議統合生物学委員会・環境学委員会合同自然環境保全再生分科会のメンバーは、津波に見舞われた海岸を調査した。目にしたのは、クロマツの実生や海浜植物など自然の要素が蘇りつつある場所に植林のための盛り土が大規模に行われ、近くでは防潮堤の敷設工事が始まっている様子であった。筆者が委員長を務めた分科会は、それをきっかけに審議を重ね、生物多様性と生態系のはたらきを損なわないインフラ整備のあり方を推奨する提言、『復興・国土強靱化における生態系インフラストラクチャー活用のすすめ』をまとめて公表した。
欧米ではグリーンインフラストラクチャーと表現される内容とも重なる手法を「生態系インフラストラクチャー」と表現した理由は、防災に関しては「生態系にもとづく災害リスクの軽減(EcosystembasedDisaster Risk Reduction :Eco-DRR)」という政策が国際的に影響力を強めつつあったことに加えて、日本では「グリーン」という言葉は、植栽や公園・緑地がイメージされやすく、誤解されるおそれがあったからである。
Eco-DRRは、沿岸ではマングローブ林やサンゴ礁などの保全再生によって、直接暴露されれば災害を引き起こす可能性のある撹乱の緩衝帯をつくるなど、生態系を防災に活かす手法である。河川氾濫原や河口部の湿地など、居住すれば災害をうける可能性の高い場所は、生物資源の採集地(写真1)などとして利用した伝統的な土地利用のあり方がそれにあたる。資源採集や自然を活かしたレクリエーションの場などとして活用すれば、リスクを避けつつ社会は自然の恵みを長期的に享受できる。整備にも維持にもあまりコストがかからないことも社会の選択肢としての利点である(表)。
河川治水事業として20 年ほど前から実施されている関東地方の渡良瀬遊水地の湿地再生事業は、現代の日本における代表的なEco-DRR事業である(写真2)。しかし、日本では、未だ防災政策の主流どころか傍流にも位置づけられてはいない。
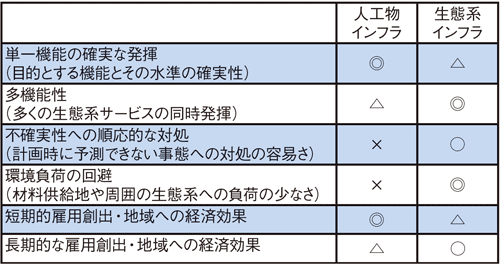 表 人工構造物によるインフラ整備と生態系インフラストラクチャーの特徴の比較
表 人工構造物によるインフラ整備と生態系インフラストラクチャーの特徴の比較
(出典:『復興・国土強靭化における生態系インフラストラクチャー活用のすすめ』 日本学術会議自然環境保全再生分科会 2014 http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-22-t199-2.pdf)
自然にもとづく問題解決
21世紀は、予想・予測をはるかに超える「撹乱イベント」とともに幕を上げた。2004年のインド洋の津波、2011年の東北地方太平洋沖地震と津波、気候変動による嵐の激化の表れである2005年のハリケーン・カトリーナや2012年のハリケーン・サンディ、日本での線状降水帯による洪水や土砂崩れの多発など、いずれも「前代未聞」、「想定外」と表現しなければならないような災害である。気候変動が進めば気象災害のリスクはますます高まる。将来世代を含めた人々の命と暮らしを守り持続可能な社会を築くには、地域の伝統的知識・文化にも目を向けた新たな科学的な発想にもとづくインフラ整備の計画や実践が必要である。
私たちが生態系インフラストラクチャーと名付けた手法やその頃までに提案されていたいくつもの類似の概念は、「自然にもとづく問題解決(Nature-based Solution, NbS)」という最近国際的に重視され始めた「アンブレラ概念」に包摂される。欧州環境庁(EEA)は、2021年4月に、『ヨーロッパにおける自然にもとづく解決策:気候変動への適応策と災害リスク低減への政策、知見、実践』と題する報告書を発表した。「自然にもとづく解決策」が気候変動適応と防災においていかに有効であるかを検討し、今後の課題を明らかにするものであり、これまでに実施された取り組みの評価もなされている。
そのようなインフラ整備は、それぞれの場所特有の生物多様性や生態系の機能を有効に活用する科学的な計画にもとづく。海辺を対象とする場合には、土砂や生物の動きでつながっている流域全体に目を向け、そこでのヒトの営みにも考慮して、人々の安全と豊かな暮らしを守る計画が必要となる。持続可能であるためには、将来世代の選択肢を狭めることがないようにする配慮が重要である。そうした生態系インフラ整備が、日本の海辺でも、地元の意見、自然誌や生態学などの科学からの意見も参考にして計画され、実践されることを望みたい。(了)
第505号(2021.08.20発行)のその他の記事
- 液化水素運搬船が開く脱炭素社会 川崎重工業(株)水素戦略本部副本部長執行役員◆西村元彦
- 持続可能な社会を支える生態系インフラストラクチャー 東京大学名誉教授◆鷲谷いづみ
- 能登の里山里海で実践するオーガニック養殖 金沢大学理工学域能登海洋水産センター センター長◆松原 創
- 編集後記 日本海洋政策学会会長◆坂元茂樹
