News
【開催報告】Journal of Disaster Research 特別号公刊記念イベント「気候変動に伴う移住とその脆弱性」に関する国際セミナー
気候変動問題への関心が世界的に高まる中、気候変動に伴う海面上昇によって海抜の低い沿岸国や島嶼国では、人々の移転問題が大きな課題の一つとなっている。人々の移住の動機は複合的であるが、IPCC海洋・雪氷圏特別報告書(SROCC)が示すように将来的な世界規模での海面上昇、沿岸域での災害リスクが高まるという予測を受け、気候変動に伴う移民の発生に備えた国家および国際社会の対応が求められる。
笹川平和財団海洋政策研究所では、東京大学、環境法研究所(米国)、法政大学らと共同で、太平洋島嶼国における気候変動と移転問題に関する研究を実施し、調査研究によって得られた知見を、Journal of Disaster Research特別号として2019年12月に公刊した。本セミナーは、執筆者を招き共同研究の知見を共有するとともに、さらなる研究展開に向けての公開議論を行うことを目的に開催された。
はじめに、酒井英次笹川平和財団海洋政策研究所副所長より開会挨拶として、気候変動の深刻化に伴って熱帯低気圧、海面上昇、洪水といった沿岸域のリスクが高まっていること、さらには漁獲量の減少などによる食糧安全保障の問題などが顕在化し、とりわけこうした問題は太平洋島嶼国にとって火急の課題であることを述べた。将来、気候変動によって人々が移住を余儀なくされた場合に、受入国にうまく調和しながら生活を立て直すための仕組みづくりと、そのための研究の必要性について強調した。

酒井英次笹川平和財団海洋政策研究副所長による開会挨拶

司会を務めた前川美湖主任研究員
中山幹康東京大学大学院教授が続いて今回特別号として公刊された太平洋地域における気候変動と移転問題に関する共同研究の概要について紹介した。この共同研究では、海面上昇による国土の浸食が問題視されている環礁国としてマーシャル諸島共和国、キリバス共和国、および比較対象として火山島であるミクロネシア連邦の3つの島嶼国から国外に移住した移民を対象とした調査を行った。共通の研究課題として、1)将来、環礁国の人々が移住を余儀なくされた場合に、教育的・能力的な面で彼らは十分に準備ができているのか、2)すでに移住した人々は移住後うまく生活再建をしているのか、この2点を挙げた。
続いて、Carl Bruch氏(環境法研究所国際部長)は、いわゆる「気候変動難民」を取り巻く現状として、難民条約の適用の難しさと、国際人権法下で一定の権利を保障する可能性について示唆した。しかしながら「気候変動難民条約」のような単独の法規ではなく、既存の法的枠組みを活用した「ツールキット」アプローチが有効であると述べ、アノテ・トン前キリバス大統領が提唱した「尊厳ある移住」の概念を具体化し、実効的な法的支援を形成していくことが重要であると締めくくった。
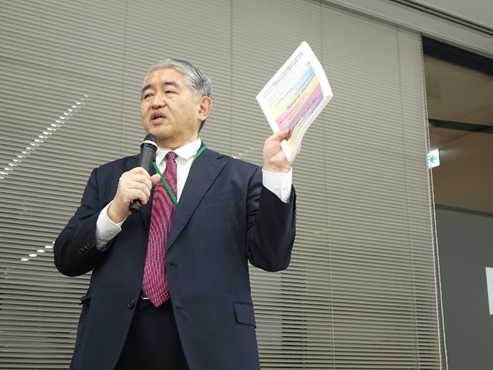
中山幹康東京大学教授

Carl Bruch環境法研究所国際部長

Malisa Laelan氏

Shanna McClain氏
次に、同じく米国オレゴン州に移住したミクロネシア人(マーシャル人、ミクロネシア連邦出身者、パラオ人、いずれもCOFA締結国)を対象とした調査についてKapiolani Micky氏(在オレゴン州ミクロネシア人会)、Scott Drinkall 氏(環境法研究所客員研究員)が発表した。調査結果によると、それぞれの出身によって移住の特徴が分かれ、例えばパラオ人が教育のために移住した比率が高いのに対して、マーシャル人は家族の都合により移住した比率が高かった。そのほか気候変動の影響についても、複数のマーシャル人が移住の間接的な要因に気候変動を挙げていたのに対し、他の二カ国の出身者の意思決定にはほとんど影響していなかった。いずれの出身者も、それぞれ特有の問題に移住後直面しており、移住後に実際に必要とされていたものが理解できたことから、米国移住前の状況を改善するような施策を検討する必要性があると両氏は述べた。
前川美湖 笹川平和財団海洋政策研究所主任研究員、Priyatma Singh氏(フィジー大学講師)は、キリバスから隣国フィジーに移住した人々、およびキリバスに在住する学生を対象に実施した調査に関する報告を行った。Singh氏はフィジー政府が昨年施行した国内の移転ガイドラインについて紹介し、過去に実際に村単位で計画移住が行われた例を踏まえつつ、今後もステークホルダー間の対話、そしてエビデンスに基づいた政策形成のための研究活動が肝要であると述べた。前川主任研究員はフィジーに在住するキリバス人移民へのインタビュー調査を通じて見えた課題として、米国における島嶼国出身者と異なり、キリバス人移民のための情報共有の仕組みが存在しない点を指摘した。キリバス人移民の事例からは、移住前に十分な準備を行っていた移民が比較的に円滑に生活再建を達成していた一方、情報面や法的な支援面での課題が残るとの見方を示した。

Kapiolani Micky氏とScott Drinkallによる発表の様子

前川美湖主任研究員とPriyatma Singh氏による発表の様子

全体討論の様子
当日プログラム
| 13:00-13:15 開会挨拶 | 酒井英次 笹川平和財団海洋政策研究所副所長 |
| 13:15-13:45 講演1 | 国際共同研究およびJournal of Disaster Research特別号の概要 中山幹康 東京大学大学院新領域創成科学研究科教授 |
| 13:45-14:15 講演2 | 環境移民のための実効性を有する法制度 Carl Bruch 環境法研究所国際部長 |
| 14:15-14:45 講演3 | 移住と移転先での生活再建:米国スプリングデールにおけるマーシャル人社会およびマジュロにおけるマーシャル人大学生の比較 Malisa Laelan 在アーカンソー州マーシャル人会、Shanna McClain 環境法研究所客員政策アナリスト |
| 14:45-15:00 休憩 | |
| 15:00-15:30 講演4 | 太平洋島嶼出身者の米国オレゴン州への移住:生活の質向上への促進要因および阻害要因 Kapiolani Micky 在オレゴン州ミクロネシア人会、Scott Drinkall 環境法研究所客員研究員 |
| 15:30-16:00 講演5 | キリバスからフィジーへの移住者の生活再建 前川美湖 笹川平和財団海洋政策研究所主任研究員、Priyatma Sign フィジー大学講師 |
| 16:00-16:45 |
ディスカッション |
| 16:45- | 閉会 |